大井川鉄道井川線の旅の帰りに、旅の締めくくりとして塩郷の吊橋を渡ることにしました。
塩郷の吊橋は大井川本川に架かる吊橋の中では一番長く、長さ220メートル、高さ約11メートルです。戦後に地元の中学生が通学のために、自転車に乗ったままで吊り橋を渡る姿がよく見られたと記されていました。雨の日でも傘をさして片手運転で通行していたというから驚きです。かなり揺れるので、おっかなびっくりで歩いている身には、とてもできそうにはないです。以前奈良県十津川村の谷瀬の吊橋を、地元の人が小型のバイクで渡るところを実際に見たことがあります。慣れた人にはなんということはないのかもしれませんが、神業に近いですね。

正式名は久野脇橋という様ですが、愛称の「恋金橋」は、川根町政40周年事業により、久野脇地区に伝わる地名のもととなった恋の伝説からつけられたといいます。

幅広になっているところには金網が張ってあります。
橋の下を道路と線路が通っている真上にあたり、落下物を防ぐためのもののようです。



橋の中央からの眺望

渡りきった対岸からの眺望

橋のたもとからの眺望
上流方向を望む





下流方向を望む

橋の下からの眺望


吊橋の下を通る道路や線路が見えます。




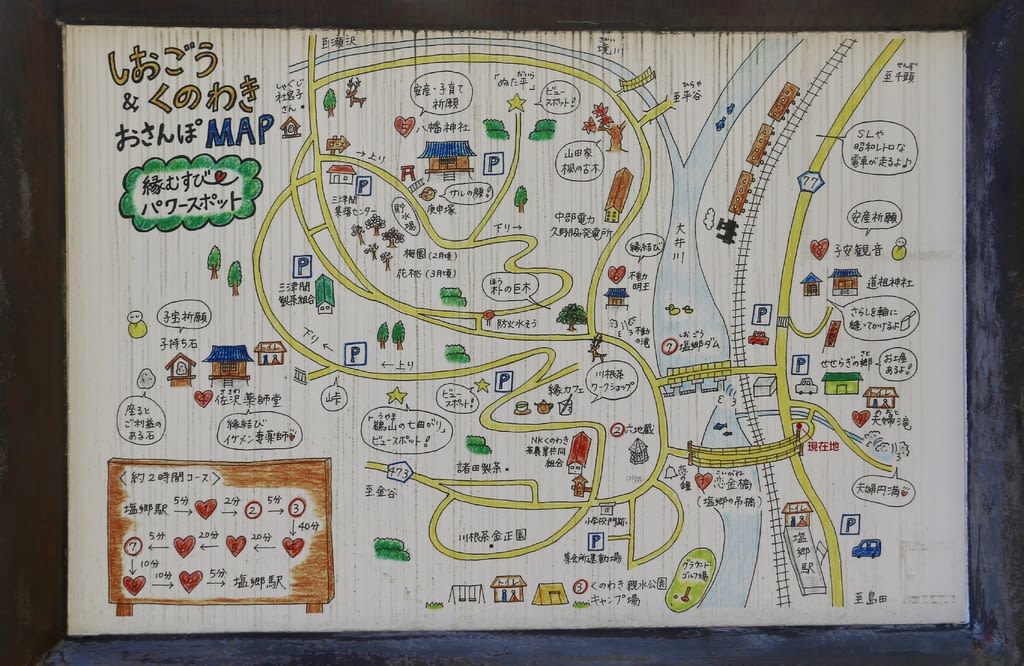

大井川本川には12もの吊橋があり、支川を含めると30ほどの吊橋があるようです。
大井川本川大井川に架かる吊橋
久野脇橋(恋金橋)
ハタマ吊橋
両国吊橋
山の吊り橋
飛沫(しぶき)橋
南アルプス接岨峡大吊橋
井川大橋
小河内の吊橋(廃橋)
中の宿吊橋
千葉山の吊り橋
西向の吊橋
小長井の吊橋
塩郷の吊橋は大井川本川に架かる吊橋の中では一番長く、長さ220メートル、高さ約11メートルです。戦後に地元の中学生が通学のために、自転車に乗ったままで吊り橋を渡る姿がよく見られたと記されていました。雨の日でも傘をさして片手運転で通行していたというから驚きです。かなり揺れるので、おっかなびっくりで歩いている身には、とてもできそうにはないです。以前奈良県十津川村の谷瀬の吊橋を、地元の人が小型のバイクで渡るところを実際に見たことがあります。慣れた人にはなんということはないのかもしれませんが、神業に近いですね。

正式名は久野脇橋という様ですが、愛称の「恋金橋」は、川根町政40周年事業により、久野脇地区に伝わる地名のもととなった恋の伝説からつけられたといいます。

幅広になっているところには金網が張ってあります。
橋の下を道路と線路が通っている真上にあたり、落下物を防ぐためのもののようです。



橋の中央からの眺望

渡りきった対岸からの眺望

橋のたもとからの眺望
上流方向を望む





下流方向を望む

橋の下からの眺望


吊橋の下を通る道路や線路が見えます。




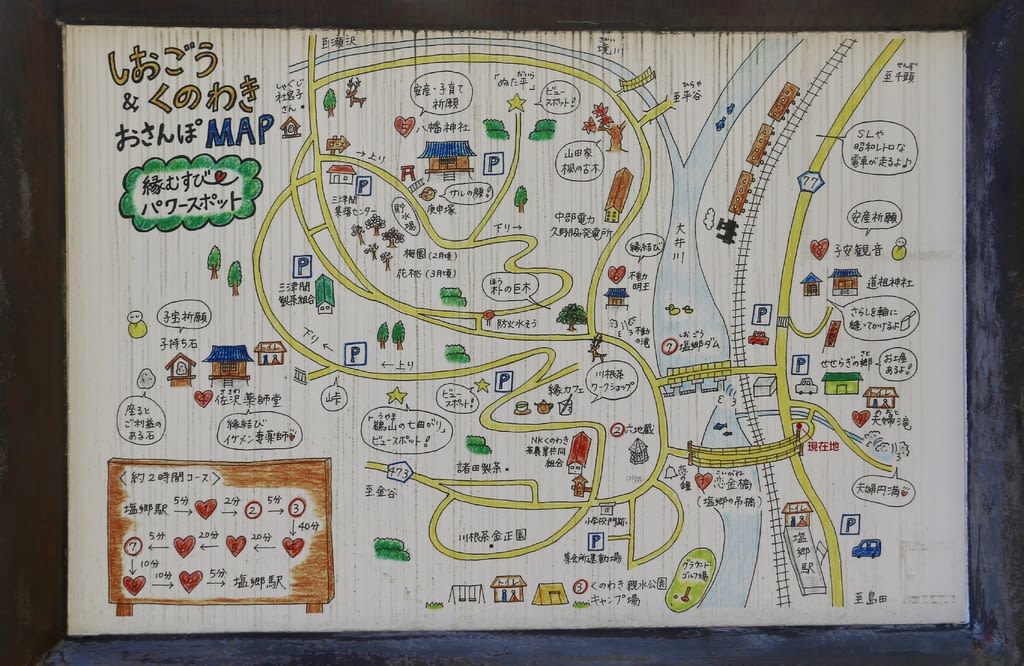

大井川本川には12もの吊橋があり、支川を含めると30ほどの吊橋があるようです。
大井川本川大井川に架かる吊橋
久野脇橋(恋金橋)
ハタマ吊橋
両国吊橋
山の吊り橋
飛沫(しぶき)橋
南アルプス接岨峡大吊橋
井川大橋
小河内の吊橋(廃橋)
中の宿吊橋
千葉山の吊り橋
西向の吊橋
小長井の吊橋




















ここを学生たちは雨の日には傘をさして渡っていたと言うのですから驚きと言うより有りませんね。
しかし、長い!
この辺りだったか上下に一本綱が渡して有るだけの吊り橋が有りませんでしたっけ?
それをクリアしなければ下山口に辿り着けないと言う曲芸まがいを強いられる吊り橋。
その映像を観て南アの登山を断念した事が有りました。
慣れとはおそろしいものですね。
こんな長い橋を傘をさしながら渡るなんて、とてもじゃないができそうもありませんね。
上下に一本綱があるだけの吊り橋まであるのですか、それを渡ろうとしたら命懸けですね。
百戦錬磨のたかさんでもビビリましたか。
そんなところを渡る人ってどんな人なのでしょう。世の中にはすごい人がいるものですね。
最初の写真を見ただけで震えました!!
足がすくみそうですヨ。
吊り橋ですから、横揺れもあるでしょうに・・・
雨の日は傘をさしたまま片手運転で自転車を走らす等・・・
曲芸に近い印象を受けます!
イケリン様も渡られたのですよネ。
一方通行と言う事は無いでしょうから・・・
渡り切る迄、ヒヤヒヤものだったのでは?
それにしても、大井川には12もの吊り橋があるとは・・・
高い山間を流れていれば必然的にそうなるのでしょうが・・・
支流も含めて30近い吊り橋が在るのは大井川だけでしょうネ。
かなり以前ですが、徳島県の祖谷渓の吊り橋を渡った事が在ります。
橋全体が蔓で作られていました。
横揺れでバランスが崩れて恐ろしかった記憶が甦りましたヨ。
神輿のような乗り物に乗せてもらったり、人の肩に乗せてもらったり、
浮世絵などに描かれていますが、増水時にはそれも出来ませんし、
吊り橋の出現で、交通の便が格段によくなったことが分ります。
それにしても、細い、しなる、揺れる、登り下りあり、で
ここを渡るのも慣れないと怖そうですね。
自転車で傘をさいての通行とは、驚きでした(^_-)-☆
昔は「越すに越されぬ大井川」だったのに、今は12も吊橋して渡るなんて、信じられません。
でも子供も女性も渡っていますね。
渡ってみたいような気もします。
いや、やっぱりお写真を見せて頂くだけにします。
周りは絶景ですね。
揺れる橋の上から下が見えるので、落ちることはないとは思ってはいても
恐怖感がありますね。一方通行ではないのですが、すれ違いはギリギリなので
みんなが渡りきるまで待つしかないですね。
大井川の支流を含めて30もの吊り橋があるとは思っても見ませんでした。
おそらく日本一吊り橋の多い川ではないのでしょうか。
祖谷のかずら橋は私も渡りました。蔓が使用されているので、山の吊り橋りと
いう雰囲気が満点ですね。あの橋に使用されているのは、「シラクチカズラ」
(サ ルナシ)の蔓で、その蔓はしなやかで丈夫だそうですね。
渡り慣れた人には、なんてことはないのでしょうが、
観光で訪れたものにとっては、ふわふわと揺れる感覚がなんとも不気味ですね。
とはいうものの、好奇心から渡って見たいという気持ちが起こるのもまた事実です。
思い出の一つとして、渡って見たという人も多いのではないのでしょうか。
この吊り橋がない頃は、対岸に渡るのに苦労されていたようです。
車が通れる橋をかけると費用も大変なので、吊り橋という選択になったのでしょうが、
ぐるっと回って対岸まで行く必要がなくなっただけでも、地元の人にとっては
ありがたかったことでしょうね。
歩いていても、かなり揺れる橋を自転車に乗ったままで渡るなんて想像も
つきませんね。それも傘をさしてですからね。
今では上流にダムができた上に橋もたくさんできて、越すに越されぬということは
ありえないことでしょうが、昔は増水するたびに何日も足留めとなって、
宿泊を余儀なくされたようですね。
私のような年寄りとは違って、若い人は女性も子供さんも、スイスイと歩いて
行きますよ。中にはスカート姿の人もいて、下から見えるかも・・・なんて
言いながらも渡って行かれますよ。(笑)