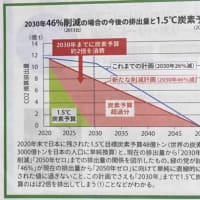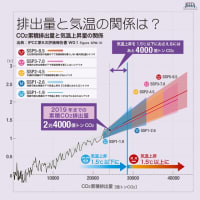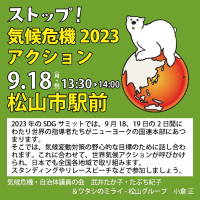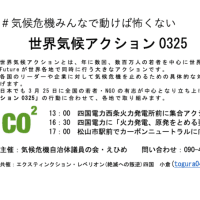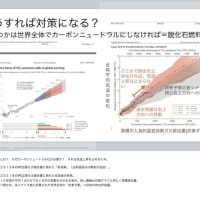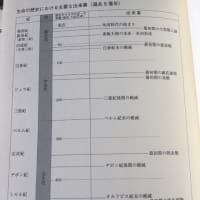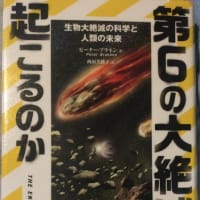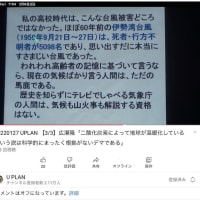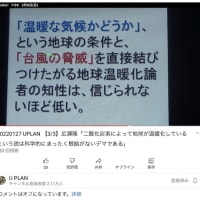昨日は市民派の阿部悦子県議の一般質問がありました。
原発関連で頂いた原稿とテープ起こしを一部紹介します。一部、再質問部分のテープ起こしは少しずつ追加していきます。青地が、県側の答弁です。
(ちなみに、もう録画ビデオが公開されていますね、早くなりました。)
−−−−−−
阿部悦子県議(環境市民=一人会派)
3・伊方原発再稼働問題について伺います。
安倍首相は、福島第一原発の高濃度放射能汚染水漏れ問題で、IOC総会の席で「コントロールされている」と断言、さらに「影響は港湾内0.3平方キロメールで完全にブロックされている」とも発言しましたが、この発言に信ぴょう性がないことは、地元漁業者が最も知るところです。
総理の発言がどんなに虚偽であるのか、世界はこれから厳しく検証・断罪することになります。
一方、原子力規制委員会の田中委員長は、タンクの増設は限界であり、薄めて海洋に流すしかないと発言しました。
(1)汚染水流出について伺います。
(ア)知事は、田中規制委員長の発言について、どのように考えますか。伊方原発で同様の事態に陥った場合、汚染水の放流を認めますか、認めませんか。
岡田県民環境部長)
まず汚染水問題に関して規制委員長の発言についてのご質問がございました。
原子力規制委員長の発言につきましては経緯等を含めまして詳細を承知しておりません。
伊方原発についてはこのような事故を起こさないよう現在国において新規制基準に基づく厳しい審査が行われておるものと承知をしておりまして、汚染水の放出を仮定したような質問についてはお答えができかねます。
(イ)地下水の流入がない場合でも、事故時の炉心の冷却に用いた汚染水は貯めるしかありません。伊方原発敷地内に汚染水を貯蔵すると仮定して、面積はいくらあり、貯蔵するタンクの容量はいくらありますか。
伊方原発の敷地はすでに建物でほぼ埋まっており、ろ過設備やタンクが設置できるとは思えず、また細長い佐田岬半島内を設置場所に選ぶのも現実的ではありません。
以下も続けて岡田県民環境部長)
次に伊方原発敷地内での汚染水の貯蔵可能量等についてのご質問でございます。
ただいまお答えしました通り伊方原発の安全性については国の審査が行われているところでありまして四国電力では汚染水が発生することがないよう安全対策を講じているとしております。
(2)原子力防災対策で伺います。
原子力規制庁は原発の新規制基準や原子力災害対策指針は、過酷事故が起こることを想定しています。そもそも日本の全ての原発では、これまで過酷事故を想定しませんでした。1973年に伊方原発の設置許可の取り消しを求めて提訴した伊方訴訟の口頭弁論で国側は、住民側代理人が「周辺住民の退避時間と被曝量」をきいたところ、「逃げることを想定していない」と答えたことが公判記録に残っています。その後79年のスリーマイル、86年のチェルノブイリ事故の後も日本は安全神話を死守しました。99年に起きたJCOの事故後に国は「原子力災害対策特別措置法」を作りましたが、これに基づいて策定された国や県の「原子力防災計画」も、「避難計画」も、福島原発事故で役に立たなかったことは周知の事実です。原発の「安全」という概念は失われ、全て幻想に終わっています。
今年7月に策定された県の「地域防災計画」についても同じです。
(ア)県は、防災計画の第2編、「原子力災害事前対策」の中の第12章「防災知識の普及」で原子力災害に関する一般的知識を、県民に対し普及啓発するとしていますが、過酷事故が起こりうるという180度これまでと違う考え方を、県民にどのように普及していくのか伺います。
次に原子力防災対策といたしまして過酷事故についての普及に関するご質問がございました。防災対策は万一の事故に備えて様々な事前対策や応急対策を講じていくことが重要でありまして、県民の皆さんにもこのような観点から防災会議の公開、広域避難計画等の報道発表や県市町の広報誌での周知、原子力防災訓練への住民参加などにより原子力防災知識等の普及啓発をはかっておるところでございます。
(イ)これまでの防災計画では、住民が被ばくをする前に避難が完了するとの建前でしたが、過酷事故の想定に伴って、例えば原発から5キロから30キロ圏、UPZと呼ばれる地域の住民は、平常時の約1万倍の放射線が検出されることが避難基準とされており、高濃度の放射能の中を避難することになっています。これで住民の安全と安心が確保できると思いますか。
次に原発から5キロから30キロ圏の住民の避難についてのご質問がございました。本年6月に県が策定いたしました広域避難計画では住民の皆さんの安全確保を大前提といたしまして、まず5キロ圏内のPAZ内の住民については大量放出の恐れのある全面緊急事態に至る前の段階から準備及び避難を実施し、5キロから30キロ県内のUPZの住民は空間放射線量の上昇に応じて段階的にまず屋内避難、次に避難を実施することとしております。
この計画を実効性あるものにするために現在重点区域7市町におきまして、より具体的な避難行動計画を策定しているところでございまして、県としては住民の皆さんの安全と安心の確保のためにその策定を積極的に支援している所でございます。
(ウ)伊方町人口の約半数に当たる5000人は、原発より西の半島部に暮らしています。この人たちの避難はどうするのか、具体的にお答えください。
「下を見たら、くらくらするような、手すりもない急な石段を登りつめた所や狭い背戸にくっつくように家が建ち、よその庭を通ってしか行けない家々に住む人々がいます。事故が起きた時、細長い半島、伊方や三崎半島からから脱出するのに弱い岩盤のいくつものトンネルがあります。海がしけたら船は出せない。津波が来たら船も岸壁に着けない。ここに住むおばあちゃんは、「私らはよう逃げん、どないして逃げるの。あきらめとらい、と言います」これは、現地に行った人の報告です。県の「防災計画」はこれらの人を念頭に置いているとは思えません。
次に原発より西の半島部の人たちの避難についてのご質問でございます。
原発以西の住民のみなさんの避難については、放射性物質の大量放出の恐れのある全面緊急事態に至る前の段階から早めの準備及び避難を開始する事としており、原則として自家用車で松前町へ向けて避難することとしております。
また万一放射性物質の大量放出に至った場合には住民が残ってる場合には大分県等への避難も含めまして自衛隊や海上保安部等の航空機や船舶等、投入可能な陸海空あらゆる手段を用いて対応することとしております。
阿部) 伊方5千人の避難についての備えですけれども、伊方町は孤立集落はないと言われていますけれども、しかし県が指定した急傾斜地で土砂災害を起こし崩壊すると予想される区域が100ヶ所あります。土石流による土砂災害指定区域は193ヶ所になっています。集落単位だけではなくて個々の家がそれぞれに孤立する、最も厳しい地域なんです。そのことに対してどう備えているかを聞きます。
半島から西にいらっしゃる方々の避難につきまして、地形上急傾斜地や土砂災害が多いところで集落というよりか個々の地域が大変な地域であるのにそれをどう避難さしていくのかと言うことでございますが。
これにつきましては6月に策定しました県の広域避難計画、これで県としての基本パターンは示しておりますが、そういうことも含めましてより詳細な対応をどうするかこれを今伊方町の方で避難行動計画として策定しておるところでございまして、その対応を待ちたいと考えております。
内閣府は、平成22年に「中山間地における孤立可能性集落」の調査結果を公表しました。四国の山は急峻な上に脆弱であり、巨大地震時には土砂災害被害が大きく、山が岩盤ごと崩れる「深層崩壊」が起こると分析しています。この点は昨日、村上、福羅両議員が指摘されています。
愛媛県での「孤立する可能性がある集落」は530か所です。このような集落は、高齢化率も高く、人々が逃げられず、孤立する怖れがあります。
(エ)原子力災害対策重点区域が含まれる7市町での「孤立する可能性のある集落」の数と人口をそれぞれ示して、防災計画でどのような対応を取るのかお答えください。
次に重点区域内の市、町における孤立可能性集落についてのご質問がございました。孤立可能性集落については一定の条件により市町ごとの集落数をアンケート調査した例は承知しておりますが、実際の発生は災害の状態によって大きく異なってくるものでございまして、その調査を基に想定することはできないものと考えております。
災害発生時の孤立集落対策といたしましては何よりもその発生状況を迅速に把握し、対策を講じることが重要と考えておりまして、県地域防災計画では市町が孤立地域を把握し、通信手段や緊急救助手段の確保等を行うこと、県は市町や関係機関と連携して県防災ヘリ等による救出や物資輸送緊急支援物資の確保や斡旋を行うことなど必要な対策を規程しているところでございます。
阿部) 重点区域で540の集落があると言われていますが、私が市町に聴き取りを行った結果ではこの7市町には200の集落が孤立可能性集落としています。このことをご存じないのでしょうか。
重点区域内、阿部議員がお調べになったところで200以上の孤立集落があるのにそれを承知してないかとのことでございましたが、平成20年、内閣府が調査したこの200の集落数これについては承知してございます。
ただ、答弁の中でお答えしました通り、被害の発生状態というのはこの状況によって大きく変わりますことから、この200を前提とした対応ということはなかなか難しいのではないか、ただ、そういった数に囚われるということではなく孤立集落対策としては何よりもその発生を迅速に把握した上で早急に対応することが必要であるとの答弁をさせていただきました。
(オ)県は「原子力災害対策重点地域」を30キロとしていますが、福島事故で放射能被害は同心円状に広がるのではないことは、誰もが知るところとなりました。、県防災計画で、これが見えません。京都府は放射能の拡散予測システムSPEEDIで福島事故級の事故が起きた場合、若狭の原発からどのように放射能が流れるか予測計算を行っています。兵庫県、滋賀県、岐阜県なども独自の予測計算を行って防災計画に反映しようとしています。愛媛県でなぜ同じような予測計算を行わないのかお答えください
次に原子力防災対策に関しましてSPEEDIの活用についてのご質問でございます。
SPEEDIについては、県でも毎年実施する原子力防災訓練で活用しておりますほか、原子力安全技術センターへ委託いたしまして代表的な気象条件下での拡散予測計算を行いまして防災業務の参考といたしましてこれらの予測結果につきましては全て県のホームページで掲載しているところでございます。
なお今年6月に策定した県広域避難計画におきましては30キロ圏内だけでなく圏外でありましても必要に応じて避難等の防護措置を実施することを記載してございます。
阿部) SPEEDIを使って予測をしろということを求めていますが、この防災計画にはそれが書かれていません。40キロ圏にも高い放射性物質が及んだ飯館村の人たちの教訓が活かされていないと思います。これをどのように活かしているのかお聞きします。
SPEEDIの活用でございますが、防災計画の中に具体的にSPEEDIの記載がないじゃないかと言うことでございますが、愛媛県地域防災計画原子力対策編の第8章住民避難等の実施のところにおきまして書いてございますのが国からの提供を受けた緊急モニタリングの結果及びSPEEDIの予測結果の分析等から必要な防護措置を講じる、このような記載がしっかりと入れてございます。
(カ)防災計画では「避難経路の指定」の項目はあるものの、具体的な記述がありません。県は避難時間シミュレーションを、民間に委託したと言いますが、この結果を踏まえた具体的な避難方法が防災計画に書き込まれて、住民に周知徹底されるまでは、伊方原発の再稼働はありえないのではありませんか。
次に地域防災計画における避難経路の記述や避難時間シミレーションについてのご質問でございますが、避難経路につきましては県地域防災計画に基づいて本年6月に策定した、県広域避難計画におきまして基本的なパターンとして複数の経路を記載しております。
また避難シミュレーションによって得られた結果は、この秋に予定しております原子力防災訓練での検証結果と合わせまして広域避難計画等に反映していくこととしております。
これらの原子力防災対策は再起動の条件というよりも原発自体の安全対策と並行いたしまして充実強化を図っていくべきものと考えております。
阿部) 民間のシミュレーションを元に秋にはこのシミュレーションをやると言っていますけれども、私が担当課に聞いたのは、2月にこのシミュレーションが出てくると聞いています。どうなっていますか。
シミュレーションにつきまして、先ほど秋にこのシュミレーションも反映させて計画に反映させていくと答弁したけれどもシミュレーションそのものは2月じゃないかと言うようなお話でございましたが、最終的なシミレーションについては2月で契約をしてございますが、秋にはこの広域避難計画、市町の避難行動計画に反映すべき部分については報告を求めてございますので、答弁の通り、秋にはこのシミュレーションの結果を反映出来るものと考えております。
(キ)県防災計画では、「災害対策本部の立ち上げ」を「国との協議の上で」とするなど、国頼みの記述が多く見られます。福島事故のおり、福島県は国より前に2キロ圏内の避難指示を出しました。これでも遅かったのです。また国も県も「ヨウ素剤配布」の指示が出せない時点で、的確にヨウ素剤を配布出来た三春町の例もあります。県は国任せではなく、市町と連携して初期対応の判断能力を磨くべきであると考えますが、いかがですか。
次に地域防災計画での災害対策本部について国頼みの記述が多いのではないかとのご質問でございますが、県地域防災計画の国との協議の上でなどの記述は原子力原子力防災を統括する国との連携を密にしてことに当たるとの意味でございまして国頼みとは考えてございません。
県災害対策本部は県自らの判断で立ち上げを行うとともに住民に対する避難指示等については国の判断が原則ではございますが緊急に必要な場合には県知事または市町長が自ら判断することとしております。なおこうした防災対策は先ほども申しました通り原発対策と並行して充実強化を図っていくべきものと考えておりまして、再起動の条件と考えてございません。
(3)知事が、再稼働についての重要な判断材料にするという「伊方原発環境安全管理委員会」について伺います。
(ア)県民への広報と傍聴の受け付けはどうか。今のやり方では「オープンにしたくない」という「隠ぺい体質」さえ感じます。周知時期と方法、議事録の公開時期、制限人数などを改めてはいかがですか。傍聴枠を広げて、当日でもスペースがあれば傍聴者を受け入れるなど、柔軟性をもっていただきたい。
次に、伊方原発環境安全管理委員会についてのご質問がございました。
まず委員会の広報と傍聴の受付方法についてのご質問ですが、伊方原発環境安全管理委員会の開催の周知や傍聴人の決定については、審議会等の会議の公開に関する指針に基づいて行っておりまして議事録の公開については出来る限り早期に公開できるように取り組んでおりますことから問題があるとは考えてございません。
また傍聴についても円滑な会議の運営の為、指針に基づき事前に期日を明示して募集しているものであり、応募された方々との公平性確保の観点からぜひ決められた手続きを遵守していただきたいと考えております。
(イ)原発の再稼働の是非が県政の最重要課題であり、「議会基本条例」の主旨からも、県議会と議員には当委員会及び防災会議等の、案内をするべきと思いますが、いかがですか。
次に県議には委員会等の案内をすべきではないかとのご質問でございますが、伊方原発環境安全管理委員会や防災会議等の開催にあたりましてはホームページへの掲載や報道機関への情報提供によりまして広く県民からの傍聴の申し込みを受け付けまして希望される方には可能な限り傍聴していただいているところでございます。
阿部)委員会のことですけれども、議会基本条例との関係です。議会基本条例第15条には、議会は二元代表制の元、互いの役割を尊重しつつ対等かつ緊張ある関係を保持しながら、みづからが持つ機能を遂行しなければならないとあり、知事部局は議員の政務調査に対してオープンで開かれた立場で臨むべきだと思いますが、いかがでしょうか。
それから議会の方の委員会等への参加でございますが、二元代表制の元、県民の代表たる県議として別枠的な出席をお求めになることではございますが、限られたスペースの中で広く県民を募集いたしましてできるだけ多くの希望の方に傍聴頂きたいと考えておりまして県議会議員の皆様の中にも正規の手続きを踏んでご出席、傍聴頂いてる方もございますのでぜひ阿部議員についても手続きを踏んだ上でご出席を頂ければ幸いと考えております。
(ウ)7月17日に行われた「環境安全管理委員会」の席での発言で、規制庁と四電の安全性に関する資料の審査について、「莫大な量の審査には人数が足りない」という主旨の発言や、「大丈夫とはいえず」「額面通り信じるしかない」などの専門委員の発言もありました。一方、規制庁からは「今の新基準で安心と言いたいのですけれども」との発言もありました。これらの発言から、「環境安全管理委員会は、再稼働の責任は負えない」と思いますが、いかがですか。
報道によると、伊方町議会に設置された「原子力発電対策特別委員会」では再稼働への疑問が複数委員から出され、中村委員長も「福島事故の原因が分かっていない時点での再稼働は、無理」と見解を示しています。さらに、9月13日、山下伊方町長は「観光振興で原発依存から脱却する」と発言しました。 これらの報道から、新たな圧力がかからない限りは、伊方町と議会、伊方町住民は、再稼働を望んでいないと私は考えます。
最後ですが7月に開催されました環境安全管理委員会での委員等の発言についてのご質問でございます。
7月17日の伊方原発環境安全管理委員会原子力安全専門部会における委員の発言につきましては原発の安全確保におきまして、国と同様の審査をすることに疑義がなされたものでございまして、委員として地域の特性をしっかり確認する趣旨があるとの趣旨であると承知をしております。
また原子力規制庁の説明は安全性に責任を負わないというものではなく、絶対安全は無いとの認識の下さらなる安全性を追い求めていく旨の趣旨と承知しておりまして、いずれも安全性について責任を負えないとしたものではございません。以上でございます。
(4)原発が過酷事故を起こすと、一瞬にして人類の未来を脅かすことを、私たちは福島事故から学んでいます。人類の歴史が始まって400万年、農耕生活が始まってから1万年です。その歴史の中で人間がほんの数十年間、瞬間的に使う電気のために、これから10万年も管理しなければならない高濃度放射性廃棄物を生み出すのが原発です。
3条件が、もし整って伊方原発が再稼働するとなると、どんなメリットが愛媛県にあると思うのか知事にお尋ねします。
中村県知事)
阿部議員に原発の再稼働についてお答えいたします。
原発の再起動につきましては国全体の将来を左右する問題でありまして、県の立場にとらわれることなく何よりも大前提となるのが安全性の確保、そしてエネルギー政策上の原子力の位置づけ、これらについてそれを司る国がさまざまな観点から充分議論した上で、確固とした方針を決定することは絶対に必要であると考えます。
私としてはそうした国の責任ある説明を聞いた上で、これはもう従来からずっとお話をさせていただいておりますけれども、事業者たる四国電力の取り組みの姿勢、そしてまた県民の代表たる県議会の議論等も含めた地元の考えも踏まえ総合的に判断をしてまいりたいと考えております。その他の問題につきましては関係理事者の方からお答えさせていただきます。
阿部議員再質問)
知事は答弁されましたが、これは再稼働にどんなメリットがあるのかを聞くものでした。全くお答えをいただいていません。答弁漏れとしてもう一度お答えください。
中村県知事)
原発の問題を考える時に一番重要なことは安全性の問題であることは言うまでもないところであります、この安全性につきましては原子力規制庁が新たに設置をされ、専門家の皆さんが集い、最新の知見に基づいた新しい安全基準というものを策定致しました。それに合致しているかどうかということを今審査している段階でございます。ですからこの審査の段階を終えない限り再稼働云々の議論をすることはできないということになります。さらに、そういった結果を踏まえて、総合エネルギー政策を司る国がどのような判断を示すのか、これが重要であります。
特にエネルギー政策というものは、国によって条件が随分と異なって参ります。それは資源の事情もあるでしょうし、地理的な条件もあるでしょうし、産業構造もあるでしょうし、経済規模もあるでしょうし、国民の生活水準もあるでしょうしまた、それに伴う電力消費量の問題もあるでしょう。だからこそ、国によって異なるエネルギー政策というものは、国全体の将来を左右する大きな課題であり、先ほども申し上げたんですけれども、県という立場にとらわれることなく大きな、国という視点での議論が必要になってまいります。
その結果国の方針が示されてくるというふうな段階を迎えます。一方、最初から申し上げていますとおり、再稼働の議論をするためには、国の方針と、電力事業者たる四国電力の姿勢、これも電力会社によって随分と異なってまいりますのでこの姿勢、そしてそれらを受けた議会等々をはじめとする住民の皆さんの議論というのが前提となってくるということを申し上げ続けてまいりました。特にこの2つめの電力会社の姿勢につきましては当然のことながら新しい知見によって示された基準にクリアするための要請というのが国から示されるわけでありますけれども、我々としてはそれは最低条件であって、県という立場から気付いたことについてはどんどんと電力会社に要請を行いこれを実現していただくということが重要であると考え続けてきました。
その結果が、原子力本部の移転であり、あるいは国が示した電源対策以上のものを追加して実施することを求めた電源対策の問題であり、あるいは住民説明で半径20キロ圏域は一軒一軒丁寧に説明を行うよう要請したり、またその他にも国は一切示していない揺れ対策というものについて対応を取るという要請もさせていただきました。
ただ、これは地区ごとに原発ごとに事情は異なります、なぜならばもう皆さんご存知の通り伊方原発は、福島と同様の津波が襲ってくる地形ではありません。ですから私としては揺れ対策に拘ったわけですが、こうしたことに電力会社がどのような対応をするかということを、議員のみなさん、あるいは県民のみなさんは見つめ続けているんだろうとこういう風に思います。
そういう結果として最終的に議会等々の議論も踏まえ総合的に判断をしてまいりたいということをお答えさせていただきましたものでございます。
その他の質問につきましては関係理事者の方からお答えさせていただきます。
−−−−−−−
と言うことで、どういうメリットがあるか、についてはまたも県知事は答弁拒否でした。
(カネだよカネ、ものすごい利権が絡んでいるのさ…とはFRYING DUTCHMAN の"humanERROR"の一節。)