◇ 自然郷も、いよいよ夏本番!
これから8月~9月は、自然郷ではたくさんの山野草が咲きます。
自然郷は、我が国でも有数の貴重な山野草の自生地です。
また、珍しい蝶もたくさん姿を現わします。
平成23年に全国で実施された「蝶調べ」では、自然郷が我が国でも有数の蝶生息地であることが確認されました。
下界では、もうすでに猛暑! しかし、自然郷は「クーラー要らず」です。
高地トレーニング を兼ねて、自然郷で健康法 に努めましょうか。
「コメント」欄にも投稿記事と訃報があります。(7月24日)
※ 「コメント」欄の見方は、ブログ記事本文の右脇(右上または右下)に4つ小さくあるアイコンのうち一番左端のアイコン(「コメント」)をクリックします。
◇ 今日(7月25日)は、下界も自然郷も今年一番の暑さ!
今日(7月25日)、中央道・甲府盆地を走行したら、車載の外気温度計が 39℃ を示していました。
野辺山高原を走行した時は、31℃ でした。
ちなみに、この日の気象庁観測では、野辺山高原の最高気温は29.5℃でした。
美鈴地区の当山荘では、今日25日は、最高気温 31.5℃ でした。
現在、夜の9時前ですが、外気温 20.9℃ を示しています。 どんどん気温が下がっています。
すごい寒暖の差です。 (※26日午前2時には、17.2℃ )
山梨県内では涼しい長坂では 34℃ でした。 長坂の住民の方曰く「(今日も)クーラーはつけない」そうです。 日陰や朝晩は涼しいからだそうです。
今日のこの程度は、当地では「健康的な夏の暑さ」かもしれません。
しかし、この猛暑現象は、地球温暖化の影響で、今後さらにひどくなると予想されます。
いずれ気温40℃突破は、時間の問題でしょう。
(たまりまセブン! 自然郷へ逃げていらっしゃい! )
◇ 自然郷の自生種で、シカが食べない植物・食べる植物一覧(7月29日追補)
【 シカの食害対策 】
自然郷の「自生種」植物で、「シカが食べない植物」「シカが食べる植物」を以下の通り一覧にしました。
どういうわけか、皆さん、よりによって「シカの大好物」ばかり育てていますね!
自然郷の自生種植物には、シカが食べないものも多いので、シカの食害対策 として、こうした シカが食べないもの を選んで育成するのも一方法です。
たとえば、サクラソウ、クリンソウ、コウリンカ、オトギリソウ、レイジンソウ、シャクナゲ、レンゲツツジなどはいかがですか?
今、ウツボグサがあちこちに咲いていますが、リンドウみたいなきれいな色です。これもシカは食べません。
シカが食べる 植物を保護・育成する場合は、その植物の部分に何らかのシカ対策 を講じた方がよいでしょう。
ところで、当山荘の スズラン が、今年はすっかり全部、シカに食べられていました。
スズランを食べたシカは死にます。 でも、山荘内にはその後もシカに食われた形跡があちこちにあるので、スズランを食べなかったシカの仕業でしょう。
一方、スズランの方は根っこが残っているので、また来年、芽を出します。
スズランは、シカの大好物であるオオバギボウシと葉っぱがよく似ているので、また来年、シカに食べられるかもしれません。
そういえば、シカに食べられたオオバギボウシが、その後、見事によみがえって、花を咲かせています。 食べられた方も負けていません。
今年は、とくに山荘が草でボウボウになってしまいました。 山野草などには興味も関心もない人には「全然、花が咲いていない!」ように見えますが、実はその中を山野草が負けずにたくさん咲いています。
「心、あらざれば、見えるものも見えず!」
せっかく我が国でも有数の自然に恵まれた自然郷に物件を持っているのですから、小さな山野草やチョウチョ・野鳥・野生動物などにも目を向けてみましょう。
そして、彼らから 「命」とか「生きざま」を学びましょうか。
(1)基本的には シカが食べない 植物 ( シカの食害をあまり被らないもの )
アカバナ、 アザミ(フジアザミ、ノアザミ、ノハラアザミ、タイアザミなど。 時々食べられている)、
イカリソウ、 イケマ、 イチヤクソウ類、 イブキジャコウソウ、シロバナイブキジャコウソウ、
イワカガミ(ウサギには食べられている)、 イワニガナ(別名:ジシバリ)、 ウサギギク、
ウスユキソウ(時々食べられる)、ヤマハハコ(時々食べられる)、 ウツボグサ、
オオヤマフスマ(別名:ヒメタガソデソウ)、 オトギリソウ、シナノオトギリ、コケオトギリ、
オサバグサ、 キオン、 キケマン、 キジムシロ、 キリンソウ、 キンポウゲ、
キンミズヒキ、ミズヒキソウ、 クサフジ、 クモキリソウ、 クリンソウ、 クルマバナ、イヌゴマ、
クワガタソウ、 ケブカツルカコソウ、 コウリンカ、 サクラソウ、 ササバギンラン、
サワギキョウ、 サワギク(別名:ボロギク)、 サンリンソウ、 シラタマノキ、 シャクナゲ、
スズラン(実際には食べられている。 しかし、食べたらシカは死ぬ)、 センボンヤリ、 ダイコンソウ、
チダケサシ、ハナチダケ、 ツマトリソウ(時々は食べられている)、 ツリフネソウ、キツリフネ、
トリカブト(時々食べられている)、 ノコギリソウ、 ハナイカリ(時々食べられている)、
ハルリンドウ、 ヒメイチゲ、 ベニバナイチヤクソウ、 ホタルサイコ、
マムシグサ類(ヒロハテンナンショウ、コウライテンナンショウ)、 マルバダケブキ、 ミツバツチグリ、
ミツバツツジ、 ミヤマモジズリ、 ヤブレガサ、 ヤマオダマキ(時々食べられている)、
ヤマホタルブクロ(時々食べられている)、 ヤマラッキョウ、 ラショウモンカズラ、 ルイヨウボタン、
レイジンソウ、 レンゲツツジ
(2) シカが食べる 植物( シカの食害対策が必要なもの )
アオスズラン、 アキノキリンソウ(あまり食べないが、でも食べる)、 アズマギク、
イブキボウフウ、ヤブジラミ、 ウメバチソウ、 オオウバユリ(鹿の大好物)、 オカトラノオ、
オキナグサ(鹿の大好物)、 オミナエシ(鹿の大好物)、 カラマツソウ、 カワラナデシコ、
オオバギボウシ(鹿の大好物)、コバギボウシ(鹿の大好物)、 クガイソウ(鹿の大好物)、
クサボケ(鹿の大好物)、 クサボタン(鹿の大好物)、 クサレダマ、 クルマユリ(鹿の大好物)、
クロユリ(鹿の大好物)、 コオニユリ(鹿の大好物)、 コミヤマカタバミ、 サラシナショウマ、
シモツケ、 シモツケソウ、 ショウジョウバカマ、 シラヤマギク、 センブリ、
ソバナ(鹿の大好物)、 タカネバラ(鹿の大好物)、 タチツボスミレ、
タマガワホトトギス(鹿の大好物)、 タムラソウ(鹿の大好物)、 チゴユリ、 チダケサシ類、
ツバメオモト(鹿の大好物)、 ツボスミレ、 ツリガネニンジン(鹿の大好物)、
トモエシオガマ(鹿の大好物)、 ニガナ、 ノコンギク(鹿の大好物)、 ヒロハノマンテマ、
フウロ類(グンナイフウロ、アサマフウロ、ハクサンフウロ、タチフウロ、など)、
フシグロセンノウ(鹿の大好物)、 ホソバノキソチドリ、 マイヅルソウ(ウサギにも食べられる)、
マツムシソウ(鹿の大好物)、 ミヤマエンレイソウ(鹿の大好物)、 ミヤマハンショウヅル、
ヤナギタンポポ、 ヤナギラン(鹿の大好物)、 ヤマアヤメ、ヒオウギアヤメ、
ヤマシャクヤク、シロバナヤマシャクヤク、 ヤマユリ(鹿の大好物)、
ユウガギク(鹿の大好物)、 ユウスゲ、ニッコウキスゲ、 リンドウ、 ワレモコウ(鹿の大好物)
※以上は、自然郷の「自生種」だけに限定してリストしました。
それにしてもかなりの数です。「自生種以外」にまで範囲を拡げると、もっと、とてつもない数になるでしょう。
さすが、自然郷は「我が国でも有数の山野草の自生地」です。
自然郷の山野草(10)&自然郷の蝶(1)
クガイソウ(九蓋草、九階草)

↑茎(草の根元から花までの間)に、葉っぱが9段(もしくは8段)になって付いているので、クガイソウ(九蓋草、九階草)と呼ばれています。
花期は7月~8月。明るい所や暗い所、どこでも咲いていますが、シカの大好物です。
クガイソウも薬草です。 自然郷の自生種山野草には、じつに「薬草」が多いです。
「薬草」といえば、滋賀県の伊吹山が有名です。
クガイソウも伊吹山に多いので、別名:イブキ クガイソウとも呼ばれています。
花期の時期に、根・茎を採取して乾燥させ、煎じて煮詰めたものを濾して服用すると、リュウマチや関節炎に効き、利尿作用があるといわれています。
また、これらを原料にした「伊吹浴剤」は、保温効果があり、冷え症や美肌に良いとされています。
【伊吹山伝説】
西暦330~340年頃のことです。
大足彦忍代別(オオタラシヒコ オシロワケ、後世になって「景行天皇」と追号された)の皇子 小碓(オウス、小碓尊とも小碓命とも小碓王とも書く。あだ名は、日本武尊(ヤマトタケル)とも、日本童男(ヤマトオグナ)とも呼ばれた)が、東国遠征からの帰途、尾張の地にしばらく滞在していました。
ここで、伊吹山にヤマト朝廷の意に従わない者がいると聞き、その者を従わせるべく、オウスは剣を持たないで丸腰のまま伊吹山に向かいました。
しかし、伊吹山では、道に迷わされたあげく、毒気にあたって、ついにオウスは意識が混濁してしまいました。
そこでやむなく下山したのですが、三重県能褒野(のぼの)のあたりで、とうとうオウスは絶命してしまいました。年30歳とのことです。
(『日本紀』(通称:日本書紀)および『古事記』の景行天皇紀)
この話のように、古代から伊吹山には薬草がたくさん群生しており、オウスはこれらの薬草のうち毒草にあたって死んだといわれています。
どのような状況でオウスが毒にあたったのか? 『日本紀』や『古事記』では触れていません。
一説には、伊吹山の土着民からの毒矢を受けて、その傷が悪化したという見方をする研究者もいます。
※ちなみに、景行天皇のあとは、オウスの異母弟:稚足彦(ワカタラシヒコ、後世になって「成務天皇」と追号された)が継ぎました。
そして、成務天皇のあとを、オウスの子:足仲彦(タラシナカツヒコ、後世になって「仲哀天皇」と追号された)が継ぎました。
仲哀天皇の妻が「神功皇后」、仲哀天皇と神功皇后との間の子が八幡神社の祭神「応神天皇」です。
応神天皇はヤマトタケルことオウスの孫です。
コウリンカ(紅輪花)

↑絶滅危惧種です。キク科。花期は8月~9月。日当たりの良い草むらに生えます。
タンポポみたいな感じですが、花ビラが反っくり返っています。
シカは食べません。
ヒョウモンチョウ(豹紋蝶)


自然郷では、数ある蝶のうち、モンシロチョウとヒョウモンチョウが早くから姿を見せます。
↓モンシロチョウは、皆さんご存知の一般的な蝶です。

↓クガイソウと、ヒョウモンチョウ



↓クガイソウと、ウラギンヒョウモン、ヒメキマダラセセリ、ダイミョウセセリ の3ショット

↑上から、ウラギンヒョウモン、ヒメキマダラセセリ、ダイミョウセセリと並んでいます。
↓クガイソウと、ギンボシヒョウモン、ヒメキマダラセセリ の2ショット

↓クガイソウと、ギンボシヒョウモン

↓コウリンカと ヒョウモンチョウ

***************************************
【 自然郷特派員より 】
自然郷オーナーの皆さま お元気でお過ごしでしょうか?
今回は少々 趣を変えて”自然の魅力”以外の「自然郷の魅力」を自然郷特派員が別角度から
独断と偏見で、あれこれ上げてみたいと思います。
もし異論や新情報、特ダネ等あればコメント欄に投稿して頂ければ追加します。
オーナーの皆さんも自然郷の魅力を多数 発信してください。
それでは別角度から見た「自然郷の魅力」とは、
1.真夏でも大変涼しく湿度も低く快適!(平均的には23℃位で当然エアコンなど不要)
2.自然郷・南牧村周辺では渋滞がない!(とくに別荘地には関係車両以外入って来ない)
3.静かな別荘ライフを満喫できる!(ロッジ宿泊者以外、観光客がいないので落ち着ける)
4.電気は中部電力なので60Hzでよい!(50Hzより消費電力が少なく、電気料金も安い)
5.虫はいるが「蚊」がいない!(蚊に刺されてかゆい思いをしない、香取線香など不要)
6.鹿・狸・テンなどは生息しているが「熊」がいない!(暗夜でも安心して外を歩ける)
7.夜空の満天の星が凄い!(空気が澄んでおり、星がきれいなどとは言い表せない)
8.水道の水が冷たくて美味しい!(自然郷で飲むコーヒーは最高でしょう)
9.高原ロッジの管理が行き届いてよい!(今年の大雪では大奮闘されたそうだ・・・)
10.野辺山駅前は閑散としてざわついてないのがよい!(自然郷と直接関係ないが・・・)
などなど独断と偏見です。他にも良い所が沢山あると思いますので、コメント欄にて投稿を
お願いします。
※ 「コメント」欄の見方は、ブログ記事本文の「末尾にスクロール」 して、右下に4つ小さくあるアイコンのうち一番左端のアイコン(「コメント」)をクリックします。
※ 「コメント」欄への投稿の仕方は、ブログ記事本文の末尾にあります。
☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆

















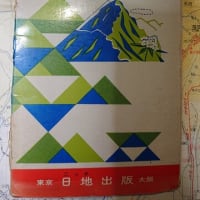
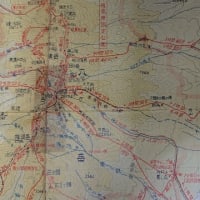

私の山荘は、1階から2階まで全部、北米杉の角ログです。
(1)何年経ってもセトリングがおさまらないので、とうとう引き戸が開かなくなりました。
(2)北米杉は、我が国固有の材木ではないので、私はその匂いが大嫌いです。入荘して1~2日は匂いに慣れるまでツライです。
(3)北米杉は、杉の一種でもあるので、木が軟らかいです。そのため、アリが好んで侵入してきます。毎年、アリ対策です。
(4)外壁がログ材なので、表面を保護塗装してありますが、これがしょっちゅう再塗装する必要に追われます。
(5)また、ログ材の隙き間をコーキング処理してふさいでおかないと、隙き間風や、雨水の浸水、虫の侵入に悩まさせられます。
(6)ログハウスは太陽の熱で蓄熱するので、冬は電気床暖房だけで暖かいのですが、それが夏には裏目に出て、外は涼しくとも屋内は暑いです。
また、ログハウスは窓が小さいので、風通しが悪い。
ゆえに、自然郷でもログハウスの場合は、夏、クーラーが欲しいです。(クーラーの要らない自然郷なのに!)
結論:日本ではログハウスなんて、建てるもんじゃない!
※また愚痴ってしまった。暑さにやられたか?
死因は脳梗塞、満84歳でした。
門馬圭子さんは、かの渋谷の忠犬ハチ公を世に知らしめた、日本犬と日本狼の研究家「斎藤弘吉」の姪です。
過日、渋谷区立郷土博物館で開催された「ハチ公特別展」では、重要な情報を提供していただきました。
あらためて御礼申し上げます。そして、心よりご冥福をお祈り申し上げます。
※当ブログに「訃報」を掲載することについては、ずいぶん躊躇しました。
①:具体的な「区画番号」を出さないこと、
②:「コメント」欄に掲載すること、
ならば、訃報を掲載しても差し支えがないものと判断しました。
よろしくご理解ください。
気のせいか、このところ自然郷オーナーだけでなく、いろいろな所で、亡くなった!とか、体調を崩した!という声を多く聞きます。
自然郷も開発以来50年も経過してくると、さすがに自然郷にも高齢化の波が押し寄せて来ます。
そのため、自然郷オーナーもスムーズに世代交代していけばよいのですが、残念ながら次世代を担う若い世代には自然郷の魅力がイマイチ浸透していません。
当オーナー会ブログは、こうした現象を原因とする自然郷の近未来に対し、大きな危惧を抱いており、そのため、単にオーナー各位への情報提供にとどまらず、広く一般に自然郷の魅力を知らしめたいという目的に基づいております。
オーナー各位のご理解とご協力をお願いする次第です。