官僚制と組織論を考えるのに貴重な資料をご覧ください。
官と民の生きざまに対して示唆に富むことこの上ないです。
『失敗の本質―日本軍の組織論的研究』戸部良一 寺本義也 鎌田伸一 杉之尾孝生 村井友秀 野中郁次郎 中央公論新社
はしがき
たとえば日本の大東亜戦争史を社会科学的に見直してその敗北の実態を明らかにすれば、それは敗戦という悲惨な経験のうえに築かれた平和と繁栄を享受してきたわれわれの世代にとって、極めて大きな意味を持つことになるのではないか。
大東亜戦争史上の失敗に示された日本軍の組織特性を探求するという新たなテーマは、……
われわれは本書が、戦史に社会科学的分析のメスを入れた先験的研究となること、またわが国ではおそらく初めて組織論の立場から軍事組織を実証的に分析した本格的研究となることを期したが、むろん本書は完璧なものではありえない。
序章 日本軍の失敗から何を学ぶか
本書は、日本がなぜ大東亜戦争に突入したのかを問うものではないからである。
本書はむしろ、なぜ敗けたのかという問いの本来の意味にこだわり、開戦したあとの日本の「戦い方」「敗け方」を研究対象とする。
大東亜戦争における諸作戦の失敗を、組織としての日本軍の失敗ととらえ直し、これを現代の組織にとっての教訓、あるいは反面教師として活用することが、本書の最も大きなねらいである。
そもそも軍隊とは、近代的組織、すなわち合理的・階層的官僚組織の最も代表的なものである。戦前の日本においても、その軍事組織は、合理性と効率性を追求した官僚制組織の典型と見られた。
しかしながら、問題は、そのような誤判断を許容した日本軍の組織的特性、物量的劣勢のもとで非現実的かつ無理な作戦を敢行せしめた組織的欠陥にこそあるのであって、この問題はあまり顧みられることがなかった。
危機、すなわち不確実性が高く不安定かつ流動的な状況――それは軍隊が本来の任務を果たすべき状況であった――で日本軍は、大東亜戦争のいくつかの作戦失敗に見られるように、有効に機能しえずさまざまな組織的欠陥を露呈した。
結局、本書がめざすところは、大東亜戦争における日本軍の作戦失敗例からその組織的欠陥や特性を析出し、組織としての日本軍の失敗に籠められたメッセージを現代的に解読することなのである。
米軍の成功と日本軍の失敗とを分かつ重大なポイントとなったのは、不測の事態が発生したとき、それに瞬時に有効かつ適切に反応できたか否か、であった。
インパール、レイテ、沖縄は、日本の敗色が濃厚となった時点での作戦失敗の主要な例である。……。人間関係を過度に重視する情緒主義や、強烈な使命感を抱く個人の突出を許容するシステムの存在が、失敗の主要な要因として指摘される。
ここでは、組織の環境適応理論や、組織の進化論、なかんずく自己革新組織、組織文化、組織学習などの概念を用いて、日本軍の失敗の本質に関する総合的理論化が試みられる。
一章 失敗の事例研究
ノモンハン事件(昭和一四年五月~九月)は、当初関東軍にとって単なる火遊びにすぎなかったが、結果は日本陸軍にとって初めての敗北感を味わわせたのみならず、日本の外交方針にまで影響を与えた大事件となった。
関東軍第一課参謀辻政信少佐起案 「満ソ国境紛争処理要綱」
すなわち皇軍の伝統は打算を超越し、上下父子の心情をもって統合するにあり、血を流し、骨を曝す戦場における統帥の本旨とは、数字ではなく理性でもなく、人間味あふれるものでなければならない、との思想であった
これを聞いた磯谷関東軍参謀長は、数千の将兵が血を流した土地を棄てて撤兵することは統帥上なしえない、と主張し容易に納得しなかった。そこで中央部は、「要綱」を強制して関東軍の感情を刺激することを怖れ、「要綱」の実施を命ずる処置をとらなかった。関東軍の立場を尊重し、実施はあくまでもその自発的意思によるという従来の方法をとったのである。
大本営としては作戦終結の意思を持っていたが、統帥の原則として実際の作戦運用はできるだけ現地の関東軍に任せるべきであると考えていた。したがって、大本営の指導方式は、まず関東軍の地位を尊重して、作戦中止を厳命するようなことはせず、使用兵力を制限するなどの微妙な表現によって中央部の意図を伝えようとしたのである。
ソ連軍の攻勢の結果、多数の日本軍第一線部隊の連隊長クラスが戦死し、あるいは戦闘の最終段階で自決した。また生き残った部隊のある者は、独断で陣地を放棄して後退したとしてきびしく非難され、自決を強要された。日本軍は生き残ることを怯懦とみなし、高価な体験をその後に生かす道を自ら閉ざしてしまった。
当時の関東軍の一師団に対する検閲後の講評は、「統率訓練は外面の粉飾を事として内容充実せず、上下徒に巧言令色に流れて、実践即応の準備を欠く、その戦力は支那軍にも劣るものあり」というものであった。
また関東軍の作戦演習では、まったく勝ち目のないような戦況になっても、日本軍のみが持つとされた精神力と統帥指揮能力の優越といった無形的戦力によって勝利を得るという、いわば神懸り的な指導で終わることがつねであった。
情報機関の欠陥と過度の精神主義により、敵を知らず、己を知らず、大敵を侮っていたのである。
「日本軍の高級将校は無能である」 ソ連第一集団軍司令官ジューコフ
ミッドウェイは、短期間であったが連戦連勝を続けてきた日本軍側が初めて経験した挫折であり、太平洋を巡る日米両軍の戦いにおけるターニング・ポイントとなった。
劣勢な日本軍が米国海軍に対して優位に立つには、多少の危険をおかしても、奇襲によって自主的に積極的な作戦を行い、その後も攻勢を持続し相手を守勢に追い込み、「米国海軍および米国民をして救うべからざる程度にその士気を阻喪せしめ」るほかない。これが山本(連合艦隊司令長官)の判断であった。
ガダルカナル作戦は、大東亜戦争の陸戦のターニング・ポイントであった。海軍敗北の起点がミッドウェイ海戦であったとすれば、陸軍が陸戦において初めて米国に負けたのがガダルカナルであった。
作戦司令部には兵站無視、情報力軽視、科学的思考方法軽視の風潮があった。それゆえ、日本軍の戦略策定過程は、独自の風土をもつ硬直的・官僚的な思考の体質のままに机上でのプランを練っていく過程で生まれる抽象的なものであったが、
戦略的グランド・デザインの欠如
したがって、本来的に、第一線からの積み重ねの反復を通じて個々の戦闘の経験が戦略・戦術の策定に帰納的に反映されるシステムが生まれていれば、環境変化への果敢な対応策が遂行されるはずであった。しかしながら、第一線からの作戦変更はほとんど拒否されたし、したがって第一線からのフィードバックは存在しなかった。
大本営のエリートも、現場に出る努力をしなかった。
インパール作戦は、大東亜戦争遂行のための右翼の拠点たるビルマの防衛を主な目的とし、昭和十九年三月に開始された。
インパール作戦→作戦構想自体の杜撰さ
「私は盧溝橋事件のきっかけを作ったが、事件は拡大して支那事変となり、遂には今次大東亜戦争にまで進展してしまった。もし今後自分の力によってインドに侵攻し、大東亜戦争遂行に決定的な影響を与えることができれば、今次対戦勃発の遠因を作った私としては、国家に対して申し訳が立つであろう。」(第一五軍司令官牟田口)
東条の指摘した五つの問題点すべてについて綿密な検討を加え確信を得たうえでの決断であったのではない。軍事的合理性以外のところから導き出された決断がまず最初になされ、あとはそれに辻褄を合わせたものでしかなかった、と極言してもよいであろう。
つまり、いわゆるコンティンジェンシー・プラン(不測の事態に備えた計画)が事前に検討されていなければならなかった。ところが実は、この必要性の認識こそ第一五軍の作戦計画にまったく欠如していたものであった。
牟田口によれば、作戦不成功の場合を考えるのは、作戦の成功について疑念を持つことと同じであるがゆえに必勝の信念と矛盾し、したがって部隊の士気に悪影響を及ぼす恐れがあった。
ところが河辺は、「そこまで決めつけては牟田口の立つ瀬はあるまい。また大軍の統帥としてあまり恰好がよくない」と、中の命令案を押さえてしまった。ここでも、「体面」や「人情」が軍事的合理性を凌駕していた。
ことに後者は、インパール作戦開始前に何度か修正されてしかるべき体験を味わわされたにもかかわらず少しも改められず、先入観の根強さを示すとともに、組織による学習の貧困ないし欠如を物語った。また、「必勝の信念」という非合理的心情も、積極性と攻撃を同一視しこれを過度に強調することによって、杜撰な計画に対する疑念を抑圧した。そして、これは陸軍という組織に浸透したカルチュア(組織の文化)の一部でもあった。
ここに取り上げるレイテ海戦は、敗色濃厚な日本軍が昭和一九年一〇月にフィリピンのレイテ島に上陸しつつあった米軍を撃滅するために行った起死回生の捨身の作戦であった。
一〇月二〇日の「朝日新聞」は次のように報じた。
「我部隊は……敵機動部隊を猛攻し、其の過半の兵力を壊滅して之を潰走せしめたり」
しかし、実際には米軍艦艇の損害は、撃沈されたものは一隻もなく、損害空母一、軽巡二、駆逐艦二隻の計五隻のみである。……。ここで重要なことは、この日本側の戦果の過大評価が、あとで見るようにその後のレイテ海戦に大きな影響を及ぼすことになるという事実である。とくに、海軍は一六日の偵察によって、敵空母、機動部隊がほとんど無傷で健在であるのを確認したが、この事実を大本営陸軍部には知らせなかったのである。
栗田艦隊「反転」
いずれにしろ、各部隊およびそれらの間の不信、情報、索敵関係の低能力と混乱とが直接、間接に「謎の反転」とむすびついていることだけは確かであった。
「……連合艦隊長官としては、いくさに勝ち目がない泥田の中にますます落ちこんでしまうばかりだから、速やかに終戦に導いてくれと、直截に口を切ることは立場上ちょっとできなかった。」(豊田福武『最後の帝国海軍』)
策定されたのは、「乾坤一擲」「起死回生」「九死に一生」の捷号作戦(しょうごうさくせん)であった。
日本海軍が、一部の例外的な人々を別として、戦艦と巨砲による「艦隊決戦」を最も重視していたことは周知のとおりである。栗田艦隊旗艦の「大和」、「武蔵」はそうした思想のいわば成果であり結晶であった。
「作戦の外道」→特攻攻撃
大東亜戦争において硫黄島とともにただ二つの国土戦となった沖縄作戦は、昭和二〇年四月一日から六月二六日の間、……(日本軍)約八万六四〇〇名と(米軍)約二三万八七〇〇名とが沖縄の地で激突し、戦死者は日本軍約六万五〇〇〇名、住民約一〇万名、米軍一万二二八一名に達する阿修羅の様相を呈した。
北・中飛行場問題は、大本営、第一〇方面軍が第三二軍の実態掌握に努力を尽くさず、かつ国軍全般の戦略デザインに占めるべき沖縄作戦の戦略的地位・役割を一点の疑義もなく明確に示す努力を怠った点に、第一の発生原因が求められる。
第二の原因は、第三二軍の上級司令部に対する真摯な態度の欠如に求められる。たとえ上級統帥が麻のごとく乱れる事態があったにせよ、国軍全般の戦略デザインとの吻合を顧慮することなく、自軍の作戦目的・方針を半ば独立的に決定すすることは、軍隊統帥の外道としてきびしく指弾されなければならない。
二章 失敗の本質――戦略・組織における日本軍の失敗の分析
あいまいな戦略目的
日本軍の作戦計画は、一般的にかなり大まかで、その細部については、中央部の参謀と実施部隊の参謀との間の打ち合わせによって詰められることが通例であったといわれる。
しかし、レイテ海戦の場合には、ことは作戦目的とそれに基づく栗田艦艦隊の目標と任務に関する作戦の根幹にかかわる事柄である。
ノモンハン事件の際にも、陸軍中央部は関東軍の自主性を尊重するという形で結局作戦目的についての明確な意思表示を遅らせてしまった。
レイテ海戦の場合も、実施部隊の自由裁量性を許容する前提として、まず作戦目的に関する価値観の統一をこそはかるべきであったと思われる。
インパール作戦では、第十五軍がインド侵攻を作戦目的としたのに対し、その上級司令部であるビルマ方面軍、南方軍はビルマ防衛を意図するという形で意思の不統一があった。
台北会議における沈黙の応酬に典型的に見られるように、上級司令部と現地軍との間には、戦略思想の統一のための積極的な努力はほとんど払われなかった。
結局、日本軍は六つの作戦のすべてにおいて、作戦目的に関する全軍的一致を確立することに失敗している。
この点で、日本軍の失敗の過程は、主観と独善から希望的観測に依存する戦略目的が戦争の現実と合理的論理によって漸次破壊されてきたプロセスであったということができる。
本来、グランド・ストラテジーとは、「一国(または一連の国家群)のあらゆる資源を、ある戦争のための政治目的――基本的政策の想定するゴール――の達成に向かって調整し、かつ指向すること」である。(リデルㇵ―ト『戦略論』)
ここで強調されている論理は、ある程度の人的、物的損害を与え南方資源地帯を確保して長期戦に持ち込めば、米国の戦意喪失、その結果としての講和がなされようという漠然たるものであり、きわめてあいまいな戦争終末観である。
短期決戦の戦略志向
さらに開戦時の最高指導者である東条英機首相兼陸相も「戦争の短期決戦は希望するところにして種々考慮する所あるも名案なし、敵の死命を制する手段なきを遺憾とす」と述べていた。
日本軍の戦略思考が短期志向だというのは、以上の発言でも明らかなように、長期の見通しを欠いたなかで、日米開戦に踏み切ったというその近視眼的な考え方を指しているのである。
短期決戦志向の戦略は、前で見たように一面で攻撃重視、決戦重視の考え方とむすびついているが、、他方で防禦、情報、諜報に対する関心の低さ、兵力補充、補給・兵站の軽視となって現われたのである。
主観的で「帰納的」な戦略策定――空気の支配
戦略策定の方法論をやや単純化していえば、日本軍は帰納的、米軍は演繹的と特徴づけることができるであろう。
さらに厳密にいうならば、日本軍は事実から法則を析出するという本来の意味での帰納法も持たなかったとさえいうべきかもしれない。
日本軍の戦略策定は一定の原理や論理に基づくというよりは、多分に情緒や空気が支配する傾向がなきにしもあらずであった。これはおそらく科学的思考が、組織の思考のクセとして共有されるまでに至っていなかったことと関係があるだろう。
沖縄作戦の策定にあたって最後まで科学的合理性を主張した八原高級参謀が、日本軍は精神力や駆け引き的運用の効果を過度に重視し、科学的検討に欠けるところが大であると嘆じたのはまさにこのことをさしているのである。
これはもはや作戦というべきものではない、理性的判断が情緒的、精神的判断に途を譲ってしまった。
「全般の空気よりして、当時も今日も(「大和」の)特攻出撃は当然と思う」(軍令部次長小沢治三郎中将)
日本軍が個人ならびに組織に共有されるべき戦闘に対する科学的方法論を欠いていたのに対し、米軍の戦闘展開プロセスは、まさに論理実証主義の展開にほかならなかった。
ガダルカナルでの実戦経験をもとに、タウラ上陸作戦、硫黄島上陸作戦、沖縄作戦と太平洋における合計一八の上陸作戦を通じて、米海兵隊が水陸両用作戦のコンセプトを展開するプロセスは、演繹・帰納の反覆による愚直なまでの科学的方法の追及であった。
他方、日本軍のエリートには、概念の創造とその操作化ができた者はほとんどいなかった。
日本軍の最大の特徴は「言葉を奪ったことである」(山本七平『一下級将校の見た帝国陸軍』
狭くて進化のない戦略オプション
こうした日本軍の戦闘上の巧緻さは、それを徹底することによって、それ自体が戦略的強みに転化することがあった。いわゆる、オペレーション(戦術・戦法)の戦略化である。
こうした硬直的な戦略発想は、秋山真之をして「海軍要務令が虎の巻として扱われている」と嘆かせたほどであるが、昭和九年の改訂以後結局一度も改訂されず、航空主兵の思想が海軍内部で正式に取り上げられるチャンスを逸してしまった。連合艦隊参謀として実戦の経験も豊富な千早正隆は、「海軍要務令で指示したことが実際の戦闘場面で起きたことは一度もなかったといってよい」と述べている。
その意味で戦略は進化すべきものである。進化のためには、さまざまな変更(バリエーション)が意識的に発生され、そのなかから有効な変異のみが生き残る形で淘汰が行われて、それが保持されるという進化のサイクルが機能していなければならない。
牟田口司令官は、作戦不成功の場合を考えるのは、必勝の信念と矛盾すると主張した。
岡崎久彦によれば、「統帥綱領」のように高級指揮官の行動を細かく規制したものは、アングロ・サクソン戦略にも、ドイツ兵学にもなく、日本軍独特のもののようである。
いずれにしろ、こうした一連の綱領類が存在し、それが聖典化する過程で、視野の狭小化、想像力の貧困化、思考の硬直化という病理現象が進行し、ひいては戦略の進化を阻害し、戦略オプションの幅と深みを著しく制約することにつながったといえよう。
アンバランスな戦闘技術体系
陸軍に「ふ」兵器と名付けられた秘密兵器があった。……。これが世にいう「風船爆弾」であった。
「現地調達」という言葉が多用されたが、結局ロジスティック軽視の日本的表現であることが多かったのである。
*ロジスティック
英語の綴りは「logistic」。「記号論理学の」「兵站学の、物流の」といった意味。「ロジスティック回帰」などと言う場合は、前者の「記号論理学の」といった意味。「物流の」といった意味の場合は、「ロジスティック」よりも「ロジスティクス」と表現するのが一般的。ロジスティクス(logistics)は、「物流」「輸送」などといった意味の英単語。(Weblio)
人的ネットワーク偏重の組織構造
ノモンハン事件を流れる一本の糸は、出先機関である関東軍が随所で中央部の統帥を無視或いは著しく軽視したという事実であり、さらに、関東軍内部では、第一課(作戦)作戦班長服部卓四郎中佐、同ノモンハン事件主担任辻政信少佐を中心とする作戦参謀が主導権を握っていたという組織構造上の特異性である。
以上のような事実は、日本軍が戦前において高度の官僚制を採用した最も合理的な組織であったはずであるにもかかわらず、その実体は、官僚制の中に情緒性を混在させ、インフォーマルな人的ネットワークが強力に機能するという特異な組織であることを示している。
強い情緒的結合と個人の下剋上的突出を許容するシステムを共存させたのが日本軍の組織構造上の特異性である。本来、官僚制は垂直的階層分化を通じた公式権限を行使するところに大きな特徴がある。その意味で、官僚制の機能が期待される強い時間的制約のもとでさえ、改装による意思決定システムは効率的に機能せず、根回しと腹のすり合わせによる意思決定が行われていた。
そこ(日本的集団主義)で重視されるのは、組織目標と目標達成手段の合理的、体系的な形成・選択よりも、組織メンバー間の「間柄」に対する配慮である。
米海軍のダイナミックな人事システムは、将官の任命にも生かされていた。米海軍では一般に少将までしか昇進させずに、それ以後は作戦展開の必要に応じて中将、大将に任命し、その任務を終了するとまたもとに戻すことによってきわめて柔軟な人事配置が可能であった。この点、「軍令承行令」によって、指揮権について先任、後任の序列を頑なに守った硬直的な日本海軍と対照的である。米軍の人事配置システムは、官僚制が持つ状況変化への適応力の低下という欠陥を是正し、ダイナミズムを注入することに成功したのである。
属人的な組織の統合
近代的な大規模作戦を計画し、実施するためには、陸・海・空の兵力を統合し、その一貫性、整合性を確保しなければならない。
結局、日本軍が陸海軍共通の作戦計画として策定したのは、昭和二〇年一月二〇日決定の「帝国陸海軍作戦大網」が最初であった。
*なぜ「帝国軍」ではないのか。分裂の極み、統帥権が機能していない。
学習を軽視した組織
およそ日本軍には、失敗のというべき蓄積・伝播を組織的に行うリーダーシップもシステムも欠如していたというべきである。
「百発百中の砲一門、よく百発一中の砲百門を制す」(日本海海戦直後の東郷司令長官の訓示)
失敗した戦法、戦術、戦略を分析し、その改善策を探求し、それを組織の他の部分へも伝播していくということは驚くほど実行されなかった。
大東亜戦争中一貫して日本軍は学習を怠った組織であった。
……米第三艦隊参謀長ロバート・B・カー二―少将はレイテ島攻略を前にして次のように語った。
「どんな計画にも理論がなければならない。理論と思想にもとづかないプランや作戦は、女性のヒステリー声と同じく、多少の空気の振動以外には、具体的な効果を与えることはできない。」
(陸軍士官学校・海軍兵学校の)学生にとって、問題はたえず、教科書や教官から与えられるものであって、目的や目標自体を創造したり、変革することはほとんど求められなかったし、また許容もされなかった。
海軍の用語に、「前動続行」という言葉がある。これは、作戦遂行において従来通りの行動をとり続けるという戦闘上の概念であるが、まさに日本軍全体が、状況が変化しているにもかかわらず「前動続行」を繰り返しつつあった。
しかし、本来学習とはその段階にとどまるものではない。必要に応じて、目標や問題の基本構造そのものをも再定義し変革するという、よりダイナミックなプロセスが存在する。組織が長期的に環境に適応していくためには、自己の行動をたえず変化する現実に照らして修正し、さらに進んで、学習する主体としての自己自体をつくり変えていくという自己革新的ないし自己超越的な行動を含んだ「ダブル・ループ学習(double loop learning)」が不可欠である。日本軍は、この点で決定的な欠陥を持っていたといえる。
第六軍司令官は、辻参謀が勝手に第一線に行って部隊を指揮したりしたのは軍紀をみだす行為であって、責任をとって予備役に編入させるべきだと強く主張した。また、陸軍省人事局長も、この見解を支持した。しかし、参謀人事を掌握する参謀本部総務部長は、将来有用な人物として現役に残す処置をとった。
にもかかわらず、日本軍はその責任を問おうとしなかった。ノモンハンの事例に見られるように戦闘失敗の責任は、しばしば転勤という手段で解消された。
責任を問われなかった軍人たち
辻参謀・南雲長官・草鹿参謀長・福留中将・栗田長官……
三章 失敗の教訓――日本軍の失敗の本質と今日的課題
これら(失敗の)原因を総合していえることは、日本軍は、自らの戦略と組織をその環境にマッチさせることに失敗したということである。
零下三〇度になっても機能しうるようにつくられていた砲や機材は、高温多湿の熱帯では十分機能しなかったし、組織自体もアメリカ軍とジャングルを中心に展開する戦場にマッチしたものではなかったのである。(山本七平『一下級将校の見た帝国陸軍』)
……火力重視の米軍の合理主義に対し白兵重視のパラダイムを精神主義にまで高めていったのだろう。
一方、海軍の艦隊決戦主義は、日本古来の兵学を踏襲し、日本海海戦によって検証され、体系づけられた、といわれる。明治三八年の日本海海戦は、世界の海戦史上いまだかってない完全勝利であった。
日本軍は、米軍のように、陸・海・空の機能を一元的に管理する最高軍事組織としての統合参謀本部を持たなかった。
明治以来、陸軍はソ連を仮想敵国とほぼ限定し、作戦用兵は北満の原野を予想戦場とする大陸作戦に偏っていた。
一方海軍では、米海軍を仮想敵とし、戦艦軍を中心に輪形陣で太平洋を西進してくる米艦隊の遊撃を想定した。
これに対して日本軍は、大本営という統合部門を持ちながら、強力な統合機能を欠いたために、陸軍はソ連―白兵主義、海軍は米国―艦隊決戦主義という目標志向性の差を最後まで調整することができなかった。
それらの人びと(実務的陸軍の将校と理数系に強い海軍将校)がオリジナリティを奨励するよりは、暗記と記憶力を強調した教育システムを通じて養成されたということである。
組織は学習しながら進化していく。つまり、組織はその成果を通じて既存の知識の強化、修正あるいは棄却と新知識の獲得を行っていく。組織学習(organizational learning)とは、組織の行為とその結果との間の因果関係についての知識を、強化あるいは変化させる組織内部のプロセスである、と定義される。
学習棄却
より情緒的陸軍
既述のように組織が絶えず内部でゆらぎ続け、ゆらぎが内部で増幅され一定のクリティカル・ポイントを超えれば、システムは不安定域を超えて新しい構造へ飛躍する。そのためには斬新的変化だけでは十分でなく、ときには突然変異のような突発的な変化が必要である。したがって、進化は、創造的破壊を伴う「自己超越」現象でもある。
ガダルカナル戦では、海兵隊員が戦争のあい間にテニスをするのを見て辻政信は驚いたといわれている。
これに対して、日本軍には、悲壮感が強く余裕や遊びの精神がなかった。
およそイノベーション(革新)は、異質なヒト、情報、偶然を取り込むところに始まる。官僚制とは、あらゆる異端・偶然の要素を徹底的に排除した組織構造である。日本軍は異端を嫌った。
日本軍の最大の失敗の本質は、特定の戦略原型に徹底的に適応しすぎて学習棄却ができず自己革新能力を失ってしまった、ということであった。
日本軍が特定のパラダイムに固執し、環境変化への適応能力を失った点は、「革新的」といわれる一部政党や報道機関にそのまま継承されているようである。すべての事象を特定の信奉するパラダイムのみで一元的に解釈し、そのパラダイムで説明できない現象をすべて捨象する頑なさは、まさに適応しすぎて特殊化した日本軍を見ているようですらある。さらに行政官庁についていえば、タテ割りの独立した省庁が割拠し日本軍同様統合機能を欠いている。
事実、戦後の日本経済の奇跡を担ったのは復員将兵を中心とする世代であり、彼らが「天皇戦士」から「産業戦士」への自己否定的転身の過程で日本的経営システムをつくり上げたという指摘もある。(中村忠一『戦後民主主義の経営学』)問われているのである。
日本的企業組織も、新たな環境変化に対応するために、自己革新能力を創造できるかどうかが問われているのである。
文庫版あとがき
このような自己革新組織の本質は、自己と世界に関する新たな認識枠組みを作り出すこと、すなわち概念の創造にある。しかしながら、既成の秩序を自ら解体したり既存の組み替えたりして、新たな概念を作り出すことは、われわれの最も苦手とするところであった。日本軍のエリートには、教義の現場主義を超えた形而上的思考が脆弱で、普遍的な概念の創造とその操作化できる者は殆どいなかったといわれる所以である。
自らの依って立つ「概念」についての自覚が希薄だからこそ、いま行っていることが何なのかということの意味がわからないままに、バターン化された「模範解答」の繰り返しに終始する。それゆえ、戦略策定を誤った場合でもその誤りを的確に認識できず、責任の所在が不明なままに、フィードバックと反省による知の積み上げができないのである。その結果、自己否定的学習、すなわちもはや無用もしくは有害となってしまった知識の棄却ができなくなる。過剰適応、過剰学習とはこれにほかならなかった。
日露戦争から三六年後の一九四一年、わが国は既存の国際秩序に対して独自のグランド・デザインを描こうとする試みを開始した。そして、三年八ヵ月の失敗の検証をへて、この試みは挫折した。これによって、日露戦争によって獲得した国際社会の主要メンバーとしての資格と地位をすべて喪失した。
企業をはじめわが国のあらゆる領域の組織は、主体的に独自の概念を構想し、フロンティアに挑戦し、新たな時代を切り開くことができるかということ、すなわち自己革新組織としての能力を問われている。
平成三年七月 執筆者一同
*平成二十九年四月十四日抜粋終了。
*日本人は「形而上的思考が脆弱」、すなわち哲学していないのである。
*抜粋者は一九四一年八月生まれ、こんなことが行われていたとは露知らずであった。
 いらっしゃいませ! 以下のキ-ワ-ドをコピペして、右サイドの「このブログ内で」検索をお楽しみください。→ DB DC 年金カウンセリング 若い人 年金カウンセラ- 日本版401k 勝手格付け 確定給付 運用 確定拠出 年金履歴書 もらい損ね年金 基金広報誌 年金図表 401k調査旅行 アセット・ミックス 年金証書 イリノイ大学ブリーフ 年金の行方 組織 受託者責任 厚生年金基金アーカイブ 分散投資 フリ-ランス 代行返上 基金解散 企業年金連合会 業務分掌表 主婦 事例 iDeCo 年金eBook ポ-トフォリオ 加入員台帳 年金手帳 利差益 年金支給開始 年金のキホン 年金の加入記録 年金の仕組み 年金の請求 年金生活 ROE投資 老後 自分年金 年金加入歴 事例で学ぶ アメリカ年金 年金加入期間 加給年金 素材抜粋 読書 国民年金 厚生年金 厚生年金基金 GPIF PDF
もらい損ね企業年金 惚けた遊び …… 外に、あなたの年金フレーズ、キィワ-ド、疑問点を検索してみてください。必ず、お役に立ちます! ご訪問、ありがとうございます。先ずはお楽しみください。
いらっしゃいませ! 以下のキ-ワ-ドをコピペして、右サイドの「このブログ内で」検索をお楽しみください。→ DB DC 年金カウンセリング 若い人 年金カウンセラ- 日本版401k 勝手格付け 確定給付 運用 確定拠出 年金履歴書 もらい損ね年金 基金広報誌 年金図表 401k調査旅行 アセット・ミックス 年金証書 イリノイ大学ブリーフ 年金の行方 組織 受託者責任 厚生年金基金アーカイブ 分散投資 フリ-ランス 代行返上 基金解散 企業年金連合会 業務分掌表 主婦 事例 iDeCo 年金eBook ポ-トフォリオ 加入員台帳 年金手帳 利差益 年金支給開始 年金のキホン 年金の加入記録 年金の仕組み 年金の請求 年金生活 ROE投資 老後 自分年金 年金加入歴 事例で学ぶ アメリカ年金 年金加入期間 加給年金 素材抜粋 読書 国民年金 厚生年金 厚生年金基金 GPIF PDF
もらい損ね企業年金 惚けた遊び …… 外に、あなたの年金フレーズ、キィワ-ド、疑問点を検索してみてください。必ず、お役に立ちます! ご訪問、ありがとうございます。先ずはお楽しみください。










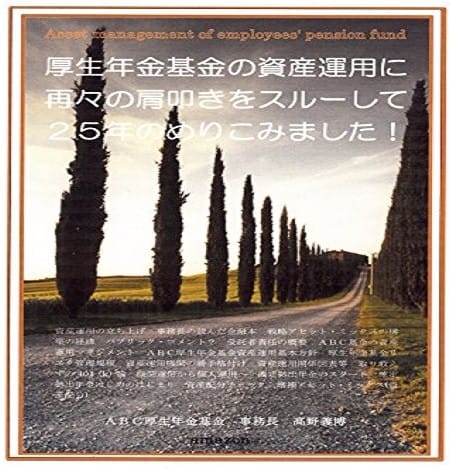




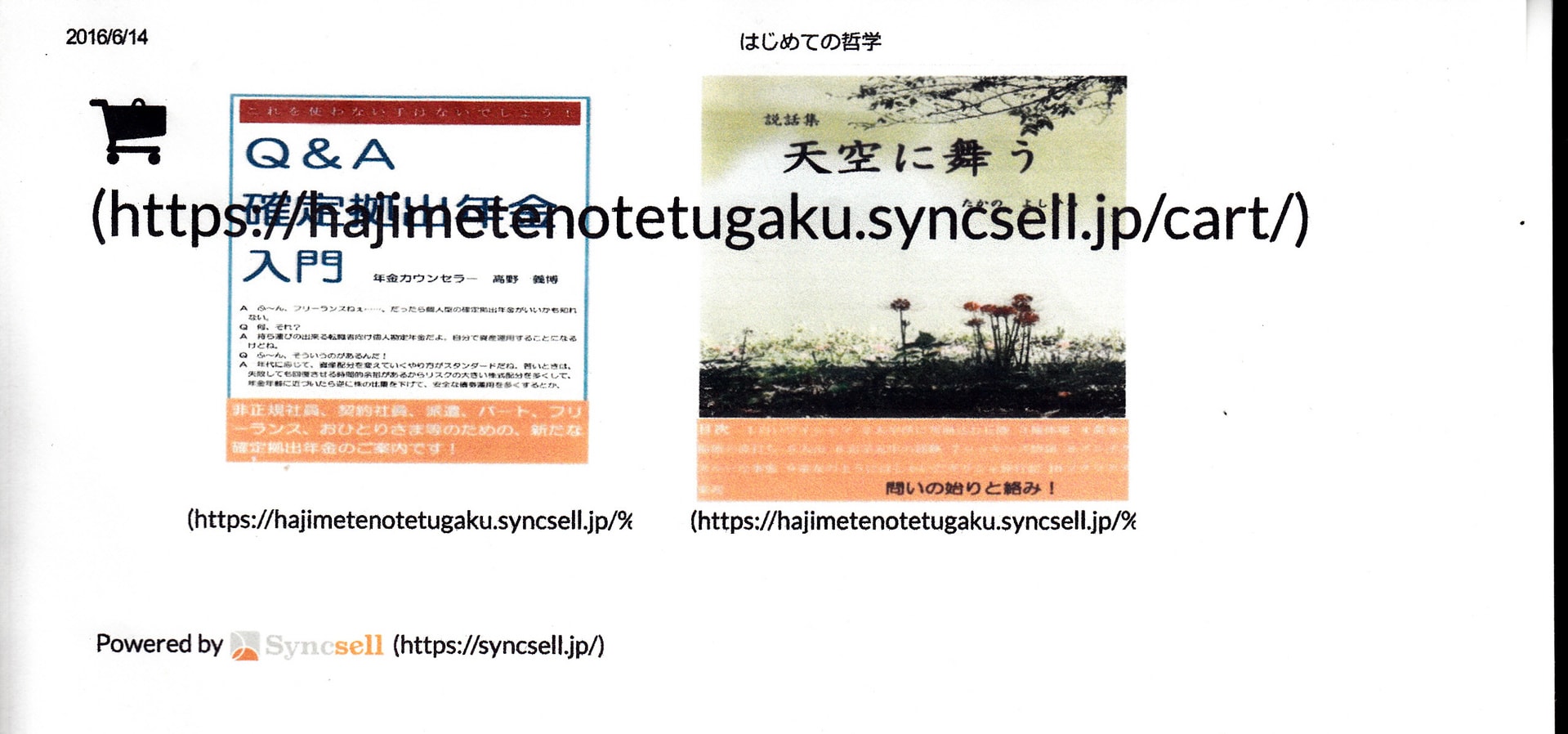









 みんなの年金・基本のキ・10問です! →
みんなの年金・基本のキ・10問です! →

