
「暗号について」を改訂しました。改訂部分は以下の通りです。
飯島宗享著『気分の哲学』毎日新聞社 昭和45年3月発行
以下にP.22~P.27抜粋
(P.22)
自己意識の成立とか、自意識の誕生とか、自我の自覚とか言われるあの経験のことだ。その最初の経験とそのときの気分を、鮮度をおとさずに確保しておくことが、これからの話の基盤として大事なことは、もちろんきみにも理解できるだろうね。
自我のめざめと断絶感
B 言われてみると、なるほど、アナムネーゼよりその方が先に思いつかれていいことだったように思われます。生まれてから初めての経験だったし、今から思うと、あの時を境にして子供から大人の他界に足を踏み入れたような気がするんですが、実際、あの時は驚いたのなんの、一瞬にして世界がまるで変貌して、波が退いていくように、にわかに何もかもが自分からドンドン、ドンドン離れていって、わおっと叫んだおぼえがあります。自分だけがひとりぼっちに収り残されたのか、自分が突然まるであのカフカの『変身』のように甲虫か何かに変ってしまったのか、直面までの自分とちかって、何もかもが、自分以外の何もかもが、まるで自分と縁どおいものになってしまっているんで、異様だったな。それに、いきなりでしょう。体か浮くって形容がありますけど、心が宙に浮いたようで、全然とりとめがなくって、気がついたら、ひどく心ぼそくて、
(P.23)
それから無性に恐くなって、駆け出したっけ。
A よくおぼえてるね。ぼくもおぼえてるけど、そのときの気分の記憶があざやかなほど、情景の記憶ははっきりしない。大きなショックだったから、そんなときは心象の風景としての気分の方に気を奪われて、目や耳が受け取ったものは上の空になるらしいよ。だが、あのショックの経験は話してみると誰でも忘れられないものとして、ちゃんとおぼえているようだね。ぼくは、その当時、中学生だったわけだが、好んで散歩にいく丘の林のなかに、展望のきく草原があって、そこに腰をおろして、町の家並や木々の頭越しに有明海の海を眺めてるときのことだったな。こまごましたことは、あとから考えるとわかるけれども、その瞬間の印象としては残っていない。
B ぼくも、そのときの記憶はありますが、凪景はそれほどはっきりしてないですね。子供のころ、家族がふと他人に思えるような瞬問があったり、自分の手足が自分とは無関係の棒ぎれにみえたり、またそれに類する経験がありましたけど、それは何かの錯覚たろうと思っていた。だから、あの体験もなにか不思議なことだくらいにしか思われなかったですね。ただ、地方から東京にやってきて、国電の中だったか、そのときは別で、何かあるなと思った。
A なんだ、つまらない面がぼくと似てるんだな。心象の風景といっしょに物象の風景も、きみから聞かせてもらえるかと思ったのに。……だけどね、そのときの光景をまざまざと記憶している人も、案外、たくさんいるらしくて、いつだったか学生の卒業論文を見ていたら、そのなかの
(P.24)
一人がこの経験について実に鮮明な印象を記している一節があったんで、論文そのものはみんな学生に返しだけど、その箇所だけは写しをとって、しまっといたんだ。どこか、そこらにあるはずだから、見てみよう。……これですがね、そう、いい機会だから、披露しておこう。こういう文章なんだ―
「ある事件が十三歳の時、校庭で起きた。晩秋のある晴れた日、私は昼食後の満腹感で校庭を歩いていた。他の中学生たちは、校庭で遊んでいた、すると急に、風の音と彼らの遊び声が、ボリュームを落とし、あたりが静まり、私は白いワイシャツが風に揺れているさまを見つづけていた。それは風の強い日の旗のように、バタバタと音をたてていた。その衣服の白さと、バタバタという音だけに、私の意識は集中された。その時、ひどい孤独とともに私は叫んだ。――ああ! 彼らも人間だ、と。その白さ、バタバタという音は、私の意識に他人としてそこに〈ある〉という感じを、たたきつけた。」(この一文は高野義博君のもの)
B なんだか、あんまりうまく表現されて、整いすぎて、まさにそうだという気もちといっしょに、そうだと思うとたんに、ほんとにそうだっただろうか、なにか、経験とズレがあるんじゃないか、という気もしますが……
A 今は言葉が信用できなくなった時代だと言われるが、ほんとにそうだと思う言葉に出あったときほど、待てよ、これは眉に唾をつけて吟味する必要かおるのではないかと、警戒してかかる
(P.25)
心理が、きみにそんな気をおこさせるんでしょうね。しかし、言葉の問題はどうせあとで話題になるだろうけど、だいたい、言葉と経験とはズレてるのが建前で、ズレがあるからこそ、それを埋めようとして言葉が重ねられたり、作られたりもするんだと、考えておかなきゃならんだろうね。ズレ方はさまざまだし、それに応じて人間のさまざまなあり方かあり、それにともなう気分もあるというわけだ。経験は経験であって、結局のところは、言葉になりきれないんだ。「経験の言葉」なんて言ってみたって、私の経験という私に固有の具休的で、その限りで一回的な、個別的なものを、言葉という抽象的で、普遍的で、だからこそ共同性の媒体にもなりうるものに、移しこんで伝えようとしても、それは悲願にとどまって、その願いゆえの努力が大事なものを作り出すにはしても、願いそのものの完全な実現は、ないんだな。人間の孤独なんてことが、心の深いところで誰にもつぶやかれるのも、そのためだろう。交わりのための言葉は、みんな嘘ッパチで、だから、言葉らしい意味のある言葉といえば、せいぜい、自分ひとりの場でのモノローグ(独白)ぐらいで、それしか信じられないと言ってみても、その独り言だって、自分の経験とのあいだには、たいへんな距離があると気づくものだ。
B たしかに、さっきの高野さんの文章でしたか、あの文章を聞かせてもらって、その時は経験とのズレみたいなものを感じたのですが、考えてみると、ぼくがぼくの経験を記録してみても、記録されて言葉になったとたんに、ぼくはやっぱり同じことを感じるだろう、という気がしてき
(P.26)
ました。経験と言葉とのあいだには埋めようのない溝があると覚悟してかかれ、なんて言われると、抵抗を感じて、そのことはそれとして適当な機会にまた持ち出したいと思いますが、Aさんに言いくるめられたというのではなしに、率直に考えて、やはり高野さんの記録は、的確な表現として高く評価したいです。
A 彼の場合も、もちろん、その体験は現在の彼の意識と言葉で顧みられて、文章に定着されているわけだ。それから数年たった今、彼にもういちど書いてもらったら、彼の今の関心や言葉を反映するような、別の衷現になることは否めないだろうね。けれども、これを書いた当時の高野君は、キルケゴールだのヤスパースだのサルトルだのといった思想家のことを噛っていたわけだから、その影響は彼の表現のうちにあるだろうけど、この表現のうちには、十三歳の経験当時にも現在にも通じる本質的に不変なものが出ていると思う。つまり、その瞬間においては、他の人も他の物も、自分と自分でないものとの隔絶の大きさにくらべれば、それらの間の個々の差が意識から落ちていくほど、もっぱら自分と他者との断絶感だけが自分の手もとにあった、ということだ。十三歳の経験当時だと、きみの言葉を借りると「心が宙に浮いたようで、とりとめなく、心ぼそく、怖かった」というような気分が圧倒的で、その意味を考えたりするよりも、まずは周章狼狽、恐慌状態ですよね。他者の存在の自覚とか、自我とか、それら二つの自覚の同時的成立とか、そんな意味づけをともなった理解は、あとのこと、少なくともその経験に反省を加えるだ
(P.27)
けの余裕をとりもどしてからのことですね。その後、自分でもそれに類する経験を重ねたり、他人にも同様な経験があることを知ったりするうちに、非日常的で異様な特別の出来事ではあるにしても、自分がそのために狂人でも天才でもあるわけではなく、むしろ普通の人間なのだということの証拠でさえあり、そういうものとして「人間」を理解するようになっていくのだけれども、初経験のときは、たいへんですよね。
思春期の「情動不穏」
B ひところ、「情動不穏」なんて言葉が電車のなかの吊り下げ広告や新聞広告などでしきりに目について、辞典を引かなくても、何かものものしい言葉の意味まで、ちゃんとその広告のなかに説明してあったものですが、要するに、いらいらするとか、気もちが集中しないとか、ふっと心がどこかへいってしまうとか、かなりひどい心理的な不安定さを、現代の成人病として印象づけて、その神経症状をノイローゼにまでしないために、そして人間蒸発の予防にもなりますよって調子で、精神安定剤、といっても鎮静剤のたぐいでしょうが、トラソキライザーの広告宣伝がこの言葉を使ってましたが、おぼえていらっしゃいますか。
高野義博著『述語は永遠に……』書出し部分
ベルだ、ベルだ、出て行ってしまうぞ、「新幹線ひかり」、畜生奴、飛乗らにゃあ。痛い! 何だ、彼奴は、人の足蹴っ飛ばしておいて、どんザラ奴! 痛い、痛いぞ、畜生。今になって痛くなってきた、唾付けとこうか……何処へ行った? ああ、彼奴か? ガラス越しの口吻だ。何とかの遊び、だ。ここは何号車だろう? 鳴り始めと同じ音量のはずなのに……びっくりさせやがったなあ、ドスでも刺されたみたいだった。暑いなあ! チェッ、心理学か、気を遣いすぎる駅員奴、ボリュームをいっぱいにしておいてスィッチを入れやがったな……そうしておいて、気づかれない位ずつ下げていくんだろう。ボリュームを握っている触覚、ベルの音量を聴いている耳、気遣い心、お役目ご苦労さん……じゃないね。スピーカを通しているんじゃないから。直だもの、「物そのもの」というわけだ。……とすると、こちらの耳の所為か、「聞く耳、持たん者は聞け」か、もう一つ、「つんぼにゃあ、聞こえぬ」と、……しかも、ベートーベェンは聴いた、と……。混んでいるなぁ、ここは……ううん、いい匂い! コーヒーも欲しいけど腹も……。何時だろうなあ……昼飯だなあ。先に食っとくか……でも、いっぱいだろうなあ……後にしようか。四号車なのか。皆座って……る、ああ、あそこ二つとも。ちょうどいいや、後ろ向きだ、おっ、危ない。揺れる、揺れる、こん畜生! うん? 今、何て言った? ……「畜生! 」運転手に言ったつもりなのか、この列車に言ったのか。おっと又々。十返舎一九は狂歌を吟じながらの二人連れを東海道に泳がせ、もちろん二本足だったが……私はここに座って……最後の列の……Dか、じゃないE席だ、ああ、いい席だ、お誂えだ、一人になれる……
肉が痙攣したのを機に、針を刺されたような激痛が走り、ガバッと跳ね起きようとしたが……身動きも出来ない重さで押さえつけられ、潰されそうになっている自分に、まるで過去を一巡りしてきたかのように気がついた。ウンウン唸ってその重いものを跳ね除けようとするのだが、手も足も硬直したみたいに意のままにならない。うなされてでもいたのだろうか。切れ切れの呻き声のような谺が記憶の網に引っ掛かって震えていた。それは有るとも無いともはっきりしないほんの幽かな想い出のよう……しかし、その更に奥まったところには、自分が気のつく前の、夢の記憶のような暗黒の大陸が黒々と横たわっているのが感じられたし、意識の轍を見失う遙か彼方に燎原の火の、残り火のようなものがチョロチョロと燃えているのがはっきり望めた。しかし、大腿部の破けるような痛みと胸から肩にかけての引きつるような痛みに加えて軀の何処か、場所のはっきりしない遠方の地、これと名指せない多義的な地点、心の内科的辺境に、何か尋常とは異なった特殊な痛み、というか……感覚、いや、自我の放棄され尽くした後の、為されるがままの、決壊中の堤防の心地。形式から内容の抜け出してしまった後の、蝉の抜け殻のような半透明な白々しさがあって、死に行く者が手の届かない所へ行ってしまったりこの世へと再び上がって来たりしているかのように、ある境界を彷徨っていた。
蜥蜴の緑や紫に入り交じる切り離された尻尾が時々引きつりを起こしてピクピクッと生き返るように、痛みが暗黒の大陸と燎原の火の方へのめり込みそうな私を目の前の現実へと引き戻していた。相手を抱き込む仕儀になっていた私の両手は痩せ猫の背を、濡れたその背を撫でたときの感覚……そのゾオッとする気味悪さを離すに離せぬままであった。痛みは鉄の爪でも立てられたよう……少しでも軀を動かせば、動かしただけ食い込み……そこから血がゾロゾロと垂れ流れ……既に、私は血の海に横たわっていた。ベットリした血の流れがゆっくりと暖かい臭気を発して鼻を抜けていった。そうして、ついに、私が目にしたのは……ピューマのような……あるいは豹のような、いや、虎のようにしなやかな、そう、ゆったりと構えていて虎かもしれない。何かそういう猫の縁者、猫科の動物。……その虎とおぼしきものがしっかと私の上に覆い被さり、鋼の爪を胸の上に突き立て、そのしっとりとした三叉の口は胃の辺りの臭いを嗅ぎながら鼻をピクピク……させて……狙っていた、が……? ……風がふっと切れたかのように、ふと、私はある疑問に取り付かれてしまった。……そんなはずはないと、よく見れば見るほど疑問であったものは徐々に確信に変わらざるを得なかった。そ、そんなはずはないのだが、……その虎とおぼしきものの仕草や視線の置き具合が……どことなく……この私自身に似ているのを驚き呆れながら発見したのだ。な、なんということだ……。
(以下略)
高野義博著『情緒の力業』第一章
第一章〈現実〉の出現
序 志学元年の経験
一般に、我々は孔子の言うように「十有五にして学に志す」と言われている。自ら意識的に学び始めるというこの志学の年、十五歳説は前後二、三年のズレはあっても客観的な事実として現代の実証的な心理学者もつとに認めているところである。
これに関して、W・ジェイムズは次のように言っている。我々は、「普通十四歳から十七歳までに」「自分は未完成であり不完全であるという感じ、思案、意気阻喪、病的な内省、罪悪感、来世に対する不安、懐疑の悲しみ」等々の強い印象を残す経験をする、と。
また、E・ミンコフスキーは、これを次のように述べている。「思春期は、それまでまどろんでいた力の荒々しい目覚めによって、単に幼少年期から成年期への移行期であるだけではなく、われわれの前に一つの生、つまりわれわれの生の展望を開きながら、われわれのうちでの〈人間〉への目覚めの時期ともなっている」のであると。つまり、俗に反抗期とか自意識の誕生とか言われるこの経験は少年期特有の経験なのである。
この経験は外部世界の不意の登場によってもたらされる、という点に特徴がある。というのも、それまで〈見て見ず〉であった事象を誕生以来初めて意識を伴って、〈それ〉として〈そこ〉に見始めるのであるから。この新たな目、つまり意識を伴った目で万事万象を見始めることを指して、孔子は〈志学〉と言ったものと思われるのである。
ところで、昔から、このような特異な経験をする端境期の少年を対象にして地上のあらゆる地方に、その土地特有の大人の仲間入りを儀式化した人会式・イニシエイションが数多く執り行われているし行われていた。これは、この時期の少年のこの特有な経験に注目し、それを日常的な事件にしてしまわないため特異性を更に展開するために儀式化し、そこに教育的な配慮をこめた先人の知恵の成果なのである。
しかし現代では、この儀式は影が薄くなり村落や共同体の導きは無くなり、先達は呆けてしまい、少年達は自ら一人一人が試行錯誤を繰り返しながら孤立した環境のなかで学びとって行かなければならないような状況に放り出されているのである。
一 志学以前
この志学以前、人は世界と一体になってその生成変化のままに生きているのである。そこは、身の回り全てが親密な具体的事象だけで構成されている、ごく限られた個性的な空間である。
その世界は、人が〈見て見ず〉のままにその都度その都度一回限りの具体的な環境を素早く完全燃焼して直に生きている充実空間である。また、自他の区別のない同体融合している混濁状態であり、神秘的な共存感、神聖血縁的な連なりによって意味深い生命感に溢れた関係で構成されているのである。その生の場は〈活発な安らぎ〉という形容矛盾の許容される永続状態であって、そこだけで足りていて知ろうとしないのである。
このように、その生の場は風習、習慣、伝統等によって形作られ、それらの影響力が絶対の力を発揮するのである。それらが生の基盤を構成し、それらがその人の生き方を方向付けてしまうのである。つまり、世界を意識的に己が意志の下に構成するのではなく、むしろ、己が意志をそれらへの順応のために晒すのであり、そうするようにあらゆる場面が仕組まれているのである。意志が働く余地が無い程それらが振るう力は絶大であって、意志はそれらの内的な世界に限定されてしか生きる道は無いのである。それらは、感受性も事の運び方も物への対処の仕方をも支配決定し、人格にある独特な資質を形成するのである。
この資質に関して、W・ハイゼンベルクはある講演で、次のように語ったという。「この前の大戦以来、日本からもたらされた理論物理学への大きな科学的貢献は、極東の伝統における哲学的思想と量子論の哲学的実体の間に、なんらかの関係があることを示しているのではあるまいか。今世紀の始め頃にヨーロッパでまだ広く行われていた素朴な唯物的な思考法を通ってこなかった人達の方が、量子論的なリアリティの概念に適応することがかえって容易であるのかもしれない」と。
また、J・P・サルトルの小説の主人公ロカンタンが存在の不安に怯えて嘔吐することについて、イスラーム哲学者井筒俊彦が次のように言って、西洋人と東洋人の生き方の背景を説明してこの資質の違いに触れている。「仏教的表現を使って言うなら、世俗諦的意識の働きに慣れ、世俗諦的立場に身を置き、世俗諦的にしかものを見ることの出来ない人は、たまたま勝義諦的事態に触れることがあっても、それだけの準備が出来てないからそこにただ何か得体の知れない、ぶよぶよした淫らな裸の塊しか見ないのである」
要するに、対象的・文節的に把握仕切れないその不気味な塊を前にして、ロカンタンは精神的失禁、すなわち吐いてしまうのである。「これに反して、東洋の精神的伝統では〈嘔吐〉に追い込まれはしない」(同)
確かに日本の場合、ロカンタンのように肉体的生理的嘔吐発作が起きようがないように唯心的精神土壌が生活全般を包み論理が唯心的に構造化されていると言えるだろう。それは、例えば日本のいろんな職人衆の生き方に見られるように、〈一つの仕事〉の完成を目指す為に全てがその王道に沿って構造化されている生き方を強いられる伝統的な生活にも現れている。
心理学者A・マズローはこれを次のように言っている。「日本映画「生きる」に見られるような(……)仕事によって自己実現をするということは同時に、自我の追及と満足を得ることであり、また真の自我ともいうべき無我に到達することである」と。
このような生活基盤の伝統の中に生きている我々が身辺を見回し、人生の意味を尋ね始めるきっかけとなる〈志学〉の経験をしたときに、伝統や環境が効果的に作勤しないで精神のバランスを失ったとしても、また、時代と共に徐々に効果が薄れているとはいえその基盤までは侵されていない唯心的土壌の大いなる手の内に保護されていることには変わりがない。そのため、ロカンタンのように嘔吐をする者は少ないだろうが、無我に到達するための長い試行錯誤を余儀無くされる者は多いだろう。己が意志により作り上げた明確な線を示す生き方ではなく、傍目にはどっちつかずの生き方をする者がである。というのも、「革新者」は伝統の強力に叩きのめされ排除されるのである。むしろ、その叩きに自分を晒すことこそ求められるのである。
それというのも、我々の生きている日本の生活空間はなんといっても概念的な曖昧さが漂う唯心的土壌であり、概念以前の集団表象の残響に関わる世界であるからである。
この辺りの事情について、現代の小説家辻邦生は次のように言っている。「われわれの国上は、かつて共同体的な集団表象のなかでは、民族と同体化した神聖血縁的な上地であり、民族の父祖、神々、英雄がそこにつねに生きつづけた。われわれと国土との間には(……)意味深い生命にあふれた関係が存在していた」と。
唯心的・精神主義的戦術で今次世界大戦で大敗を喫し、それまでの神聖血縁的な融即一体的な生き方から集団表象の無力に目覚め民主主義という概念的に明確な科学的生き方の導入を企り〈第二の開国〉をせざるを得なかった日本は、今、また、無機化していく生活の風化に晒されて意味の欠如した無限空転を続けているのである。
我々は以下にこの〈志学元年〉である経験を経て、〈現実〉がどのように出現してくるのか、時代の状況がどのように我々一人一人に絡まってくるのか、その構造を探ってみたいと考えるのである。つまり、融即的土壌に科学的方法はどのように根付こうとしているのか、それがどういう浮き草状態を呈しているのか、どのような問題を抱えているのか、どのようにしたらこの難問を突破出来るのかを人間の内面の心理的葛藤の場に見ていこうというのである。
二 志学の経験
我々は誕生に次ぐ幼児期・少年期を環境や伝統の大いなる手に保護育成されて過ごし、その時代特有の教育・倫理・道徳・宗教・価値観等の形成する方向に導かれるのである。ということは、社会の志向する心性に幼い心は造型されて、その心性の絶対性のなかで融即的な強い関連で結ばれた世界に生きるのである。「われわれはこれまで聞き方を学んだことのないものは聞かないのです」(J・ラカン)という排除と独断によって形成された一宇宙を作りあげるのである。
その生々流転して止まぬ生にすっかり自動対応して、止どまることを知らずに生きていくこの世界は一面幸福な世界ではある。そこだけで足りているのであれば。しかし、世の中に変わらないものは無いのだし、追っ付けそこには変化の兆しが現れるのである。
その世界に破綻が生ずるのが、つまり有機的関連で強く結ばれていたものに疑わしさが付着し始めるのが、先に触れた〈志学元年〉の経験である。
それは、ツルゲーネフが『ハムレット』から引用しているように、
この心が主になって
自分の選択を支配し
人々を区別することを
覚えた時から
始まるのであり、有機的関連で結ばれていたものの間に区別を設け、融即的なものを分離し客観化して、意味深い関係を排除し抜き去った〈対象〉として、そこに据置き初めてからである。
それもこれもみな、不意に登場した外部世界のために、世界を問うはめに陥ったので、かような事態に投げこまれるのである。
先にも触れたように、この〈志学〉の年の経験は一応誰でも少年期の十五歳前後に経験するもののようである。ただ、人によってその印象が強かったり弱かったりするようである。同じような経験をした者が他人のその経験の話を聞き、又は本の中でそういう場面に出会ったときに、記憶の底に眠っている忘れ果てていた己の経験に巡り合うということが間々あることである。それというのも、この経験が独特な経験であって少々不可思議な印象を残しはするが非日常的な経験であるため故意に抹殺され無視されるからである。
ところが、この経験の印象の強い者は大変なショックを受けるのである。その突然の襲来と有無を言わせぬ強烈さで、まるで何か名付けようのない巨大なものに鷲掴みにされ、右に左に引きずり回されるような驚天動地な経験であり、心の中で何かが爆発でもしたかのように爆風が駆け巡り、 情緒が動転して一大活劇を演じるのである。このような大きなショックを受けた者にとって、世界は判断対象となり一大疑問符となってしまうのである。
一方、記憶の底に沈んでしまう程度のショックである者には、伝統的な形式の大いなる手の保護力が有効に働き、その瞬間的経験は無かったかのように忘れ去られるのである。
この後者については、その受容の構造、意志や知性の客観性がどう組み立てられているのか、興味のあるところではあるが、当面ここで問題にしたいのは前者、大きなショックを受け呆然自失となる者の経験である。
さて、この経験について著者はかって次のように書いたことがある。
ある事件が十三歳の時、校庭で起きた。晩秋のある晴れた日、私は昼食後の満腹感で校庭を歩いていた。他の中学生達は、校庭で既に遊んでいた。すると急に、風の音と彼等の遊び声が、ボリュームを落とし、辺りが静まり、私は白いワイシャツが風に揺れているさまを見続けていた。それは風の強い日の旗のように、バタバタと音をたてていた。その衣服の白さと、バタバタという音だけに、私の意識は集中された。その時、ひどい孤独とともに私は叫んだ。
「――ああ、彼等も人間だ」と。
その白さ、バタバタという音は、私の意識に他人としてそこに〈ある〉という感じを、叩き付けた。
これは、彼等中学生も著者と同じように人間なのだということを著者の尊大さからその時初めて認めたということではなく、存在の事実として、客観的対象として、そこに彼等が居る事実を認めさせられたのである。第三人称である外部世界の不意の登場に立ち会ったのである。私と彼等との間の無限の間隔、つまり〈距離の感覚〉という奇妙な世界にいる自分に気がついたのである。
村上陽一郎は、この経験について次のように述べている。「その閃いたなにものかを今になって理屈付けてみれば、それは、彼と自分とは違う人間なのだ、という一種の距離感覚であったのだ。
しかし、別の観点からすれば、このように対象化して自我の前に据置くことこそ、ハムレットの言うように「この心が主になって」行う行為であるから尊大と言えばこれ程尊大な行為もないであろう。全宇宙をほとんど自身の内部に限定し、「幼年期の間は、もっとも直接的な必要や恐怖によるのでないかぎり、ぼくは外部世異にぼとんど関心を示さなかった」というM・レリスの言うような幼年期の尊大さに比べれば。
さて、〈志学元年〉の経験以後の世界で、我々は物象を目の前に据えて、繁々と見詰めるのであった。それというのも、世界が今までとは違った相貌を示したからなのであり、そこに見慣れぬものが不思議なものがざわめているので、視線を固定せざるを得ないのである。世界をそのあるがままの状態から無理矢理引き剥し、流動生成してやまぬものの一片を、あるいはその一面を、釘付けにして観察対象として固定せざるを得ないのである。すなわち、物象の〈対象化〉を計るのである。
「何だろう? あれらは」という前屈みの姿勢に、不意に登場した外部世界は解けぬパズルのまま謎となるしかないのである。疑問文ばかりが陸続と誕生し肥人化するのである。つまり「人生は生きるに値するか」、「人生の意味は何か」、「我々は何処から来、何処へ去るのか」、「世界を思いのままに動かしている何者かがいるのか」、「このような問いを発している、私とは何か」(鈴木大拙)等々。これらの問いは、突き詰めてみれば「実在の究極的意味の探求」(同)となるのではあるが、ここに重大な落とし穴があるのは後々になって初めて気が付くことである。というのも設問の「実在とは何か」という形式そのままに、回答も同じ形式――客観形式によることが前提されているのだし、強要されもするのである。
すなわち、これらの問いの根源の問い「私とは何か?」に対して「私は……である」という主語―述語形式による回答が待機しているのであり、さらにこの回答には述語の確定ということが前提されているのである。この前提は、意識ならびに言葉を使っての確定であるということを更に前提しているのである。
ところで、学説の別れるところではあるが意識の本来的資質は「志向性」であり、言葉のそれは「分節性」であろう。この両者が合いよって世界を呈示してくるのであるから、客観形式としての述語の確定は〈厳密さ〉をその旨とし、〈留まるを知らず〉がその本来の姿となるのであって、〈曖昧さと放棄〉こそこの問うという形式の絶対のタブーとなるのである。こうして我々は問いの無い融即的な状態から、志学の経験を経て不意に登場した外部世界について、問う羽目になるのである。
そこで、この問うという作業がどのようになされ、〈現実〉をどのように呼び出すのかを次に探つてみたいと考えるのである。
三〈現実〉の出現
世界に融即混在し得た状態に、突然、外部世界が登場し、見慣れぬ不思議なものに取り囲まれて、身の廻り一帯の全てについて問う羽目になってしまった者に、初めて〈現実〉が出現するのである。それ以前の問わない者にはここでいう〈現実〉は存在しない。有るのは生成流動してやまない奔放な生、有機的関連でがっしり構成された既成の価値観で完成されている生ばかりである。その生の形式はこのように論述すること自体が本来無意味なことである。なぜなら、停滞は何処にもないのだから。言葉が取り付くことの出来ない言葉以前の世界なのであるから。
本来滞りのない生に停滞をもたらし、〈現実〉を呼び出してしまう〈問うという作業〉は意識と言葉という鍬を使っての土壌の掘り起こしのことである。末開墾の土壌は見はるかす彼方まで広いるのであり、掘り起こされた土塊の数々が歯形も生々しく放り出されているのである。
そう、「処女地が犯された!」という暗く重い密やかな念がこの作業には常に付纏うのである。しかし、この心情に反して意識と言葉という鍬は〈厳密さ〉を旨として〈留まるを知らず〉に振り降ろされ続けるのである。末開墾の生成流動してやまぬ土壌は問いという鍬に振り起こされ客観性という白い腹を晒け出すのだ。跳ね回っていた魚も問いにこづかれてついにおとなしくなり対象という死体となるのである。
一般に意識とは名の無い物象を命名によって把握するところに生ずる主体の内的状態をいうのであり、名の無いところに〈対象〉を構成して、その構成物によって世界を知覚することをいうのである。生成流動してやまない渦雲状星団のホウボウたる流れをハムの輪切りのように切り取って目の前に据えることをいうのである。
ということは、意識はそこに対象を定立し得なければ意識ではないのであるから、意識が対象に向かう意気込みには存亡のかかった懸命なものがあるのである。
その志向性を旨とする意識によって名の無い物象は自我の前に対象として定立されて、AなりBなりの名を得るのである。名を得るとは、それをそれとして他の一切から分離、区別し、一定のものとして固定することである。つまり、分節を旨とする言葉によって、それと指定されるのであり、その言葉をもって世界の一端に組み込まれるのである。これが名の無い物象が人間の経験の世界に入って来るときの基本構造である。
問いの型式――意識と言葉によって〈現実〉がこのように人間の経験の中に出現してくるのに引き金となったのは言うまでもなく〈志学元年〉の経験であったが、この経験の成立条件として忘れてならないのが、問いを問う者白身の〈自我の目覚め〉という特別な事態である。〈志学元年〉の経験の成立、すなわち〈現実〉の出現、外部世界の登場は全面的にこの〈自我の目覚め〉によっているのである。
このような〈志学元年〉の経験によって我々はそれまでとはまったく異質の世界に入って行くことになるのだが、その世界は突然やってきてまったく動く気配を見せないのである。それは暴力的な訪れ方をして、以前の世界に取って替わって居すわり続ける不可逆な構造を持った事態なのである。
それでは、その〈自我の目覚め〉とはどういう事態であるのだろうか。〈目覚め〉というのだから、その前は微睡んでいたことになる。まず〈自我の微睡み〉という事態があり、次いで〈自我の目覚め〉いう事態が生じたのである。
〈自我の目覚め〉は言葉と意識による対象の定立であったが〈自我の微睡み〉はそういうもののない融即的な混在界のことであり、先天的な、ならびに後天的条件によって感受性の傾向、つまり質が方向付けられている準本能的事態である。自意識的判断によって選択された世界ではなく、先験的所与として既に与えられて存在する世界であって、解決すべき何もない、判断形成される主体的作業以前の事態を〈自我の微睡み〉というのである。
このような自我の微睡みの事態に、自我の目覚めは「突発的な出来事として、まるで用意のないところを奇襲されたように、自分が作りだしたのではなく、自分が襲われた思いがけぬハプ二ングとしてやってくるものだから、自分がそれに対して受け身であるだけに、その出来事は悩みでもあり不安でもあるという気分にともなわれてやってくる」(飯島宗享)のである。そして、従来までの基準であったものが疑わしくなり、「それ以前までの基準にあぐらをかいて、惰性的、習慣的にかまえていてはすまない状況がそこに生じている」(同)のである。
それは微睡みから目覚めに強制的にうながされることであり、というのも、それは「事件」として人を襲うからであるが、新たな基準によって自分と世界とをとりまとめなければならない問いを発している自分を発見するということである。それは空間と時間に関する外界、物象、事象等を己が意識野に連れ来たって〈見られる客体〉として目の前に据付作業をしている意志的な自分を発見することである。その自分が物を融即的事態から分離、分節して対象化するのである。「我」であり、「汝」である「もの」が出現し、〈過現未〉が切り取られ抽出されるのである。このように、〈自我の目覚め〉はその実、その裏に、〈他我の自覚〉を自我の中に生じさせることを含んでいるのであるが、それもこれも「我」が「汝」を「我」から引き離したものとして見詰めて問うからである。
問うということは、問う者を現実の外に置くこと、あるいは問う者と問われる者との分離を前提にしているのであるから、この問うという作業は倫理的証明の形において究明される概念的詮索、客観的な営為であり、知性の行為なのである。この知性の本来的な資質は〈厳密さ〉と〈留まるを知らず〉を旨とするので、次から次へと問いを生み出して、『述語は永遠に……』(拙著)溢れ続けて主語を満たすことはないのである。満たされない主語は宙ぶらりんのままの状態の打破を目指し、火急に回答を求めて〈述語捜し〉に奔走するのである。句点「。」のエンドマーク目掛けて主語―述語のコスモスを。
このように、出現した〈現実〉に対して自我は知性的に対応して、従来の融即的混在とは異次元の「我」と「汝」、「外界」と「内界」等の対立的な存在の次元に入って行くのである。外部世界に面した自我の対応は、その〈現実〉を目の前に捕まえようとするのであり、知性の網によって主語―述語構文の中に閉じ込めようと企るのである。その意識的な閉じ込めの体系が論理であり概念である。それは言葉により構築された理念であり観念である。
世界は一自我の中に、このように構築されて、これがあるがままの〈現実〉だとして自我によって呈示されるのである。ということは、自我は〈現実〉を統一する根拠であり、〈現実〉が成立する礎石なのである。
このようにして、外部世界の不意の登場の間に「自我」と〈現実〉という主観と客観が間を置かずに出現しているのである。それは融即的混在界では、主観・客観の分裂・分節とはならず両様の働きが団塊状で行われているのであった。それが、問いが生じたことによって、今までの所与の世界に対して自我の意志によって構想され得る反自然的な世界の可能性が誕生したのである。世界に対して意志的に立ち向かう素地が出来たということであると同時に、意識による開明が端緒に付いたということである。
我々は次に、この自我の意志によって構想される世界観の二つの基本構造、つまり客観性によるのと主観性によるのとを考えてみたいと思うのである。
Amazonで今のうちご覧ください。










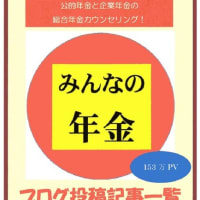






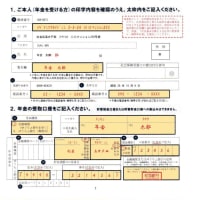

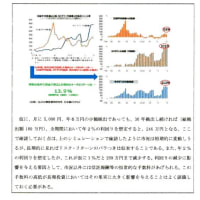
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます