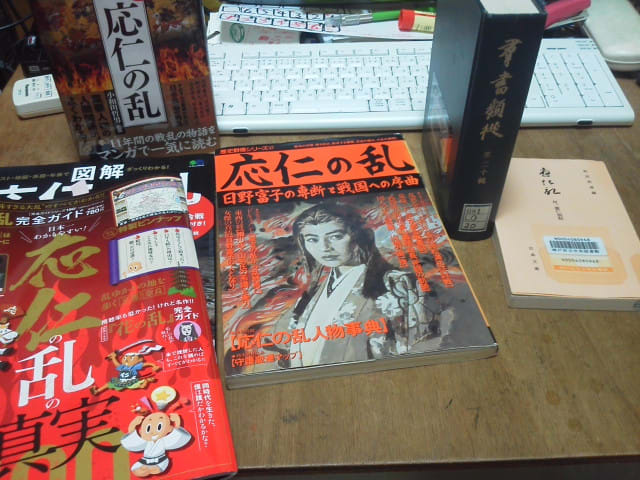
右から
・古典文庫版「応仁記(一巻本≒二巻本)」+「応仁別記」
・群書類従 第二十集 「応仁記(三巻本)」
・学研 歴史群像シリーズ37 応仁の乱(通称:学研の赤い本)
・応仁の乱 完全ガイド(晋遊舎)
・その下:図解 応仁の乱(枻出版社)
・奥:マンガ 応仁の乱(宝島社)
だいたい、右のほうが古い本です。
-----------------------------------
このうち、4つの本において、
応仁の時点で存命していない赤松貞村が応仁の戦場にいるのですが、(通称:ゾンビ貞村)
結論から言うと、
●「応仁記(一巻本≒二巻本)」+「応仁別記」が「応仁記(三巻本)」へとリミックスされる過程で、
たぶんあまり赤松家の事情に詳しくない編纂者が、
嘉吉の乱(1441)の赤松伊豆守=赤松貞村が、応仁の乱(1467)の赤松伊豆守(おそらくは貞村の息子・貞祐)でもあると混同してそう書きこんでしまった。
●学研の赤い本の作図者は、群書類従版「応仁記(三巻本)」を参照して作図した。
●「応仁の乱 完全ガイド(晋遊舎)」や、「図解 応仁の乱(枻出版社)」などの最近出ている関連本は、
学研の赤い本をそのまま参考にして戦況図を作っているので、エラーが継承されてしまった・・・
------------------------------------
<もすこし詳しく>
まず大前提として、赤松貞村は、応仁の乱のときには、すでに亡くなっています。
例として、wikipediaをコピペしますが、
死亡時期については、他の紙の本にも書かれています。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E6%9D%BE%E8%B2%9E%E6%9D%91
wikipediaは改訂されるかもしれないので、現時点での記事をコピペしますが・・・
嘉吉元年(1441年)6月24日に将軍義教が西洞院にある赤松邸で殺害された際、貞村も幕臣たちとともに参加していたのだが、
満祐の嫡子・赤松教康が足利義教を襲撃すると、その場から逃げ出した。
後に幕府軍が満祐を討伐する際、貞村は細川持常が指揮する幕府大手軍に加わったのだが、目ぼしい活躍はなかった。
嘉吉元年閏9月には、貞村の所領が闕所とされ、軍功の対象となった[2]。
『建内記』嘉吉元年九月二十四日条には貞村が落馬あるいは夜討されたという記述があるが、嘉吉3年(1444年)ごろまでは活動していたとされる[3]。
「赤松氏大系図」では文安4年(1447年)に死亡したとされている。
万一生きていたとしても、明徳4年(1393年) 生まれなので、応仁の乱の1467年には数えで75歳、
若年の当主・赤松政則(1455生まれ、数えで13歳)を旗頭にして主軍を率いるにしても、老年過ぎないでしょうか。
※いえ、(大和国の筒井氏の)成身院光宣は数え78歳で戦場に出てはいるのですが
----------------------
<源流にあると推測される「応仁記(一巻本)」ではどう書かれているのか>
※なぜ一巻本が三巻本の源流なのか、については省く
(古典文庫の)「応仁記」を読んでみると、
洛北の合戦(p73)では、
「舟橋より下をば、細川下野守・丹波の守護内藤、赤松伊豆守をぞ向られける。」(カタカナをひらがなにしました)
(古典文庫の)「応仁別記」のほうには、
p137に<山名金吾(宗全)が文正元年末(開けると文正2年=応仁元年)に集めた一味の大名として>赤松伊豆千代寿丸、
p138に<文正2年正月15日に(細川)勝元のほうに味方した人々のうちに>赤松次郎政則・同伊豆守貞祐(実際は示+右なのですが、漢字が出ない)、
p165に 赤松伊豆守○貞村(小さめの○の横に貞村と小さく書かれている)、の名前がありますが、
この赤松伊豆守○貞村は、嘉吉の乱(1441)のことについての記述です(なんか時代が行ったり来たりするのです)。
つまり、これらすべて、「応仁の戦場の赤松伊豆守」が赤松貞村だとは言っていません。
※ほかにもなんか伊豆に関する記述があったらすんません。
-----------------------
<だがそのリミックスの「応仁記(三巻本)」では・・・>
ものすごく端折った言い方をすれば、
応仁記(一巻本) + 応仁別記 ⇒ 応仁記(三巻本) ですが、
その応仁記三巻本(群書類従版)を、ありがたいことに私訳された方(芝蘭堂さま)がおられまして、
http://muromachi.movie.coocan.jp/ouninki/ouninki19.html
そちらと群書類従版の原文を読み合わせて分かったのですが、
>舟橋より下へは、細川下野守、丹波守護内藤備前守、赤松伊豆守貞村を向けられた。
(原文「舟橋ヨリ下ハ細川下野守。丹波守護内藤備前守。赤松伊豆守貞村ヲゾムケラレケル。」 p378)
ここが(群書類従版)応仁記三巻本で、応仁の戦場にいる赤松伊豆守が貞村だと(初めて)明言してしまった部分です。
ややさかのぼりますが、(三巻本)応仁記には、
http://muromachi.movie.coocan.jp/ouninki/ouninki12.html
>- 義就・政長闘乱の事 -
に、
(山名方についたほうとして)
>赤松伊豆守が子息千代寿丸
(細川方についたほうとして)
>赤松次郎入道政則、同貞祐、同道祖松丸、
とありますが、
(原文「赤松伊豆守ガ子息千代寿丸」「赤松次郎入道政則。同貞祐。同道祖松丸。」p368)
赤松円心の次男・貞範を祖とする赤松伊豆殿(春日部家)についての考証は、
こちらで見事に行われているのですが、
http://ochibo.my.coocan.jp/rekishi/akamatu/ikka/aka_izu_kakei.htm
(「落穂ひろい」ふーむ様)
もし、この伊豆守を貞村としてしまうと、いまだ子息が幼名なのがおかしい(気がします)。千代寿丸は貞村の子ではない(はず・・・)。
千代寿丸の父の伊豆守は、貞村の息子・教貞だろう(貞村・教貞は応仁元年時点で、すでに死去している)。
だが、教貞は伊豆守を称したであろうか・・・
ところで、「入道」とはいかに!?
赤松政則の幼名は「次郎法師(丸)」(赤松則村(円心)の幼名も「法師丸」だった気がするが、ソースが見つからん・・・)だが、
さすがに、この年で入道はしていないはず(それとも寺に預けられていたのでもいうのだろうか)。
また、一巻本に比べ、貞祐の前の「伊豆守」が消えてしまっている。
-----------------------------
<つまり何が起こったのか!?>
(古典文庫の)応仁記(一巻本)+ 応仁別記 ⇒ (群書類従の)応仁記(三巻本)
のリミックスが行われる際に、応仁の赤松伊豆守=貞村であると勘違いし、
そのつじつまを合わせるために、間違った加筆修正がされてしまった。
「応仁別記」を記述した作者は、
・「伊豆「守」の子息」ではなく、伊豆殿(系)の千代寿丸であり、
・応仁の乱のさいの赤松伊豆守は貞祐
だとわかっていたのだが、(※「伊豆」と「伊豆守」を明確に区別している)
三巻本にまとめあげられるときのエラーにより(これは意外に後世のことなのかもしれないし、群書類従にまとめあげられるときのエラーかもしれないのだが・・・私・ひろさわの調査不足です)、応仁の乱にゾンビ貞村が跳梁跋扈することになってしまった。
・・・ということではないでしょうか(弱気)
※赤松教貞が「伊豆守」を名乗ったかどうかは、のちの研究課題に。
-------------------------------------------------------
<これは想像ですが>
伊豆殿(系)内部で継承権争いがおこり、
継承権を奪取しようとしている千代寿(教貞晩年の子と考えれば幼名でもおかしくない)とその取り巻きが山名方につき、
継承権を持つ伊豆守貞祐(もし貞村が応仁に生きていれば「じいさん」なので、この貞祐は「おっさん」)が細川方について赤松本流の政則(こちらは元服したけど子供)を旗印として、お家再興を名目に、邪魔な兄の子の千代寿(もうすぐ元服の子供)と戦っていると考えれば、
いかにも応仁の乱でありそうな流れである・・・・
「花の乱」で描かれたほど、赤松政則は
なお、赤松政則も伊豆守であるとする記述がある系図もあると付け加えておきます。
※いまひとつ強く主張することが出来ないのですが、問題提起として、とりあえず、公開しておきます。












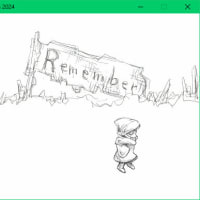

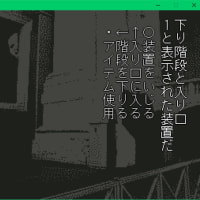
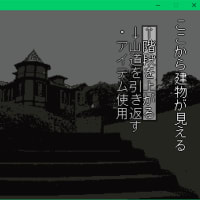
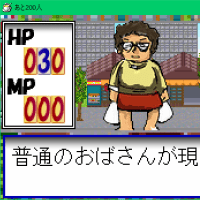








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます