







勝山市史P913.
北谷村聞書。
五所が原のくらし。
「てんぼ」てんぼはわらじの上へはくもの。
「しゃなくみ」は足袋の上はいてわらじをつける。ゆきわらじは、すわらじ゛の
1倍半位の大きさで、親緒はついていない。
「たばこ」たばこ入れを、ソキロ、インロウという。
タバコは高いので代用品を飲んだ。
サンケラ(サルトリイバラ)は、すぐに粉になりよくない。
栃の葉はタバコによく似ているので、刻んで使う。
とうもろこしのびけばかりのんでいた人もあったが、あまりうまくない。
よもぎは、もめばすぐ粉になり味も良い。
「食事」
(あさい)は朝飯。 (まえびるは)午前のこびる(間食) (上り)は昼飯。 (よけ)は夜飯。
タバコは栽培したものは貴重な現金収入なので 自分たちでは色々工夫して
タバコもどきを考えていた事、先人たちのご苦労をおもう。

勝山の風土。p198から。
谷。 加賀大杉の圓光寺門徒が多い。
中野俣。 平家の落人の伝説、また小豆峠の出作りで定着定着したもの14戸。
御所が原。 源野の姓多く源氏の子孫との伝説がある。
我が家は御所が原の源野の本家。
また織田、苅安の姓も相当あって白峰の系統であろうと思われる。
御所が原の名は木地氏と関係が深いといわれている。
出作りからの定住。
白峰村村史の織田家文書「はく山麓十八ケ村留帳」によると、
「年中一両度村方へ罷出儀にて、家内、女、童共、本村存ぜず、、、、」
とあり、推測されるのは、文久3年(1863)ごろから永久的出作りが始まり
家数480軒の38パーセントがそれであったと考えられる。
その出先については次の記録がある。
1.青山大膳頭領分 上打波、下打波、木根橋、小原、栃神谷、
1.小笠原左衛門領分 浄土寺山、暮見山、平泉寺山、谷(東山、御所が原、上原、奥の河内含む) 中野俣。
1. 御両所 杉山。
東山いこいの森はほとんど白峰からの出作りでした。
何とか御所が原物語りを作りたい。










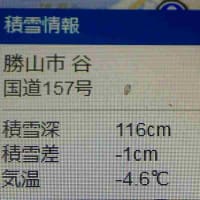





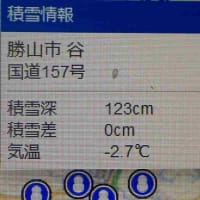
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます