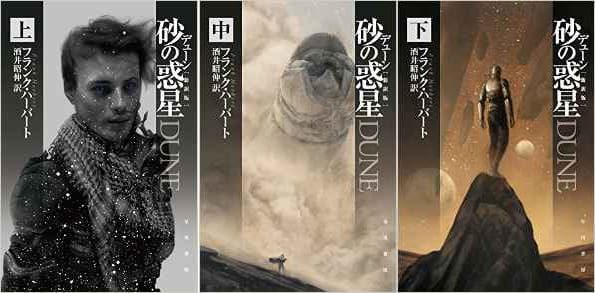ビル・ビバリー著
彼等が「箱庭」という一軒家を根城にヤクをさばいていた一味の末端、15歳の少年イースト。突然の一斉手入れで小さな組織は壊滅。
見張りを仕切っていたイーストは「叔父」に呼び出され処罰の代わりに、裏切り者とされる一人の男をコロすことを命令される。
叔父が指定した仲間、無責任大学生・オタク野郎・コロし屋少年の4人は、LAから2000マイル彼方(日本列島縦断より遠い)ウィスコンシンにいるその男のもとへ……黒人少年達は、ぼろ車で旅立った。
イーストの目前に広がる初めて見る大自然。彼等を待ち受ける差別。武器は途中で調達しなければならない。幼くして老獪な世界観をもつイーストだが、その老獪さはちっとも役に立たず、散々な道行きになっていく…。たどり着いた先に待ち受けるものは。
読書の達人であるミステリ評論家の方々がこぞって絶賛した話題作ー。
「書評七福神の九月度ベスト発表!」http://honyakumystery.jp/4479
こんなふうに粗筋を書くと何だか面白そうだ。映画「スタンド・バイ・ミー」のちびっ子ギャング版とでもいうか。
久しぶりの読書会に参加、その課題本。読後感としては「積極的にけなそうとは思わないが、それほど面白くもなかった」という感じ。順調な出だしから、無責任野郎のわがままで頓挫するあたりまで、どうも型にはまったような印象。イーストの見る光景が詩的なレトリックで描かれるのだが、どうもちぐはぐな感じ。イーストの気持ちに寄り添えない。
オジキは何故少年達ばかりで悪事をなしていたのか。凶暴な大人の存在が希薄なのだ。
なぜこのエピソードを展開しないのかと、物足りないところも所々あり「ふーん」という感じ。
拳銃を入手するあたりのエピソードを読んだあたりから気がついたのだが、このお話は「英雄の旅」の型にのっとっているようだ。キャンベルやボグラーの言う神話的構成をアレンジし「頭で書いた」様に思える。気持ちが入らず、テクニックで書いたという感じだ。詩的である文章がどこか白々しかったのも、そんなところが原因なのか。
そういえば三章という構成も、ドラマ作りで云うところの三幕構成にのっとっている?
「東の果て、夜へ」を、人物のアーキタイプ、12ステージ展開などをあてはめると、その配置や意図が(アレンジがあっても)結構丸見えな感じだ。「帰還」がどう描かれるのかと思って読んでいたので、結末には、ああなるほどそういう風にしたのか、という感興。もちろん「英雄の旅」の型を踏まえているから悪いというわけではない。(そんなことを言ったらスター・ウォーズも駄目ということになる)調理仕切れていない生な感じがするということだろうか。
聞けば作者は大学で英文学と創作を教える先生だとか。このお話は授業の教材なのかしら?
それと、こういうお話だからこそ巻頭に「略地図」が掲載されていればなあ、と思いました。
「英雄の旅」という物語の型については、以下のサイトの解説がわかりやすいです。
漫画の描き方研究ラボ
『神話の法則』の三幕構成
https://kenkyu-labo.com/02/shinwanohosoku.html
ハリウッド式の三幕構成とは
https://kenkyu-labo.com/02/2_0_1.html
余談ですが、3年前の別の読書会で読んだ本、
ポール・オースター「ガラスの街」にも同様の神話的構造がありました。
こんなお話に神話的構造が隠れているという発見が面白いです。
ヒーローズジャーニーの視点から一見難解な物語がきれいに解けてしまいます。あんまり痛快なの僕の気分もアゲアゲ。このブログでいろんな自分なりの見方を書いてきましたが、その中でも「解けたぞ!」という最高の瞬間でした。(残念だけど感想文として残していなかった)
当時「ガラスの街・英雄の旅」「ガラスの街・ヒーローズジャーニー」で検索してみましたが、何もヒットしませんでした。そんな視点から読み解いた人はあんまりいないのだろうか? 読書会でもこういう視点から語った人はいませんでした。ほんとは一項もうけるべきだけれども、3年前のことで記憶があいまいなのでメモとして書いておきます。
当時の読書会リポートを見ると、もう一つ読解の提案として僕は「キュビズム」をあげてたようです。多方向からの視点を一つの画面に盛るということを言ったのだと思います。自分探しのお話をこういう構造におとしこみ、ミステリの意匠をまぶして作品に昇華させるのはさすがだなあと思います。
(そこに注目すればこの前の読書会の「東の果て、夜へ」も同じなんだけど)