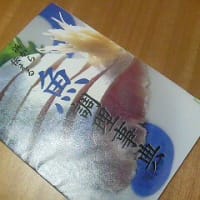これまたインド発。しかしこれはフィクション。
Youtubeによっていろんな映像が見れるようになりました。
先日見たのは、インド映画『サティー』。1989年公開。
監督はアパルナ・セン。
って誰ですか?
調べてみると、もともと俳優としてデビューして、後に監督になった方です。
1945年、コルカタ生まれ。父は映画監督、母は詩人。
1961年、16歳のとき「三人娘Teen Kanya (Three Daughters)」という映画で女優デビューしました。
近年、インド映画と言えば超のつく娯楽大作の宝庫として日本でも知られるようになりましたが、ひと昔前なら、インド映画と言えばサタジット・レイの作品。
ぼくは見たことありませんが、いわゆる「芸術性の高い」映画です。アパルナ・センの父親は映画監督ですが、その友人にサタジット・レイがいて、彼女の映画デビュー作も、サタジット・レイの監督作品でした。こういう娯楽よりも芸術性に重きをおいた映画のことを、インドではParalell Cinemaと呼ぶそうです。
で、この『サティー』。
タイトルは、日本で有名なショッピングセンターとは何のかかわりもありません。
「サティー」というのは本来は女神の名前ですが、インドのある習慣のことを指します。
日本では「寡婦殉死」とも訳されます。
どんな習慣かというと、夫が死んでその遺体を焼く薪の上に妻(まだ生きてる)が座り、一緒に焼かれる(もちろん死ぬ)というおっそろしい習慣です。
そうすることによって、寡婦の名誉と尊厳が守られ、崇拝される、と。
もっとも、インド全土で寡婦がみんな殉死したかと言うと、さすがにそんなことはなくて、ブラフマン(カーストの最上位)に限られたようです。そしてたぶん、すべてのブラフマン家系でサティーがおこなわれたわけではない。
しかしそうは言っても、大変なことには違いないわけで、インドにやってきたイギリス人は腰を抜かして驚きました。
その一人に、ジョブ・チャーノックという男がいます。
東インド会社の幹部です。寒村に過ぎなかったコルカタの開発を計画&実行して、コルカタの創始者と言われています。
「33歳でフーグリ沿岸すべての工場の差配をつとめていたとき、パトナを訪ね、観光気分でサティー見物に出かけた(中略)。チャーノックは未亡人マリアの美しさにひとめ惚れして、ボディーガードの兵士たちにその場からさらわせ、妻にして混血児4人をもうけた。」(安引宏、今井爾郎1989『カルカッタ大全』人文書院)
これは、1660年代のことのようです。
「あれ?」と思った人は勘がいい。
インドの女性の名前で「マリア」って不自然でしょ。これはどうも、チャーノックが勝手につけた名前のようです。
焼かれたりさらわれたり勝手に名前付けられたり、人の気持ちってものはどうなるんじゃい!?
と思いたくなるエピソードです。実際、インドでは、近年でもサティーがたまにおこなわれていて、そのたびに、人権と宗教、伝統をめぐる論争が巻き起こっています。
サティーは法律では禁止されているので、やるほうはそのつもりでやってるはずです。
*****
今回はこの論争までは立ち入れませんが、映画『サティー』はそのことを扱った映画だと思って見ました。
時代設定は1828年。ジョブ・チャーノックが火の中から寡婦を救い出し=拉致してから150年ほどあとのことです。この翌年、イギリス領インドではサティーが禁止されることになります。
冒頭、にぎやかな行列が現れます。
行列の中ほどに、輿に乗せられた若い女性。朦朧とした表情です。
行列の参加者の会話から、どうやら薬を飲まされたことがわかります。
そして、彼女は夫の遺体を焼く薪のなかに飛び込む。
…しかし、映画でサティーが登場するのはこれだけ。
あと1回、中ほどのところで、村の司祭が、「イギリス人はサティーを禁止しようとしている。けしからん!」と息巻いているシーンがありますが、「サティー」と銘打ったわりには、これだけ。少なくとも表面上は。
主人公は、冒頭のサティーの行列を木陰から目撃していた女性「ウマ」。
ウマは孤児で、オジ夫婦のところに引き取られています。オジはまずまずですが、その妻はウマをことあるごとに罵る。厄介者扱い。
ウマは口がきけない。しかも、予言によって将来寡婦になる(夫に先立たれる)、と。さらに悪いことに、ウマの一族はブラフマン。
ブラフマンの家系の女性で寡婦になると運命付けられていて、しかも厄介者扱いでたぶん死んでも誰も悲しまないとなると、ウマはサティーになることがほとんど確実。すごい設定です。
ところが、ウマは年頃になっても(というか幾分か過ぎてる)結婚しない。
将来寡婦になる、と予言された女性と結婚する男がそうそういるものではありません。あいつと結婚したらオレ死ぬの!?ってね。
じゃあ結婚しなければいいじゃない、というのは浅はかな考えで、ウマが片付かないと、この家のほかの子どもたちも結婚できない。年上が結婚しないと年下のものは結婚できないという規則があるそうです。繰り返しますが、これはフィクションです。このアイデアのもとになる規則が事実あったのかもしれませんが、こんなふうにガチガチに適用されていたかどうかは「?」です。
それはともかく、とにかくウマは結婚しなきゃならない。
しかし人では結婚相手がいない。
そこで、
「木はどうだ?」
とウルトラC級の解決策を提案したのは、村の司祭でした。
しかし、「木と」といったのは単なる思い付きではありませんで、占いでもありませんで、ふだんからウマが気に入っていた大きな木があったからでした。
そして訳もわからず木と結婚させられるウマ。
しかし、もともと居場所がなくてよくここへきていたので、ウマにはよかったのかもしれません。
ところでこのウマを演じたシャバナ・アズミという女性、すばらしい美人ですが、彼女もまたParalell Cinema系の女優です。娯楽志向のボリウッド映画にも出ますが、そっちではそれほど知られた存在ではないようです。有名なのだと、ボリウッド映画でも屈指の名作と言われる「Masoom」(未見)にも出演していますが、インド映画好きな人が「これ、誰だろう?」というくらいのようです。で、彼女が木と仲良くするウマを演ずる場面はとても美しい。
むごい継母とかいますが、この辺まではまだほのぼのとしたものさえ漂っています。
しかし、この後、事態は急変。
・・・とまあこんな話です。結末はここには書かないことにします。
結局サティーはどうなった?
ってことですが、見ているうちに忘れました。
インドの女性がとらわれている因習の数々の代表としてサティーを使った、と言う見方もできるかもしれません。教科書みたいでつまらない見方ですが。
監督のアパルナ・センの立ち位置からすると、難しいかもしれません。
センは女性です。インテリです。
ですが、ブラフマンの家系です。つまり、サティーをおこなってもよい立場。
もしかしたら、自分の家系にサティーをおこなった寡婦がいたかもしれない。
サティーに対するセンの態度と言うのは、少なくともこの映画からははっきりしません。
しらみつぶしに探せば、ネット上でもどこかでセンの考えが見つかるかも知れませんが。
うーん、やっぱり結末書いちゃおう。
知りたくない人はここまでで。
*****
さて、木と結婚したウマですが、ある嵐の晩、村のインテリ(教師)を家まで送っていくように命じられます。ウマの家での地位がよく分かるシーンでして、要するに、使用人扱いなんです。
で、行った先で、雨に濡れたウマにムラムラっときたこの野郎が…。
てなわけでウマは妊娠してしまいます。
「ウマは木の子どもを身ごもったと村人は信じ、生まれてくる子どもを神さまとして崇めるようになりました」みたいな昔話チックな展開にはなりません。残念ながら。
そうではなくて、これまでもさんざんウマにつらく当たってきた義母が、こんな不義の子どもを生ませるわけにはいかない、と呪術師に相談して、薬を与えて堕胎させることにします。もちろん男は口をぬぐっています。責任なんか取りません。「だってぼく結婚してるんだもん」とでも言ってるようなインテリ面がむかつきます。
まあ、映画の中の人にそんなに怒っても仕方ないので、もしこんなブログを最後まで読んだ未婚の(既婚でもいいですが)女性がいたら、このことは覚えておいてもいいでしょう。男は責任なんか取らない。つか、男任せにするってのは、万馬券狙い、裏ドラねらいくらいのギャンブルである、と。
つい怒りに任せて脱線しました。
薬を飲んでウマは苦しむ。
そして、夫である木のところにいく。
ここでまた、ものすごい嵐が。
そして翌朝、村人が発見したのは、折れた木の下敷きになって死んでいるウマの姿でした。
この記事によると、
この木は「夫」として「妻」の尊厳を救い、高めた、それはすなわち象徴的な「サティー」であるとのことです。
そこでつながるのか。なるほど。
しかしぼくが思ったのは、あのスケベなインテリ野郎(しかしあの人、ぼくの友人の誰かを思い出させる)がウマに手を出したりしなければ、「木と結婚する」ってのも悪くないアイデアだったんじゃないかということです。
先日書いた、犬と結婚した男もそうですが、象徴的に結婚するってのは、何かを解決する方法でもあるわけです。まあ、役場は受理してくれないでしょうし、扶養手当とか控除とかも適用してくれないでしょうが、それはそれ。みんなが「結婚してるんだ」と思ってくれればそれでいいわけです。
Youtubeによっていろんな映像が見れるようになりました。
先日見たのは、インド映画『サティー』。1989年公開。
監督はアパルナ・セン。
って誰ですか?
調べてみると、もともと俳優としてデビューして、後に監督になった方です。
1945年、コルカタ生まれ。父は映画監督、母は詩人。
1961年、16歳のとき「三人娘Teen Kanya (Three Daughters)」という映画で女優デビューしました。
近年、インド映画と言えば超のつく娯楽大作の宝庫として日本でも知られるようになりましたが、ひと昔前なら、インド映画と言えばサタジット・レイの作品。
ぼくは見たことありませんが、いわゆる「芸術性の高い」映画です。アパルナ・センの父親は映画監督ですが、その友人にサタジット・レイがいて、彼女の映画デビュー作も、サタジット・レイの監督作品でした。こういう娯楽よりも芸術性に重きをおいた映画のことを、インドではParalell Cinemaと呼ぶそうです。
で、この『サティー』。
タイトルは、日本で有名なショッピングセンターとは何のかかわりもありません。
「サティー」というのは本来は女神の名前ですが、インドのある習慣のことを指します。
日本では「寡婦殉死」とも訳されます。
どんな習慣かというと、夫が死んでその遺体を焼く薪の上に妻(まだ生きてる)が座り、一緒に焼かれる(もちろん死ぬ)というおっそろしい習慣です。
そうすることによって、寡婦の名誉と尊厳が守られ、崇拝される、と。
もっとも、インド全土で寡婦がみんな殉死したかと言うと、さすがにそんなことはなくて、ブラフマン(カーストの最上位)に限られたようです。そしてたぶん、すべてのブラフマン家系でサティーがおこなわれたわけではない。
しかしそうは言っても、大変なことには違いないわけで、インドにやってきたイギリス人は腰を抜かして驚きました。
その一人に、ジョブ・チャーノックという男がいます。
東インド会社の幹部です。寒村に過ぎなかったコルカタの開発を計画&実行して、コルカタの創始者と言われています。
「33歳でフーグリ沿岸すべての工場の差配をつとめていたとき、パトナを訪ね、観光気分でサティー見物に出かけた(中略)。チャーノックは未亡人マリアの美しさにひとめ惚れして、ボディーガードの兵士たちにその場からさらわせ、妻にして混血児4人をもうけた。」(安引宏、今井爾郎1989『カルカッタ大全』人文書院)
これは、1660年代のことのようです。
「あれ?」と思った人は勘がいい。
インドの女性の名前で「マリア」って不自然でしょ。これはどうも、チャーノックが勝手につけた名前のようです。
焼かれたりさらわれたり勝手に名前付けられたり、人の気持ちってものはどうなるんじゃい!?
と思いたくなるエピソードです。実際、インドでは、近年でもサティーがたまにおこなわれていて、そのたびに、人権と宗教、伝統をめぐる論争が巻き起こっています。
サティーは法律では禁止されているので、やるほうはそのつもりでやってるはずです。
*****
今回はこの論争までは立ち入れませんが、映画『サティー』はそのことを扱った映画だと思って見ました。
時代設定は1828年。ジョブ・チャーノックが火の中から寡婦を救い出し=拉致してから150年ほどあとのことです。この翌年、イギリス領インドではサティーが禁止されることになります。
冒頭、にぎやかな行列が現れます。
行列の中ほどに、輿に乗せられた若い女性。朦朧とした表情です。
行列の参加者の会話から、どうやら薬を飲まされたことがわかります。
そして、彼女は夫の遺体を焼く薪のなかに飛び込む。
…しかし、映画でサティーが登場するのはこれだけ。
あと1回、中ほどのところで、村の司祭が、「イギリス人はサティーを禁止しようとしている。けしからん!」と息巻いているシーンがありますが、「サティー」と銘打ったわりには、これだけ。少なくとも表面上は。
主人公は、冒頭のサティーの行列を木陰から目撃していた女性「ウマ」。
ウマは孤児で、オジ夫婦のところに引き取られています。オジはまずまずですが、その妻はウマをことあるごとに罵る。厄介者扱い。
ウマは口がきけない。しかも、予言によって将来寡婦になる(夫に先立たれる)、と。さらに悪いことに、ウマの一族はブラフマン。
ブラフマンの家系の女性で寡婦になると運命付けられていて、しかも厄介者扱いでたぶん死んでも誰も悲しまないとなると、ウマはサティーになることがほとんど確実。すごい設定です。
ところが、ウマは年頃になっても(というか幾分か過ぎてる)結婚しない。
将来寡婦になる、と予言された女性と結婚する男がそうそういるものではありません。あいつと結婚したらオレ死ぬの!?ってね。
じゃあ結婚しなければいいじゃない、というのは浅はかな考えで、ウマが片付かないと、この家のほかの子どもたちも結婚できない。年上が結婚しないと年下のものは結婚できないという規則があるそうです。繰り返しますが、これはフィクションです。このアイデアのもとになる規則が事実あったのかもしれませんが、こんなふうにガチガチに適用されていたかどうかは「?」です。
それはともかく、とにかくウマは結婚しなきゃならない。
しかし人では結婚相手がいない。
そこで、
「木はどうだ?」
とウルトラC級の解決策を提案したのは、村の司祭でした。
しかし、「木と」といったのは単なる思い付きではありませんで、占いでもありませんで、ふだんからウマが気に入っていた大きな木があったからでした。
そして訳もわからず木と結婚させられるウマ。
しかし、もともと居場所がなくてよくここへきていたので、ウマにはよかったのかもしれません。
ところでこのウマを演じたシャバナ・アズミという女性、すばらしい美人ですが、彼女もまたParalell Cinema系の女優です。娯楽志向のボリウッド映画にも出ますが、そっちではそれほど知られた存在ではないようです。有名なのだと、ボリウッド映画でも屈指の名作と言われる「Masoom」(未見)にも出演していますが、インド映画好きな人が「これ、誰だろう?」というくらいのようです。で、彼女が木と仲良くするウマを演ずる場面はとても美しい。
むごい継母とかいますが、この辺まではまだほのぼのとしたものさえ漂っています。
しかし、この後、事態は急変。
・・・とまあこんな話です。結末はここには書かないことにします。
結局サティーはどうなった?
ってことですが、見ているうちに忘れました。
インドの女性がとらわれている因習の数々の代表としてサティーを使った、と言う見方もできるかもしれません。教科書みたいでつまらない見方ですが。
監督のアパルナ・センの立ち位置からすると、難しいかもしれません。
センは女性です。インテリです。
ですが、ブラフマンの家系です。つまり、サティーをおこなってもよい立場。
もしかしたら、自分の家系にサティーをおこなった寡婦がいたかもしれない。
サティーに対するセンの態度と言うのは、少なくともこの映画からははっきりしません。
しらみつぶしに探せば、ネット上でもどこかでセンの考えが見つかるかも知れませんが。
うーん、やっぱり結末書いちゃおう。
知りたくない人はここまでで。
*****
さて、木と結婚したウマですが、ある嵐の晩、村のインテリ(教師)を家まで送っていくように命じられます。ウマの家での地位がよく分かるシーンでして、要するに、使用人扱いなんです。
で、行った先で、雨に濡れたウマにムラムラっときたこの野郎が…。
てなわけでウマは妊娠してしまいます。
「ウマは木の子どもを身ごもったと村人は信じ、生まれてくる子どもを神さまとして崇めるようになりました」みたいな昔話チックな展開にはなりません。残念ながら。
そうではなくて、これまでもさんざんウマにつらく当たってきた義母が、こんな不義の子どもを生ませるわけにはいかない、と呪術師に相談して、薬を与えて堕胎させることにします。もちろん男は口をぬぐっています。責任なんか取りません。「だってぼく結婚してるんだもん」とでも言ってるようなインテリ面がむかつきます。
まあ、映画の中の人にそんなに怒っても仕方ないので、もしこんなブログを最後まで読んだ未婚の(既婚でもいいですが)女性がいたら、このことは覚えておいてもいいでしょう。男は責任なんか取らない。つか、男任せにするってのは、万馬券狙い、裏ドラねらいくらいのギャンブルである、と。
つい怒りに任せて脱線しました。
薬を飲んでウマは苦しむ。
そして、夫である木のところにいく。
ここでまた、ものすごい嵐が。
そして翌朝、村人が発見したのは、折れた木の下敷きになって死んでいるウマの姿でした。
この記事によると、
この木は「夫」として「妻」の尊厳を救い、高めた、それはすなわち象徴的な「サティー」であるとのことです。
そこでつながるのか。なるほど。
しかしぼくが思ったのは、あのスケベなインテリ野郎(しかしあの人、ぼくの友人の誰かを思い出させる)がウマに手を出したりしなければ、「木と結婚する」ってのも悪くないアイデアだったんじゃないかということです。
先日書いた、犬と結婚した男もそうですが、象徴的に結婚するってのは、何かを解決する方法でもあるわけです。まあ、役場は受理してくれないでしょうし、扶養手当とか控除とかも適用してくれないでしょうが、それはそれ。みんなが「結婚してるんだ」と思ってくれればそれでいいわけです。