薄暗い水の中を彼はゆっくりと上昇していった。
遥か上方にほのかな明かりが見える。あそこまで行けたら・・水面に出れる。
身体がなかなか思うように動かず、もどかしかった。
なんとかあそこまで・・行かなくては・・・
「お、眼が覚めたか?」
という声と、眼鏡を掛けた男の顔が飛び込んできた。
同時に突然眩い光に晒され、クリストファーは思わず眉を顰めた。それと共に理由のわからない恐怖が胸に溢れる。
反射的に身を起こそうとする彼を、先ほどの男が優しく、しかし確固として制した。
「落ち着け。ここは安全だ、何も心配することはない」
「僕は・・一体・・?」 言葉が巧く紡げない。酷く喉が渇いているのに気づいた。
男はその知的な眼差しで注意深く彼の様子を観察した。
「君はもう1週間も気を失ったままだったんだ。随分心配したよ。気分はどう?」
「・・水」
「あ、そうだな、そりゃ喉が渇いてるだろう」 男は振り向いてそこにいるらしい誰かに声を掛けた。「白湯を持ってきてくれ。程よく人肌に冷ましたやつね」
程なくもうひとつの人影がクリストファーの視界に登場した。丸顔のまだ子供々々した少年だ、手にマグを持っている。それを直接クリストファーに差し出そうとするのを、男が脇から奪い取った。そして疑い深げに中身を検査する。
「ちゃんと冷ましたよ」 少年が不満そうに言った。
「水入れて冷まさなかったろうな?」
「いんちきはしてないって、ちゃんとお湯から冷ました!」
「わかったわかった、じゃ起こすの手伝って」
ベッドの脇に回り込みながら、少年はクリストファーのほうを盗み見た。が、目線が合うと慌てて顔を逸らせる。
「静かにゆっくり身を起こすんだ。無理するなよ」 男が優しく言った。
少年の腕に支えられて、クリストファーは上体を起こした。とたんに眩暈がする。くず折れそうな身体を少年が慌てて受け止めた。結果として彼はクリストファーの背後で半ばベッドに横座りする形になった。
口元にマグの冷たい感覚、そして甘露のような液体が口角を満たした。
思わず貪ろうとするクリストファーに「急に飲んだら身体に悪い、少しずつ飲むんだ」と言いながら、男はマグの角度で白湯の流れを調節した。慣れたものだった。
やがて喉の渇きが収まり、落ち着いた様子を暫く見守った後、男は立ち上がった。
クリストファーの限られた視界から外れたところで、男が少年に話している。
「傷口はほぼ塞がったみたいだな。内臓が傷ついてなくて本当にラッキーだった。もう少したって大丈夫なようだったら、この前買っといたベビー・フードから適当なのをみつくろって与えてみるといい。但し、様子を見ながら少量づつだぞ、失血が酷かった上に、1週間何も食ってないんだからな」
ひとしきり指示を与えると、青年は去っていった。ドアの閉まる音が聞こえた。
暫くして、少年がおずおずとベッド脇にやってきた。
「気分はどう?」 無理して平静を装っているが、しっかり緊張している。
「・・・」
「あれはミッコ、うちの下宿人なんだ」と聞かれたわけでもないのに説明した。「フィンランドからカロリンスカに研修に来ている医者の卵さ。彼がいてくれてほんと助かったよ。僕一人じゃどうにもならなかった」
「・・・」
「僕の名はアレクサンドル、アレクサンドル・マヨロフ。パパとママはバレエの公演でずっと留守だ。今この家にいるのは僕だけだから、気兼ねすることないよ」
「・・ずいぶん世話になったみたいだな。・・有難う」 漸くクリストファーの思考回路が作動し始めた。自分の声がまるで他人のもののように虚ろに聞こえる。
「いいって、気にすんな」 少年、もといアレクサンドルはほっとしたように応じた。
クリストファーの脳裏にここ暫くの悪夢のような出来事が蘇えってきた。
『あれから1週間経ったって?』
問いたいことは山のようにある。しかし、あまりに重過ぎて、そこに意識を持っていっただけで気が遠くなりそうだった。一体どこから手をつければいいのか見当もつかない。
そういう彼の心境を察知したように、アレクサンドルが言った。
「とにかく体力つけるのが先決だ。何か食べてみる?」
ベビー・フードを小匙で食べさせて貰う(アレクサンドルは断固として自分で食べることを許さなかった)のはなんとも情けなかったが、お陰で多少元気を回復した。
手伝ってもらってベッドからソファに移動する。それだけで全体力を使い果たしたようにぐったりした。
ソファにもたれてぼんやりと虚空を見つめていると、アレクサンドルがまた躊躇いがちに話しかけてきた。
「うなされてずっと彼の名を呼んでいたよ」
「彼?」
「うん、アドリアン、アドリアンって」
「・・・・・」
「よっぽど仲が良かったんだね」 奇妙なことだが、そういうアレクサンドルの声色にはあるかなしかの嫉妬が含まれているようだった。
が、クリストファーはそれには気づかず、ただ暗い笑みを浮かべた。
「仲が良いなんてもんじゃないよ」
「ふん?」
「あいつのこと・・この手で絞め殺してやりたい・・と本気で思う」
「・・え?」
「自分が人をここまで憎めるなんて・・知らなかった」
クリストファーの瞳は底知れず暗い絶望の色を湛えて前方を凝視していた。が、明らかに何も見ていない。その視線は、ここにはない遥か彼方の見知らぬ風景に向けられてでもいるかのようだ。
そんな彼をアレクサンドルは不思議そうに、そして不安げに見守り続けた。
その23へ
遥か上方にほのかな明かりが見える。あそこまで行けたら・・水面に出れる。
身体がなかなか思うように動かず、もどかしかった。
なんとかあそこまで・・行かなくては・・・
「お、眼が覚めたか?」
という声と、眼鏡を掛けた男の顔が飛び込んできた。
同時に突然眩い光に晒され、クリストファーは思わず眉を顰めた。それと共に理由のわからない恐怖が胸に溢れる。
反射的に身を起こそうとする彼を、先ほどの男が優しく、しかし確固として制した。
「落ち着け。ここは安全だ、何も心配することはない」
「僕は・・一体・・?」 言葉が巧く紡げない。酷く喉が渇いているのに気づいた。
男はその知的な眼差しで注意深く彼の様子を観察した。
「君はもう1週間も気を失ったままだったんだ。随分心配したよ。気分はどう?」
「・・水」
「あ、そうだな、そりゃ喉が渇いてるだろう」 男は振り向いてそこにいるらしい誰かに声を掛けた。「白湯を持ってきてくれ。程よく人肌に冷ましたやつね」
程なくもうひとつの人影がクリストファーの視界に登場した。丸顔のまだ子供々々した少年だ、手にマグを持っている。それを直接クリストファーに差し出そうとするのを、男が脇から奪い取った。そして疑い深げに中身を検査する。
「ちゃんと冷ましたよ」 少年が不満そうに言った。
「水入れて冷まさなかったろうな?」
「いんちきはしてないって、ちゃんとお湯から冷ました!」
「わかったわかった、じゃ起こすの手伝って」
ベッドの脇に回り込みながら、少年はクリストファーのほうを盗み見た。が、目線が合うと慌てて顔を逸らせる。
「静かにゆっくり身を起こすんだ。無理するなよ」 男が優しく言った。
少年の腕に支えられて、クリストファーは上体を起こした。とたんに眩暈がする。くず折れそうな身体を少年が慌てて受け止めた。結果として彼はクリストファーの背後で半ばベッドに横座りする形になった。
口元にマグの冷たい感覚、そして甘露のような液体が口角を満たした。
思わず貪ろうとするクリストファーに「急に飲んだら身体に悪い、少しずつ飲むんだ」と言いながら、男はマグの角度で白湯の流れを調節した。慣れたものだった。
やがて喉の渇きが収まり、落ち着いた様子を暫く見守った後、男は立ち上がった。
クリストファーの限られた視界から外れたところで、男が少年に話している。
「傷口はほぼ塞がったみたいだな。内臓が傷ついてなくて本当にラッキーだった。もう少したって大丈夫なようだったら、この前買っといたベビー・フードから適当なのをみつくろって与えてみるといい。但し、様子を見ながら少量づつだぞ、失血が酷かった上に、1週間何も食ってないんだからな」
ひとしきり指示を与えると、青年は去っていった。ドアの閉まる音が聞こえた。
暫くして、少年がおずおずとベッド脇にやってきた。
「気分はどう?」 無理して平静を装っているが、しっかり緊張している。
「・・・」
「あれはミッコ、うちの下宿人なんだ」と聞かれたわけでもないのに説明した。「フィンランドからカロリンスカに研修に来ている医者の卵さ。彼がいてくれてほんと助かったよ。僕一人じゃどうにもならなかった」
「・・・」
「僕の名はアレクサンドル、アレクサンドル・マヨロフ。パパとママはバレエの公演でずっと留守だ。今この家にいるのは僕だけだから、気兼ねすることないよ」
「・・ずいぶん世話になったみたいだな。・・有難う」 漸くクリストファーの思考回路が作動し始めた。自分の声がまるで他人のもののように虚ろに聞こえる。
「いいって、気にすんな」 少年、もといアレクサンドルはほっとしたように応じた。
クリストファーの脳裏にここ暫くの悪夢のような出来事が蘇えってきた。
『あれから1週間経ったって?』
問いたいことは山のようにある。しかし、あまりに重過ぎて、そこに意識を持っていっただけで気が遠くなりそうだった。一体どこから手をつければいいのか見当もつかない。
そういう彼の心境を察知したように、アレクサンドルが言った。
「とにかく体力つけるのが先決だ。何か食べてみる?」
ベビー・フードを小匙で食べさせて貰う(アレクサンドルは断固として自分で食べることを許さなかった)のはなんとも情けなかったが、お陰で多少元気を回復した。
手伝ってもらってベッドからソファに移動する。それだけで全体力を使い果たしたようにぐったりした。
ソファにもたれてぼんやりと虚空を見つめていると、アレクサンドルがまた躊躇いがちに話しかけてきた。
「うなされてずっと彼の名を呼んでいたよ」
「彼?」
「うん、アドリアン、アドリアンって」
「・・・・・」
「よっぽど仲が良かったんだね」 奇妙なことだが、そういうアレクサンドルの声色にはあるかなしかの嫉妬が含まれているようだった。
が、クリストファーはそれには気づかず、ただ暗い笑みを浮かべた。
「仲が良いなんてもんじゃないよ」
「ふん?」
「あいつのこと・・この手で絞め殺してやりたい・・と本気で思う」
「・・え?」
「自分が人をここまで憎めるなんて・・知らなかった」
クリストファーの瞳は底知れず暗い絶望の色を湛えて前方を凝視していた。が、明らかに何も見ていない。その視線は、ここにはない遥か彼方の見知らぬ風景に向けられてでもいるかのようだ。
そんな彼をアレクサンドルは不思議そうに、そして不安げに見守り続けた。
その23へ















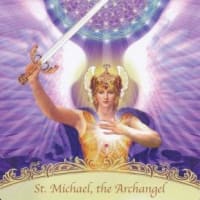





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます