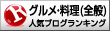・緑茶Green teaりょくちゃ
2025年(令和7年)5月1日は、八十八夜で茶摘みの季節です。南北に長い日本ではお茶の種類によって新茶の収穫時期は異なり、産地により八十八夜を含む4~5月頃が収穫の最盛期この日に摘んだお茶は新茶、一番茶と言われ、これを飲むと、無病息災、長生きすると言われます。
2025年(令和7年)5月1日は、八十八夜で茶摘みの季節です。南北に長い日本ではお茶の種類によって新茶の収穫時期は異なり、産地により八十八夜を含む4~5月頃が収穫の最盛期この日に摘んだお茶は新茶、一番茶と言われ、これを飲むと、無病息災、長生きすると言われます。
煎茶の製造工程 荒茶工程|お茶ができるまで|お茶百科 (ocha.tv)
どうやって作られているのか?緑茶は、茶葉を摘み取って加熱し、発酵させずに乾燥させて作られます。
緑茶の作り方
お茶の葉を摘み取ってすぐに加熱し、発酵(酸化発酵)しないようにして作ったのが緑茶、完全に発酵(酸化発酵)させるのが紅茶、その中間に位置するのがウーロン茶などの半発酵茶です。 また、緑茶は、加熱の方法の違いによって釜炒り製(中国式)、蒸し製(日本独特のもの)の二通りに分けられます。
⒈茶畑で茶摘みを 毎年4月下旬から5月になると行なわれています。.
2.蒸しで摘採(てきさい)したばかりの生葉は品質劣化を防ぐことから、ただちに湿気度の高い空気を送り、呼吸熱を下げ味・香りを決める「蒸す」 工程としてあります。
3.蒸された新芽は、次に「揉み」の作業工程で行います。
4.次に乾燥へ 揉みが終わると、茶葉の「乾燥」です。
5.大方の荒茶の完成で「選別」の工程に入ります。
6.最終段階で火入れにより、茶葉を乾燥させ、香りを引き出す工程です。茶葉の芯まで火を入れることで、うまみや香りが引き立ち、お茶の味や香り、鮮度を保つことができます。 100℃を超える温度で加熱することで茶葉内部まで均一に温め、芯水(茶葉の中に含まれる水分)を逃がします。短時間で乾燥させます。火入れの温度や時間などの微妙な加減を重要視し茶の種類のみならず、季節・その日の温度、湿度等によって、火入れ時の温度・時間の調整をし、その調整の仕方により風味の異なるお茶に仕上がり生葉に対して歩留りは23%程度になります。
緑茶とは、茶葉を発酵させずに作られたお茶の総称で、煎茶や玉露、番茶、抹茶、焙じ茶などが含まれます。その成分は、
◇煎茶浸出液100g中でエネルギー2kcal、水分99.4g、たんぱく質0.2g、脂質(0)g、炭水化物0.2g、灰分0.1g、ナトリウム3mg、カリウム27mg、カルシウム3mg、マグネシウム2mg、リン2mg、鉄0.2mg、亜鉛Trmg、銅0.01mg、マンガン0.31mg、ビタミンA(0)μg、ビタミンD:(0)μg、ビタミンE:-mg、ビタミンK:Trμg、ビタミンB1:0mg、ビタミンB2:0.05mg、ナイアシン0.2mg、ビタミンB6:0.01mg、ビタミンB12:(0)μg、葉酸16μg、パントテン酸0.04mg、ビタミンC6mg 食物繊維-g
程度です。
新茶といわれる八十八夜の茶摘みは、立春(2月3日ごろ)から数えて88日の5月2日(2025,5,1)ごろにあたり一番茶としての茶摘みを行なっています。
北限が秋田、岩手県で6月頃が新茶の時期にあたり暖かい地方と前後すると2ヶ月のずれがあり出荷しているようです。2番茶、3番茶は、夏茶ともいわれ6月中旬、7月下旬から茶摘みし3月から9月にかけての出荷です。
お茶は、アルカリ性で穀類、蓄肉、魚介類、卵類の酸性食品により過剰に傾きがちな血液中の酸をアルカリ性にする働きがあります。
煎茶でカフェイン(茶葉2.3%、浸出液:茶葉10g/90℃430ml、1分0.02g)、タンニン(茶葉13.0%、浸出液:茶葉10g/90℃430ml、1分0.07g)、葉緑素、ビタミンC(浸出液6mg/100cc)を含み旨みの成分とし、主にアミノ酸のテアニン(アミノ酸:集中力をアップさせる)、アルギニン、アスパラギン酸、グルタミン酸を含みます。
ポリフェノールは70℃以下のほうがカテキン(渋み、エビガロカテキンガレードでで1/2を占める:消臭、抗ウイルス)の吸収がよいとしています。熱湯では、分子が大きく吸収されにくいようです。食事の1時間前に飲むと油を分解しやすいといいます。
緑茶の香りは、数多くの香気成分が合わさって生み出しています。代表的な香気成分には、青葉アルコール(別名リーフアルコール)、リナロール、ゲラニオール、ピラジン、ジメチルスルフィド、 ピロールなどです。
◇青葉アルコールLeaf alcoholは、蒸らし時間が短い煎茶に、煎茶や新茶に多く含み若葉の爽やかな香りに由来します。心を落ち着かせます。化学式は C6H12O、分子量は 100.16。 IUPAC命名法では (Z)-3-ヘキセン-1-オールまたは cis-3-ヘキセン-1-オールとしています。
不飽和アルコールのひとつで、ほとんどの緑の葉に特に生葉に多く含みます。1933年、京都大学の武居三吉教授により緑茶の香り成分として発見したものです。葉を揉むなど衝撃を加えると匂いが強くなり、芝生も刈った時の方がより匂いを感じとることができるのです。ストレス解消・疲労回復・記憶力アップ・花粉症の軽減・快眠・免疫力低下の抑制に働くといいます。新茶に多く含むことから、新茶は普通の茶葉より「青葉アルコール」の濃度が高く、より強く働きます。
◇リナロオールとゲラニオールの芳香性は上級煎茶ほど多く含み一番茶の上級煎茶ほど香りが良いのです。
◇ピロールPyrroleは緑茶を火入れ(乾燥)する際に発生する香りの成分で、緑茶の香りを特徴づける成分のひとつです。
緑茶の一杯で朝には眠気覚ましにスッキリ、 昼なら、食後に口中をサッパリと、 夜には一日の疲れを癒やすため、低温で淹(い)れまろやかなお茶としてリラックスできます。 時間帯に合ったお茶を試して自分に合うお茶の飲み方を楽しみましょう。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。
どうやって作られているのか?緑茶は、茶葉を摘み取って加熱し、発酵させずに乾燥させて作られます。
緑茶の作り方
お茶の葉を摘み取ってすぐに加熱し、発酵(酸化発酵)しないようにして作ったのが緑茶、完全に発酵(酸化発酵)させるのが紅茶、その中間に位置するのがウーロン茶などの半発酵茶です。 また、緑茶は、加熱の方法の違いによって釜炒り製(中国式)、蒸し製(日本独特のもの)の二通りに分けられます。
⒈茶畑で茶摘みを 毎年4月下旬から5月になると行なわれています。.
2.蒸しで摘採(てきさい)したばかりの生葉は品質劣化を防ぐことから、ただちに湿気度の高い空気を送り、呼吸熱を下げ味・香りを決める「蒸す」 工程としてあります。
3.蒸された新芽は、次に「揉み」の作業工程で行います。
4.次に乾燥へ 揉みが終わると、茶葉の「乾燥」です。
5.大方の荒茶の完成で「選別」の工程に入ります。
6.最終段階で火入れにより、茶葉を乾燥させ、香りを引き出す工程です。茶葉の芯まで火を入れることで、うまみや香りが引き立ち、お茶の味や香り、鮮度を保つことができます。 100℃を超える温度で加熱することで茶葉内部まで均一に温め、芯水(茶葉の中に含まれる水分)を逃がします。短時間で乾燥させます。火入れの温度や時間などの微妙な加減を重要視し茶の種類のみならず、季節・その日の温度、湿度等によって、火入れ時の温度・時間の調整をし、その調整の仕方により風味の異なるお茶に仕上がり生葉に対して歩留りは23%程度になります。
緑茶とは、茶葉を発酵させずに作られたお茶の総称で、煎茶や玉露、番茶、抹茶、焙じ茶などが含まれます。その成分は、
◇煎茶浸出液100g中でエネルギー2kcal、水分99.4g、たんぱく質0.2g、脂質(0)g、炭水化物0.2g、灰分0.1g、ナトリウム3mg、カリウム27mg、カルシウム3mg、マグネシウム2mg、リン2mg、鉄0.2mg、亜鉛Trmg、銅0.01mg、マンガン0.31mg、ビタミンA(0)μg、ビタミンD:(0)μg、ビタミンE:-mg、ビタミンK:Trμg、ビタミンB1:0mg、ビタミンB2:0.05mg、ナイアシン0.2mg、ビタミンB6:0.01mg、ビタミンB12:(0)μg、葉酸16μg、パントテン酸0.04mg、ビタミンC6mg 食物繊維-g
程度です。
新茶といわれる八十八夜の茶摘みは、立春(2月3日ごろ)から数えて88日の5月2日(2025,5,1)ごろにあたり一番茶としての茶摘みを行なっています。
北限が秋田、岩手県で6月頃が新茶の時期にあたり暖かい地方と前後すると2ヶ月のずれがあり出荷しているようです。2番茶、3番茶は、夏茶ともいわれ6月中旬、7月下旬から茶摘みし3月から9月にかけての出荷です。
お茶は、アルカリ性で穀類、蓄肉、魚介類、卵類の酸性食品により過剰に傾きがちな血液中の酸をアルカリ性にする働きがあります。
煎茶でカフェイン(茶葉2.3%、浸出液:茶葉10g/90℃430ml、1分0.02g)、タンニン(茶葉13.0%、浸出液:茶葉10g/90℃430ml、1分0.07g)、葉緑素、ビタミンC(浸出液6mg/100cc)を含み旨みの成分とし、主にアミノ酸のテアニン(アミノ酸:集中力をアップさせる)、アルギニン、アスパラギン酸、グルタミン酸を含みます。
ポリフェノールは70℃以下のほうがカテキン(渋み、エビガロカテキンガレードでで1/2を占める:消臭、抗ウイルス)の吸収がよいとしています。熱湯では、分子が大きく吸収されにくいようです。食事の1時間前に飲むと油を分解しやすいといいます。
緑茶の香りは、数多くの香気成分が合わさって生み出しています。代表的な香気成分には、青葉アルコール(別名リーフアルコール)、リナロール、ゲラニオール、ピラジン、ジメチルスルフィド、 ピロールなどです。
◇青葉アルコールLeaf alcoholは、蒸らし時間が短い煎茶に、煎茶や新茶に多く含み若葉の爽やかな香りに由来します。心を落ち着かせます。化学式は C6H12O、分子量は 100.16。 IUPAC命名法では (Z)-3-ヘキセン-1-オールまたは cis-3-ヘキセン-1-オールとしています。
不飽和アルコールのひとつで、ほとんどの緑の葉に特に生葉に多く含みます。1933年、京都大学の武居三吉教授により緑茶の香り成分として発見したものです。葉を揉むなど衝撃を加えると匂いが強くなり、芝生も刈った時の方がより匂いを感じとることができるのです。ストレス解消・疲労回復・記憶力アップ・花粉症の軽減・快眠・免疫力低下の抑制に働くといいます。新茶に多く含むことから、新茶は普通の茶葉より「青葉アルコール」の濃度が高く、より強く働きます。
◇リナロオールとゲラニオールの芳香性は上級煎茶ほど多く含み一番茶の上級煎茶ほど香りが良いのです。
◇ピロールPyrroleは緑茶を火入れ(乾燥)する際に発生する香りの成分で、緑茶の香りを特徴づける成分のひとつです。
緑茶の一杯で朝には眠気覚ましにスッキリ、 昼なら、食後に口中をサッパリと、 夜には一日の疲れを癒やすため、低温で淹(い)れまろやかなお茶としてリラックスできます。 時間帯に合ったお茶を試して自分に合うお茶の飲み方を楽しみましょう。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。