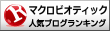・☕コーヒーの日Coffee Day こーひ-のひ
1983年(昭和58年)に全日本コーヒー協会で10月1日を「コーヒーの日」と制定しています。コーヒー業界では10月1日にはじまり、翌年の9月末に終わる「コーヒー年度」というものがあって、これは栽培から出荷までの1年間の流れに沿ったものです。
1983年(昭和58年)に全日本コーヒー協会で10月1日を「コーヒーの日」と制定しています。コーヒー業界では10月1日にはじまり、翌年の9月末に終わる「コーヒー年度」というものがあって、これは栽培から出荷までの1年間の流れに沿ったものです。
コーヒー年度のスタートにあたり、またこれからの季節、暖かいコーヒーがよく飲まれるために、この日に制定しています。
三大嗜好飲料として紅茶・コーヒー(珈琲Caffee)・ココア(又はマテ茶)、世界三大コーヒーはブルーマウンテン(ジャマイカ)、キリマンジャロ(タンザニア)、コナ(ハワイ)として掲げられています。
すっかり日本人にも溶け込んだコーヒーについてです。歴史への登場は酒や茶には遅れますが、現在では世界で最も多くの国々で飲用している嗜好飲料です。
コーヒーがいつ頃から人間への利用があったかは、はっきりした記述は示されていません。
三大嗜好飲料として紅茶・コーヒー(珈琲Caffee)・ココア(又はマテ茶)、世界三大コーヒーはブルーマウンテン(ジャマイカ)、キリマンジャロ(タンザニア)、コナ(ハワイ)として掲げられています。
すっかり日本人にも溶け込んだコーヒーについてです。歴史への登場は酒や茶には遅れますが、現在では世界で最も多くの国々で飲用している嗜好飲料です。
コーヒーがいつ頃から人間への利用があったかは、はっきりした記述は示されていません。
アカネ科、アビシニア(エチオピア)原産、中南米が主産地です。コーヒーは、コーヒー豆(コーヒーノキの種子)を焙煎し粉砕して熱湯ないし水で成分を抽出した飲料のことです。
コーヒーノキは熱帯地域で栽培する高さ6mに達する常緑樹、葉は、卵形で先が尖(とが)り、対生、暗緑色で波打ち光沢があります。
3年目頃よりジャスミンに似た香りの良い白い花を咲かせ、果実をほぼ年中収穫し肉質で2個の種子(1個1~1.5cm)を有し、楕円状で2つ一組でコーヒーチェリーとも呼ばれ成熟すると深紅色になります。果実の赤い果肉は甘く食べられ、有史以前から野生種の利用があったと考えられます。
アラビカ種は原産地エチオピアで、リベリカ種は西アフリカ沿岸でヨーロッパ人が発見する以前から栽培し利用しています。現在見られる「焙煎した豆から抽出したコーヒー」が登場したのは13世紀以降と見られています。
豆を焙煎するようになった経緯は不確かですが、13世紀に入って以前は薬として、やがて生豆から煮出されるコーヒーは焙煎され始めました。焙煎した豆のその味と香りは、それまでのコーヒーとは全く違うものになり、競って飲むものとなっていったのではないかと推測します。
当時の焙煎方法は、陶器や鉄製の浅い皿状のものに生豆を入れて、それを火にかけて棒でかき混ぜるという原始的な方法のようです。
日本には1700年代前後に長崎出島へオランダ人によって紹介がありましたが普及したのは上流階級を中心に明治時代に入ってからといわれます。日本での産出はなく、ほとんどすべてが輸入品で占められ加工しています。
第二次世界大戦でコーヒーは敵国飲料として輸入停止になり、戦後は昭和25年から輸入が始まり現在に至っています。
コーヒーはアラビア語でコーヒーを意味するカフワ (アラビア語:qahwa) が転訛したものです。日本語の「コーヒー」は、江戸時代にオランダ人からもたらされた際の、オランダ語: koffie(コーフィー)に由来します。漢字で珈琲のほか可否・架非・加非・咖啡・カフェーなどの字もあてられています。
コーヒーの木の栽培は、コーヒー・ベルトと呼ばれる、温暖な赤道を中心とした南北25度の地域で行われています。平均気温は約20℃、年間降雨量は約1,500~2,000mm、水はけがよく、適度に日当たりの良いことが必要です。4~5年かけて育てた木よりコーヒー豆が採取できます。農園では収穫がしやすいように1.5~2mほどに剪定しています。
コーヒーはコーヒー豆(コーヒーノキの種子)を焙煎し粉砕して熱湯ないし水で成分を抽出した飲料のことです。
硬い実で、成熟に9ヶ月ほどかかります。また、枝の先端に付く1粒だけ丸い種子はピーベリーPeaberryと呼ばれ、珍重しています。
米国農務省の統計によると一番に生産量が多いのがブラジルで、南米地域の世界の生産量全体の約3割を占めています。
日本には1700年代前後に長崎出島へオランダ人によって紹介がありましたが普及したのは上流階級を中心に明治時代に入ってからといわれます。日本での産出はなく、ほとんどすべてが輸入品で占められ加工しています。
第二次世界大戦でコーヒーは敵国飲料として輸入停止になり、戦後は昭和25年から輸入が始まり現在に至っています。
コーヒーはアラビア語でコーヒーを意味するカフワ (アラビア語:qahwa) が転訛したものです。日本語の「コーヒー」は、江戸時代にオランダ人からもたらされた際の、オランダ語: koffie(コーフィー)に由来します。漢字で珈琲のほか可否・架非・加非・咖啡・カフェーなどの字もあてられています。
コーヒーの木の栽培は、コーヒー・ベルトと呼ばれる、温暖な赤道を中心とした南北25度の地域で行われています。平均気温は約20℃、年間降雨量は約1,500~2,000mm、水はけがよく、適度に日当たりの良いことが必要です。4~5年かけて育てた木よりコーヒー豆が採取できます。農園では収穫がしやすいように1.5~2mほどに剪定しています。
コーヒーはコーヒー豆(コーヒーノキの種子)を焙煎し粉砕して熱湯ないし水で成分を抽出した飲料のことです。
硬い実で、成熟に9ヶ月ほどかかります。また、枝の先端に付く1粒だけ丸い種子はピーベリーPeaberryと呼ばれ、珍重しています。
米国農務省の統計によると一番に生産量が多いのがブラジルで、南米地域の世界の生産量全体の約3割を占めています。
しかし、2位以下にはアジア国の躍進が目立って全体の生産量の3割近くを担うようになりました。現在の生産国2位はベトナム、3位がコロンビア、4位がインドネシア、5位がエチオピアです。
ほぼ輸入に頼っている日本ですが、2015年度の財務省の調べでは、ブラジル、ベトナム、コロンビアの上位3か国の比重が高く全体輸入量の約70%を占め全体の輸入量は30万トンを越えています。
世界の一人当たりの消費量は1位ノルウェー、2位スイス、EU(European Union28カ国=欧州連合)・アメリカ3位、日本4位でノルウェーでは日本の3倍のコーヒーを消費しています。
国別消費量ではEU:1位、アメリカ2位、ブラジル3位、日本が4位に続きます。
生産量の7~8割はアラビカ種で約70カ国で栽培・収穫・生産しています。そのコーヒー農園では、生のコーヒー豆のことで生豆(なままめ・きまめ)を取り出し精製作業までを行っています。コーヒー豆の種類は、主に生産地で分けられ名前の付け方は、国名(ブラジル、コロンビア、ケニア、コスタリカ等)、山域(キリマンジャロ、ブルーマウンテン、エメラルドマウンテン等)、積出港(モカ、サントス等)、栽培地名(コナ、マンデリン、ジャワ等)などです。更に特定の農園の名前を冠したコーヒー豆も増えつつあります。
代表的なコーヒー豆は
◇ブルーマウンテン(ジャマイカ)
最高級の品質と呼ばれ卓越した香気を持ち、調和の取れた味わい、軽い口当りと滑らかな咽越しが特徴です。ジャマイカで生産するコーヒーのうちごく一部の産地のものがブルーマウンテンとブランド付けられています。その中でもさらにランク付けをしています。
◇キリマンジャロ(タンザニア)
世界の収穫量の1%程度と少なくタンザニア産の日本での呼び方で強い酸味とコクが特長です。野性味あふれると評されることが多く深い焙煎では上品な苦味主体で浅煎り~中煎りとは違った風味が楽しめるといいます。
◇コナ(ハワイ)
非常に強い酸味とコク・風味を特徴としています。ブレンドに用いると良質な酸味が与えられブルーマウンテンに次ぐブランドで高価で取引しています。
他にも
◇モカ(イエメン、エチオピア)
香気に優れ独特の酸味を持ち、甘みとコクが加わります。もっとも古いブランド名です。コーヒー原産地であり、イタリアなどではコーヒーのことをモカと呼びます。イエメン産のマタリ、エチオピア産ハラー、シダモ等が知られています。
◇グアテマラ
酸味とコクに優れ、香気も良好で全体的に華やかさとキレのいい後味が特徴です。
◇ブラジル
香りの甘さが軽快で酸味・コク、苦みともに軽くバランスが良い。安価でありブレンドのベースとして多く使われています。
ほぼ輸入に頼っている日本ですが、2015年度の財務省の調べでは、ブラジル、ベトナム、コロンビアの上位3か国の比重が高く全体輸入量の約70%を占め全体の輸入量は30万トンを越えています。
世界の一人当たりの消費量は1位ノルウェー、2位スイス、EU(European Union28カ国=欧州連合)・アメリカ3位、日本4位でノルウェーでは日本の3倍のコーヒーを消費しています。
国別消費量ではEU:1位、アメリカ2位、ブラジル3位、日本が4位に続きます。
生産量の7~8割はアラビカ種で約70カ国で栽培・収穫・生産しています。そのコーヒー農園では、生のコーヒー豆のことで生豆(なままめ・きまめ)を取り出し精製作業までを行っています。コーヒー豆の種類は、主に生産地で分けられ名前の付け方は、国名(ブラジル、コロンビア、ケニア、コスタリカ等)、山域(キリマンジャロ、ブルーマウンテン、エメラルドマウンテン等)、積出港(モカ、サントス等)、栽培地名(コナ、マンデリン、ジャワ等)などです。更に特定の農園の名前を冠したコーヒー豆も増えつつあります。
代表的なコーヒー豆は
◇ブルーマウンテン(ジャマイカ)
最高級の品質と呼ばれ卓越した香気を持ち、調和の取れた味わい、軽い口当りと滑らかな咽越しが特徴です。ジャマイカで生産するコーヒーのうちごく一部の産地のものがブルーマウンテンとブランド付けられています。その中でもさらにランク付けをしています。
◇キリマンジャロ(タンザニア)
世界の収穫量の1%程度と少なくタンザニア産の日本での呼び方で強い酸味とコクが特長です。野性味あふれると評されることが多く深い焙煎では上品な苦味主体で浅煎り~中煎りとは違った風味が楽しめるといいます。
◇コナ(ハワイ)
非常に強い酸味とコク・風味を特徴としています。ブレンドに用いると良質な酸味が与えられブルーマウンテンに次ぐブランドで高価で取引しています。
他にも
◇モカ(イエメン、エチオピア)
香気に優れ独特の酸味を持ち、甘みとコクが加わります。もっとも古いブランド名です。コーヒー原産地であり、イタリアなどではコーヒーのことをモカと呼びます。イエメン産のマタリ、エチオピア産ハラー、シダモ等が知られています。
◇グアテマラ
酸味とコクに優れ、香気も良好で全体的に華やかさとキレのいい後味が特徴です。
◇ブラジル
香りの甘さが軽快で酸味・コク、苦みともに軽くバランスが良い。安価でありブレンドのベースとして多く使われています。
◇コロンビア
酸味と甘味が重厚だが突出せずバランスが良く安価でコーヒーの基本の味で多くはブレンドのベースに使われています。
コーヒーの精製は生産地で行われ精製した生豆と呼ばれ、カビなどの発生を防ぐために水分含量が10~12%で保存し、消費地に輸出しています。焙煎の工程は消費国でロースターと呼ばれる大手のコーヒー豆卸業者が行うほか、コーヒー豆小売りを行う販売店や喫茶店などで自家焙煎します。
酸味と甘味が重厚だが突出せずバランスが良く安価でコーヒーの基本の味で多くはブレンドのベースに使われています。
コーヒーの精製は生産地で行われ精製した生豆と呼ばれ、カビなどの発生を防ぐために水分含量が10~12%で保存し、消費地に輸出しています。焙煎の工程は消費国でロースターと呼ばれる大手のコーヒー豆卸業者が行うほか、コーヒー豆小売りを行う販売店や喫茶店などで自家焙煎します。
また家庭で生豆から焙煎することも可能で、近年は専門店等で生豆の小売も見られています。
浅煎り→深煎りの順の焙煎度を用い一般に、浅煎りは香りや酸味に優れ深煎りは苦味に優れ嗜好に合わせます。焙煎したコーヒー豆は、抽出される前に粉状に細かく粉砕(グラインド)し挽きます。粉砕は粉の大きさに応じて、細挽き、中挽き、粗挽きします。
嗜好によりコーヒーの風味は、焙煎・挽き加減・淹(い)れ方・用いる器具などにより異なります。
レギュラーコーヒーは、焙煎・粉砕したコーヒーの粉を、湯または水に接触させることで中の成分を抽出し、コーヒー飲料が出来上がります。抽出の仕方にウォータードリップ(水出し)は1杯に8時間程度を要しています。ペーパードリップ、ネルドリップなどがあります。
浅煎り→深煎りの順の焙煎度を用い一般に、浅煎りは香りや酸味に優れ深煎りは苦味に優れ嗜好に合わせます。焙煎したコーヒー豆は、抽出される前に粉状に細かく粉砕(グラインド)し挽きます。粉砕は粉の大きさに応じて、細挽き、中挽き、粗挽きします。
嗜好によりコーヒーの風味は、焙煎・挽き加減・淹(い)れ方・用いる器具などにより異なります。
レギュラーコーヒーは、焙煎・粉砕したコーヒーの粉を、湯または水に接触させることで中の成分を抽出し、コーヒー飲料が出来上がります。抽出の仕方にウォータードリップ(水出し)は1杯に8時間程度を要しています。ペーパードリップ、ネルドリップなどがあります。
コーヒーサイフォンを用いる方法もあります。
コーヒー豆はその消費目的に応じて数種類混合し、ブレンドコーヒーと呼ばれています。一方一種類の焙煎豆のみからなるコーヒーをストレートコーヒーと呼びます。
コーヒーのバリエーションとしては、アイスコーヒー、カフェ・オ・レ 、エスプレッソ 、ブラック、カプチーノ、ウィンナ・コーヒー 、アラビア・コーヒーなどです。
◇トルココーヒーは小鍋に、深煎り細挽きの粉と水、砂糖を入れ直火にかけ、かき混ぜながら煮沸し、煮立つ直前に火から離し落ち着いたら再度火にかける。これを2、3回繰り返し、表面の泡を消さないようにカップに注きます。濃く煮出し、濾さずにカップに注いだものから上澄みだけを飲みます。
◇コロンビア式コーヒー
ティントとも呼ばれる、黒砂糖を加えた沸騰した湯を用い、火を落してから粉を加え、数分静置して粉が沈んだところで上澄みだけ飲む形式です。
◇インディアンコーヒー
南インドで好まれるインド風カフェ・オ・レで鍋にミルクを入れて温め、ミルクが沸騰直前に深煎で入れたコーヒーと、砂糖、塩少々を入れます。2つのカップを行き来させて、泡立てて飲みます。
◇アメリカン・コーヒー
本来は浅煎り豆から薄めに抽出したコーヒーのことです。アメリカで一時期コーヒー豆の高騰により少ない量でもおいしく飲めるように浅煎りを用いていたことを起源としています。
◇グリーン・コーヒー
焙煎する前の生豆の状態から成分を抽出したコーヒーで、加熱で壊れやすいクロロゲン酸が効率的に摂取できることから、2011年のインドMallya HospitalのM.V.Nagendranらによる研究結果以降、アメリカを中心にブームとなっていいるようです。
コーヒー豆はその消費目的に応じて数種類混合し、ブレンドコーヒーと呼ばれています。一方一種類の焙煎豆のみからなるコーヒーをストレートコーヒーと呼びます。
コーヒーのバリエーションとしては、アイスコーヒー、カフェ・オ・レ 、エスプレッソ 、ブラック、カプチーノ、ウィンナ・コーヒー 、アラビア・コーヒーなどです。
◇トルココーヒーは小鍋に、深煎り細挽きの粉と水、砂糖を入れ直火にかけ、かき混ぜながら煮沸し、煮立つ直前に火から離し落ち着いたら再度火にかける。これを2、3回繰り返し、表面の泡を消さないようにカップに注きます。濃く煮出し、濾さずにカップに注いだものから上澄みだけを飲みます。
◇コロンビア式コーヒー
ティントとも呼ばれる、黒砂糖を加えた沸騰した湯を用い、火を落してから粉を加え、数分静置して粉が沈んだところで上澄みだけ飲む形式です。
◇インディアンコーヒー
南インドで好まれるインド風カフェ・オ・レで鍋にミルクを入れて温め、ミルクが沸騰直前に深煎で入れたコーヒーと、砂糖、塩少々を入れます。2つのカップを行き来させて、泡立てて飲みます。
◇アメリカン・コーヒー
本来は浅煎り豆から薄めに抽出したコーヒーのことです。アメリカで一時期コーヒー豆の高騰により少ない量でもおいしく飲めるように浅煎りを用いていたことを起源としています。
◇グリーン・コーヒー
焙煎する前の生豆の状態から成分を抽出したコーヒーで、加熱で壊れやすいクロロゲン酸が効率的に摂取できることから、2011年のインドMallya HospitalのM.V.Nagendranらによる研究結果以降、アメリカを中心にブームとなっていいるようです。
◇サルタナコーヒー
コーヒー豆ではなく、コーヒーの実を乾燥させたものを少し焙ってから煮出したものです。イエメンではギシルと呼んでいます。
生豆から抽出して飲むレギュラーコーヒー以外に抽出の手間を掛けずに手軽にコーヒーを飲むためのものとして、インスタントコーヒー、缶コーヒー、リキッドコーヒーLiquidcoffee(液体コーヒー:ペットボトル・紙パック入り)があります。
種子そのものが生豆(なままめ、きまめ)の状態で4、5年の保存が可能です。飲用時にブレンドして好みの味で焙煎(ばいせん200~250℃)、粉砕したら不純物を取り除く方法(ドリップ式、ネルの袋でこすなど)ですぐに飲むようにすることにより香りを楽しめます。
コーヒー豆ではなく、コーヒーの実を乾燥させたものを少し焙ってから煮出したものです。イエメンではギシルと呼んでいます。
生豆から抽出して飲むレギュラーコーヒー以外に抽出の手間を掛けずに手軽にコーヒーを飲むためのものとして、インスタントコーヒー、缶コーヒー、リキッドコーヒーLiquidcoffee(液体コーヒー:ペットボトル・紙パック入り)があります。
種子そのものが生豆(なままめ、きまめ)の状態で4、5年の保存が可能です。飲用時にブレンドして好みの味で焙煎(ばいせん200~250℃)、粉砕したら不純物を取り除く方法(ドリップ式、ネルの袋でこすなど)ですぐに飲むようにすることにより香りを楽しめます。
焙煎温度、浸出するときの熱湯の温度、時間、ブレンドの仕方によって香り、風合いに違いがでます。
アイスコーヒーは、濃クロロゲン酸にマルトースをグルコースに分解する酵素であるα-グルコシダーゼの阻害活性が認められています。
アイスコーヒーは、濃クロロゲン酸にマルトースをグルコースに分解する酵素であるα-グルコシダーゼの阻害活性が認められています。
インスタントコーヒーは、浸出液を粉末化したもので100%純粋のコーヒー豆より製造し混ぜものはないのですが、缶コーヒーには、メーカーによって乳化剤、デキストリン、香料、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳とさまざまに混入しているものもあります。
コーヒーには飲む以外に様々な用途があります。
食品原料としてコーヒー豆から抽出したエキスを香り付けや味付けのために用いた和洋菓子・清涼飲料などにも用いています。
そのほかの使い方として、コーヒー豆の出し殻を脱臭剤・成形木炭として使われます。
特色ある成分とし香り成分(ジテルペン類)のカフェストール Cafestol、カフェオール・ カーウェオールKahweol、アルカロイドのカフェイン0.05g~0.1g/浸出液150ccがあり脳神経に刺激を与え鎮静、利尿作用を有します。
タンニンの主成分のクロロゲン酸(タンニン酸、レギラー>インスタント/可飲部:風味を左右している)が珈琲豆に多く水に溶ける苦味の成分で抗酸化、脂肪分解作用、消臭、心身を緊張させる作用があります。
香りの成分で、ピラジンが血栓を作りにくくし肝機能を強化します。 メラノイジンMelanoidin は褐色色素とも言われ、コーヒーの色や苦味に関わる物質ですが、脂質の酸化 を防ぎいで動脈硬化を予防します。
焙煎過程でほとんど分解されてしまうトリゴネリンTrigonelline(アルカロイド)を含み認知症予防に有効であり近年、トリゴネリンをなるべく分解しないような焙煎方法を検討がおこなわれています。
喫煙とともにコーヒーの多飲(5杯/1日以上)によってコレステロール、ホモシステイン(認知症、動脈硬化症の原因物質といい悪玉アミノ酸ともいう)値の上昇が見られています。葉酸、ビタミンB6、B12の働きで抑制、改善するといいます。
抽出されたコーヒーは0.04%程度のカフェインを含みます。一日に300mg以上(コーヒー3杯に相当)のカフェインを常用する人には、カフェイン禁断頭痛と呼ばれる一種の禁断症状が現れることがあります。
急性作用として特に消化器疾患、高血圧、パニック障害などの疾患がある場合など、特定の患者や病態によっては、これらの通常は無害な作用が有害に働くことがあるため、注意が必要です。
アイスでもホットでも美味しく飲め今日では日本人の生活の中にも溶け込んでいます。朝に一杯のコーヒーは目覚めのコーヒーです。コーヒーから一日の元気を貰(もら)いましょう。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。
(初版2020.10.1)