
私が中学3年の時、国語の教科書で読み、非常に感銘を受けた魯迅の「故郷」は、現代でも教科書に採用されている永遠のベストセラー小説。ラストの一節「希望は本来有というものでもなく、無というものでもない。これこそ地上の道のように、初めから道があるのではないが、歩く人が多くなると初めて道が出来る。」は当時の私にはなかなか理解できなかったし、今もその意味が十分わかっているとは言い難い。
 おそらく魯迅自身の体験に基づいて書かれていると思われるこの小説は、清朝末期の中国が舞台。高級官吏になって20年ぶりに故郷を訪れた「私」。かつて住んでいた家が売却されることになり、その前に一目自分が少年時代を過ごした村の様子を見ておこうと戻ってきた。幼馴染のルントウが、息子を連れて会いに来てくれたが、すっかり風貌が変わっていた。以下引用ーーー紫色の丸顔はすでに変じてどんよりと黄ばみ、額には溝のような深皺が出来ていた。目許は彼の父親ソックリで地腫れがしていたが、これはわたしも知っている。海辺地方の百姓は年じゅう汐風に吹かれているので皆が皆こんな風になるのである。彼の頭の上には破れた漉羅紗帽が一つ、身体の上にはごく薄い棉入れが一枚、その著《き》こなしがいかにも見すぼらしく、手に紙包と長煙管《ながぎせる》を持っていたが、その手もわたしの覚えていた赤く丸い、ふっくらしたものではなく、荒っぽくざらざらして松皮《まつかわ》のような裂け目があった。ーーーしかも物言いが非常によそよそしい。ルントウが発した「旦那様…」と言う「私」との身分差を強調するような呼びかけは、かつて仲良かった二人の関係をルントウの側から断ち切るかのようである。「私」が夢見ていた美しく、懐かしい故郷はそこにはなかった。昔は「豆腐屋小町」と崇められていた美人の娘は、強欲な女性に変わっていた。
おそらく魯迅自身の体験に基づいて書かれていると思われるこの小説は、清朝末期の中国が舞台。高級官吏になって20年ぶりに故郷を訪れた「私」。かつて住んでいた家が売却されることになり、その前に一目自分が少年時代を過ごした村の様子を見ておこうと戻ってきた。幼馴染のルントウが、息子を連れて会いに来てくれたが、すっかり風貌が変わっていた。以下引用ーーー紫色の丸顔はすでに変じてどんよりと黄ばみ、額には溝のような深皺が出来ていた。目許は彼の父親ソックリで地腫れがしていたが、これはわたしも知っている。海辺地方の百姓は年じゅう汐風に吹かれているので皆が皆こんな風になるのである。彼の頭の上には破れた漉羅紗帽が一つ、身体の上にはごく薄い棉入れが一枚、その著《き》こなしがいかにも見すぼらしく、手に紙包と長煙管《ながぎせる》を持っていたが、その手もわたしの覚えていた赤く丸い、ふっくらしたものではなく、荒っぽくざらざらして松皮《まつかわ》のような裂け目があった。ーーーしかも物言いが非常によそよそしい。ルントウが発した「旦那様…」と言う「私」との身分差を強調するような呼びかけは、かつて仲良かった二人の関係をルントウの側から断ち切るかのようである。「私」が夢見ていた美しく、懐かしい故郷はそこにはなかった。昔は「豆腐屋小町」と崇められていた美人の娘は、強欲な女性に変わっていた。
魯迅に限らず私たちも、過去の美しい思い出を玉手箱に閉じ込めておけず開けてはみたものの、昔のような輝きは得られず落胆する経験を、多かれ少なかれ持っているのではないだろうか?だとするなら、思い出は思い出として浸っているのがいいのかもしれない。
 おそらく魯迅自身の体験に基づいて書かれていると思われるこの小説は、清朝末期の中国が舞台。高級官吏になって20年ぶりに故郷を訪れた「私」。かつて住んでいた家が売却されることになり、その前に一目自分が少年時代を過ごした村の様子を見ておこうと戻ってきた。幼馴染のルントウが、息子を連れて会いに来てくれたが、すっかり風貌が変わっていた。以下引用ーーー紫色の丸顔はすでに変じてどんよりと黄ばみ、額には溝のような深皺が出来ていた。目許は彼の父親ソックリで地腫れがしていたが、これはわたしも知っている。海辺地方の百姓は年じゅう汐風に吹かれているので皆が皆こんな風になるのである。彼の頭の上には破れた漉羅紗帽が一つ、身体の上にはごく薄い棉入れが一枚、その著《き》こなしがいかにも見すぼらしく、手に紙包と長煙管《ながぎせる》を持っていたが、その手もわたしの覚えていた赤く丸い、ふっくらしたものではなく、荒っぽくざらざらして松皮《まつかわ》のような裂け目があった。ーーーしかも物言いが非常によそよそしい。ルントウが発した「旦那様…」と言う「私」との身分差を強調するような呼びかけは、かつて仲良かった二人の関係をルントウの側から断ち切るかのようである。「私」が夢見ていた美しく、懐かしい故郷はそこにはなかった。昔は「豆腐屋小町」と崇められていた美人の娘は、強欲な女性に変わっていた。
おそらく魯迅自身の体験に基づいて書かれていると思われるこの小説は、清朝末期の中国が舞台。高級官吏になって20年ぶりに故郷を訪れた「私」。かつて住んでいた家が売却されることになり、その前に一目自分が少年時代を過ごした村の様子を見ておこうと戻ってきた。幼馴染のルントウが、息子を連れて会いに来てくれたが、すっかり風貌が変わっていた。以下引用ーーー紫色の丸顔はすでに変じてどんよりと黄ばみ、額には溝のような深皺が出来ていた。目許は彼の父親ソックリで地腫れがしていたが、これはわたしも知っている。海辺地方の百姓は年じゅう汐風に吹かれているので皆が皆こんな風になるのである。彼の頭の上には破れた漉羅紗帽が一つ、身体の上にはごく薄い棉入れが一枚、その著《き》こなしがいかにも見すぼらしく、手に紙包と長煙管《ながぎせる》を持っていたが、その手もわたしの覚えていた赤く丸い、ふっくらしたものではなく、荒っぽくざらざらして松皮《まつかわ》のような裂け目があった。ーーーしかも物言いが非常によそよそしい。ルントウが発した「旦那様…」と言う「私」との身分差を強調するような呼びかけは、かつて仲良かった二人の関係をルントウの側から断ち切るかのようである。「私」が夢見ていた美しく、懐かしい故郷はそこにはなかった。昔は「豆腐屋小町」と崇められていた美人の娘は、強欲な女性に変わっていた。魯迅に限らず私たちも、過去の美しい思い出を玉手箱に閉じ込めておけず開けてはみたものの、昔のような輝きは得られず落胆する経験を、多かれ少なかれ持っているのではないだろうか?だとするなら、思い出は思い出として浸っているのがいいのかもしれない。











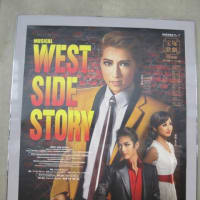








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます