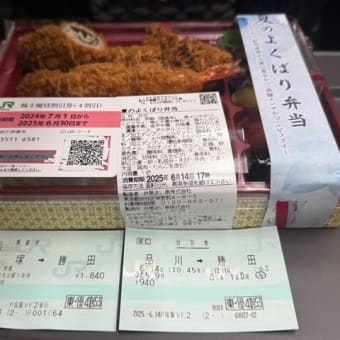横浜港が貿易の玄関口だった時代は相当の輸送量があり入換機もかなりの両数の配置があったようです。また横浜港に上陸したGHQ幹部の専用列車牽引のため横浜機関区には専用機が配置されていたと言う話も残っています。しかし私が横浜機関区へ遊びに行く様になった時代では既に蒸機の配置は無く、DD13の配置のみでした。ただここのDD13の一部には総括制御出来る500番台が配置されて高島―根岸の石油輸送に活躍していました。写真のDE10はDD13淘汰後に横浜機関区に配置されていました。 (写真は再掲) 80,06,11 横浜機関区 DE10526号機
今は面影もありませんが、今の原鉄道模型博物館の少し西よりに横浜機関区がありました。その歴史は極めて古く汐留―桜木町に鉄道が開通した当初の終点側の機関区が桜木町にあり、その機関区が手狭になり移動した機関区が横浜機関区の前身にあたる横浜機関庫と言う事で日本で最古の歴史を持つ機関区でした。その後高島機関庫→高島機関区を経て昭和22年(1947年)に横浜機関区となったと記録に残されています。
私にとって横浜機関区は高島線のD51の折返し機関区と言う認識でした。新鶴見から高島まで牽引し到着して石炭の掻き寄せと給水をして方向を転換して、その後ゆっくりと駐機しているD51を眺めに何度も通いました。たぶん小学6年生に戸塚に引越してから横浜が近くなった事もあり通い始めたのだと思います。ある日は授業が早めに終わると親から戸塚―横浜の子供運賃のお金だけもらって電車に乗って横浜機関区の当直で名前を書いた上で許可をいただき撮影するでもなくD51を半日とか長い日は一日中眺めていた事もありました。一日いると蒸機の煙で真っ黒になります。それを見かねてたぶん20歳前後の燃料係が”坊主、その顔で家に帰ったらお母さんに叱られるぞ!風呂は入って行け”と言うのです。私が躊躇しているとその燃料係は腰のベルトにぶら下げていたタオルを丁寧の洗ってから私の渡し”これで顔を洗って帰りな!”と言ってくれた事がありました。その時、私はそのタオルで顔を拭いたかどうかの記憶はありませんが、子供心にその燃料係のやさしさを感じ、その後国鉄に入社を希望した何パーセントかはあの燃料係の後に続きたいと言う思いからでした。
この機関区は歴史ある立派な扇型車庫を有して機関区廃止後は一時、扇型車庫の保存活動もあった様ですがそれも身を結ばず解体されましたが転車台だけはD51516号機が保存されている本牧公園に移築され今も保存されています。
弊ブログ関連記事
https://white.ap.teacup.com/dt200a/281.html#comment