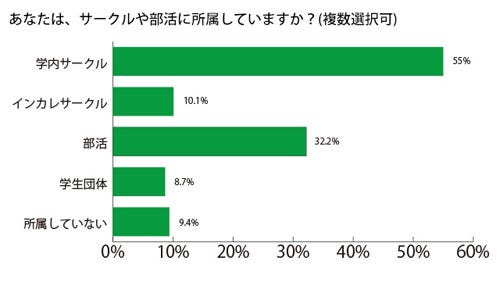Q.他人に質問するときに心がけていることを教えてください
周到に用意された質問に答えるのはとても簡単。反対に、相手が気持ちよく答えてくれるように上手に質問することはなかなか難しいもの。今回はマイナビニュース会員のうち男女300名に、疑問点を質問したり、ヒアリングするときに心がけていることを聞いてみた。
Q.他人に質問(疑問点、ヒアリングなど)するときに心がけていることを教えてください
■事前に調べてまとめる
・「まずは自分で調べる」(35歳男性/情報・IT/営業職)
・「すぐに聞かず、自分で調べてもう絶対にわからない、解決できないと思ったときに聞くようにしている」(33歳女性/学校・教育関連/事務系専門職)
・「ある程度内容をまとめてから質問する」(28歳男性/建設・土木/技術職)
・「事前に質問することを洗い出しておく」(35歳女性/情報・IT/事務系専門職)
・「いくつも質問するのではなくポイントを絞っておくこと」(33歳男性/小売店/販売職・サービス系)
■質問の意図を示す
・「何故、その質問をしたいのか、背景も含めて説明する」(27歳男性/自動車関連/技術職)
・「自分がどこまで調べて、どう理解しているか伝えてから質問している」(27歳女性/自動車関連/事務系専門職)
・「何がわかっていて、何がわからないのかはっきりさせること」(29歳女性/情報・IT/クリエイティブ職)
・「自分がなにがわからないかを整理する」(24歳女性/情報・IT/技術職)
・「わからない点を先に言う、それから事態の詳細を伝える」(25歳男性/電力・ガス・石油/事務系専門職)
■質問攻めは厳禁
・「メモを取り、同じ質問を繰り返さない」(26歳女性/団体・公益法人・官公庁/秘書・アシスタント職)
・「何度も同じことを聞かないように気をつけている、頭でちゃんとまとめてから聞くようにする」(30歳女性/金融・証券/秘書・アシスタント職)
・「連続で質問するとウザがられるので控える」(26歳男性/農林・水産/技術職)
・「質問ばかりしないようにする」(30歳女性/団体・公益法人・官公庁/事務系専門職)
・「長々ダラダラ質問しない」(29歳女性/生保・損保/営業職)
■知ったかぶりをしない
・「わからない時は都度確認する」(40歳女性/医薬品・化粧品/販売職・サービス系)
・「わからなくてもうやむやにしない」(48歳男性/電機/技術職)
・「ちゃんと理解しているか確認する」(38歳男性/情報・IT/技術職)
・「予め分からない事柄をメモし、1つ1つ解決しながら質問するようにしている」(43歳男性/機械・精密機器/技術職)
■相手の状況に配慮
・「その人が忙しくなさそうなときに声をかける」(27歳女性/団体・公益法人・官公庁/事務系専門職)
・「『お忙しいところすみません』などと言ってから質問する」(52歳女性/印刷・紙パルプ/クリエイティブ職)
・「今いいですか?と確認をとってから聞く」(30歳女性/自動車関連/事務系専門職)
・「相手の時間を奪っているのだという意識を持つことにしている」(27歳男性/電力・ガス・石油/事務系専門職)
・「低姿勢で学ぶようにしている」(22歳男性/運輸・倉庫/専門職)
・「聞き終わったらお礼を言う」(27歳女性/運輸・倉庫/その他)
■ヒヤリングでの口調や態度
・「笑顔で話す」(27歳男性/金融・証券/営業職)
・「話せるように和やかに」(46歳男性/電力・ガス・石油/技術職)
・「きつい口調でなく、優しい口調にする」(27歳女性/情報・IT/営業職)
・「威圧的にならないようにする」(33歳女性/その他/その他)
・「相手の意見を肯定してからいろいろ考えて質問する」(34歳女性/団体・公益法人・官公庁/事務系専門職)
・「相手への敬意を忘れずに、否定的なことばかり言わないようにする」(30歳男性/情報・IT/技術職)
・「逃げ道を作り、追い込まない」(48歳男性/通信/事務系専門職)
■不快感を与えない
・「あまりプライベートなことに立ち入らないようにする、分かりやすいように要点を明確にさせる」(32歳女性/その他/クリエイティブ職)
・「自分が聞かれて嫌な事、困る事は相手に対しても聞かない」(35歳男性/情報・IT/技術職)
・「相手が答えにくいような質問はあらかじめしない」(27歳女性/学校・教育関連/その他)
・「不快な気持ちにならないような聞き方をする」(32歳男性/小売店/事務系専門職)
・「嫌味な印象をもたれないようにする」(35歳女性/機械・精密機器/事務系専門職)
■答えやすいよう配慮
・「答えやすいよう二択などにしてきく」(30歳女性/通信/事務系専門職)
・「言い換えたり、例えばを出して答えやすくしている」(23歳女性/商社・卸/事務系専門職)
・「説明が難しいときは相関図などを簡単に書いて一緒に持っていき説明する」(25歳女性/情報・IT/技術職)
・「5W1Hを意識する」(27歳女性/商社・卸/技術職)
・「具体的に質問する事」(31歳女性/金融・証券/事務系専門職)
■よく聞くこと
・「まず最後まで聞く」(24歳女性/アパレル・繊維/販売職・サービス系)
・「相手の顔(目)を見て、真剣に聞く」(27歳女性/団体・公益法人・官公庁/事務系専門職)
・「相手の話をさえぎらない」(31歳男性/商社・卸/事務系専門職)
・「相槌以外極力口を挟まない」(29歳女性/金属・鉄鋼・化学/事務系専門職)
・「何か言いかけたらしっかり聞く」(27歳男性/運輸・倉庫/事務系専門職)
■ズバッと聞くのも効果的
・「ストレートに濁さず聞く」(29歳男性/医療・福祉/専門職)
・「単刀直入にきく」(28歳女性/団体・公益法人・官公庁/事務系専門職)
・「まわりくどく聞かないようにすること」(37歳女性/商社・卸/事務系専門職)
・「何を知りたいかをはっきり言う」(40歳男性/学校・教育関連/営業職)
・「自分が思ってることをストレートにつたえる」(33歳男性/機械・精密機器/技術職)
■総評
他人に質問する時に気をつけていること、まずは疑問点を尋ねる時の準備から見ていこう。多かったのは「自分で調べて」「疑問点を洗い出し」「ポイントをまとめる」こと。分からないからといって、すぐに聞くのではなく、調べてみて、質問事項をまとめることで、相手に「どこまで理解してどこから理解していないか」「どうしてそれを疑問に思ったのか」を伝えることもできるようだ。質問される側も「何が分からないのか分からない」状況を避けられ、お互いのストレスにならずに済むだろう。
質問の時にやってはいけないことは、「何度も同じ質問をする」「知ったかぶりをする」こと。そのためにメモを取り、分からないことはその都度確認する、という真摯な姿勢で質問に望む人が多いようだ。質問に質問を重ねるというのも嫌がられる行為の1つ。それを避けるためにはやはり事前の準備が大事になるだろう。
回答者に対して敬意をはらうことも重要。「相手の時間を奪っているのだという意識を持つことにしている」という回答があったように、教えてもらう側の人間はへりくだる、低姿勢で「学ぶ」という態度が必要だろう。忙しくない時を狙って「今いいですか?」の一言、終わったらお礼を言う、というのも常識だ。
ヒヤリングなどの場で注意したいことは、「和やかな雰囲気作り」と「相手を肯定すること」のようだ。「名前を先に言うと柔らかい印象を与える」とか「クッション言葉を交える」なんて、細かなテクニックを駆使している人もいた。質問ばかりで相手を追いつめることももちろん厳禁。プライベートに立ち入ったり、聞かれたくないことを根掘り葉掘り聞くのも、相手に不快感を与えてしまうので、避けられていた。
相手が答えやすいような質問を用意するという意見もあった。具体的にする、図を用いる、質問を二択にする、言い換えたりたとえを用いる、5W1Hを意識するなど、いろいろなテクニックが明かされていた。質問全般にいえることは、とにかく「相手の話を良く聞く」ということ。話を途中で遮ったり、口を挟んだりしない、また相手の目を真剣に見るなど、真面目に聞こうとしているという態度を見せることが最も重要かもしれない。
「回りくどくしない」「ズバッと単刀直入に聞く」なんて意見もあった今回のアンケート。相手のもっている知識や情報を引き出すために、直球を投げてみたり変化球を使ってみたり、相手の打ちやすい球を考えて、さまざまなノウハウが駆使されているようだ。
調査時期: 2015年1月30日~2015年2月1日
調査対象: マイナビニュース会員
調査数: 男性137名 女性163名 合計300名
調査方法: インターネットログイン式アンケート