今週はなぜか毎日小学校へ。
校外学習の引率とか、読み聞かせとか、調理実習のお手伝いとか、そのほかもろもろ。
まるで友達の家みたいに校長室でコーヒー飲んでくつろいで帰ってます・笑
昨日は、6年生の教室で
「地雷ではなく花をください」
を読んできました。
6年生ともなると、仲間同士のおしゃべりが楽しくて、絵本の読み聞かせなんてうざ~いみたいな態度の子もいたりするんだけど・・・
基本的には放っておきます。
子どもって不思議なモンで、自分勝手におしゃべりしてても
聞きたい話の時にはパッと気付いてこちらに耳を傾けるんですよね。
あれは本当に不思議。
昨日も、絵本を読んでるときは一番後ろの女の子のグループがこそこそ話をやめなかったんだけど
あとがきについて話し出したら一瞬でシ~ンと静まり返りました。
この絵本のあとがきは黒柳徹子さんが書いてるんですけど
お菓子やチョコレートに似せた地雷がたくさんばらまかれているという内容があるんです。
大人が、落ちてるチョコを「わ~い!チョコみっけ」と喜んで拾うわけはないですよね?
ということは、これは確実に子どもたちを殺すために作らればらまかれた地雷だということになります。
みんなどう思う?
という話をちょろっとしたら
それまでしゃべってた子どもたちもいつのまにか静まり返ってこちらの話に耳を傾けていました。
先週の読み聞かせのときも、医療関係の専門学校出身のお母さんが
余った時間で「人体解剖」の経験談を話したら、子どもたちが一瞬で静まり返って話に食いついてきたと言ってました。
今の子どもたちは人の話が聞けないなんて言う先生方もいますけど
そんなことはないんですよね。
自分のアンテナにひっかかりそうな話はパッと聞ける貪欲な好奇心をみんな持ってると思います。
いろんな大人の話を聞く中で、子どもたちの将来の選択肢が増えることもあるだろうし。
あ、最後に一問だけ10回クイズをしたんですけど
「ケンタッキーって10回いって」
「鳥は英語で?」
子どもたち「チキン!!」
私「よっしゃ~!!キターーーー!!!」
「鳥は英語でバードでした。チキンは鶏肉でした!」
ひとりで盛り上がる私に子どもたちの反応は「ただのひっかけやん?」
・・・せっかくいい話したんだけど
最後はやっぱり変なオバチャンでした。
ショボン。
校外学習の引率とか、読み聞かせとか、調理実習のお手伝いとか、そのほかもろもろ。
まるで友達の家みたいに校長室でコーヒー飲んでくつろいで帰ってます・笑
昨日は、6年生の教室で
「地雷ではなく花をください」
を読んできました。
6年生ともなると、仲間同士のおしゃべりが楽しくて、絵本の読み聞かせなんてうざ~いみたいな態度の子もいたりするんだけど・・・
基本的には放っておきます。
子どもって不思議なモンで、自分勝手におしゃべりしてても
聞きたい話の時にはパッと気付いてこちらに耳を傾けるんですよね。
あれは本当に不思議。
昨日も、絵本を読んでるときは一番後ろの女の子のグループがこそこそ話をやめなかったんだけど
あとがきについて話し出したら一瞬でシ~ンと静まり返りました。
この絵本のあとがきは黒柳徹子さんが書いてるんですけど
お菓子やチョコレートに似せた地雷がたくさんばらまかれているという内容があるんです。
大人が、落ちてるチョコを「わ~い!チョコみっけ」と喜んで拾うわけはないですよね?
ということは、これは確実に子どもたちを殺すために作らればらまかれた地雷だということになります。
みんなどう思う?
という話をちょろっとしたら
それまでしゃべってた子どもたちもいつのまにか静まり返ってこちらの話に耳を傾けていました。
先週の読み聞かせのときも、医療関係の専門学校出身のお母さんが
余った時間で「人体解剖」の経験談を話したら、子どもたちが一瞬で静まり返って話に食いついてきたと言ってました。
今の子どもたちは人の話が聞けないなんて言う先生方もいますけど
そんなことはないんですよね。
自分のアンテナにひっかかりそうな話はパッと聞ける貪欲な好奇心をみんな持ってると思います。
いろんな大人の話を聞く中で、子どもたちの将来の選択肢が増えることもあるだろうし。
あ、最後に一問だけ10回クイズをしたんですけど
「ケンタッキーって10回いって」
「鳥は英語で?」
子どもたち「チキン!!」
私「よっしゃ~!!キターーーー!!!」
「鳥は英語でバードでした。チキンは鶏肉でした!」
ひとりで盛り上がる私に子どもたちの反応は「ただのひっかけやん?」
・・・せっかくいい話したんだけど
最後はやっぱり変なオバチャンでした。
ショボン。











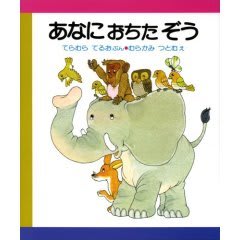
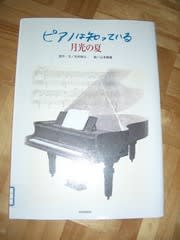
 は
は

 と笑う子、手を振る子
と笑う子、手を振る子 。
。 シーンが大うけ
シーンが大うけ

