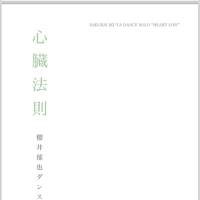ジュリアン・シュナーベルの映画『潜水服は蝶の夢を見る』を観ました。
半端ではない映画です。この映画から、僕ら人間は脳の中に翼をもっていることが感じられました。僕は、翼が欲しくてダンスをやってきました。踊っても踊っても、飛び立てぬけれど、いつかは・・・、と、信じるまま、支えられるままに、現在があります。そんな自分の背中を確実に押してくれたのが、この映画。さらに、人は関係の中でこそ真に生きることが出来るということも、痛いほど再認識させられました。関係こそ、クリエイトしてゆくものだということも・・・。
主人公は、病によって動けぬ身を人に預けます。仕事・恋・家族、人生の盛りのある日突然。全身が麻痺して声も出せない、動かせるのは片方の目だけ、という状態へ。死んでしまいたい。その思いからの脱出が、イマジネーションへの信頼に気付くことから始まります。きっかけは、言語療法。まばたきを利用した意思疎通が療法士から提案されます。アイ・コンタクトによって言葉を綴るのです。そして主人公は、心の中を語ろうと決意します。現実は不自由でも、心に浮かぶイメージは自由なのです。不自由と絶望を受け入れたとき、イメージは記憶と想像のあいだを飛翔し始めます。魂につながり、人の関係を動かし始めます。主人公と家族や友人は、感じ合うこと、に対する超人的な努力を開始します。そして、まばたきだけのコミュニケーションが、主人公の人生を描いた一冊の本にまで結実する。この本が映画の原作です。つまり、彼らのコミュニケーションは、世界にまで広がって、今、映画として僕らの目の前にまでつながっている。
監督は、ご存知の通り、現代を代表する美術家です。シュナベールは画家をめざすなかで、「新しい」という観念自体に絶望した事があるそうです。芸術全体が束縛されていた「新しさ」という呪縛。しかし、もはやあらゆる主題が描きつくされ、あらゆる主義も無効なほど世界は多様になっている。はたして自分がアーティストである必要があるのか。絶望。そこから解き放たれたのは、絶望を受け入れて現実の「ありきたり」の物や事を再評価することへのシフトチェンジだったようです。
彼の代表作である、割れた皿による絵画は、なぜ感動的なのか。彼は、アルバイトをしていたレストランの捨てられた皿を拾い集め、その破片をはり巡らせて花の絵を創ったのでした。それは、すでに「花の絵」ではありません。「花の絵」のフォルムをまとった、別なる宇宙でした。打ち捨てられた皿は、現実にある絶望の破片のようです。そして、描かれた花は、すでに花という主題ではなく、より抽象化された人間の思いであり、描きつくされたことさえあえて描かずにはいられない、コミュニケートする事自体への渇仰なのではないか、と僕は感じたのでした。
そんな作家が創る映画ですから、やはり深い。この上なく美しい映像、息をのむショットの連続は言うにおよばず。さらにU2やトム・ウェイツ、バッハを始めとする音楽の切ないこと・・・。しかし、この映画の凄さは、その斬新な手法に溺れることなく、あくまで人生を描き切るシネマとしての充実感を僕らにプレゼントしてくれる点だと思いました。昨日を受け入れよう、明日を信じよう、今をこそ大事にしよう。そんな「ありきたり」の思いを、これほど切実に受け止めさせてくれる映画は、めったにないと思います。
半端ではない映画です。この映画から、僕ら人間は脳の中に翼をもっていることが感じられました。僕は、翼が欲しくてダンスをやってきました。踊っても踊っても、飛び立てぬけれど、いつかは・・・、と、信じるまま、支えられるままに、現在があります。そんな自分の背中を確実に押してくれたのが、この映画。さらに、人は関係の中でこそ真に生きることが出来るということも、痛いほど再認識させられました。関係こそ、クリエイトしてゆくものだということも・・・。
主人公は、病によって動けぬ身を人に預けます。仕事・恋・家族、人生の盛りのある日突然。全身が麻痺して声も出せない、動かせるのは片方の目だけ、という状態へ。死んでしまいたい。その思いからの脱出が、イマジネーションへの信頼に気付くことから始まります。きっかけは、言語療法。まばたきを利用した意思疎通が療法士から提案されます。アイ・コンタクトによって言葉を綴るのです。そして主人公は、心の中を語ろうと決意します。現実は不自由でも、心に浮かぶイメージは自由なのです。不自由と絶望を受け入れたとき、イメージは記憶と想像のあいだを飛翔し始めます。魂につながり、人の関係を動かし始めます。主人公と家族や友人は、感じ合うこと、に対する超人的な努力を開始します。そして、まばたきだけのコミュニケーションが、主人公の人生を描いた一冊の本にまで結実する。この本が映画の原作です。つまり、彼らのコミュニケーションは、世界にまで広がって、今、映画として僕らの目の前にまでつながっている。
監督は、ご存知の通り、現代を代表する美術家です。シュナベールは画家をめざすなかで、「新しい」という観念自体に絶望した事があるそうです。芸術全体が束縛されていた「新しさ」という呪縛。しかし、もはやあらゆる主題が描きつくされ、あらゆる主義も無効なほど世界は多様になっている。はたして自分がアーティストである必要があるのか。絶望。そこから解き放たれたのは、絶望を受け入れて現実の「ありきたり」の物や事を再評価することへのシフトチェンジだったようです。
彼の代表作である、割れた皿による絵画は、なぜ感動的なのか。彼は、アルバイトをしていたレストランの捨てられた皿を拾い集め、その破片をはり巡らせて花の絵を創ったのでした。それは、すでに「花の絵」ではありません。「花の絵」のフォルムをまとった、別なる宇宙でした。打ち捨てられた皿は、現実にある絶望の破片のようです。そして、描かれた花は、すでに花という主題ではなく、より抽象化された人間の思いであり、描きつくされたことさえあえて描かずにはいられない、コミュニケートする事自体への渇仰なのではないか、と僕は感じたのでした。
そんな作家が創る映画ですから、やはり深い。この上なく美しい映像、息をのむショットの連続は言うにおよばず。さらにU2やトム・ウェイツ、バッハを始めとする音楽の切ないこと・・・。しかし、この映画の凄さは、その斬新な手法に溺れることなく、あくまで人生を描き切るシネマとしての充実感を僕らにプレゼントしてくれる点だと思いました。昨日を受け入れよう、明日を信じよう、今をこそ大事にしよう。そんな「ありきたり」の思いを、これほど切実に受け止めさせてくれる映画は、めったにないと思います。