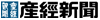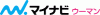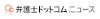SEIKYO online (聖教新聞社):ジャーナリスト 田原総一朗さん 時代を変えるのはしがらみのない若者たちだ
鋭い眼で時代を捉え続けてきた言論人・田原総一朗さん。27年続く人気討論番組「朝まで生テレビ!」(テレビ朝日系)の司会・進行役を務め、雑誌での対談や著作の執筆など多方面で活躍する。物事の本質に迫る言論は、傘寿(80歳)を超えても衰えを知らない。トレンド感覚をもって現代社会に切り込む、日本を代表するジャーナリストに聞いた。これからを生きる若者に伝えたいこと、とは――。
――近年、メディアで、“政治に興味のない社会学者”や“家を建てない建築家”など、今までにない若手論客と積極的な対話をされています。彼らと話してみて、率直に、これからの日本は明るいと感じますか、暗いと感じますか。
明るい。日本の夜明けが見えてきた。
特に、1981年前後に生まれた世代、僕は彼らを「81(ハチイチ)世代」と呼んでいるが、その若い世代に夜明けが強く感じられる。
――上の世代からは、最近の若者は草食系で欲望がなく、社会への関心も薄いなどの批判の声も聞かれます。それでも若者に期待されるんですね。
僕たちの世代は、権力を倒せと火炎瓶を投げて戦い、権力さえ倒せば世の中がよくなると思っていた。しかし、81世代は、そうした絶対的な「敵はいない」と言う。
彼らは、物心ついたころには不況で、高度経済成長もバブルも知らない。毎年のように代わる総理大臣は、権力者というより、隣の“おじさん”の延長の存在だ。
火炎瓶を投げる相手がいない。だったら「自分たちで何かやるしかない」と考えている。そこが面白い。
――「自分たちで」という思いが、立場の違いなどを越えて人とのつながりを大切にする、今の若者の気質を生み出していると感じます。ほかに田原さんの感じる若者の特質はありますか。
かつて、ホリエモンこと堀江貴文氏がネクタイも締めず、Tシャツ姿で「大人の世界」を荒々しく壊そうとした。
81世代が上の世代と違うのは、乱暴にやらないことだ。言葉遣いも、とても丁寧だ。実はやろうとしていることは、かなり型破りなことで、そういう意味では乱暴なのだが(笑い)。
それともう一つ。何も知らないのに、いきなりベンチャービジネスを始めるなんてことはしない。企業に入って、生きるためのノウハウを身につけてからやりたいことをやる。ある種の堅実さがある。
加えてソーシャルビジネスというように、もうけるためだけではなく、人の役に立ち、世の中を変えたいと考えている。
――著書の中で“世の中を良くすることを志す若者が多い。その存在自体がこの国の希望だ”とも語られていますね。なぜ若者に、このような変化が生じたと思われますか。
高度経済成長やバブルの時代を生きてきた人は、いつかまたと、まだ、そこへの期待や願望がある。知っているから、経験したから、過去のしがらみに縛られてしまう。
若者は知らない。だから、縛られない。国に良いアイデアはないので、自分たちで良い仕組みを作って国にパクらせてもいい、なんてことを考えたりする。新世代ならではの発想だ。
僕たちの世代は、がんじがらめの中で自由に生きようとした。インディペンデンツ(独立心)などと叫ばなければいけないほど国家や権力、社会に縛られていた。
若き日、僕は東京12チャンネル(現・テレビ東京)で働いていた。大手の局と違い、金もない。人材も多くない。他と同じことをやっていたら、誰もうちまでチャンネルを回さない。そこで大手ではできない斬新というか危ない番組をやった(笑い)。
「塀の上を走れ」が僕の仕事の姿勢だった。刑務所の塀の中にギリギリ落ちないということだ。これは今も変わらないが(笑い)。しがらみを切ることでしか視聴者の目をこちらに向けられなかったわけだ。
81世代は、しがらみとは無縁であり、無人の荒野を行くがごとく自由だ。
――社会である以上、自由といわれてもさまざまなことに縛られているように思います。目に見えないしがらみを破るのは難しく、一部の力ある人だけが可能なことのように感じている人も多いのでは?
こんなしがらみ破ってやる――今の時代、そんなハングリー精神はいらない。誰もが自由で、やりたいことは何でもできる。そう思えばいいことだ。
成長の時代は終わり、成熟の時代に入った、という意見が多いが、僕は違うと思う。ネットの世界で、何千万、何億という会員を獲得し、どんどん成長しているビジネスがある。“失われた20年”など、固定概念にとらわれた大人が言っているだけだ。違った形で成長は続いている。
そういう社会のしがらみは、皆が勝手に感じているだけで本当は存在しない。「今の若者はかわいそうだ」「就職も難しい」「社会保障も薄くなる」という多くの声があるが、かわいそうなのは、守りの意識ばかりで自己変革できない今の大人たちの方ではないか。
――田原さんは、若者を「保守の中の“新しい革新”」の代表と定義されています。これまでの枠組みの中で、新たな価値を創造していく。そういう若者世代が、自身の可能性を開くためにすべきことは何でしょうか。
批判をやめることだ。「批判の時代」は終わった。
昨年の選挙で、アベノミクス批判をしていた野党に、ならば自分たちの経済政策を出せと言ったらどこも出せなかった。結局、批判ばかり。マスコミもそうだ。
批判からは、革新はない。変化の激しい今の時代に批判なんてしている余裕はない。何をするか、何をやっているかが問われている。
――最後に、これからを生きる若者へのエールをお願いします。
大人たちは頼りない。自分たちでやるしかない。
しがらみがない世代だから、新しい時代をつくれる。未来は君たち若者にかかっていることは確かなのだから。
■プロフィル
たはら・そういちろう 1934年、滋賀県生まれ。岩波映画製作所、東京12チャンネル(現・テレビ東京)を経てフリーに。98年には、戦後の放送ジャーナリスト1人を選ぶ城戸又一賞を受賞。現在、「激論! クロスファイア」(BS朝日)などに出演中。母校・早稲田大学で次世代のリーダーの養成を目的とした講座「大隈塾」の塾頭も務める。著書に『私が伝えたい日本現代史1934―1960』(ポプラ新書)、『私が伝えたい日本現代史1960―2014』(同)など。
集団になると何をしでかすか分からない若者ですら、個人個人はしっかりとした考えを持っていることは感じていましたからね。
ある意味、こんなオッサンよりも頼りになるのかもしれませんな。