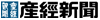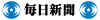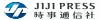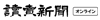(マイナビニュース)
●東北新幹線で320km/h実現、E6系「スーパーこまち」&N700Aも本格始動
JR東日本、JR東海、JR西日本、JR四国、JR九州は21日、来春のダイヤ改正について発表した。ダイヤ改正日は2013年3月16日となる。
東北新幹線で最高速度320km/h運転が実現し、秋田新幹線E6系( http://news.mynavi.jp/photo/news/2012/12/11/048/images/001l.jpg )「スーパーこまち」がデビュー、東海道・山陽新幹線でN700A( http://news.mynavi.jp/photo/news/2012/11/22/037/images/001l.jpg )も本格的に活躍を始める一方、新幹線200系( http://news.mynavi.jp/column/trainphoto/047/index.html )やJR西日本の特急形電車183系(元485系)( http://news.mynavi.jp/column/trainphoto/043/index.html )、JR東日本に1両のみ存在する123系の運転終了も発表された。各社の発表をもとに、来春のダイヤ改正の概要をまとめた。
○秋田新幹線E6系の投入で、E3系の置換えも進む
東北新幹線はダイヤ改正以降、「はやぶさ」3往復と「はやて」下り1本において、宇都宮~盛岡間の最高速度が300km/hから320km/hへ向上。その結果、東京~新青森間が最速2時間59分で結ばれ、現行の列車と比べて最大11分短縮されることになった。
秋田新幹線では新型車両E6系がデビュー。東京~秋田間の列車15往復のうち4往復がE6系による「スーパーこまち」となり、東京~盛岡間では「はやぶさ・スーパーこまち」としてE5系と併結運転を行う。E6系の宇都宮~盛岡間の最高速度は300km/h(現行の列車は275km/h)。東京~秋田間を最速3時間45分で結ぶ。
ダイヤ改正後、東北新幹線のE5系は3編成が追加投入され、新青森駅発着の列車はすべてE5系での運転に。秋田新幹線の新型車両E6系も4月以降、毎月1~2編成のペースで落成予定で、「こまち」に使用されるE3系を順次置き換えていくという。
上越新幹線では来年1月26日よりE2系による運行がスタートし、3月16日のダイヤ改正でもE2系を追加投入。これにともない、200系はすべての線区での定期列車の営業運転を終了することになった。200系より加速性能の良いE2系に置き換えることで、「とき」の平均到達時分が2分短縮(東京~新潟間2時間5分)される。また、現行の東京~新潟間ノンストップ「Maxとき」1往復は、E2系による「とき」に変更され、停車駅に大宮駅が追加される。
○デビュー後も追加投入続くN700A、JR西日本所有の編成も登場予定
東海道新幹線ではダイヤ改正に先立ち、2月8日より最新のN700A(JR東海所有)による営業運転がスタート。6編成が700系に代わって投入され、ダイヤ改正以降、N700系またはN700Aを使用する「のぞみ」「ひかり」「こだま」の定期列車の本数は208本(現在は199本)になるという。N700Aは山陽新幹線(JR西日本管内)も走行する。
JR東海の発表によれば、N700Aは2013年度末までに13編成を投入予定とのこと。JR西日本も来年12月頃にN700Aを1編成投入するほか、2013~2015年度にかけてN700系の改造も行うと発表している。
東海道新幹線の輸送力増強の一環で、新大阪駅ではダイヤ改正に合わせて、新たに27番線を供用開始する。東海道・山陽新幹線では運行体系も一部変更され、早朝時間帯の広島発東京行「のぞみ」を増発。広島駅を朝6時台に発車する列車はおおむね20分おきの運転となり、7時台も計5本の運転に。東京~新大阪間「のぞみ」のうち1往復が区間延長され、東京~岡山間の運転となる。
なお、東海道・山陽新幹線のN700系と700系(ともに16両編成の車両)で提供されてきたオーディオサービスについては、今回のダイヤ改正をもって廃止に。NHKラジオ第1放送の車内配信は継続され、手持ちのFMラジオで聴取できる。
山陽・九州新幹線直通列車については、広島~鹿児島中央間を結ぶ「さくら」1往復を新設。広島駅7時36分発「さくら451号」、鹿児島中央駅20時6分発「さくら458号」が運転される。利用者の多い週末の金曜から日曜にかけて、臨時の「みずほ」(新大阪~鹿児島中央間)も登場。一方、九州新幹線博多~熊本間では列車本数の見直しが行われるとのことだ。
次のページではJRの各在来線のダイヤ改正について紹介する。
●常磐線特急はE657系に統一、東京近郊を走る211系は残りわずかに
○651系&E653系の今後の動向が気になるも…
2013年3月16日に行われるJR各社のダイヤ改正。在来線でとくに大きな動きが見られるのがJR東日本だ。首都圏を中心に新型車両の投入、従来の車両の置換えが行われる。
常磐線では特急用の新型車両E657系( http://news.mynavi.jp/column/trainphoto/038/index.html )を追加投入。これにともない、特急「スーパーひたち」「フレッシュひたち」はすべてE657系での運行となる。E657系は10両固定編成で運転され、勝田駅での分割・併合作業もなくなるため、上野~高萩・いわき間の一部列車では到達時分が最大5分短縮されるとのこと。
なお、現行の「スーパーひたち」651系( http://news.mynavi.jp/column/trainphoto/039/index.html )、「フレッシュひたち」E653系( http://news.mynavi.jp/column/trainphoto/040/index.html )のダイヤ改正以降の動向については、今回の発表では明記されていない。
高架化工事が進む浦和駅では、宇都宮線・高崎線および京浜東北線の線路と並行する湘南新宿ラインにもホームが新設されることに。ダイヤ改正と同時に供用開始し、湘南新宿ラインの全列車に加え、JR・東武直通特急「日光」「きぬがわ」「スペーシアきぬがわ」(上下8本)も同駅に停車する。
2014年度の東北縦貫線開業を前に、宇都宮線と高崎線では4ドアの新型車両E233系の投入が進み、3ドアの211系を置き換える。宇都宮線の上野駅発着の電車はすべて4ドア車両に統一されるとのこと。高崎線も大半がE231系・E233系での運転となるが、3ドアの211系も4往復残されるという。
211系に関しては、房総地区の総武本線・成田線で運転されている車両(3ドア5両編成)( http://news.mynavi.jp/column/trainphoto/045/index.html )も、編成増強による混雑緩和と円滑な乗降りの促進のため、すべて209系(4ドア6両編成)に置き換えられることになった。一方、JR東日本長野支社管内では、一部の普通列車で211系による運行がスタート。同支社では、一般に「長野色」と呼ばれる淡いブルーとグリーンの帯をまとった211系の写真も公開( http://www.jreast.co.jp/nagano/pdf/121221.pdf )している。
中央本線塩尻~辰野間で運転される1両編成の電車・123系は、今回のダイヤ改正をもって運転終了。代わって2両編成のE127系が投入されるという。E127系は茅野~長野間の一部普通列車にも使用される。日光線は全列車205系リニューアル車両(4ドア4両編成)での運転となり、107系など現行の車両を置き換える。
JR東日本ではその他、中央快速線の到達時分の短縮や、「東京メガループ」(武蔵野線、京葉線、横浜線など)の利便性向上が図られる。また、東日本大震災で被災した区間のうち、常磐線浜吉田~亘理間と石巻線渡波~浦宿間で列車の運転を再開するとのこと。
○JR東海の117系引退、「セントラルライナー」廃止に
JR東海は東海道線や中央線などでダイヤを見直す。とくに中央線では、名古屋~中津川間の「セントラルライナー」(運賃のほかに乗車整理券310円が必要)の運転を取りやめることに。これにともない、昼間から夜にかけてのダイヤパターンが大幅に変更され、昼間時間帯は名古屋~瑞浪・中津川間の快速列車をおおむね20分間隔で運転。平日夕方から夜にかけてのダイヤも見直され、下り「ホームライナー」は17時台以降、名古屋駅を毎時58分に発車、21時台まで計5本の運転となる。
東海道線においては、2010年より進めてきた313系の新製投入が完了。これで同社管内の東海道線の快速・普通列車はすべて、JR発足以降に製造された車両となる。国鉄時代に製造された117系電車については、定期列車から引退することになった。
名古屋地区の東海道線では、朝の通勤時間帯を中心に輸送力増強を図り、大垣~豊橋間で快速の増発や区間延長を実施。豊橋駅8時5分発までのすべての快速と、大垣駅を6~7時台に発車する名古屋方面の快速の全列車を8両編成とする。
静岡地区の東海道線でもダイヤの一部見直しを行う。昼間時間帯における東海道新幹線「のぞみ」から快速「みえ」への接続も改善され、名古屋駅での乗換えの時間が10~15分程度に。2013年の伊勢神宮式年遷宮を前に、伊勢方面への利用が便利になる。
○特急「くろしお」白浜・紀伊田辺発着はすべて287系に
JR西日本のダイヤ改正では、京都・大阪から南紀方面の特急「くろしお」と、北近畿方面の特急に大きな変化が。今年3月より新型車両287系が投入された特急「くろしお」は、来春のダイヤ改正でも287系の追加投入が進み、紀勢本線(きのくに線)白浜駅・紀伊田辺駅発着の列車はすべて287系での運転となる。
朝の通勤時間帯に運転される「くろしお2号」は始発駅が海南駅から和歌山駅に変更され、オーシャンアロー車両(283系)を使用。代わって海南駅を朝6時16分に発車する「くろしお4号」が増発され、287系での運転となる。
特急「こうのとり」「きのさき」「はしだて」の一部列車で使用されてきた485系改造の183系は、今回のダイヤ改正で381系に置き換えられ、定期列車での運転を終えることに。キハ189系を使用する特急「はまかぜ」は、山陰本線城崎温泉~浜坂間の構内線形改良工事が完成し、速達化が実現するのにともないスピードアップが図られ、鳥取発大阪行「はまかぜ2号」の所要時間は現在より12分短縮(4時間1分)される。
アーバンネットワークにおいては、225系16両が追加投入されるのを受け、平日朝夕の通勤時間帯を中心に新快速の充実を図る。すでに土休日の新快速は終日12両編成で運転されているが、ダイヤ改正以降、大阪駅16時発以降の三ノ宮・姫路方面、大阪駅17時発以降の京都・米原方面の新快速が終電まですべて12両編成に。平日朝の新快速も、12両編成で運転する時間帯が拡大される。
京阪神圏ではその他、JR京都線やJR宝塚線などで利用状況に合わせた列車の設定変更を実施。なお、平日朝の通勤時間帯にJR京都線・JR神戸線で普通列車に使用されてきた205系については、ダイヤ改正をもって両路線での運転を終了する。
○「豊肥ライナー」格下げ、「九州横断特急」は「くまがわ」を統合
JR九州は来春のダイヤ改正で熊本~三角間の特急「A列車で行こう」が1往復増発され、計3往復の運転に。各列車とも三角駅で天草宝島ライン「シークルーズ」に接続し、天草への旅行がさらに便利になる。
熊本地区の豊肥本線では、昼間時間帯に運転されていた快速「豊肥ライナー」が、ダイヤ改正後はすべて普通列車に。快速がこれまで通過していた駅にも停車し、乗車チャンスが増加する。熊本~肥後大津間では朝の時間帯に普通列車が増発されるほか、光の森駅発着の一部列車が区間延長され、肥後大津駅発着となる。日中は列車の間隔も均等化され、九州新幹線との接続も改善される。
福岡都市圏では昨年に続き、鹿児島本線で朝の時間帯にロングシート車両を追加投入。朝夕の普通列車の車両数も増やし、朝7~9時に博多駅に着く二日市方面からの列車(計21本)に関して、輸送力(定員)はダイヤ改正前と比べて約4%(720人)アップするとしている。
今年7月の九州北部豪雨で運転を見合わせている豊肥本線宮地~豊後竹田間の復旧見込みは2013年8月末頃の予定。それまでは引き続き特別ダイヤでの運転を実施し、特急「九州横断特急」も人吉~宮地間と豊後竹田~別府間でそれぞれ折返し運転を行う。なお、JR九州が公表した時刻表によれば、ダイヤ改正後の「九州横断特急」は現行の特急「くまがわ」の半数以上を統合しており、「くまがわ」は熊本~人吉間1往復のみの運行とされている。
JR四国も特急列車の区間変更や普通列車との接続改善などを実施。夕方の時間帯に岡山・高松方面から丸亀・多度津方面への速達化と利便性向上を図るべく、特急「いしづち」「しおかぜ」および「しまんと」「南風」の併結作業を宇多津駅から多度津駅に変更。土讃線では多ノ郷駅に特急列車4本を停車させ、通勤・通学時間帯の乗車チャンス拡大を図る。
各社とも、今回発表された内容は2012年12月現在の情報。最終的な列車時刻はJR時刻表3月号などで告知(新幹線・在来線特急の一部列車は2月号にも掲載)するとしている。