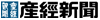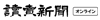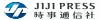(産経新聞)
街宣活動で在日外国人への差別をあおるなどのヘイトスピーチ(憎悪表現)が問題となっている。国連の人種差別撤廃委員会が8月、日本に対しヘイトスピーチの問題について、責任ある個人や団体を捜査し、必要な場合は起訴するよう要請した。こうした声を受け、自民党では法規制を含めた対策の検討が始まっている。ヘイトスピーチに対する法規制は必要か否か、元法政大教授の五十嵐仁氏とジャーナリストの木村太郎氏に見解を聞いた。(溝上健良)
■「自由は無制限ではない」五十嵐仁氏
--法規制の必要性について
「ヘイトスピーチは大きな問題で、規制するのは当然の話だ。東京・新大久保ではデモの影響で商店に経済的な損害も出ており、京都の朝鮮学校へのデモでは子供が恐怖心を抱くなど具体的な被害が発生している。これは言論による暴力そのもので、放置されれば人種や民族、宗教にもとづいて少数派が差別されて当然であるかのような、自由度の低い社会になってしまう危険性がある」
--国連の人種差別撤廃委員会から日本は法規制を求められている
「国外から指摘される前に法規制をやるべきだった。指摘されてなお問題が解決できていないというのも情けない。何らかの形でヘイトスピーチを根絶せねばならず、法規制なしでもなくなれば結構だ。ただ現実には“言葉の暴力”は野放し状態になっている。現行法で対処できていないわけで、そうであれば新たな法規制が必要だろう」
--言論の自由との兼ね合いは
「ヘイトスピーチを『個人または不特定多数に対して、人種、民族、宗教などの属性にもとづいて差別し、排除や憎悪をあおり立てる言動』などと定義し、取り締まる対象を明確に限定することが必要だ。これには大音響のデモの他、ネットの書き込みやプラカードも含まれる。出版物の出版禁止ということもあり得るだろう。乱用や適用拡大による言論の自由侵害をどう防ぐかは、法規制のある欧州諸国を参考にすればよい」
--デモ行進中、ヘイトスピーチが確認されたらどう対処すればよいか
「在特会(在日特権を許さない市民の会)のように問題となるデモを行っている集団は、指定暴力団やアレフのように団体指定をしてデモ行進を禁止すべきだ。また、それ以外の集団がデモ中にヘイトスピーチを始めた場合、デモを中止させることはあり得るだろう。集会・結社の自由の例外ということになるが、自由を侵害する者を規制しなければ自由は守れない。公共の福祉を侵害するような自由を排除することによって、自由で民主的な社会は守られる」
--法規制で、例えば「移民反対」といった言論が規制される恐れは
「そうならないよう、ヘイトスピーチの定義を限定し明確にする必要がある。今の在特会でも『日韓断交』のような政治的な主張はありうる話で、それまで拡大適用されないような定義が必要になる。あいまいな部分については、最終的には裁判で争えばいい」
--最近、在特会の主張は以前よりおとなしくなっているようだ
「社会的な批判の高まりでヘイトスピーチがなくなるのが一番いい。その意味では、新たな法規制を検討すること自体にも一定の効果が期待できる」
■「表現の自由を死守せよ」木村太郎氏
--ヘイトスピーチの現状について
「まず最初に断っておきたいが、在特会がやっているようなヘイトスピーチに対してはいいとは思わないし、大反対だ。それとは別に、新たな法規制でヘイトスピーチを取り締まるということには異論がある。自分の職業を考えても、表現の自由は民主主義社会で一番大事なものだと思う。国連の人種差別撤廃委員会では『言論の自由の枠を超えている』などと指摘されるが、そんなことはありえない」
--ではどう対処すべきか
「歯止めをかける法律は現にある。京都の朝鮮学校をめぐる裁判では民事で原告の朝鮮学校側が地裁・高裁で勝っている。刑事でも侮辱罪や威力業務妨害罪で有罪確定している。これは実際に被害が生じた場合は、今ある法律で十分対処できるという事例だ。悪口も言論の自由の範囲内で、悪口をすべて取り締まるということはあってはならない。実際に被害があった場合に、救済する法は整っているといえる」
--日本は国連の委員会から法整備を求められているが
「国連の立場と日本の立場とは異なっていていい。国連憲章を通読しても『民主主義』とは一言も書いてない。国連は民主主義を啓蒙(けいもう)する組織ではないわけで、そこは日本の価値を大事にして構わない。表現の自由は民主主義にとって一番大事な価値だろう。仮に法規制するとして、どう線引きするのか。どこまでがヘイトでどこまでOKなどと線引きできるわけがないし、したとすれば民主主義を危うくすることにもなりかねない。そこはリベラルの人も同じ意見ではないかと思う」
--特定団体のデモを禁止したり、デモを途中で中止させたりすることは
「それは集会・結社の自由を定めた日本国憲法に完全に抵触する。そう軽々しく言ってもらいたくない話だ。表現の自由をしっかり守らねば民主主義が成り立たなくなってしまうだろう。少しでも表現の自由を規制するような法律を作ってしまうと、民主主義はそこから崩れていきかねず、新たな法規制はやってはいけない」
--仮にデモでヘイトスピーチが行われた場合、事後に罰すべきだと
「名誉毀損(きそん)行為があった場合にはどんどん被害を親告すればいい。仮にそれで取り締まれないとしたら、今ある法律の運用がまずいということだ」
--ヘイトスピーチを定義するときに「少数派に対する差別をあおるような言動」などとされる傾向があるが
「例えば、韓国人に対する差別はダメでそれ以外に対してはOKなどということになれば、韓国人はむしろ『何で自分たちだけ特別扱いするのか』と怒るのではないか。『自分たちだって反論できるよ』と。仮に私自身が外国人だったら怒りますよ」
最近は報道されなくなったけど、かつて大久保で行われていたヘイトスピーチは酷かったと思う。
『表現の自由』を放棄させられる口実を、自ら官憲に与えてしまうように感じていたからね。
自分的には『自由は無制限ではない』とする五十嵐氏の意見に賛成するけど…。