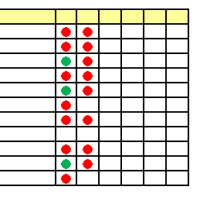研修通信に書いた内容です。
1年生の最初の授業で配慮したこと(1)
1.いきなり授業をする
一番素直に指示が聞ける時期です。
授業のシステムをインプットすることを重視しました。
教師の自己紹介は名前だけ、生徒の自己紹介などは
(生徒はもう何回もやっていて飽きていると思われるので)
行いませんでした。
2.教科書を準備できたら起立
まず指示をして行動させる。
ほとんどが持ってきている。当然ほめる。よい行動はほめて「強化」する。
忘れた生徒には予備の教科書を貸す。
技術では友人に借りにいかないように注意する。
(貸し借りはトラブルの原因となる。)
ここでもルールを確認する。
授業前に借りに来ることと返すときに
「ありがとうございました」と言うことである。
忘れた生徒も「ありがとうございました」と言うことで
ほめられる。大事なのは「教えて、ほめる」ことである。
3.プリントに日付・名前を書いたら起立
指示したことをやらせきることが大切である。
全員起立は確認のために有効な方法である。
ただしあまり多用しない方がよい。
(生徒に負荷がかかる方法なので)
最初は肝心なのでここでは書けた者から起立させた。
指示を聞いていない(名前を書いていない)生徒がいる。
ADHD(注意欠陥)の可能性もあるので席と名前を記憶しておく。
4.空白の時間を作らない
名前を書けた生徒が起立していく。
やっていなかった生徒にプレッシャーがかかる。
こうやって指示を通していく。書けていなかった生徒を
待つことになるが、何もする事がない時間は作ってはいけない。
「空白禁止の原則」である。
今回は立っている生徒に対して、名前を書かなくてはならない理由を
説明した。
5.指示の意味を説明する
授業で使ったワークシートは回収して、成績に入れることを説明する。
だから名前が書かれていないと損することを説明した。
言われたことをするだけでは「命令」「服従」の関係である。
「なぜこれをするのか」理由を納得して行動することが、
子どもは精神的に安定する。「趣意説明の原則」である。
6.説明はしない。
生徒は説明をすればするほど聞いていないものである。
大事なことは生徒に答えさせるとよい。先ほどの説明の場面では
このようにした。
出席番号が書いていないプリントがあります。
先生はどうすると思いますか?
先生は親切そうだから名簿で出席番号を調べてくれると思う人?
(挙手を求める)
調べないと思う人?(挙手する生徒がいる)
その通り。一番後ろに回して減点します。
長々と説明はしない。
一方通行ではなく、双方向の授業を心がけることで、
生徒に「当事者意識」を持たせる。
7.笑顔で授業をする
先ほどの趣意説明の言葉であるが、
文面で見るときつく感じる。
実際は笑顔でしゃべっている。
同じ注意をするにも、できるだけ「低刺激(ローインパクト)」に
なるように心がけている。
1年生の最初の授業で配慮したこと(1)
1.いきなり授業をする
一番素直に指示が聞ける時期です。
授業のシステムをインプットすることを重視しました。
教師の自己紹介は名前だけ、生徒の自己紹介などは
(生徒はもう何回もやっていて飽きていると思われるので)
行いませんでした。
2.教科書を準備できたら起立
まず指示をして行動させる。
ほとんどが持ってきている。当然ほめる。よい行動はほめて「強化」する。
忘れた生徒には予備の教科書を貸す。
技術では友人に借りにいかないように注意する。
(貸し借りはトラブルの原因となる。)
ここでもルールを確認する。
授業前に借りに来ることと返すときに
「ありがとうございました」と言うことである。
忘れた生徒も「ありがとうございました」と言うことで
ほめられる。大事なのは「教えて、ほめる」ことである。
3.プリントに日付・名前を書いたら起立
指示したことをやらせきることが大切である。
全員起立は確認のために有効な方法である。
ただしあまり多用しない方がよい。
(生徒に負荷がかかる方法なので)
最初は肝心なのでここでは書けた者から起立させた。
指示を聞いていない(名前を書いていない)生徒がいる。
ADHD(注意欠陥)の可能性もあるので席と名前を記憶しておく。
4.空白の時間を作らない
名前を書けた生徒が起立していく。
やっていなかった生徒にプレッシャーがかかる。
こうやって指示を通していく。書けていなかった生徒を
待つことになるが、何もする事がない時間は作ってはいけない。
「空白禁止の原則」である。
今回は立っている生徒に対して、名前を書かなくてはならない理由を
説明した。
5.指示の意味を説明する
授業で使ったワークシートは回収して、成績に入れることを説明する。
だから名前が書かれていないと損することを説明した。
言われたことをするだけでは「命令」「服従」の関係である。
「なぜこれをするのか」理由を納得して行動することが、
子どもは精神的に安定する。「趣意説明の原則」である。
6.説明はしない。
生徒は説明をすればするほど聞いていないものである。
大事なことは生徒に答えさせるとよい。先ほどの説明の場面では
このようにした。
出席番号が書いていないプリントがあります。
先生はどうすると思いますか?
先生は親切そうだから名簿で出席番号を調べてくれると思う人?
(挙手を求める)
調べないと思う人?(挙手する生徒がいる)
その通り。一番後ろに回して減点します。
長々と説明はしない。
一方通行ではなく、双方向の授業を心がけることで、
生徒に「当事者意識」を持たせる。
7.笑顔で授業をする
先ほどの趣意説明の言葉であるが、
文面で見るときつく感じる。
実際は笑顔でしゃべっている。
同じ注意をするにも、できるだけ「低刺激(ローインパクト)」に
なるように心がけている。