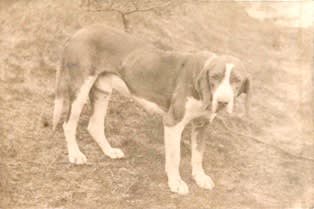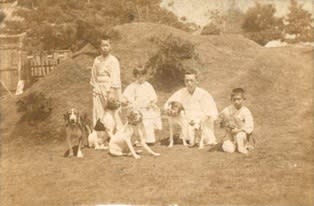明治26(1893)年の「シカゴ万国博覧会(コロンブス世界博覧会)」は、コロンブスのアメリカ大陸発見400年を記念してアメリカで開催されました。
シカゴ万博において、日本は従来のように工芸品を輸出品と捉えるのではなく、工芸を含めた美術品を万博の美術館に展示することで、日本の文化が世界水準であると示すことを目指して、官民挙げて出品物の選定作業をすすめていきます。
シカゴ万博への出品を見据え、「有限責任浪花蒔絵所」から改組された「日本蒔絵合資会社」ですが、その設立者である住友家・芝川家からは共に廣瀬宰平、芝川又平(初代又右衛門)が大阪府の「臨時博覧会事務委員」に選任されます。
大阪府でも「全市総動員の有様」で準備が進められる中、明治25(1892)年12月1日、日本蒔絵合資会社社長 芝川又平宛に次のような通知が届きました。
「閣龍(コロンブス)世界博覧会大阪府下出品に係る渡航代理人の義、総会の決議に基き二名の内一名は貴会社を指名候條御承諾相成度候也。但汽車、汽船賃は中等実費の積を以御渡し可申筈」
この通知を受け、日本蒔絵合資会社役員・野呂邦之助は出品物の種類、意匠などの調整のため、「屏風」「菓子器」「料紙箱」、珍しいところでは「イス、ソーハ(ソファ)、テーブル」といった出品物の一部を携帯して上京します。これらの作品をもとに、森村市太郎、岡倉覚三(天心)、今泉雄作等によって、どのような品物が万博への出品物に適するかが議論されました。
そして明治26(1893)年2月、日本蒔絵合資会社からは「美術品」*)3点を含む計19点の出品が決定し、希望を託されたそれらの品々は、いよいよアメリカの地へと運ばれます。
5月、博覧会が開会しますが、当時、アメリカは史上未曾有の不景気でした。結果、売約品はわずか一点。「開会前よりの期待は全然裏切られ 多年の希望も水泡に帰し」た結果となってしまいました。
価格の高さもあって販売は思うようにいかなかったものの、芝川家の記録によると、出品物のうち「吉野山蒔絵料紙箱」、「客椅子」の2点が「銅牌」を受賞したとあります。最後にその賞状の訳文を掲載し、このお話の締めくくりといたしましょう。
「前世記の最良品に劣らざる名作にして日本美術の此の一種無類なる部門に於て美術的熟練及び忍耐の欠乏せざるを示す。例令は金地及梨子地の上に桜花の浮上げ細工を施したる料紙文庫及硯箱及其他蒔絵の如きは殊に著しき進歩を示す。」
*)万博への出品は「美術品」と「通常品」に分かれており、事前の厳しい審査を経て「美術品」として出品された漆工品はごくわずかだったという。
■参考
初代・芝川又右衛門 ~蒔絵への情熱 日本蒔絵合資会社の設立~
■参考資料
「投資事業顛末概要七 日本蒔絵合資会社」
「世界の祭典 万国博覧会の美術」、東京国立博物館ほか編集、NHK/NHKプロモーション/日本経済新聞社、2004
※掲載している文章、画像の無断転載を禁止いたします。文章や画像の使用を希望される場合は、必ず弊社までご連絡下さい。また、記事を引用される場合は、出典を明記(リンク等)していただきます様、お願い申し上げます。
シカゴ万博において、日本は従来のように工芸品を輸出品と捉えるのではなく、工芸を含めた美術品を万博の美術館に展示することで、日本の文化が世界水準であると示すことを目指して、官民挙げて出品物の選定作業をすすめていきます。
シカゴ万博への出品を見据え、「有限責任浪花蒔絵所」から改組された「日本蒔絵合資会社」ですが、その設立者である住友家・芝川家からは共に廣瀬宰平、芝川又平(初代又右衛門)が大阪府の「臨時博覧会事務委員」に選任されます。
大阪府でも「全市総動員の有様」で準備が進められる中、明治25(1892)年12月1日、日本蒔絵合資会社社長 芝川又平宛に次のような通知が届きました。
「閣龍(コロンブス)世界博覧会大阪府下出品に係る渡航代理人の義、総会の決議に基き二名の内一名は貴会社を指名候條御承諾相成度候也。但汽車、汽船賃は中等実費の積を以御渡し可申筈」
この通知を受け、日本蒔絵合資会社役員・野呂邦之助は出品物の種類、意匠などの調整のため、「屏風」「菓子器」「料紙箱」、珍しいところでは「イス、ソーハ(ソファ)、テーブル」といった出品物の一部を携帯して上京します。これらの作品をもとに、森村市太郎、岡倉覚三(天心)、今泉雄作等によって、どのような品物が万博への出品物に適するかが議論されました。
そして明治26(1893)年2月、日本蒔絵合資会社からは「美術品」*)3点を含む計19点の出品が決定し、希望を託されたそれらの品々は、いよいよアメリカの地へと運ばれます。
5月、博覧会が開会しますが、当時、アメリカは史上未曾有の不景気でした。結果、売約品はわずか一点。「開会前よりの期待は全然裏切られ 多年の希望も水泡に帰し」た結果となってしまいました。
価格の高さもあって販売は思うようにいかなかったものの、芝川家の記録によると、出品物のうち「吉野山蒔絵料紙箱」、「客椅子」の2点が「銅牌」を受賞したとあります。最後にその賞状の訳文を掲載し、このお話の締めくくりといたしましょう。
「前世記の最良品に劣らざる名作にして日本美術の此の一種無類なる部門に於て美術的熟練及び忍耐の欠乏せざるを示す。例令は金地及梨子地の上に桜花の浮上げ細工を施したる料紙文庫及硯箱及其他蒔絵の如きは殊に著しき進歩を示す。」
*)万博への出品は「美術品」と「通常品」に分かれており、事前の厳しい審査を経て「美術品」として出品された漆工品はごくわずかだったという。
■参考
初代・芝川又右衛門 ~蒔絵への情熱 日本蒔絵合資会社の設立~
■参考資料
「投資事業顛末概要七 日本蒔絵合資会社」
「世界の祭典 万国博覧会の美術」、東京国立博物館ほか編集、NHK/NHKプロモーション/日本経済新聞社、2004
※掲載している文章、画像の無断転載を禁止いたします。文章や画像の使用を希望される場合は、必ず弊社までご連絡下さい。また、記事を引用される場合は、出典を明記(リンク等)していただきます様、お願い申し上げます。