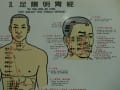ここでいう頭痛とは、くも膜下出血のような重篤なものではなく日常的に起こるタイプのものです。
世間でふつう頭痛と言われるものは、偏(片)頭痛と筋緊張性頭痛に分けることができます。
偏頭痛は別名血管拡張性頭痛という通り、脳の血管がなんらかの原因によって拡張するため起こる頭痛です。筋緊張性頭痛はこれまた言葉通り頭及び頚の筋肉の緊張によってひき起こされるタイプの頭痛です。
さてここまで読み進んで、「あれっ?脳が痛いものがないな。」と思われた方はいませんか?そうなんです実は*1「頭痛」とは脳が痛むわけでなく、その周辺の血管や筋肉が痛む症状なのですね。
頭痛の治療薬は、偏頭痛の場合に限っても少なくともこれだけあります。
[予防薬]
1.エルゴタミン製剤 拡張した血管を収縮させる
2. 坑セロトニン薬 セロトニンの働きを抑えて拡張した血管を収縮させる
3.抗うつ薬 うつ状態を改善
5.Ca拮抗薬 脳血管細胞へのCaイオンの流入を抑える
6.キサンチン製剤 中枢神経系を興奮させる 細動脈に作用し脳血管を収縮させて脳血流量を減少させる
[治療薬]
1.セロトニン受容体作動薬 脳のセロトニン受容体に作用 発作時の脳血管の拡張や神経性炎症を抑える
2. 非ステロイド系消炎鎮痛剤 前々回、近藤医師の説を参照
3.抗不安薬 不安状態を緩和
4.トリプタン系薬剤 10年くらい前に偏頭痛の特効薬として発売されて注目をあびた
このうち非ステロイド系消炎鎮痛剤、及びトリプタン系薬剤、及びエルゴタミン製剤、あるいはこれらを含む市販の頭痛治療薬、風邪薬の連続服用による「*2薬物乱用頭痛」が最近増加しているといいます。それは特に頭痛の特効薬として華々しくデビューしたトリプタン系製剤が発売された後顕在化したといわれています。
薬物乱用頭痛になった場合、薬をやめれば元に戻ります。「1~2週間は頭痛がひどくなるが、その後は頭痛が減ってくる。気持ちを切り替えることができれば、離脱はそれほど難しいことではない。」とのことですが、不安や鬱がベースにある患者の中には気を紛らわせるために薬を乱用する人もいる。このためいったん離脱しても、4割は再び薬物乱用頭痛に戻ってしまうともいわれています。
偏頭痛の原因は「セロトニン説」や「三叉神経説」、「遺伝説」などがありますが、まだはっきりとはわかっていません(現代医学では)。
自分でできる対処法としては
1.頭を冷やす(決して温めない=脳の血流を増やしてしまうので)
2.カフェインを取る
3.飴など糖分を含んだものを摂取する(低血糖だとなりやすいので)
やってはいけないことは
1.赤ワイン、チーズ、チョコレートの摂取
2.アルコール類の摂取(血管が拡張するため)
3.安静はあまりよくない(むしろ動いている方が楽)
今回は、自分の得意ではない現代医学側からみた頭痛についてあえて書きました。それは以前取り上げた慶応大学医学部の近藤誠医師も言っておられるように、症状(病気)を持っている人はそのことについてよく知り、あなたまかせにしないで(相手がどんなに高名な病院であっても)、自分の治療は自分で選択するという気持ちを持っていただきたいからです。
*1 http://www.naoru.com/zutuu.htm(ナオルコム)
すべての痛みは、脳で感じる。例えば手を切っても、手で痛みを感じるのではなく、手を切ることで手の細胞が傷つき、そこからブラジキニンやヒスタミンなどの『痛み物質』が放出される。それらの痛み物質が知覚神経の受容体に結合すると痛みを感じさせるための神経シグナルが発生する。そしてその神経シグナルは(プロスタグランジンで強化されて)脊髄を上がって脳に入り、中継点である視床を通過して大脳皮質に入る。ここで始めて私たちは痛みを感じる。
ところが脳には痛み物質の受容体がない。そのため脳内で出血や炎症が起こっても痛みを感じることはない。
それなのに、どうして頭痛が起きるのだろうか?
「頭痛」って、何が痛むの?
「会社を休む理由の1番は頭痛なのだそうです。では、頭痛で痛むのは具体的にどの部分なのだろう。「頭」といっても脳や頭蓋骨が痛みを発している訳ではなく、実は頭の筋肉や血管の痛みなのだ。頭痛の診察をする医師は、患者さんの痛みの表現で、頭痛のタイプを判断するという。そして、ほとんどの頭痛は次の2つのタイプのいずれかになるらしい。
1.緊張型頭痛:「ジンジン・ズーン・グー・ギュー」
2.片頭痛:「ズキズキ・ズキンズキン・ドクドク・ガンガン」
(NHKためしてガッテンより)
*2 薬物乱用頭痛の診断基準
①頭痛は一ヶ月に15日以上ある
②1種類以上の鎮痛薬を3ヶ月を超えて乱用している
)月10日以上、トリプタンまたは複合鎮痛薬を使用
)単一成分の鎮痛薬、トリプタンや消炎鎮痛剤の組み合わせの合計で月15日以上使用
③頭痛は薬の飲みすぎで起こったか、以前よりはっきりと悪化している
次回は、東洋医学的アプローチで書きたいと思っています。
参考文献
中国新聞、「ナオルコム」