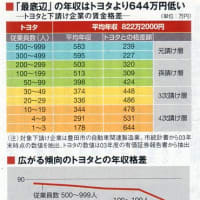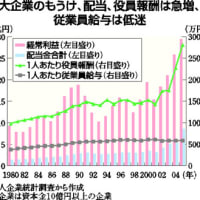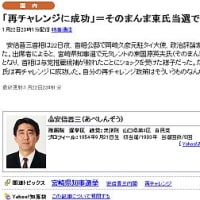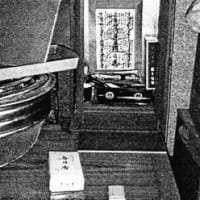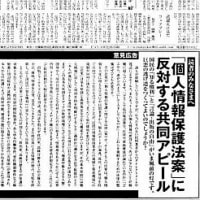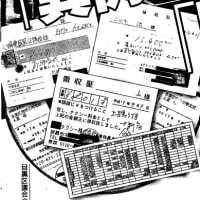201X年 5月 3日の新聞に載った広告……もちろんブラックユーモアなのだが、ほんとうにこうならないことを祈りたい。
政府与党が出してくる様々な法案を全て通していたら、また、新聞やテレビがこれまでのように、メディアだけをその規制から除外するように働きかけ続けるのであれば、そうなるのは非現実的なことではないから。
参考:
・国民投票法案、メディアの自主規制残す…与党・民主合意~本当か?! (情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士)
・探偵業法の例外を限定していいのか?~共感を呼ぶ主張を! (情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士)
それにしても、ふと、恐竜のように巨大化し、反応が鈍くなっている今の新聞・テレビでは、与党の企みのある悪法案のラッシュから世の中を守るということは出来ないのでは、と思えたりもする。
そして、ネットで様々な記事を読んでいると、次のような弁護士さんの言葉に出くわした。
「市民社会の危機に本格的な取り組みを──急がれる現場取材の理論化と記者訓練」という記事も氏は書かれているが、読んで「個人情報保護法」の反対運動の時にとても尽力された弁護士さんであることを思い出した。
「共謀罪、もっと身近にひきつけて」(弁護士 梓澤和幸のホームページ)
…(略)…
4、何故、メディアは騒がない?
こういう話は、鋭敏な感性をもった人が、はじめ騒ぐ。
ジャーナリストは環境の監視役だから、一番最初に騒ぐべきなのだが。こういう感覚が弱っているのではないか。いやこの俺もそうだ。
記者たちがではなく、この世の中全体がどことなくピリピリしていないのである。
と思って朝ごはんのとき家族に聞くとそうでもない、ラジオでもテレビでもけっこうやっているという。ただわかりにくい、というのだ。
わかりにくいということは、伝える人がよくわかっていないということだ。演説の名手だった義父がいっていた。自分がわからないことは絶対相手にわからせることができない。粉々にくだけるほどにわかることが大切なんだなうん。と自らうなずいていた。
とにかく、共謀という文字をはなれよう。刑法の構成要件をあらゆる罪について大改正する、処罰しやすく、捜査官憲が民間に入りやすくする大改正なのだということを、記者の言葉の力量で浸透させることだ。
5、現況 四月二八日、衆院法務委員会では、強行採決はさけられた。五月九日に参考人質疑となった。
稼がれた時間のうちに、ブログ、H.P.でどんどん話を広げよう。そして東京新聞が特報面でとりあつかったように大きなメデイアの人々にもがんばっていただきたい。
マスメディアは「共謀罪」の問題の報道はあまりやっていないという印象を受けるし、先月28日に与党による強行採決の危機があった時にも、その問題の大きさから比較すれば全然報道が足りなかった。連休明けの9日にはまた同じ危険性がある今も、東京新聞やほんとにごく一部の地方メディア(ここやここやここなど)を除き、まったく音なしの構えだ。
AMLでは、たぬ涼さんというかたが2日夜に、
≪長崎でも、共謀罪について「沈黙のマスコミ報道」を破り、地元マスコミ関係者の動きがありました。
まず、長崎のテレビ、新聞社の有志31人で改正案反対・強行採決中止を求めるメールを28日に、衆院法務委員会に2回に分けて送り、次いで関係労組5団体でつくる「長崎マスコミ・文化共闘会議」でも同じメールを28日に送信したということです。また、以降も具体的行動を計画中とのこと≫
という投稿をされ、「有志」「マスコミ・文化共闘会議」が衆院法務委員会に送ったメールの内容を紹介してくれた。
脳裏をかすめたのは、長崎のテレビや新聞社は、「共謀罪」の報道そのものはちゃんとやっていたのだろうか、いや、やることができたのだろうか?ということだった。
衆院法務委員会・石原伸晃委員長、理事、委員各位
「共謀罪」新設を柱とする組織犯罪処罰法改正案に反対します。
特に「共謀罪」は「現代版治安維持法」といわれるほど警察の恣意的乱用の危険性が極めて高く、ほかにも多くの問題点が指摘されています。なのに審議は不十分。国民の理解が得られているとは到底思えません。このような状況で重要なテーマを採決することは民主主義に反し、議会活動の死を意味します。28日の委員会での強行採決中止を求めます。
以上
「新聞以外にも、言論・表現の自由を」と言う前に、「現場記者に言論・表現の自由を」と言わなければならない?
新聞記者に言論の自由を (まだ旧体制下の新聞社と月極契約している人たちへ)
2.新聞業界は、新聞記者に言論の自由を与えよ
もし新聞社の冠を降ろしたくないのだったら、少なくとも、新聞記者に言論の自由を与えよ。新聞記者の良心を握りつぶすのはやめてくれ。経営者よ、公共の利益のために働きたいという希望を持って入社した記者の良心を踏みにじるな。記者は、何も企業利益のためだけに入社した訳ではない。そもそも新聞社は明らかな公的企業なのだから、むしろ会社の利益に反することも積極的にしなければならないし、それを評価指標としなければならない。現場の記者が、会社の既得権や利権について少しも批判的なことを対外的に言えないなど、とんでもないことだ。あなたたちに、そんなことを規制する権利はない。
過去に、どれだけの記者が言論を封殺され、絶望し、辞めていったか。これは社会的損失であり、もはや犯罪である。「社会の自浄作用」を失っているのだ。あまりの理不尽な環境に嫌気が差して辞めていく記者も多い。
参考:
・マスコミってなんだ? マスコミの正体とは (ポチは見た。)
・「報道の自由」の危機~強まるメディア規制のなかで知る権利を守れるか~ (図書新聞2672号 梓澤和幸氏に聞く 「誰のための人権か」)