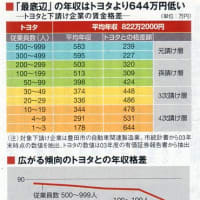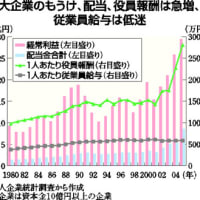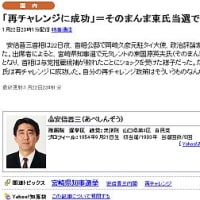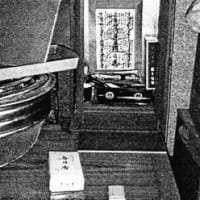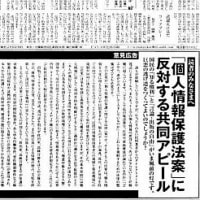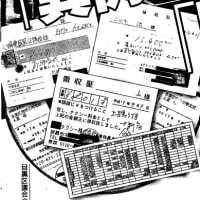「メディア」という語はサンスクリッドの「ウィデオ」から派生した語であり、その語源の意味は「目に見えない真実の価値や情報を目に見えるものとして表わし訴求する」ということらしい。
次の記事は『週刊現代』2005.11.19号の”日テレ「テレ朝」に惨敗の秋 ─視聴率競争─”の一節だが、上の意味での「メディア」の現場とはとても思えない違和感といったものを感じてしまう。
僕が今のテレビに対ししっくりとくるのは次のような佐々木俊尚氏の見解だ。
ともあれ、小泉政権全般に関しても、大新聞・テレビの批判精神のある記事、番組にはとんと出会えなかった。
もっとも、、小泉政権に対する大新聞・テレビの無批判は今に始まったことではない。
9月の衆院総選挙で、かつてNTTに勤め13年間記者クラブなどでの取材対応をしてきた経験をもとに自民党に「コミュニケーション戦略チーム」なるメディア戦略部署を立ち上げて、自民・公明の大勝利を導いた立役者だとも言われる世耕弘成・自民党参議院議員が、
「参院選に初当選してわかったことなんですが…それまで総理大臣や幹事長は入念な準備をして発言をして、記者会見でも質問を想定していると思っていた。しかしそんなことはまったくなかったんです。NTTの社長のほうが総理大臣よりよっぽどガードされてます(笑)。総理大臣が執務室を出ると記者さんにぱっと囲まれて、車に行くまでに想定していない、いろいろなことを聞かれる状況だったもんですから、なんとか改革しなくちゃと思いずっと言ってきたんです」(”圧勝自民党&弘兼憲史が伝授する サラリーマン「プレゼンの極意」” FLASH 2005.12.13号より)
と言っているが、次の立花隆氏の論考にあるように、そもそも小泉総理が困るような質問を投げかけるようなまともな記者はいなかったのである。
次の記事は『週刊現代』2005.11.19号の”日テレ「テレ朝」に惨敗の秋 ─視聴率競争─”の一節だが、上の意味での「メディア」の現場とはとても思えない違和感といったものを感じてしまう。
「ナニをやろうが、数字(視聴率)を獲っているモノの天下なんだよ!」『TVタックル』は政治家や学者、評論家が意見を述べる番組であり、しばしば出演者同士で激論の様相を呈する。その出演者の顔ぶれも他の番組では見られない人もいたりして一見公平なようにも見える。けれど、本当に視聴者にタブーのない多様な意見を提供する目的でやっているのかというと疑問も感じる。もしかしたら2年前の2003年11月の衆院総選挙の時に『週刊ポスト』に載った次の投稿にあるアメリカの激論番組のようなコンセプトの番組なのかもしれないとも思ったりする。
これはかつて日テレが視聴率王だったときの、ある幹部の発言である。だが秋の改編で巻き返しを図る日テレは目下苦戦中。その前に立ちはだかるのは、なんと万年4位のテレ朝だった──。
高級シャンパンのご褒美
「おめでとうございます!昨日放送されました『TVタックル』(10月10日放送)が20%を超えました。次も頑張りましょう」
東京・六本木ヒルズにあるテレビ朝日の社屋では、こんな社内アナウンスが流れる回数が最近増えているという。
「いま、会社の雰囲気はすごくいいですよ。視聴率が上がるたびに社内アナウンスがあり、エレベーター脇の壁に高視聴率の記録がベタベタと貼り出されるんです。社員には3万円の一時金が出たり、クオカード5000円分がスタッフにまで配られたり。この間なんか社員食堂が1日タダになりました。高視聴率を獲った番組には、社長から高級シャンパンが届くんです」(テレビ朝日社員)
いま、民放視聴率戦争で絶好調なのがテレビ朝日。その陰でかつての視聴率王者、日本テレビは圧倒されている。
この『TVタックル』にも出演したベンジャミン・フルフォード氏(元「フォーブス」アジア太平洋支局長)も、
海外から英語版に「日本への直言」
◆「日本の新聞を読む『小泉首相のパスタ好き』『安倍幹事長の好物アイス』ほかタレント扱いの軽薄さに“あ然”」(10月24日号)への意見
「アメリカも今、ジャーナリズムの危機にあります。今やメディアは巨大コングロマリットとなり、オーナーたちは財界の大物です。自分の都合でニュースを歪曲したり、時にはもみ消したりもします。広告主、政治家、その他の権力に追従するほうが商売になるのです。
特にテレビでは、中立的、分析的な意見をいうコメンテーターが排除され、極端な発言をする人を集めて、わざと激しいケンカをさせて視聴率を稼ごうとする傾向がありますが、そうした“討論”は不毛なうえ扇動的で、とてもジャーナリズムと呼べるものではありません。
イラク戦争と同時多発テロは無関係でした。イラクは大量破壊兵器を持っていませんでした。それなのに、いまだに多くのテレビ局がブッシュの戦争を擁護しています。CNNにいたっては、“大統領を批判することは国益に反する行為になりかねない”と、視聴者を脅迫します。
日本のメディアも、大衆人気の高い小泉首相や安倍幹事長の“人柄”を報じて読者・視聴者のご機嫌を取るほうが商売になると考えているのでしょうが、確かに軽薄この上ないと思います」
(ジャーナリスト=ニューヨーク州在住)
◆「これが『小泉↓菅』政権交代◯秘データだ!」(10月24日号)への意見
「私たちが日本から得る情報は、どれも小泉・自民党が圧勝するというものばかりで、週刊ポストが掲載したデータは、これと大きく異なる点が興味深い。
自民党が勝つという分析は、日本経済が回復したとか、改革が評価されたからという理由ではなく、むしろ逆に、日本の将来が相変わらず不透明で国民不安が高まっているからこそ、自民党が勝つというものです。日本の有権者は非常に保守的で、危機になればなるほど、現政権に頼る傾向があります。今回も同様に、危機を作ってきた自民党が有権者から絶大な支持を得るという皮肉な結果になる可能性はあるでしょう。
小泉首相は企業業績の回復や株価の高騰を強調して景気回復をPRする作戦に出ていますが、完全にブッシュの罠にはまっています。“日本は強くなった”というほど円高が進み、日本企業があげた利益はアメリカに吸い取られ、国内のデフレはどんどん悪化するのです。また、株高は銀行や生保の経営を一時的に回復させますが、それは改革の遅れにつながるでしょう。
小泉首相は、選挙を戦うために、改革に逆行する方向に突き進んでいるように見えます。公約にしている郵政事業、高速道路の民営化にしても、そんなことをやっている国はどこにもなく、それが構造改革なのかは疑問です」
(シンクタンク勤務=バージニア州在住)
『朝まで生テレビ!』は、自由に討論しているように見えますね。とんでもない、私が日本の財務状態を話そうとしたら、いきなりコマーシャルです。CMの間、スタッフから「その話をするな」と注意されました。と書いている。
(”私は権力者が隠す「本当のこと」を伝え続けます” 週刊現代 2005.10.15号 http://blog.goo.ne.jp/c-flows/e/5272c64ca349b120c929503373b6fa1fより)
僕が今のテレビに対ししっくりとくるのは次のような佐々木俊尚氏の見解だ。
テレビ業界で言う「顧客」というのは視聴者ではないからだ。放送局の顧客は今のところ、どこまで言ってもスポンサーである大企業でなのである。視聴者は視聴率で表されている単なる数字でしかなく、放送局には視聴者ひとりひとりと向き合って何かをしようという考え方はまったくない。彼らには視聴者とのインタラクティブなどたいして興味のある対象ではなく、知りたいことは「この番組がどの程度の視聴率を取れるのか」ということだけなのだ。今年9月の衆院総選挙でも大新聞・テレビはひどかった。「小泉郵政民営化」の正体に迫ろうとしたものは僕の知る限り皆無だ。読者や視聴者は未だに「小泉郵政民営化」とは何なのかわからないでいるのではないだろうか。諸外国の「郵政民営化」を検証する記事や番組もなく、「小泉郵政民営化」を賞賛しているブッシュ大統領のアメリカがそもそも「郵政民営化」は問題があるとして見送り未だに国営でおこなっていることも多くの人は知らないようだ。イギリスも国営で、ブレア首相は日本の郵政民営化を「日本だけが逆行してますね」と皮肉ったそうである。ドイツは民営化後、大都市以外は惨憺たる状況であるという。
極論すれば、日本の民放局というビジネスはB2Cではなく、B2Bなのである。
この放送局の考え方がいまだもって揺るがないのは、数字で裏打ちされているからだ。前回も書いたが、放送業界の広告市場は2兆円強。インターネットの広告市場は増えたとはいえ、わずか1800億円。もっと具体的に見てみれば、フジテレビの年間売上高は4550億円もあり、このうちの放送収入は3000億円にも上る。一方のライブドア。昨年9月期の決算を見れば、年間売上高は300億円あまり。さらにポータルサイトの売上だけに絞れば、わずか30億円強しかない。フジテレビの100分の1である。
(『テレビ業界がライブドアに拒否反応を示す理由とは』佐々木俊尚の「ITジャーナル」http://blog.goo.ne.jp/hwj-sasaki/e/1e4723c5c4c0295cb5ac3c6d259e5dd5より)
(注:
B2C 【B to C】(IT用語辞典 e-Word)
http://e-words.jp/w/B2C.html
電子商取引(EC)の形態の一つ。企業と一般消費者の取り引きのこと。企業間の取り引きはB to B、一般消費者同士の取り引きをC to Cという。インターネット上に商店を構えて消費者に商品を販売するオンラインショップ(電子商店)が最も一般的な形態だが、ソフトウェアや画像、音楽などのコンテンツを販売するビジネスや、オンラインゲームやオンライントレードのようにサービスを提供する事業者も登場している。)
ともあれ、小泉政権全般に関しても、大新聞・テレビの批判精神のある記事、番組にはとんと出会えなかった。
もっとも、、小泉政権に対する大新聞・テレビの無批判は今に始まったことではない。
9月の衆院総選挙で、かつてNTTに勤め13年間記者クラブなどでの取材対応をしてきた経験をもとに自民党に「コミュニケーション戦略チーム」なるメディア戦略部署を立ち上げて、自民・公明の大勝利を導いた立役者だとも言われる世耕弘成・自民党参議院議員が、
「参院選に初当選してわかったことなんですが…それまで総理大臣や幹事長は入念な準備をして発言をして、記者会見でも質問を想定していると思っていた。しかしそんなことはまったくなかったんです。NTTの社長のほうが総理大臣よりよっぽどガードされてます(笑)。総理大臣が執務室を出ると記者さんにぱっと囲まれて、車に行くまでに想定していない、いろいろなことを聞かれる状況だったもんですから、なんとか改革しなくちゃと思いずっと言ってきたんです」(”圧勝自民党&弘兼憲史が伝授する サラリーマン「プレゼンの極意」” FLASH 2005.12.13号より)
と言っているが、次の立花隆氏の論考にあるように、そもそも小泉総理が困るような質問を投げかけるようなまともな記者はいなかったのである。
人気が凋落しつつあるブッシュ、ブレアにくらべて、小泉首相の人気があまり落ちないのはなぜだろうか。要因はいくつもあろうが、私は大きな要因のひとつが、メディアの弱さだと思っている。
小泉人気を支える主たる要因ははっきりしている。小泉首相がメディアをいちばん巧みに利用している政治家だからである。日本のありとあらゆる政治家の中で、小泉首相ほどメディア露出度の高い政治家はいない。
毎日テレビにかこまれて、自分勝手な自己宣伝をすることが自由に許されるとしたら、誰だって、相当の支持を集めることができる。
小泉首相は毎日の記者会見の場に出てくるのに、各紙とも、ついこの間まで、ろくに質問らしい質問もできずに、ただマイクを突き出だすだけの、駆けだし記者ばかりだった(最近はある程度質問ができる記者もまじっている)。
アメリカのCNNでよくナマ放送で報じられる大統領記者会見の場を見たことがある人はみな知っているように、国家の長の記者会見の場は、通常、国会(議会)よりも激しい、国家の長の追及の場になるのが普通である。しかし、しばらく前までの小泉首相の毎日の会見は、ほとんど「お前はアホか?」といいたくなるような愚劣な質問しかできない記者ばかりだった。小泉首相はそれをいいことに芝居気たっぷりの自己宣伝を毎日繰り返してきた。
小泉人気が落ちないのも道理である。
(”海外メディアが伝えた小泉・郵政解散劇の評判”立花隆の「メディア ソシオ-ポリティクス」2005.08.11 http://nikkeibp.jp/style/biz/topic/tachibana/media/050811_kaigai/より)