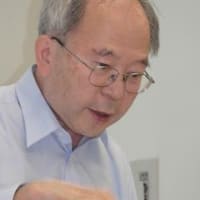拉致問題、大事な局面です。
参考に
【背信の論理 テロ指定解除】(上)拉致軽視「欠陥の融和策」
2008.6.21 09:14
拉致被害者家族の横田滋夫妻や蓮池秀量夫妻がワシントンを初めて訪れたのはブッシュ政権が誕生して間もない2001年2月だった。北朝鮮は拉致を全否定し、日本の外務省は家族たちを抑えにかかる時代だった。だがブッシュ政権は国家安全保障会議も、国務省も、問題解決への協力の姿勢をはっきりとみせた。
「日本の政府よりも頼りになります」-。凍るような厳寒の一夜、訪米を総括する質素な夕食の集いで家族の一人がもらしたのを今も覚えている。以来、ブッシュ政権は「家族会」や「救う会」にとって名実ともに希望の星であり、よりどころだった。
だがそれから7年半近く、同じブッシュ政権のライス国務長官は18日の演説で「大統領はテロ支援国家指定リストから北朝鮮をはずす意向を議会に通告することになる」と述べた。北朝鮮の核申告が要件を満たすという大前提があるとはいえ、指定解除の手順にはもう日本の拉致問題へのリンクはなかった。
北朝鮮がテロ支援国家の指定を解除されれば、日本側の拉致解決への努力は重大な打撃を受ける。北は世界銀行その他からの経済援助を得て苦境を脱せられ、日本の制裁の実効に大きな穴があき、拉致解決への圧力も減殺されるからだ。
ブッシュ政権は、クリストファー・ヒル国務次官補が北朝鮮の金桂寛外務次官と06年11月、07年1月と会談を重ねるまでは、一貫して北朝鮮の指定解除には日本人拉致事件の解決への進展が必要だとするリンケージ政策を掲げてきた。この政策は当然、日本の拉致解決への国民的悲願にも、そのための対北制裁にも強力な支えとなった。
■根強い反対論
しかしブッシュ政権は明らかに対北朝鮮政策のこの部分を変えてしまった。この変転だけをみる限り変節とか背信と評しても、そう的外れではないだろう。実際に米国側でもこの政策変更を批判的にとらえ、日本側が黙って受け入れるべきではないと主張する関係者は多い。
北朝鮮の核兵器開発問題をここ十数年追ってきた議会調査局のラリー・ニクシュ専門官は「この点だけに絞れば、日本側からSELLOUT(裏切り)と断じられても不当ではない」と語る。ブッシュ政権の1期目で国務次官として北朝鮮と交渉したジョン・ボルトン氏も「北朝鮮の核兵器を破棄させないまま、テロ国家指定だけを解除することは当初の政策を逆転させる欠陥だらけの融和策で、日本への悪影響も大きい」と非難する。
確かにライス・ヒル主導の交渉では北朝鮮の核兵器に関して、寧辺地区のプルトニウム抽出施設の「無能力化」を求めるだけで、濃縮ウランなど隠された核やシリア、イランへの核技術の拡散などは不問だった。だからこそ、拉致へのリンケージを除いても北朝鮮に報奨を与える「テロ指定解除」への反対が議会でも広範なのである。
■外交成果狙い
しかしブッシュ政権はなぜこんな拙速な対応を急にとるに至ったのか。
朝鮮情勢を専門とするヘリテージ財団のブルース・クリングナー研究員は「任期の残り少ないブッシュ政権が外交成果を誇示したいからだろう」と診断する。大統領選が過熱してバラク・オバマ候補がブッシュ外交の全否定を叫び始める前に区切りをつけるというブッシュ政権の狙いを指摘する向きもある。
それにしても、日本人拉致の悲劇への強い同情を事あるごとに表明してきたブッシュ大統領自身が、なぜ結果として拉致解決を軽視する方向へと動いたのか。「ライス国務長官が北朝鮮核問題への対応を優先させても拉致への悪影響は少ないという趣旨を大統領に説き、一任の同意を得た」(ニクシュ氏)という見方が有力である。
日本側では「拉致議連」の平沼赳夫、松原仁、西村真悟各議員らが頻繁に訪米し異例の集中度で北朝鮮のテロ国家指定解除への反対を訴えてきた。その結果、米国議会での同趣旨の反対は明らかに、輪を広げ、勢いを強めた。
ブッシュ政権はたとえ指定解除を決めても、その実施には議会の同意を得ねばならない。議会では下院ですでに北朝鮮が核拡散での潔白を証さない限り、指定解除はないとする法案が可決され、上院でも同種の動きがある。日本側が指定解除への流れに改めて激しく反発すれば、米国議会でのこうした動きもさらに強化され、指定解除の見通しは減ることとなる。
日本があくまで反対を貫く場合、具体的な政策オプションとしては(1)6カ国協議からの撤退(2)北朝鮮の「核申告」の承認への反対(3)米国の北指定解除への反対の公式表明(4)寧辺施設の破壊作業への経費支出の拒否-などがある。いずれの選択も日米関係への新たな摩擦のリスクをはらむが、みなそれなりに米側内部の反対論を鼓舞する効果をも秘める。福田政権はどんな選択を下すのか、重大な政策判断を迫られているわけである。(ワシントン 古森義久)
【背信の論理 テロ指定解除】(上)拉致軽視「欠陥の融和策」 (1/3ページ) - MSN産経ニュース
【背信の論理 テロ指定解除】(上)拉致軽視「欠陥の融和策」 (2/3ページ) - MSN産経ニュース
【背信の論理 テロ指定解除】(上)拉致軽視「欠陥の融和策」 (3/3ページ) - MSN産経ニュース
参考に
【背信の論理 テロ指定解除】(上)拉致軽視「欠陥の融和策」
2008.6.21 09:14
拉致被害者家族の横田滋夫妻や蓮池秀量夫妻がワシントンを初めて訪れたのはブッシュ政権が誕生して間もない2001年2月だった。北朝鮮は拉致を全否定し、日本の外務省は家族たちを抑えにかかる時代だった。だがブッシュ政権は国家安全保障会議も、国務省も、問題解決への協力の姿勢をはっきりとみせた。
「日本の政府よりも頼りになります」-。凍るような厳寒の一夜、訪米を総括する質素な夕食の集いで家族の一人がもらしたのを今も覚えている。以来、ブッシュ政権は「家族会」や「救う会」にとって名実ともに希望の星であり、よりどころだった。
だがそれから7年半近く、同じブッシュ政権のライス国務長官は18日の演説で「大統領はテロ支援国家指定リストから北朝鮮をはずす意向を議会に通告することになる」と述べた。北朝鮮の核申告が要件を満たすという大前提があるとはいえ、指定解除の手順にはもう日本の拉致問題へのリンクはなかった。
北朝鮮がテロ支援国家の指定を解除されれば、日本側の拉致解決への努力は重大な打撃を受ける。北は世界銀行その他からの経済援助を得て苦境を脱せられ、日本の制裁の実効に大きな穴があき、拉致解決への圧力も減殺されるからだ。
ブッシュ政権は、クリストファー・ヒル国務次官補が北朝鮮の金桂寛外務次官と06年11月、07年1月と会談を重ねるまでは、一貫して北朝鮮の指定解除には日本人拉致事件の解決への進展が必要だとするリンケージ政策を掲げてきた。この政策は当然、日本の拉致解決への国民的悲願にも、そのための対北制裁にも強力な支えとなった。
■根強い反対論
しかしブッシュ政権は明らかに対北朝鮮政策のこの部分を変えてしまった。この変転だけをみる限り変節とか背信と評しても、そう的外れではないだろう。実際に米国側でもこの政策変更を批判的にとらえ、日本側が黙って受け入れるべきではないと主張する関係者は多い。
北朝鮮の核兵器開発問題をここ十数年追ってきた議会調査局のラリー・ニクシュ専門官は「この点だけに絞れば、日本側からSELLOUT(裏切り)と断じられても不当ではない」と語る。ブッシュ政権の1期目で国務次官として北朝鮮と交渉したジョン・ボルトン氏も「北朝鮮の核兵器を破棄させないまま、テロ国家指定だけを解除することは当初の政策を逆転させる欠陥だらけの融和策で、日本への悪影響も大きい」と非難する。
確かにライス・ヒル主導の交渉では北朝鮮の核兵器に関して、寧辺地区のプルトニウム抽出施設の「無能力化」を求めるだけで、濃縮ウランなど隠された核やシリア、イランへの核技術の拡散などは不問だった。だからこそ、拉致へのリンケージを除いても北朝鮮に報奨を与える「テロ指定解除」への反対が議会でも広範なのである。
■外交成果狙い
しかしブッシュ政権はなぜこんな拙速な対応を急にとるに至ったのか。
朝鮮情勢を専門とするヘリテージ財団のブルース・クリングナー研究員は「任期の残り少ないブッシュ政権が外交成果を誇示したいからだろう」と診断する。大統領選が過熱してバラク・オバマ候補がブッシュ外交の全否定を叫び始める前に区切りをつけるというブッシュ政権の狙いを指摘する向きもある。
それにしても、日本人拉致の悲劇への強い同情を事あるごとに表明してきたブッシュ大統領自身が、なぜ結果として拉致解決を軽視する方向へと動いたのか。「ライス国務長官が北朝鮮核問題への対応を優先させても拉致への悪影響は少ないという趣旨を大統領に説き、一任の同意を得た」(ニクシュ氏)という見方が有力である。
日本側では「拉致議連」の平沼赳夫、松原仁、西村真悟各議員らが頻繁に訪米し異例の集中度で北朝鮮のテロ国家指定解除への反対を訴えてきた。その結果、米国議会での同趣旨の反対は明らかに、輪を広げ、勢いを強めた。
ブッシュ政権はたとえ指定解除を決めても、その実施には議会の同意を得ねばならない。議会では下院ですでに北朝鮮が核拡散での潔白を証さない限り、指定解除はないとする法案が可決され、上院でも同種の動きがある。日本側が指定解除への流れに改めて激しく反発すれば、米国議会でのこうした動きもさらに強化され、指定解除の見通しは減ることとなる。
日本があくまで反対を貫く場合、具体的な政策オプションとしては(1)6カ国協議からの撤退(2)北朝鮮の「核申告」の承認への反対(3)米国の北指定解除への反対の公式表明(4)寧辺施設の破壊作業への経費支出の拒否-などがある。いずれの選択も日米関係への新たな摩擦のリスクをはらむが、みなそれなりに米側内部の反対論を鼓舞する効果をも秘める。福田政権はどんな選択を下すのか、重大な政策判断を迫られているわけである。(ワシントン 古森義久)
【背信の論理 テロ指定解除】(上)拉致軽視「欠陥の融和策」 (1/3ページ) - MSN産経ニュース
【背信の論理 テロ指定解除】(上)拉致軽視「欠陥の融和策」 (2/3ページ) - MSN産経ニュース
【背信の論理 テロ指定解除】(上)拉致軽視「欠陥の融和策」 (3/3ページ) - MSN産経ニュース