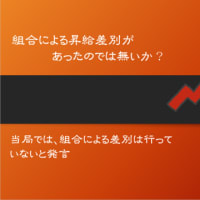にほんブログ村 JR・国鉄
ランキングに参加しています。
本日も再び「公企労レポート」からの引用をさせていただきたいと思います。
国鉄改革に対して、積極的に労使協調の方針を打ち出せない国労は、国労大会において、国労組織の存続をかけて執行部への対応の一任を打ち出したのですが、具体的な内容などは決定できないまま、閉会することとなったのですが。
今回は、国労書記長の側からの見解をみていきたいと思います。
以下、公企労レポートからの引用です。
【厳しい状況のなか。書記長就任、苦労の多いことと思います。今回の大会は、委員長発言をめぐって激しい対立を露呈したが・・・・】
委員長発言は私ども執行部の素直な気持ちです。
組合員の最大の関心ごとは自分たちの先行きはどうなるか、雇用は大丈夫かということです。その点選挙後の政治情勢がきびしくはなりましたから、雇用を確保するために妥協が必要であるとするならば、あえて妥協することも辞さないというのが委員長の気持ちです。
私どもも同じ立場です。大会では、代議員、傍聴者も多く、雇用が大事、国労を将来も存続させていくと言う事については誰も依存はありませんが、雇用を守っていくその方法について若干の意見のちがいはありました。しかし最終的には、社会党総評ブロックにきっちり軸足を置いて、総評に全面的な指導を受けながら闘っていく。そして最大の課題である雇用問題、組織防衛に全力を上げていくことに大会決定したわけです。それを受けて私どもは、大会直後の26日、第1回の中執を開催して、これまでなかった雇用対策本部を設置、ここに責任者として酒井副委員長及び専従役員を配置しました。
ということで、国労右派の委員長【この時点では主流派は国労右派が握っており、国労の組織を守るためにはその方針自体を変えることも必要であるし、社会党案(全国一律の民間会社で、株式の7割を政府が保有する特殊会社)を支持するとして民営化を容認するなど方針を変えていきつつあるときでもあったのです。ちなみに、共産党は分割民営化は反対、【当然国労非主流派の共産党系派閥は国鉄民営化自体に反対しており、この非主流派がその後イニシアチブを取るのであるがそれはもう少しあとの話となります。
さて、再び公企労レポートに戻ります。
【組合員のなかになぜ雇用不安が出てきたのか増大しているのか、どのように理解していますか】
一般論的に言えば、今日の国鉄の分割・民営化の中で、合理化により多くの余剰人員が生まれ現実に仕事が無いということで雇用不安が生まれているわけですが、同時に一つはこれをめぐって、公式・非公式を含めていろいろな話が出ていることです。たとえば国労にいたら新事業体へ行けないとか、人活センターへ行かされるとか。そういう問題がでているだけに、雇用不安が増大していると理解しています。
国鉄当局としては、国労非主流派の封じ込めが一番の狙いであり、その一環として人材活用センターなどが組織されたわけですが、そこに当局というよりも現場サイドでの他組合【動労や鉄労】のオルグが効を奏した形となったと考えられます。
実際に、国労は昭和61年半ばには国鉄の労働組合としては過半数を割り込み急速にその力を失っていくのですがそれはまた後ほどの機会にしたいと思います。
さて、改めて公企労レポートに戻りたいと思います。
【今回の「大胆な妥協」という委員長発言の真意について】
選挙中にも、またそれ以前からも、私どもは国鉄はこのままでは駄目だということは主張していましたし、社会党を支持することも決め手います。
また、雇用問題にしても社会党案の方針のもとで不安を解消していくことを考えていましたが、しかし、残念ながらこの選挙の結果ですから、政治的にはきびしい局面に立たされることになります。したがって選挙前に比べて情勢は悪くなっているだけに、最大の課題である雇用の確保については、従来以上の妥協をせざるを得ないということで、委員長あいさつでもそれを言ったわけです。
これは、中曽根内閣が国鉄改革の是非をめぐって61年7月6日衆参同時解散総選挙を行った結果、自民党が安定多数を確保したことを指すものであり、これにより国鉄の分割民営化路線は規定のものとされたのです。、
【執行部一任といっても、重要問題は機関にはかるということになっています。これはどういうことですか】
労働組合というものはもともと一定の方針を機関で決めてそれに基づいてやっていく、その結果については大会で承認を求めるということは、いずれにしてもあるわけです。その点で、重大な決定をするとき、相手もあることですから、どういう事を決断しなければならないが、いま想定できない部分があります。
「雇用は確保しますよ、しかしその代わり-」ということになった場合、あるいは重大な決断をせざるを得ないわけで、その時は機関にはかるということです。これは過去にもいろいろな協定など決めるときも、労組は組合民主主義の立場で動いていますから、機関の承認は受けています。執行部といえども勝手なことはできないわけです。
以上引用終了
ということで、最終的な結論を出すときには、やはり執行部に置いて機関の承認をえなくてはならないというところで、すでに動労のように単一組織でないところの国労の矛盾というか欠点を露呈させているように思います。
もう少し続くのですが、長くなりそうなのですが、この続きは明日以降にでも。
*****************************************************************
取材・記事の執筆等はお気軽にお問い合わせください。
下記、入力フォームからお送りいただけると助かります。
http://jnrera3.webcrow.jp/contact.html
日本国有鉄道研究家・国鉄があった時代
http://jnrera3.webcrow.jp/index.html
*****************************************************************