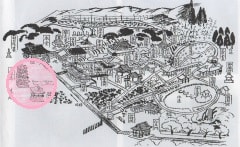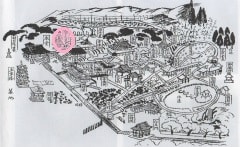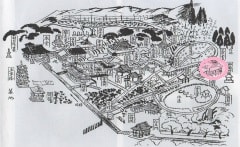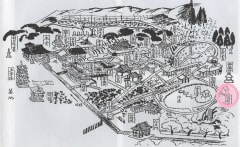2 0 1 4 年 1 月 7 日 ( 火 )
午 後 2 時 3 1 分
千 葉 県 印 西 市
摩 尼 山 松 虫 寺
神崎神社に参拝してちょっとばかりホッとした私は、拙宅に戻る途中にある
松虫寺というおもしろい名前の寺をめざしました。
地図を見る限り、軽自動車がやっと通れるような道を上ったところにあるんだろうな~と考えていました。
そして実際、自分がたどった道は、ちょっと狭い道を上るというものでした。
鬼ヅモの大会にて会員の前で「行く行く」と言いつつ、立ち寄ることのなかった松虫寺。
その松虫寺を、ついにこの日、参拝するのだ・・・・・・

と自分の中で感慨に浸りつつチャリを押し進めていると、じつに突然に、あっさりと仁王門が目に入ってしまいました。
「あ、ここね・・・」
細い道の曲がり角を曲がると、すぐに仁王門が目に入った感じ。
松虫寺の由緒は、なんと奈良時代にまでさかのぼります。
時の帝は、奈良の大仏を鋳造させた聖武天皇。
天皇には松虫姫という皇女さまがいらっしゃいました。
松虫姫のお身体は謎の病弱で、いかなる道士に加持祈祷をさせても治りませんでした。
(現在でいうところのハンセン氏病と考えられています)
ある晩、松虫姫の夢枕に薬師如来が現れ、姫にお告げを与えます。
「わたしは印旛沼のほとりの萩原郷におるので、わたしを捜して参られよ」
姫はそのことを天皇に伝え、下総国への下向を訴えました。
父である天皇はその願いを聞き届け、乳母の杉自、護衛役の権太夫と大勢の兵士、そして奈良時代きってのスーパー僧侶・行基をお供につけました。
病弱の身である姫にとってはとても大変な旅であったでしょう。
山賊に襲われた際には、権太夫らがねじ伏せました。
印旛沼が大水で渡れないときには、行基が祈って、モーセのごとく大水を鎮めて道を拓いたといいます。
護衛の兵士が次々脱落するという難儀な旅の末、松虫姫の一行は下総国の萩原郷に着くことができました。
姫はひっそりと祀られている薬師如来のお堂を見つけ、そこで勤行に励みました。
すると、誰もが治らないと思っていた姫の病は治っていきました。
村人たちは、姫の一行をたいそう温かくもてなしたそうです。
そこで一行は、都・奈良の文化を村の住民に教えてあげました。
姫は病が完治したので、都に戻ることになりました。
乳母の杉自は、村人に慕われていたこともあり、また年老いたためもう姫のお役には立てないと思い、この地に残って都の文化を伝えることに努め、この地で一生を終えたそうです。
聖武天皇は姫の完治をたいそうお喜びになり、行基に命じて薬師如来をお祀りする寺を建てさせたそうです。
(ちなみに行基が印旛沼の水を分けて道を作った場所は、現在土行という地名がついています。)
千葉テレビの「お~いお話だよ」を参考にまとめてみました。

仁王門の脇に立つ石碑にはこうあります。
松虫寺は奈良時代、聖武天皇の天平十七年(七四五)僧行基の開創と伝えられ、始め三論宗、のち、天台宗、そして、真言宗に所属し今日に至っている。
寺伝によれば、聖武天皇の皇女松虫姫、(不破内親王)が重い病に患われた時、不思議な夢のお告により、下総に下向され、萩原郷に祀られていた薬師仏を祈り、重患が平癒したので、天皇は、行基に命じて七仏薬師を刻み一寺を建立し、姫の御名をとって松虫寺と名付けられたと言う。
現在の本尊、七仏薬師如来は榧材の一木造りで、平安後期の特色を伝える優作として、昭和三十四年、国の重要文化財に指定された。
南面する仁王門、薬師堂は江戸時代、享保三年に改築されたもの、山号額は儒者、佐々木文山、薬師堂の偏額は、釈雲照の染筆である。
西面する本堂は、寛政十一年の建立で、阿弥陀如来、不動明王、松虫姫尊像をまつる。
薬師堂の裏手の松虫姫御廟は、御遺言により分骨埋葬されたものと伝えている。
※享保3年=1718年、寛政11年=1799年
※榧材 ・・・ カヤの材木。碁盤・将棋盤などに用いられています。
※一木造り ・・・ その名のとおり、一本の木から採れた木材を彫り刻んで仏像を造る方法。
それぞれの材木から仏像のパーツを造って組み合わせる方法は寄木造りといいます。
※佐々木文山 ・・・ 江戸時代前・中期の書家。
※釈雲照 ・・・ 幕末・明治期の僧。
石碑の記述をまるパクリしたので、少しばかり注を入れてみました。
不自然な句点(、)も、原文のままです。
しかもこの石碑、文章の禁則処理をしてないのか、行のあたまに句点がついてる・・・(^_^;)
それではさっそく参拝しましょうか。

まずは表玄関ともいうべき
仁王門ですね。
石碑の記述によれば江戸時代の中ごろに造られたものです。
朱塗りが色あせているものの、味のある素晴らしい御門です。
左右に仁王像が控えており、それぞれ四角い穴、円い穴から仰ぎ見ることができます。


穴から仰ぎ見た仁王像は、「悪しき心の者を排除する」という迫力に満ちています。
仁王門をくぐると、すぐそばに薬師堂が建っています。

 薬師堂
薬師堂も、仁王門と同期に改築されて、現在に続いているそうです。


扁額や絵はすっかり色あせてしまっているが、こういうのがいいんですよねぇ~。
薬師堂の裏手には、宝物庫と松虫姫御廟が静かにたたずんでいます。
 宝物庫
宝物庫の中には、松虫姫がお祀りしたとされる御本尊・
七仏薬師如来【国指定重要文化財】などの寺宝が保管されています。
七仏薬師如来は7体の像の総称であり、坐像(お座りになっている薬師如来)が1体、立像(お立ちになっている薬師如来)が6体あります。
実際には平安時代後期の作と考えられていますが、様式は平安前期に流行したものとなっており、東国への文化の伝来にタイムラグがあったことがわかります。

薬師堂の真裏にある
松虫姫の御廟です。
千葉の民話ではか弱くやさしい皇女さまというイメージの松虫姫ですが、本名は不破内親王というそうです。
そしてこの皇女さまは、都に戻ってからも波瀾万丈の一生をおくるのです。
都に戻った不破内親王は、その後天武天皇の孫にあたる塩焼王(氷上塩焼)に嫁ぎます。
そして氷上志計志麻呂とその弟川継という男子を産みます。
天平宝字8年(764年)の恵美押勝の乱で、夫の塩焼は藤原恵美押勝(藤原仲麻呂)に天皇に擁立されますが敗北、殺されてしまいました。
このときは不破内親王は皇女ということで連座を免れました。
しかし神護景雲3年(769年)、今度は称徳天皇を呪詛したとの疑いをかけられ、内親王の地位をはく奪されてしまいます。
「改名女帝」こと称徳天皇は、不破内親王を「厨真人厨女」に名を改めさせて流罪にしました。
のち宝亀3年(772年)、疑いが晴れて内親王に復帰します。
しかししかし延暦元年(782年)、今度は次男の氷上川継が謀反を起こした疑いがかかり、不破内親王も淡路に流罪となってしまいました。
その後淡路から和泉に身柄を移され、そこで失意のうちに一生を終えたといいます。
松虫姫は死に際して、自らの遺骨の一部を下総の地に葬られることを望んだそうです。
波瀾万丈の一生を終えた松虫姫は、今となっては静かに眠っていらっしゃるのでしょうか。
この日は正月明けの平日。
神崎では晴天であった空は薄曇りになっていました。
境内には私以外の人はおらず、なおいっそうの静けさがあたりを包みます。
薬師堂のお隣には、
松虫姫神社の御堂が建っています。

正面から入ります。



松虫姫を祀る神社らしく、御堂の意匠は色彩豊かなものになっています。
柱の両側にある彫像は、悪い夢を食べるというバクがかたどられているそうです。
夢枕によって下総まで下向した松虫姫ならではでしょうか。
画像の周りの白いモヤは、カメラのレンズが曇っているだけです。
ここで旅の無事を祈願して、松虫姫神社をあとにしました。
拙宅へ戻るべく、国道464号方面に進んだのですが・・・・・・
そのルートがきわめてあっさり見つかりました。
そしてそのルートはアップダウンがさほどなかったのです。
国道464号はアップダウンが多いから・・・などと考え、別ルートを検索しては道に迷い、挙げ句に参拝を断念した1月2日。
松虫姫は私に、あらためて旅のあり方を問うたのではないでしょうか。
第61回鬼ヅモ同好会麻雀大会顛末記 完
だけどいちおう番外編も用意しました。