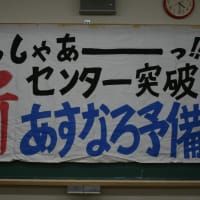京都の暑い暑い夏が終わってようやく秋の気配の感じられ始めたようにも思われる、とある週末のこと。祝日の巡りあわせで月曜までが連休になり、連休中は現場が動かないので当然資材搬入の仕事もなく何の予定も立たない。めぼしい連れはバイトにデートに行楽にと忙しく立ち回っている様子、いくつか誘いがないでもなかったが夏の温気(うんき)に当てられたのもあったんだろうけれど何をするにも面倒臭く感じられて、すべて断って三日間を無為に過ごすことにした。のだが。自ら選んだこととはいいながら、いざはじめてみると「何もしない」をするのも相当に骨が折れる。土曜の午後に空腹を覚えたころにはもうどうにもいたたまれなくなって、昼飯のついでにまずは下宿から七本松通を南に下って丸太町通沿いの中央図書館で検索目録を物色した。なにしろもう二十何年も前のことなので蔵書はおろか蔵書目録すらデータベース化されておらず、読みたい本を探したければずらずらと並ぶ棚の該当する小引き出しを開けて、みっちりと詰まっているカードを繰っていかなくてはならない。普段ならばまどろっこしくもある手順だけれど、今回のように無目的に思いつくままあちこちの引き出しを開けて回っているとあれこれと連想がつながっていって意外な書籍に行き着いたりする。要は手間と時間のかかるアクティブなアナログ版ブラウジングなのである。結局午後の何時間かをかけて目録を渉猟し、面白そうな本をとっかえひっかえしながら選んで貸し出し手続きを済ませてから昼飯に食べたかやくうどんはもう晩飯にしてもいいほどの頃合いになっている。そうして借り出してきた硬軟取り混ぜ十冊ある本を枕頭にうずたかく積み上げ、手の届く範囲にピースの缶と灰皿とメモ用のスケッチブックとペンと12色の色鉛筆セットとを並べて万全の体制を整えてから銭湯に出かけた。ほんの少し前まで日が暮れた後でも徒歩五分とかからない銭湯から下宿に戻る頃にはもう汗だくになるほど暑かったのだが、風呂上りにまだ暮色の残る中を歩いていると涼やかな空気が湯上りの火照った肌に気持ちよく感じられる。そんなことに秋を感じながら坂の上に立って紫がかったピンク色に縁取られる西の雲の色が変わっていくさまに見蕩れていた。傍から見たら阿呆が呆と突っ立っているようにも見えたろうが、そんなことをしていると少し寒くも感じられたので湯冷めをするのも莫迦らしい、坂を駆け下りて、階段を駆け上って、布団に潜り込んだ。
そこからは枕元に手を伸ばしては触れる本を「当たるを幸いなぎ倒し」手当たり次第にページを開いていったのだが、一冊を通読することはせずきりのいいところで次の本を開き、何冊かずつ同時進行で読みながら気になった事柄のメモを取ったり図版を模写したり、しているうちにうとうとと微睡(まどろ)んできて、目が覚めればまた本を開いて、途中で煙草を差し挟みながら眠って覚めてを繰り返していたようで。腹が減って時計を見ると日曜の夜明けが近い。布団を出るのも億劫だったが、そういう訳にもいかないので立った勢いでトイレを済ませ、そのまた序に大きな薬缶に水を汲んで戻ってきた。当時は水道もガスもない部屋でほしいだけ湯を沸かすのにアルコールランプと小さな五徳と薬缶を使っており、その小さな薬缶で湯が沸くのを待つ間に手回しのミルで豆を挽いて、何かの実験でもしているようなつもりになってコーヒーを淹れる。風呂上りに実感したように明け暮れ涼しく感じられるようになっていたのでドリッパーの中の豆にまぶすようにして最初のお湯を差すときの、ほんわりと立ち昇る湯気の暖かい香りが嬉しい。とはいえコーヒーだけでは腹にならないので冷蔵庫に常備してあった蜂蜜をなめながらコーヒーを飲んで腹の中からじんわりと温まった。そんなことで腹具合を誤魔化して、それでも甘いものを腹に入れて暫く経つと活字を追って凝り固まった頭の中が解けたようになって、空が薄明るくなりかけた頃に眠気に任せてそのままうとうとと寝入った。
目が覚めて時計を見ると1時間も経っていなかったが頭はすっきりしている。すっきりとした頭で本を読みメモを取って、煙草を吸ってはコーヒーを淹れて、眠気がさしたら微睡んで覚めては本を読みメモを取って煙草を吸ってコーヒーを淹れときには蜂蜜を舐めて…と繰り返しているうちに日曜の午も過ぎ、そろそろ腹具合の誤魔化しも効かなくなって来た。残りの心許なくなった缶ピースを吹かしながら、どこかに出かけようかと考えながら随分とたまったメモをぱらぱらと捲っていると、ある地図のところで手が止まった。
京都市内に残る御土居の遺構の在所が記してある。先にも触れたが御土居とは聚楽第などと並ぶ京都改造事業の一環として豊臣秀吉によって当時の京都を囲うように造られた土塁で、これを境に内側を洛中、外側を洛外とするものらしい。その一部が北野天満宮の西側に残っていて、そこから紙屋川にかかる小橋を渡って対岸の小路に抜ける辺りの雰囲気を気に入って大学への往き返りよく歩いてもいた。そんなところがまだほかにもあるかと思い、食事がてら回ってみようかとメモを片手に自転車で出かけることにした。
自転車で回れないこともないとはいえ京都を取り囲んでいたというだけあってかなりの広範囲に渡る。まずは普段の馴染みもある下宿より西側のものからと、紫野の辺りから南下して行ったが、天満宮の西に残るものほど魅力を感じるところとてなく、陽もだいぶ西に傾いて日差しと風景が黄色味を帯びている。もうやめようかと思いながらたどり着いた西大路御池から一筋東の西土居通りを二筋上がったところにある遺構はこんもりとした杜になっていて、他のところとは様子が違っている。そこまで行ってみると石の鳥居があって、額束には「正一位 市五郎大明神」とある。その奥には参道沿いに朱色の鳥居がいくつも連なっていて、潜って境内に入ってみると拝殿の鳥居の両脇に狛犬のように狐の像があり、拝殿に吊るしてある提灯には「市五郎稲荷」と大書してある。拝殿の前には「史跡 御土居」と書かれた石標が立っていて、階段を上って行った先に当たるお土居跡の上にも社があるようだ。昼でも暗いと思われる杜は薄暮の中次第に色を失っていき、ざわざわと揺れ動きながら不気味さをまとい始めている。鳥居の外とのあまりの落差に呆然とあたりを見回しながら気にかかっていたのは本殿の前に立ったときからなんとなく感じられた、妙にざわついた気配と得体の知れない臭気。と、突然本殿の陰から人が出てきて吃驚した。両手に箒とちりとりを下げたもんぺに割烹着姿のお婆さんが「お参りどっか、ご苦労さんで」と声をかけてきた。たぶん「どすか」と言っているのだろうが「す」の音が明瞭ではなく「どっか」と聞こえるのが印象に残る。
「御土居の跡を見に来たんです」
「はぁ、そうどっか」
「ここはお稲荷さんになってんですね」
「へぇ。お稲荷さんやけど、ご神体は狸ですねん」
「は?」
神社の御守をしているというお婆さんによると祭神の市五郎大明神は狸像を御神体として祀られているそうで、そんな話をしているとお婆さんの足元にわらわらと猫が集まってきた。
「猫、多いですね」
猫は好きなのだけれど、こんな雰囲気のところでどこからともなく何匹も何匹も出てこられてはあまり気持ちの良いものではない。お婆さん曰く、猫好きが嵩じて野良猫にえさをやるようになってから集まりはじめたとのこと、つい今しがたも社の裏手でえさをやっていたのだそうだ。それでどうやら得体の知れない臭いの得体が知れた。猫に与えていたえさと猫の出したものと、猫そのものの獣臭、それにこれだけいれば気配もざわつこうというものだ。
「この辺の人からは『猫稲荷』と呼ばれてますのん」
と言いながらご本人はニコリとしたつもりなのだろうが、見ているとニタリとしか形容の仕様のない笑顔になった。お礼と挨拶を述べて鳥居を潜って道路に出ると空にはまだ明るさが残っている。神社の南側に接する道から西大路通に出て北上しながら目を向けると、うっすらと暮色の残る空をバックに黒いシルエットになった杜がざわざわと揺れている。
御土居の跡に一塊になってざわめく黒い杜の中心に祀られた狸を守る狐の周りに集まる数多の猫と、そのすべての世話をするネコババァ。翌日行ってみたらそんなものは跡形もなかった、とでもなったら化かしたのは狸か狐か、それとも猫か。なんだか妙な後味を残して無為な日曜が暮れてゆく。
そこからは枕元に手を伸ばしては触れる本を「当たるを幸いなぎ倒し」手当たり次第にページを開いていったのだが、一冊を通読することはせずきりのいいところで次の本を開き、何冊かずつ同時進行で読みながら気になった事柄のメモを取ったり図版を模写したり、しているうちにうとうとと微睡(まどろ)んできて、目が覚めればまた本を開いて、途中で煙草を差し挟みながら眠って覚めてを繰り返していたようで。腹が減って時計を見ると日曜の夜明けが近い。布団を出るのも億劫だったが、そういう訳にもいかないので立った勢いでトイレを済ませ、そのまた序に大きな薬缶に水を汲んで戻ってきた。当時は水道もガスもない部屋でほしいだけ湯を沸かすのにアルコールランプと小さな五徳と薬缶を使っており、その小さな薬缶で湯が沸くのを待つ間に手回しのミルで豆を挽いて、何かの実験でもしているようなつもりになってコーヒーを淹れる。風呂上りに実感したように明け暮れ涼しく感じられるようになっていたのでドリッパーの中の豆にまぶすようにして最初のお湯を差すときの、ほんわりと立ち昇る湯気の暖かい香りが嬉しい。とはいえコーヒーだけでは腹にならないので冷蔵庫に常備してあった蜂蜜をなめながらコーヒーを飲んで腹の中からじんわりと温まった。そんなことで腹具合を誤魔化して、それでも甘いものを腹に入れて暫く経つと活字を追って凝り固まった頭の中が解けたようになって、空が薄明るくなりかけた頃に眠気に任せてそのままうとうとと寝入った。
目が覚めて時計を見ると1時間も経っていなかったが頭はすっきりしている。すっきりとした頭で本を読みメモを取って、煙草を吸ってはコーヒーを淹れて、眠気がさしたら微睡んで覚めては本を読みメモを取って煙草を吸ってコーヒーを淹れときには蜂蜜を舐めて…と繰り返しているうちに日曜の午も過ぎ、そろそろ腹具合の誤魔化しも効かなくなって来た。残りの心許なくなった缶ピースを吹かしながら、どこかに出かけようかと考えながら随分とたまったメモをぱらぱらと捲っていると、ある地図のところで手が止まった。
京都市内に残る御土居の遺構の在所が記してある。先にも触れたが御土居とは聚楽第などと並ぶ京都改造事業の一環として豊臣秀吉によって当時の京都を囲うように造られた土塁で、これを境に内側を洛中、外側を洛外とするものらしい。その一部が北野天満宮の西側に残っていて、そこから紙屋川にかかる小橋を渡って対岸の小路に抜ける辺りの雰囲気を気に入って大学への往き返りよく歩いてもいた。そんなところがまだほかにもあるかと思い、食事がてら回ってみようかとメモを片手に自転車で出かけることにした。
自転車で回れないこともないとはいえ京都を取り囲んでいたというだけあってかなりの広範囲に渡る。まずは普段の馴染みもある下宿より西側のものからと、紫野の辺りから南下して行ったが、天満宮の西に残るものほど魅力を感じるところとてなく、陽もだいぶ西に傾いて日差しと風景が黄色味を帯びている。もうやめようかと思いながらたどり着いた西大路御池から一筋東の西土居通りを二筋上がったところにある遺構はこんもりとした杜になっていて、他のところとは様子が違っている。そこまで行ってみると石の鳥居があって、額束には「正一位 市五郎大明神」とある。その奥には参道沿いに朱色の鳥居がいくつも連なっていて、潜って境内に入ってみると拝殿の鳥居の両脇に狛犬のように狐の像があり、拝殿に吊るしてある提灯には「市五郎稲荷」と大書してある。拝殿の前には「史跡 御土居」と書かれた石標が立っていて、階段を上って行った先に当たるお土居跡の上にも社があるようだ。昼でも暗いと思われる杜は薄暮の中次第に色を失っていき、ざわざわと揺れ動きながら不気味さをまとい始めている。鳥居の外とのあまりの落差に呆然とあたりを見回しながら気にかかっていたのは本殿の前に立ったときからなんとなく感じられた、妙にざわついた気配と得体の知れない臭気。と、突然本殿の陰から人が出てきて吃驚した。両手に箒とちりとりを下げたもんぺに割烹着姿のお婆さんが「お参りどっか、ご苦労さんで」と声をかけてきた。たぶん「どすか」と言っているのだろうが「す」の音が明瞭ではなく「どっか」と聞こえるのが印象に残る。
「御土居の跡を見に来たんです」
「はぁ、そうどっか」
「ここはお稲荷さんになってんですね」
「へぇ。お稲荷さんやけど、ご神体は狸ですねん」
「は?」
神社の御守をしているというお婆さんによると祭神の市五郎大明神は狸像を御神体として祀られているそうで、そんな話をしているとお婆さんの足元にわらわらと猫が集まってきた。
「猫、多いですね」
猫は好きなのだけれど、こんな雰囲気のところでどこからともなく何匹も何匹も出てこられてはあまり気持ちの良いものではない。お婆さん曰く、猫好きが嵩じて野良猫にえさをやるようになってから集まりはじめたとのこと、つい今しがたも社の裏手でえさをやっていたのだそうだ。それでどうやら得体の知れない臭いの得体が知れた。猫に与えていたえさと猫の出したものと、猫そのものの獣臭、それにこれだけいれば気配もざわつこうというものだ。
「この辺の人からは『猫稲荷』と呼ばれてますのん」
と言いながらご本人はニコリとしたつもりなのだろうが、見ているとニタリとしか形容の仕様のない笑顔になった。お礼と挨拶を述べて鳥居を潜って道路に出ると空にはまだ明るさが残っている。神社の南側に接する道から西大路通に出て北上しながら目を向けると、うっすらと暮色の残る空をバックに黒いシルエットになった杜がざわざわと揺れている。
御土居の跡に一塊になってざわめく黒い杜の中心に祀られた狸を守る狐の周りに集まる数多の猫と、そのすべての世話をするネコババァ。翌日行ってみたらそんなものは跡形もなかった、とでもなったら化かしたのは狸か狐か、それとも猫か。なんだか妙な後味を残して無為な日曜が暮れてゆく。