 日本人の作品のご紹介です!
日本人の作品のご紹介です!
今回ご紹介しますのは、伊福部昭(1914年-2006年日本)作曲の交響頌偈「釈迦」です。
伊福部昭の曲と言えば「ゴジラ」のテーマ曲を思い出される人が多いのでは無いでしょうか?
私も、伊福部昭=「ゴジラ」のテーマ曲を作曲した作曲家くらいの知識しかありませんでした(もっとも、今でも知識は皆無に等しいですが・・)
クラシック音楽、それはキリスト教を根底にしたヨーロッパ中心の音楽である、と思っておりましたが、この伊福部昭の交響頌偈「釈迦」は標題の通り、釈迦の四苦の目覚めから悟りを開くまでを描いており、東洋的な思想に基づいた曲であり、メロディーも東洋的なものを感じます。
なお、この曲は「現代曲」に分類されますが、聴き易く、美しいメロディーも登場しますので、「現代音楽」はちょっと・・という方にもお勧めします!
なお、今回の曲はCDの録音が少ないと思われるため、「準秘曲」とさせて頂きます(お叱りを覚悟の上で・・)。
それでは曲のご紹介と参りましょう。この曲は3つの曲から構成されており、演奏時間は約40分ほどとなります。
I. カピラバスツの悉達多

やや悲劇的なメロディーから曲は始まりますが、やがて柔らかく美しいメロディーが奏でられます。その後は穏やかなメロディーが続き、時折り美しい響きが登場します。
やがて、太鼓(ティンパニ?)のリズムに乗って東洋風のメロディーが奏でられますが、しばらくすると再び悲劇的というか試練を思わせるようなメロディーが奏でられます。ここでも時折り美しい響きが登場します。
そして、印象深い鐘の音がしばらくの間響き渡り、最後は静かに終わります。
II. ブダガヤの降庵

ハープの静かな音色で曲は始まります。瞑想をイメージさせるような静かなメロディーが続きます。やがて、試練を思わせるようなメロディーが奏でられます。
そして、高揚感のある演奏へと続き、力強い合唱が加わります。その歌はまるで、お経をイメージさせ、東洋的なメロディーだと思います。
やがて、再びハープの静かな音色が響き、今度は女性の優しく美しい合唱が登場します。まるで心を救われるような穏やかで美しいメロディーです。
そして、再びオーケストラの高揚感に満ちた演奏と力強い合唱が登場しますが、やがて静かな演奏に戻りハープの音色が響きます。
試練を思わせるようなメロディーが再び登場し、曲は終わります。
III. 頌偈

穏やかで美しいメロディーにて曲は始まります。再び試練を感じさせるようなメロディーが登場しますが、その後荘厳的(東洋的)なメロディーがオーケストラと合唱によって奏でられます。感動的でさえあります。
そして、鐘の音がここでも印象深く響き渡ります。その後、再び試練を感じさせるメロディーが演奏された後に、感動的なメロディーが力強い合唱にて朗々と歌い上げられ、その感動に包まれて幕を閉じます。
参考までに、私の所有するCDの中から1枚をご紹介します。
レーベルはfontecで、石井眞木指揮、新交響楽団 の演奏のものです

このCDの情報は、こちらの下の画像をクリックして頂ければご覧になれます


お願い:もし画像をクリックしても「ページを表示できません」というエラー画面が表示された場合はリンクに間違いがある可能性がございますので、ご一報頂けますと助かります












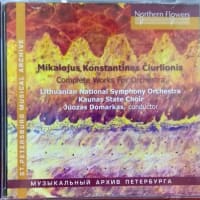
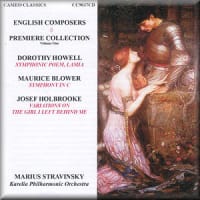
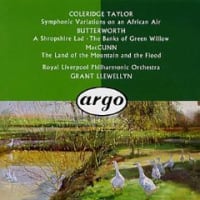

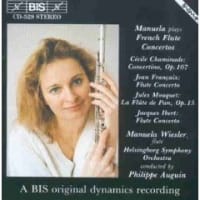
それは、私の最も尊敬する作曲家が伊福部昭氏だからです。
伊福部昭氏は、21歳のときパリで開かれたチェレプニン主催のコンクール(チェレプニン賞)で氏のデビュー作、日本狂詩曲が見事1位を獲得、それが縁で日本に来日したチェレプニンに、わずかな期間、学んだ以外はそのほとんどが独学で作曲を修めました。
伊福部氏の大著「管弦楽法」は上巻が1953年に、下巻が1968年に刊行されましたが、伊福部氏本人とその弟子たちによって最近改められ
「完本 管弦楽法」として出版されました。
今もなおオーケストレーションを学ぶ際の日本人作曲家のほとんどがこれをテキストにしているほど、
優れた書物であるそうです。
伊福部氏は戦後の東京音楽学校(現東京藝術大学音楽学部)作曲科の講師として招へいされ、
芥川也寸志氏を筆頭に、黛敏郎、矢代秋雄、松村禎三、石井眞木、三木稔、その他現在活躍する著名な作曲家を育てあげ、
芸大を退官した後、東京音楽大学の教授、学長を歴任し、2006年に他界されたあとも
二年連続で伊福部昭音楽祭が開かれ、国内有数のオーケストラメンバーを集めて
伊福部昭記念オーケストラが結成されるなど、多くの弟子や音楽関係者、そしてファンに支持されている
稀有な大作曲家です。戦後の作曲界をリードする多くの作曲家を育てたのは、池内友次郎氏と
この伊福部昭氏だと思います。二人は芸大で同時期に教官となって在職していました。
私は氏のコンサートに足を運んだ際、一度だけご本人をお見かけし、興奮のあまり震えてしまったのを
覚えております。もうだいぶお歳を召しておられたので、杖をついて歩いておられましたが、
その後から弟子の松村禎三氏が師匠の影を踏まず、付いて歩く姿を拝見して、それも感動いたしました。
松村氏も芸大教授などを歴任し、伊福部氏譲りの見事なオーケストレーションで大作を書かれている
大物作曲家です。(惜しくも師のあとを追うように2007年他界されました)
伊福部氏の門弟は結束力が強く、古弟子会、新弟子会を結成して今もなお、伊福部氏の音楽を
後世に伝えようと、日々活動しています。
伊福部氏の音楽は日本と汎アジア民族の血が脈々と流れているかのような、大陸的で大らかなフレーズと
パーカッションを多用し、バーバリックスな音色と変拍子によって構築されているのが特徴です。
現代民族音楽とオーケストレーションの大家として信望者も多く、上述の通り多くの弟子を
直接的、間接的に導いてきましたが、ご当人の作風は至って平易でわかりやすく、前衛的な響きや
観念的な楽想は一切ありません。オスティナートのリズムに乗せて激しく躍動するときもあれば
日本のわび・さびを感じる風流で思索的な楽想も多々あります。
デビュー作、「日本狂詩曲」は発表されたときには伊福部氏の集大成のような作品で、
まったくの独学で書かれたにもかかわらず、作品としては完成されていました。
第1楽章「ノクチュルヌ」はあのシベリウスも絶賛したというエピソードがあります。
北欧の大家シベリウスが日本人作曲家の伊福部氏と関わりがあるなんて、その歴史的事実に驚嘆するばかりです。
さて、ようやく本題の交響頌偈「釈迦」についてですが、曲の印象としては中東の音楽を
髣髴させるフレーズで構成されています。釈迦の出生は現在のネパール、ルンビニであるとされていますが、
仏教の発祥の地はインドであり、釈迦が仏門を開いたインドのイメージとはまた違うような印象を持ちました。
この曲の関連として付け加えますが、伊福部氏の作品に舞踏音楽「サロメ」というのがあります。
オスカーワイルドの戯曲をもとに音楽を付けたものですが、やはり中近東の音階を使った作品に仕上がっています。
このように純日本の旋法ばかりでなく、東洋全般の音階を用いて独特な音楽観を展開していきました。
「ゴジラ」のフレーズがあまりにも有名で一般的には「ゴジラの伊福部」として
知られていますが、あのフレーズは現在でもTV番組のBGMとして頻繁に使用され、
現在、大リーガーの松井選手が出ている缶コーヒーのCMにも使われています。
それはフランスをはじめとする全世界でも有名なフレーズなのですが、原曲は伊福部氏の
「ヴァイオリンと管弦楽のための協奏風狂詩曲」の第1楽章の途中に現れるフレーズなのです。
よろしければ協奏三題というCDがありますので(ご存知でしょうが)機会があればお試しください。
今回は投稿が大変長くなってしまいました。申し訳ありません。
現在出ているCDは当盤だけですので同じものです。
コメント有難うございました(^^)
何とお詳しいのでしょう!
私は、正直、日本人作曲家に関しての知識はほとんど無いのです。
今回ご紹介しました「伊福部昭」のCDは、最初からその曲を知っていた訳ではなく、たまた購入したら素晴らしい曲だった、という事なのです。
本当に最初は「ゴジラのテーマ曲」の作曲家くらいしか存じ上げておりませんでした。
本当に素晴らしい曲であり、もっと多くの日本人に聴いて頂きたいのです。
midsummervigilさんは、実際にお会いになられたということで、非常に羨ましく思います。
私は、日本人作曲家のクラシック音楽のCDは他に1枚だけ(NAXOSの日本人作曲家特集)しか所有しておらず、偶然にもmidsummervigilさんの好みと一致しまして光栄でございます。
それにしても、midsummervigilさんはその曲の背景や作曲家に関しても造詣が深く、ただただ頭が下がるばかりです。
非常に参考になりました。
また「協奏三題」は恥ずかしながら存じ上げておりませんでした。
こちらも参考にさせて頂きたいと思います。
有難うございました!
伊福部氏を最初に知ったのは、N響アワーという番組で、当時司会をされていた芥川也寸志氏が、芸大で伊福部氏に師事し、その恩師の曲を取り上げるという企画で、伊福部氏の代表作「交響譚詩」がN響により
演奏されたのを聴いたのが始まりでした。
正直、鳥肌が立つほどの興奮を覚えました。それは日本民族としての血が騒ぐとでも申しましょうか。もちろん、曲も素晴らしいのですが、ただ単に曲のフレーズとかメロディとかそういう楽曲に対しての良さという感覚より、リズムが土台にされている音楽と申しましょうか。言葉では上手く表現できませんが、自然と身体が躍動するような、それでいてどこか懐かしいようなそういう感覚に襲われたのです。
そこから伊福部氏の虜になり、ほとんどの楽曲をCDなどにより聴くことになるのですが、もしよろしければYou Tubeで伊福部昭「交響譚詩」と検索すれば外山雄三指揮:N響による演奏が第1譚詩のみ聴けますので、お時間があれば試してください。
私は秘曲こそわが国日本の音楽にあると持論があるのですが、もちろんその意味は素晴らしい音楽がたくさん存在しているのに、クラシックファンの支持が少ないことを大変残念に思っているということです。得々星の玉子ちゃまさんに申し上げているのではないので、気を悪くしないでくださいね。
これは一般的な話として思うところを述べているのですが、確かに日本の現代音楽はおよそメロディーという言葉からはかけ離れている存在にあり、何か意味ありげなクラスターの連続や音色のみの色彩に囚われた作品が多く見受けられ、作曲技法にばかり目が向けられるような風潮にあると感じます。
それは諸外国も同じような状況にあると思われますので、日本だけの問題ではないのですが、現代音楽=難しくてつまらない。というイメージができあがってしまって、聴衆を無視した評論家たちの机上の理論だけで続いているような気がするのです。
もちろん、音楽はいかに独自性を世に発表するかということで歴史を繰り返していますので、作曲家たちは日々新しいものを追求して、作曲技法の修練に邁進しているのでしょうが、その分、聴き手からはどんどん難しくなって楽しみにくいという印象が強まります。
ゆえに、聴衆が離れていき、コンサートやCDにも取り上げられない(商業ベースに乗らない)結果、
現代音楽を手がけているだけでは生活が成り立たない(収入が見込めない)のが現状です。
著名な作曲家は本来の作品を世に発表するだけでは、食べていけないので映画音楽や商業音楽、その他クライアントと契約して作曲料を頂くということをしています。
当然に、いつの時代にもそういうことはありました。例えば、ショスタコーヴィチが映画音楽を手がけたり、アルヴェーンも生涯に3本の映画音楽を作曲しています。
伊福部氏は実に300本もの映画音楽を手がけたとご本人がおっしゃっていましたが、回顧録で「生活のため仕方なしやっていたが、本来造りたい音楽を世に出せないストレスは相当なものだ」というような苦言を呈しておられます。
それだけに音楽の道は厳しいということが如実に伝わる実態なのですが、話を本筋に戻しますと、現代音楽といわれているものでも大変親しみやすく、メロディアスで印象に残る作品はたくさんあります。今は古典とされてしまっているのですが、伊福部氏の一番弟子芥川也寸志氏も初期の作品は大変リリシズムに富んだものが多いですし、別宮貞雄氏は日本人の作品では
ないと思われるような大変美しい音楽を作曲されています。原 博氏は交響曲、弦楽のためのセレナード
などの作品が有名ですが、弦楽セレナードはヨーロッパの古典音楽を模した作品で、モーツァルトを聴いているようだと評されました。
また、芸大時代作曲科の課題で当時の前衛的技法を用いず、古典的技法の習作を出したところ、担当教官に相手にされなかったというエピソードがあります。
伊福部氏と同年で作曲家としてデビューしたのは遅かったのですが、小山清茂氏は日本の民謡、特に長野県出身ですので、信州の民謡を巧みなオーケストレーションで色彩豊かにまとめられている作品を出していますし、吉松 隆氏はイギリスのCHANDOSと契約して自作のシンフォニーを発表していますが、
とても聴きやすく、ご本にも若いころはロックやジャズに傾倒していたこともあって、作風が気さくと申しましょうか、アトム・ハーツ・クラブという弦楽のための作品などは鉄腕アトムに由来する音楽で、ロック調のノリの良い曲に仕上がっています。
もちろん、好みというものもありますから、たとえ聴きやすくても受け付けない音楽は出てきます。しかし、私が伊福部昭の音楽に最初に触れたときのように感動を受けることも多くあると思うのです。
たしか、得々星の玉子ちゃまさんは「日本管弦楽作品集」を所有されているのですよね?
ナクソスのものと思いますが、あの中の曲は日本人作家のほんの一握りのものです。
無理に聴くことを勧めるものではありませんが、上述のような作曲家たちも存在することを認識していただければ幸いです。
長文すみませんでした。また別の項に投稿します。
>確かに日本の現代音楽はおよそメロディーという言葉からはかけ離れている存在にあり、何か意味ありげなクラスターの連続や音色のみの色彩に囚われた作品が多く見受けられ、作曲技法にばかり目が向けられるような風潮にあると感じます。
私も、そのイメージが付きまとっているため、日本人作曲家の曲をほとんど聴いていないのです。
ご紹介頂きました作曲家の方達に関しては、今後の参考にさせて頂きます。
まさに、今後の課題です。
私は、奇異をてらったような作品は好まず、自分の感性で美しいと思う曲しか聴きません。
(奇異をてらった曲を好まれる方には申し訳ありませんが・・)
オリジナル性、新規性も重要なのかもしれませんが、そもそも音楽とは「音を楽しむ」と書きまして、少なくとも私は「音を楽しみたい」のです。
「もう良いから、その辺で演奏を止めて下さい!」と言いたくなるような曲は、私にはどうしても聴く気にならないのです。
そう言う曲は将来の人々には「なんて素晴らしい曲なのか!」と絶賛されるのでしょうか?
画家も作曲家も「後に絶賛」という事がありますので。
なお、私の通うCDショップの店員さんが仰っていました。一昔は、上記のような奇異をてらった曲がもてはやされていたが(評論家に?)、最近は聴き易い曲も作曲されるようになってきたのだとか。
ただ、これは「日本人作曲家において」という前置き無しの話です。
色々と勉強になるお話を有難うございました!