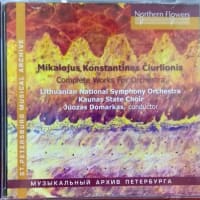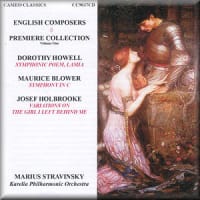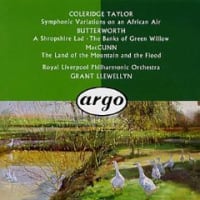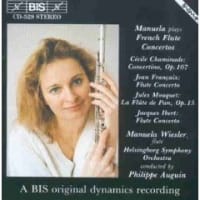今回ご紹介しますのは、「秘曲」の部類に入るかもしれません。
クニッペル(1898年-1974年ロシア(旧ソ連))という作曲家をご存知でしょうか?
私自身、この作曲家を知ったのはそれほど昔ではありません。クラシック初心者の方は恐らく初耳の作曲家だと思います。
しかし、「ポーリュシカ・ポーレ」と言う曲はもしかすると名前は知らなくても、聴いた事のある曲かもしれませんよ。私自身が、この交響曲第4番「コムソモール戦士の詩」を初めて聴いたとき、このメロディーは学校の音楽の授業か何かで聴いた事ある と思いましたから。
と思いましたから。
参考までにポーリュシカ・ポーレは、1934年に作られたヴィクトル・グーセフ作詞、クニッペル作曲の赤軍の軍歌です。今回ご紹介します交響曲第4番「コムソモール戦士の詩」の第1楽章の第2主題が独立して歌われるようになった曲で赤軍合唱団の歌唱により世界的に有名となったそうです(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
それでは、曲のご紹介と参りましょう。曲は4つの楽章から構成されており、演奏時間は約34分ほどになります。
1.第1楽章
少し不安げなファンファーレのような演奏から曲は始まります。間もなく、例の「ポーリュシカ・ポーレ」のメロディーも登場してきます。
やがて、「ポーリュシカ・ポーレ」の歌が登場します。独唱で始まり、やがて合唱となります。
そして、再び、不安げなメロディーに戻ります(戦闘をイメージするようなメロディーです)。そのメロディーに沿うような形で「ポーリュシカ・ポーレ」のメロディーも演奏されます。その後は「ポーリュシカ・ポーレ」の合唱とオーケストラによる不安げな演奏が繰り返され、やがては高らかな合唱が始まります。オーケストラと共に高らかに「ポーリュシカ・ポーレ」を歌い上げ、最後は静かに終ります。
2.第2楽章
静かに曲は始まりますが、やがて短い合唱を契機に勇壮なメロディーがオーケストラにより演奏されます。ロシアの民謡のようなメロディーも登場します。行進曲のようなテンポです。
やがて、不安げでローテンポな曲調に変わりますが、「ポーリュシカ・ポーレ」がこの曲でも登場します。ここでは、高らかに歌うというよりは、静かにそっと歌います。
3.第3楽章
ゆったりとした演奏で曲は始まります。どこか悲哀を感じさせるメロディーの演奏が続きます。曲の最後は「ポーリュシカ・ポーレ」の歌が流れて終ります。
4.第4楽章
勝利のファンファーレのようなメロディーで開始され、楽しげな合唱が続きます。ノリノリのテンポで楽しげな雰囲気の合唱と演奏が続きます。
歌詞の内容は分かりませんが、戦いに勝利してその喜びを歌っているかのような雰囲気の合唱と演奏が終始流れます。最後は「ポーリュシカ・ポーレ」のメロディーがオーケストラによって回帰され、ロシア民謡のようなメロディーの後に「ポーリュシカ・ポーレ」を合唱と演奏で高らかに歌い上げて曲は幕を閉じます。
参考までに私の所有するCDから1枚をご紹介します。
レーベルはMELODIYAで、ヴェロニカ・ドゥダロヴァ指揮、モスクワ交響楽団、Russian Academic Chamber Chorusの演奏です
今回は残念ながら、私の所有しているCDのジャケット画像のみの表示となります

クニッペル(1898年-1974年ロシア(旧ソ連))という作曲家をご存知でしょうか?
私自身、この作曲家を知ったのはそれほど昔ではありません。クラシック初心者の方は恐らく初耳の作曲家だと思います。
しかし、「ポーリュシカ・ポーレ」と言う曲はもしかすると名前は知らなくても、聴いた事のある曲かもしれませんよ。私自身が、この交響曲第4番「コムソモール戦士の詩」を初めて聴いたとき、このメロディーは学校の音楽の授業か何かで聴いた事ある
 と思いましたから。
と思いましたから。参考までにポーリュシカ・ポーレは、1934年に作られたヴィクトル・グーセフ作詞、クニッペル作曲の赤軍の軍歌です。今回ご紹介します交響曲第4番「コムソモール戦士の詩」の第1楽章の第2主題が独立して歌われるようになった曲で赤軍合唱団の歌唱により世界的に有名となったそうです(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
それでは、曲のご紹介と参りましょう。曲は4つの楽章から構成されており、演奏時間は約34分ほどになります。
1.第1楽章

少し不安げなファンファーレのような演奏から曲は始まります。間もなく、例の「ポーリュシカ・ポーレ」のメロディーも登場してきます。
やがて、「ポーリュシカ・ポーレ」の歌が登場します。独唱で始まり、やがて合唱となります。
そして、再び、不安げなメロディーに戻ります(戦闘をイメージするようなメロディーです)。そのメロディーに沿うような形で「ポーリュシカ・ポーレ」のメロディーも演奏されます。その後は「ポーリュシカ・ポーレ」の合唱とオーケストラによる不安げな演奏が繰り返され、やがては高らかな合唱が始まります。オーケストラと共に高らかに「ポーリュシカ・ポーレ」を歌い上げ、最後は静かに終ります。
2.第2楽章

静かに曲は始まりますが、やがて短い合唱を契機に勇壮なメロディーがオーケストラにより演奏されます。ロシアの民謡のようなメロディーも登場します。行進曲のようなテンポです。
やがて、不安げでローテンポな曲調に変わりますが、「ポーリュシカ・ポーレ」がこの曲でも登場します。ここでは、高らかに歌うというよりは、静かにそっと歌います。
3.第3楽章

ゆったりとした演奏で曲は始まります。どこか悲哀を感じさせるメロディーの演奏が続きます。曲の最後は「ポーリュシカ・ポーレ」の歌が流れて終ります。
4.第4楽章

勝利のファンファーレのようなメロディーで開始され、楽しげな合唱が続きます。ノリノリのテンポで楽しげな雰囲気の合唱と演奏が続きます。
歌詞の内容は分かりませんが、戦いに勝利してその喜びを歌っているかのような雰囲気の合唱と演奏が終始流れます。最後は「ポーリュシカ・ポーレ」のメロディーがオーケストラによって回帰され、ロシア民謡のようなメロディーの後に「ポーリュシカ・ポーレ」を合唱と演奏で高らかに歌い上げて曲は幕を閉じます。
参考までに私の所有するCDから1枚をご紹介します。
レーベルはMELODIYAで、ヴェロニカ・ドゥダロヴァ指揮、モスクワ交響楽団、Russian Academic Chamber Chorusの演奏です

今回は残念ながら、私の所有しているCDのジャケット画像のみの表示となります