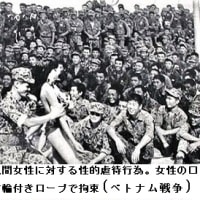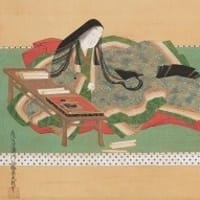後半 和泉式部の偲び歌 偲び歌を五つのパートから構想し詠みわけ
馬場あき子氏著作「日本の恋の歌 ~恋する黒髪~」一部引用再編集
*******
前半からのつづき
よひのおもひ
不尽のねにあらぬ我が身の燃ゆるをばよひよひとこそいふべかりけれ
こぬ人をまたましよりも侘しきは物思ふころのよいゐなりけり
「よひ」という時間帯は「夕暮」のあと、まだ夜半には至らぬ頃である。しょうど恋人が人目を避けて来る頃でもある。待つ人は閨(ねや)にも入らず焦れて待つ頃だ。
和泉式部はそうした時のわが身を「不尽のね」にたとえ、「わが身の燃ゆる」ことを訴えている。下句は「宵々に燃ゆる」ことを、火山の「夜火(よひ)」と掛けて洒落ているが、次の歌は「来ぬ人を待つ」夕べの物思いよりも、来るはずのない人を思いつつ起きている「宵居(よいゐ)」の物思いの方がどれだけつらいかわからないとうたう。
夜なかのねざめ
物をのみ思ひねざめの床の上にわが手枕ぞありてかひなき
(物思いばかりをして寝た夜半の寝覚めに、気がつくと私は自分の手枕をして寝ていたのであった。あの方の手枕の中に眠ることもなく、何という情ないわが手枕の寝覚めであろう)
よろこびにつけ、かなしみにつけ、共寝の夜の「手枕」の袖があることは、心強い同伴者の支えがあった日のことだったのだ。これらの歌はほぼ男に忘れられた女の悲しみに近いうたい方がされている。
あかつきの恋
住吉のありあけの月をながむれば遠ざかりにし人ぞこひしき
夢にだにみであかしつる暁の恋こそ恋のかぎりなりけれ
わが恋ふる人はきたりといかがせむおぼつかなしや明けぐれの恋
「あかつきの恋」は、「きぬぎぬ」の場を意識している。何で「住吉」の月なのかは簡明、歌枕の名歌であるとともに「住みよし」という名詞自体が理想的でめでたい。月が「澄みよし」もかけられている。まるで思いが叶っているような「住吉」の暁、「ありあけの月」は「きぬぎぬ」の男姿の背景として眺められるべき月である。
しかし和泉式部の現実にその人(敦道親王)はなく、それをここでは、死者としてではなく「遠ざかりにし人」とうたっている。自分を置いて遠く去っていった恋人という詠み方である。
和泉式部は次に「暁の恋」を「恋のかぎり」(極値)だとうたった。恋の暁は一般的には「きぬぎぬ」の別れの思いだが、すでに対象(敦道親王)を失っている和泉式部にとって、それは理想的に回想されてゆく恋なのだ。
しかしこの歌は思う人が夢にさえ現れてくれなかった暁の目覚めである。瞬時ののちにはその空しさを押しのけてあふれてくるリアルな、亡き人への悲しさがある。それはもう全く手の届かぬものゆえに、破格な激情となって涙に溺れるほかないものかもしれない。まさに究極の恋であり、完璧な恋とよべるものだといえる。
こうした完結しきった理想的な恋の後に、「もし」ともう一度自問する。そして、第三首では、「わが恋ふる人」が暁に幻のように来たとしたら、自分はその幻とどう向き合えるだろうかと考えてみる。
現実の肉体をともなわない幻のような「恋ふる人」との出会いに、和泉式部は自信がない。「わが恋ふる人はきたりといかがせむ」この上句は三句にいたって急に弱々と言葉がくずれている。そして四句は「おぼつかなしや」と詠嘆し、結句は、現と夢とのけじめがはかりがたいような「明けぐれの空」の混濁の中に自らの意識もすべり込ませてしまっている。「暁の恋」は、宮(敦道親王)との恋を反芻すると同時に、深い喪失感を目覚めさせるものにほかならなかったのだ。
参考 馬場あき子氏著作
「日本の恋の歌 ~恋する黒髪~」