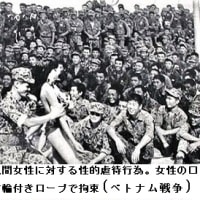解説-17.「紫式部日記」出仕
山本淳子氏著作「紫式部日記」から抜粋再編集
**********
出仕
家にいて書き始めた初期の「源氏物語」が、短期間で人気を博したのだろう。紫式部は寛弘二(1005)年か三年の年末には、彰子の女房として出仕することになった。ここには、道長か、あるいは紫式部にとってまたいとこである彰子の母源倫子の要請があったと考えられる。
前述のように、道長は知的女房によって彰子後宮を彩り、いまだに懐妊を見ない彰子と天皇の仲を促したいと考えていた。道長は最高権力者で、紫式部の父為時の越前の守補任の際の恩人でもある。女房勤めの資質も意欲もない紫式部だったが、拒むことはできなかったはずだ。
だが紫式部の内心は、居所が後宮に変わろうとも、常に「身の憂さ」に囚われていた。いっぽうで、紫式部を迎える彰子付き女房たちは、身も知らぬ才女を警戒していた。自分の殻に閉じこもる紫式部と、偏見によって彼女を毛嫌いする女房たちとはそりがあうはずもなく、紫式部はすぐに家に帰って、そのまま蟄居することになった。
不出仕は五カ月以上に及んだ。復職はそれからなので、初出仕が寛弘二年末であったとしても、「紫式部日記」記事の寛弘五年秋までに、紫式部には実質二年余の経験しかないことになる。
女房の世界は、主家に住み込み、主人への客に応対し、様々な儀式での役をこなす、「里の女」とは全く異質のものである。特に紫式部が激しい拒否感を抱いたのは、不特定多数の人に姿を晒すことや、男性関係が華やかになりがちなことだった。
だが、「紫式部日記」によれば、寛弘五年の紫式部には大納言の君や小少将の君という職場仲間がいた。
この年五月の土御門邸法華講で彼女たちと交わした和歌が、「紫式部集」古本系付載の「日記歌」なる後人作資料に載せられている。
それによれば紫式部は華やかな法事を目の当たりにしつつ「思ふこと少なくは、をかしうもありぬべき折かな」と我が物思いの丈に涙ぐみ、大納言の君は「かがり火にまばゆきまでも憂き我が身かな」と詠み返し、翌朝には小少将の君も「なべて世の憂きに泣かるるあやめ草」と詠んでいる。
出自や身分は違え、誰しもがそれぞれに苦を抱えて生きているということに、紫式部は思いをいたしただろう。
つづく