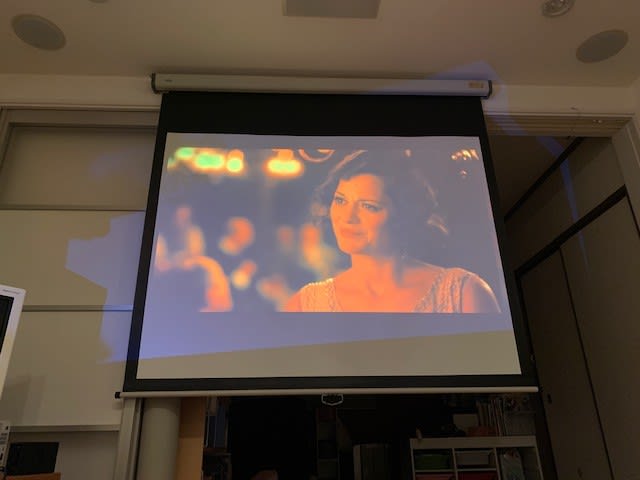今のところなんとか順調にアップすることができております。
ひで氏です。
Jukebox、3回目の今回はドノヴァン・フランケンレイターの「Call Me Papa」。
はじめてドノヴァン・フランケンレイター(Donovan Frankenreiter)を聞いたのは車の中だった。確かハワイかアメリカ本土のどちらかで運転しながら聴いていたラジオでかかったのをきっかけに気になって調べたはずだ。辿り着いたのは彼のセルフタイトルのファーストアルバムだ。リリースは2004年で、外国で聞いたことを考えて逆算すると計算が合わないので、知ったのはその数年後ではないかと思う。
ひで氏です。
当時はJack Johnsonがサーフミュージックの第一人者としてすでに台頭していた。この二人はよく比較もされるが、私ひで氏の中では全く異質な二人だ。
なんと言ってもドノヴァンの魅力は浮遊感、その一言に尽きる。
このふわふわした感じ。カリフォルニア出身のフリーサーファーであり、優しい父。
今回紹介する曲「Call Me Papa」はそんな彼の持つ空気感が全て現れている名曲だと思う。幼い我が子に対して彼はこう歌う。
You can call me papa
I call you baby
But don’t forget your mama’s my baby, too.
ぼくをパパと呼んでいいよ
ぼくも君をベイビーと呼ぶよ
でも忘れないで 君のママもぼくのベイビーなんだ
…優しい。詞の中に射している日差しがあたたかい。
そして曲を聴いてもらえればわかるが浮遊感が半端ない。
私ひで氏は彼のライブを一度京都に観に行ったことがある。
京都メトロという小箱で、非常にアットホームなライブだった。オープニングアクトを務めていたバンドも中の良い友達という感じだった。
覚えているのはライブの最後の曲がちょっとしたコールアンドレスポンス的な曲で、会場が盛り上がってきたときに彼が「誰かステージで一緒に歌ってくれ!」と客席に向かって言った。
こういうとき日本は本当に奥ゆかしい。特に前のほうの人たちは完全に遠慮して誰も手を上げないのだ。
私ひで氏はこの曲を完璧に歌う自信があった。
自分がいたのは最後列に近いところだ。もう必死の形相でアピールする。

しかしドノヴァンの目には入らなかったようだ。
ヤバいやつがいる、と敬遠されたのかもしれない。
結局は前のほうの人が無理やりステージに上げられてしまい、恥ずかしがって何も歌わないという状況になってしまったのだが、
彼は決して「なんやそれ」みたいな感じにせず、OK OKと笑ったり…その辺の対処も愛があふれていてよかった。
そしてなんといっても驚いたのはドノヴァン自身がライブ後、物販に立ってCDを販売していた。思わずそこに行き少し言葉を交わしたが、本当に気さくな人で、一緒に写真まで撮ってくれた。
彼の歌声や歌い方にも様々な人を惹きつける要素があると思うが、その辺はぜひ動画をご覧あれ。
あと彼の名前についての秘話(?)も収録しております。
Jukebox、Cは Donavon FrankenreiterのCall Me Papa!
そしてぜひ本家もご覧ください。
ひで氏です。
Jukebox、3回目の今回はドノヴァン・フランケンレイターの「Call Me Papa」。
はじめてドノヴァン・フランケンレイター(Donovan Frankenreiter)を聞いたのは車の中だった。確かハワイかアメリカ本土のどちらかで運転しながら聴いていたラジオでかかったのをきっかけに気になって調べたはずだ。辿り着いたのは彼のセルフタイトルのファーストアルバムだ。リリースは2004年で、外国で聞いたことを考えて逆算すると計算が合わないので、知ったのはその数年後ではないかと思う。
ひで氏です。
当時はJack Johnsonがサーフミュージックの第一人者としてすでに台頭していた。この二人はよく比較もされるが、私ひで氏の中では全く異質な二人だ。
なんと言ってもドノヴァンの魅力は浮遊感、その一言に尽きる。
このふわふわした感じ。カリフォルニア出身のフリーサーファーであり、優しい父。
今回紹介する曲「Call Me Papa」はそんな彼の持つ空気感が全て現れている名曲だと思う。幼い我が子に対して彼はこう歌う。
You can call me papa
I call you baby
But don’t forget your mama’s my baby, too.
ぼくをパパと呼んでいいよ
ぼくも君をベイビーと呼ぶよ
でも忘れないで 君のママもぼくのベイビーなんだ
…優しい。詞の中に射している日差しがあたたかい。
そして曲を聴いてもらえればわかるが浮遊感が半端ない。
私ひで氏は彼のライブを一度京都に観に行ったことがある。
京都メトロという小箱で、非常にアットホームなライブだった。オープニングアクトを務めていたバンドも中の良い友達という感じだった。
覚えているのはライブの最後の曲がちょっとしたコールアンドレスポンス的な曲で、会場が盛り上がってきたときに彼が「誰かステージで一緒に歌ってくれ!」と客席に向かって言った。
こういうとき日本は本当に奥ゆかしい。特に前のほうの人たちは完全に遠慮して誰も手を上げないのだ。
私ひで氏はこの曲を完璧に歌う自信があった。
自分がいたのは最後列に近いところだ。もう必死の形相でアピールする。

しかしドノヴァンの目には入らなかったようだ。
ヤバいやつがいる、と敬遠されたのかもしれない。
結局は前のほうの人が無理やりステージに上げられてしまい、恥ずかしがって何も歌わないという状況になってしまったのだが、
彼は決して「なんやそれ」みたいな感じにせず、OK OKと笑ったり…その辺の対処も愛があふれていてよかった。
そしてなんといっても驚いたのはドノヴァン自身がライブ後、物販に立ってCDを販売していた。思わずそこに行き少し言葉を交わしたが、本当に気さくな人で、一緒に写真まで撮ってくれた。
彼の歌声や歌い方にも様々な人を惹きつける要素があると思うが、その辺はぜひ動画をご覧あれ。
あと彼の名前についての秘話(?)も収録しております。
Jukebox、Cは Donavon FrankenreiterのCall Me Papa!
そしてぜひ本家もご覧ください。