麻雀の醍醐味はなんといっても役満だろ!
ということで、醍醐味を増やすためのオリジナル役満を思いつくままに。ダジャレだろうが気にしないのじゃ。
今回は「芥川 龍之介」
○地獄変












 ツモ
ツモ
ホンイツ、頭は中「4・5・9」「789」のペンチャン7あがり。 ジゴク・ペンチャン
時は平安時代、絵仏師の良秀は大殿から「地獄変」の屏風絵を描くよう命じられる。話を受け入れた良秀だが、「実際に見たものしか描けない」彼は、地獄絵図を描くために弟子を鎖で縛り上げ、梟につつかせるなど、狂人さながらの行動をとる。こうして絵は8割がた出来上がったが、どうしても仕上がらない。燃え上がる牛車の中で焼け死ぬ女房の姿を書き加えたいが、どうしても描けない。
そこで実際に車の中で女が焼け死ぬ光景を見たい、と大殿に訴えた。
そして当日、火をかけられることになったのは我が娘だった。しかし彼は動じるでもなく、見事な地獄変の屏風を描き終える。
数日後、良秀は部屋で自殺する。
○羅生門・藪の中












 ツモ
ツモ
索子ホンイツ、「8・9・中」「789」をカンチャン8あがり。頭は4索。
8ぶの中で「8・中」、8のカンチャン。羅生門で (しょう)
(しょう) 門
門
『藪の中』は『今昔物語集』の「妻を具して丹波国に行く男、大江山において縛らるること」の説話を題材としたもの。
藪の中で、ひとりの男の刺殺体が発見される。その事件を巡って、検非違使が集めた関係者の証言が語られるのだが、捕らえられた多襄丸という盗人、清水寺で懺悔する男の妻、そして巫女の口を借りて語る男の死霊、三者の証言がそれぞれ、「多襄丸による他殺」「妻による心中未遂」「男の自殺」と食い違い、真相は明らかにされない。
黒澤映画の「羅生門」は「藪の中」を題にしているが、芥川の短編「羅生門」からもモチーフが取り入れられている
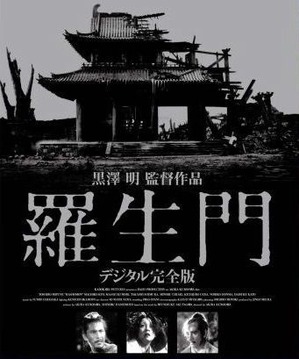
ということで、醍醐味を増やすためのオリジナル役満を思いつくままに。ダジャレだろうが気にしないのじゃ。
今回は「芥川 龍之介」
○地獄変
ホンイツ、頭は中「4・5・9」「789」のペンチャン7あがり。 ジゴク・ペンチャン
時は平安時代、絵仏師の良秀は大殿から「地獄変」の屏風絵を描くよう命じられる。話を受け入れた良秀だが、「実際に見たものしか描けない」彼は、地獄絵図を描くために弟子を鎖で縛り上げ、梟につつかせるなど、狂人さながらの行動をとる。こうして絵は8割がた出来上がったが、どうしても仕上がらない。燃え上がる牛車の中で焼け死ぬ女房の姿を書き加えたいが、どうしても描けない。
そこで実際に車の中で女が焼け死ぬ光景を見たい、と大殿に訴えた。
そして当日、火をかけられることになったのは我が娘だった。しかし彼は動じるでもなく、見事な地獄変の屏風を描き終える。
数日後、良秀は部屋で自殺する。
○羅生門・藪の中
索子ホンイツ、「8・9・中」「789」をカンチャン8あがり。頭は4索。
8ぶの中で「8・中」、8のカンチャン。羅生門で
『藪の中』は『今昔物語集』の「妻を具して丹波国に行く男、大江山において縛らるること」の説話を題材としたもの。
藪の中で、ひとりの男の刺殺体が発見される。その事件を巡って、検非違使が集めた関係者の証言が語られるのだが、捕らえられた多襄丸という盗人、清水寺で懺悔する男の妻、そして巫女の口を借りて語る男の死霊、三者の証言がそれぞれ、「多襄丸による他殺」「妻による心中未遂」「男の自殺」と食い違い、真相は明らかにされない。
黒澤映画の「羅生門」は「藪の中」を題にしているが、芥川の短編「羅生門」からもモチーフが取り入れられている
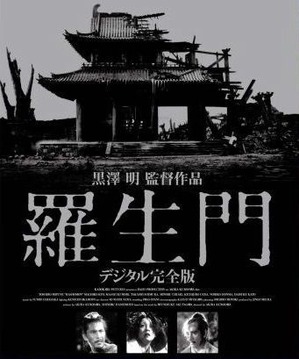













 リンク;
リンク;