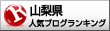今回のものは「ワイン会」と「セミナー」のとうど中間くらいのイメージ。
月に1回つづ、これから半年続きます。
基礎編、ということでしたので、いろいろ質問しちゃいまいたー♪
自己紹介をしたらお酒関係者が多かったんですが、そんなのお構いなしです。
「色を見るってどういう風に見るのですか?」
「味を確かめるって舌のどこで感じるのですか?」
「テイスティングってどうやるの?」
「空気を入れて、口の中でじゅるじゅるってやるのはどうやってやるの?」
「ワインをぺっって吐き出すのは何ていう名前なの?」
「ワインは何年も保存してもいいの?賞味期限はないの?」
無知な私は率先してソムリエのKさんに質問攻め。
Kさんはとてもいい方でねー、ダーもよくお世話になっている方だそうです。
帝国ホテルでずっとソムリエを務めていたそうで、何でも答えてくださいました。ダンディな素敵な方です。
今回のセミナーでは「ビオワイン」というものを中心に教えていただきました。
「ビオワイン」とは無添加ワインのこと。
ワイン業界でもオーガニックがだんだんと需要が増えてきているそうです。ワインには大抵、酸化防止剤(二酸化硫黄)が含まれています。この防止剤が入っていないものが「ビオワイン」
Senza SO2 Aggiunta(センツァ・ソルフォローザ・アジュンタ)・・・(二酸化硫黄添加なし)と裏面のラベルに書いてあれば、無添加のものです。
この無添加のもの、時間が経つごとに味が変化してくのです!面白かったー。
イタリアの白ワイン2004年の添加物入りと無添加のものの味比べをしました。入れた直後からも味が違うのですが、1時間経ってからテイスティングしたもの、2時間経ってからテイスティングしたもので味がまったく違うのです。無添加ものはだんだんとまろやかになっていくの。
驚いた。
他にもいっぱい面白いお話を聞いたんだけれど、おいおい書いていきます。
こんな話を帰ってきてからしていたら、イギリス人のEちゃんとアメリカ人のMちゃんが「私も行きたい」と言うので今度一緒に行きたいと思います。
それから、ずっと会いたいと思っていたKさんという酒屋さんと出会えたのも嬉しかったです。私はずっと前から彼のブログの愛読者だったのです。八ヶ岳のお店紹介などをブログに載せていらっしゃるのです。掲載してもいいかどうか、連絡してからブログのアドレスをアップしますね。
今回のワインセミナーでの印象に残った一言。(他にもいっぱいあるんだけれど)
「ワインを開けるとき、一番皆で楽しんでもらいたいのが、コルクをあける瞬間の音。眠っていたワインが「ぽっ」っと目覚める瞬間の音なのです。もし、あなたがワインをサービスする側の人間だったら、この「ぽっ」っというなんともいい音をお客様と一緒に共有をしてください。」(Kさん談)
かわいいんだ、この「ぽっ」って言う音が・・・!
「起きた」っていうか「こんにちは」っていうか「恥ずかしいな、出てきたよ、はじめまして」っていうか、そんな音に私は聞こえます。
愛美
コメント一覧

愛美

開業室長

ikeda
最新の画像もっと見る
最近の「★ 暮らし・食べること」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事