
【連載】藤原雄介のちょっと寄り道(98)
異国初体験はシベリア鉄道で始まった
シベリア鉄道は世界最長で全長約9297㎞、首都モスクワと極東のウラジオストクを結んでいる。1973年当時、ソビエト連邦では、外国人は自由に旅行することができず、「インツーリスト」という国営旅行会社が設定するお仕着せの旅程に従う他なかった。
金はなかったが、時間だけはたっぷりあった私である。当初、全行程をシベリア鉄道で走破し、モスクワまで行く予定だった。ところが、インツーリストから提示されたプランは、ウラジオストクからシベリアの中心都市ノヴォシビルスクまで鉄道で移動し、そこからモスクワまでは飛行機で。その後、モスクワから最終目的地のヘルシンキまでは再度鉄道でというものだった。

▲シベリア鉄道の出発点となったウラジオストク駅
あまり記憶が定かでないが、ヘルシンキまでの旅程は、7泊8日か8泊9日だったろうか。シベリア鉄道の乗客は、私と同じような貧乏旅行のヨーロッパの若者が多く、すぐに打ち解けてワイワイと騒ぎ、楽しい旅だった。

▲車窓からシベリアの雪景色が広がる
窓外には、回り灯籠を見ているように、ずっと同じ景色が広がる。見渡す限りの雪原、時々白樺の林、煙突から煙を吐き出している粗末な小屋が並ぶ集落。列車は何の説明もないまま、小さな駅に時々停車する。多分、水や暖房用の石炭を補充するためだろう。私たちは、列車が停車する度に暖房の効き過ぎた車内から半袖のまま外に飛び出て、体操をしたり、雪合戦をしたりして遊んだ。
すると、機関銃を構えた若い兵士たちが、どこからともなく現れて、銃身を左右に振って何か叫ぶ。多分「列車に戻れ!」とでも言っているのだろう。その様子をこぞって着膨れた近辺の住人たちが遠巻きにして物珍しそうに見物している。
私は、日露会話ブックで覚えたロシア語で愛想よく兵士たちに話しかけた。
「ハローシャ・パゴーダ!(良い天気ですね!」
彼らはニコリともせず、ハエを追っ払うように私たちを列車に追いやった。列車に乗り込んできた彼らは、かなり執拗に乗客たちの荷物を検査した。
兵士の一人が、私のバックパックから第二次大戦時に父が携行していた革製のお守り袋を取り出し、何か質問する。何を言っているのか理解できないが、多分「この革袋はいったい何だ? 開けろ!」とでも言っているのだろう。
私は、英語で説明しようとしたが、直ぐに無駄なことだと悟り、従順に革紐で厳重に閉じられた袋を開けた。それまでそのお守り袋を開けたことのない私が目にしたのは、何枚かのお札や小さく折りたたんだ手紙だった。
一人の兵士が怪訝な表情でお守りの中身を検め、もう一人は無表情のまま機関銃の銃口を私に向けて立っている。何もやましいことはないので恐れることはないはずだが、改めて目の前の銃口を見つめると恐怖とは少し違う、妙な緊張を覚えた。
列車の各車両後部には、石炭ストーブが備え付けられており、太ったおばさんが時々居眠りしながら終日石炭をくべていた。
ロシアのおばさんは、ほぼ例外なく太っているので、「太った」という形容詞は不要かも知れない。しかし、まるで「太ったおばさん」というのが複合名詞であるかのように思わず口をついて出てしまう。
食事は、毎回食堂車で提供された。結構ごちそうだったような気がする。カウンターに備え付けられた大きなサモワール(ロシアの伝統的な湯沸かし器)から熱湯を注いで淹れてくれる紅茶が楽しみだった。

▲列車に備え付けのサモワール
ノヴォシビルスクからモスクワへは最新型ジェット旅客機の「イリューシン」で飛ぶはずだったのだが、あろうことかエンジントラブルのため、急遽用意された代替機に乗り換えさせられる羽目になった。かなりくたびれた双発のプロペラ機で、生まれて初めて飛行機に乗る高揚感はあっけなくしぼんでしまったのである。
染みだらけで、食べカスが散らばった座席に腰を下ろし、ヨレヨレのシートベルトを装着すると、太った中年女性のスチュワーデス(当時はCAではなく、そう呼んでいた)が紙に包まれたアメ玉を乗客に配り始めた。
飛行機が離陸し始めると、何故アメ玉が配られたのか、その理由が分かった。機体の気密性能が悪いのだろう、潜水したときのように鼓膜が強く圧迫されて痛いのだ。無意識に何度も唾を飲み込んで所謂耳抜きをした。あまりに激しい気圧変化に、ドアの隙間から外気がヒューヒューと吹き込んでいるような気がした。モスクワに向かう飛行機はずっと夕陽を追いかけて飛んだ。初めて大気の薄い上空で目にする美しく茜色に染まる空。なんて美しいのか。私はずっと窓ガラスにへばりついていた。
そういえば、生まれて初めて炭酸水(ソーダ)を飲んだのもこのフライトであった。今でこそソーダは人気の飲み物である。しかし、当時の日本では、味があるような、ないような、酸っぱいような、苦いような、不思議な感触の炭酸水を飲む習慣は全くなかったように思う。大袈裟ではなく、この一杯の炭酸水に因って自分が未知の異文化世界に足を踏み入れたことを自覚させられた。
モスクワには、それまでに訪れた地方都市とは明らかに異なる空気が漂っていた。赤の広場、聖ワシリイ大聖堂、クレムリンなど壮麗な建物に目を奪われ、ソ連共産党の権力を具現化したようなスターリン様式の威圧的な建物群には畏怖に似た感情と共に反感が湧いて来た。

▲おとぎの国の建物のような聖ワシリイ大聖堂(モスクワ)
立派な建築物とは裏腹に街を行く人々の顔には活気がなく、うらぶれた印象が強かった。赤の広場にある有名なグム百貨店では、ほとんど空っぽのショーケースを前に何人もの店員が所在なげにおしゃべりに興じていた。
市場に行っても、物資が不足しているのは明らかで、特に生鮮食料品はほとんどなく、わずかに並べられている野菜や果物は押し並べてしなびていた。人々、特に若者の西側世界への憧憬は驚くほど強く、長髪にジーンズ姿で街を行く私に多くの若者が声をかけてきた。皆、同じ言葉を口にする。ジーンズ、セイコー、チューインガムだ。「ジーンズと時計を売ってくれ!」「レーニンのバッジとチューインガムを交換してくれ!」としつこくつきまとわれた。

▲レーニンのバッチ
ある日の午後、散歩の途中、どこかの噴水の前でぼんやりしていると、一応きちんとした身なりの中年の男に声をかけられた。片言の英語で。
「日本人ですか。私はニホンが大好きだ。日本の技術は素晴らしい。セイコー、ホンダ、ソニーはサイコー」
そんな歯の浮くようなお世辞を並べる。後にヨーロッパを放浪していて、この手の輩にはイヤと言うほど遭遇した。ほぼ間違いなく、詐欺師だった。しかし、若くて、世間知らずの私は、相手が悪人あるいは詐欺師であると直観的に思っても、ひょっとしたらいい人かも知れないのに、邪険にしては失礼じゃないかと、丁寧に応対していた。
この時はまだ人を疑うことを知らず、ビールを奢る、という男についてノコノコと近場のバーに入った。何杯かのビールを飲み干すと男は馴れ馴れしくなってきて、私の肩や腰に手を回す。そして耳元で
「外に出ようか?」
と囁いてきた。
し、しまった! コイツ、ホモだったのか! 当時、「ゲイ」という言葉はまだ使われていなくて、男の同性愛者は「ホモ」と呼ばれていたのである。
急に酔いが醒めた私は、男の手を払いのけて言った。
「オレはそういう趣味はないんだ!」
すると男は、顔色を変えて早口でまくし立てた。
もともと英語が下手くそなのに加え、興奮しているので、支離滅裂である。憤慨する男の言葉を意訳すると、こんな感じだ。
「その気があるから、付いてきたんじゃないのか。それを今更、なんだよ、酷いじゃないか! ビール代返せ!」
男は、私に暴力を振るうつもりはなさそうだった。コイツは、ホモだが、悪い奴ではないらしい。そう思った私は、男に言った。
「アンタがそういう趣味の人だとは気付かなかった。ウソじゃない。悪かったよ、ホントに。オレは、アンタのことを親切なロシア人だと思い、楽しく話をした。それだけのことだ。オレは貧乏旅行者だから、悪いけどビール代なんて払えない」
しばらくの押し問答の果て、男は冷静さを取り戻して私に説教した。
「分かった。残念だが、諦めるよ。お互いに誤解があったようだ。これからは、ヘンな奴について行くんじゃないぞ」
「ヘンなヤツってアンタみたいな?」そう言いかけて、私は口をつぐみ、男と別れた。
五木寛之が書いた『青年は荒野をめざす』の主人公、ジュンは、旅客機の中でリューバという美人のスチュワーデスと知り合い、彼女とプーシキン広場で初体験に至るのだが、現実はそう甘くなかった。
私は、美人スチュワーデスに会うことはなかったし、ロマンチックとは正反対のきわどい体験をしたのだった。
ロンドン駐在時代に知り合った日本人の中には、若い頃にシベリア鉄道でヨーロッパに渡ったという人が思いの他沢山いた。その多くは、私と同年代か、少し年上の「団塊の世代」だった。
シベリア鉄道組に共通するのは、「旺盛な好奇心と世界を見てみたい」とう強烈な思いだ。面白いことに、企業の駐在員や官僚には「鉄道組」はほとんどいない。私なんか例外に属すると言ってよいだろう。
鉄道組の何人かは、渡欧後そのまま現地に根付いて、起業したり、商売したりしている。彼らと話すと、組織に頼って生きていないので、自立心と人間としての芯の強さが際立っているように思えた。そんな人たちと酔っ払った時に、「ロンドン・シベリア鉄道友の会」を作ろうと盛り上がったのだが、結局のところ、実現はしなかった。

▲「赤の広場」に立つロシア出張中の筆者(2006年)
サラリーマンになってから、仕事でロシアには10回ほど出張しただろうか。行く度にロシアが豊かになって行くのを実感したものである。ある駐在員からこんな話を聞いた。
誕生日会などで子供たちを家に招待すると、今ではお菓子を食べる子が多いが、昔は彼らはお菓子やケーキなどには目をくれず、キュウリやトマトなどの野菜に手を伸ばしていたという。野菜不足、ビタミン不足を無意識に身体が訴えていたのである。
また、出張先のホテルで、朝、出がけに1週間分の洗濯物をベッドの上に山積みして、その上にパンティストッキングをいくつか置いておくと、夕方には、きれいに洗濯されて返ってくる、と言う話も聞いた。実際に試したら、その通りだった。タクシーの運転手にマルボロ(煙草)1箱を渡すと、モスクワの端から端まで運んでくれる、という話も本当だった。
現在のロシアについて語るのはやめておこう。政治的、歴史的に複雑な問題が多すぎて、深みに嵌まれば収拾がつかなくなってしまうだろうから。一方、私には何人かの素晴らしいロシア人の友人がいるし、ロシアの音楽、文学、舞踊も大好きだ。国家間の問題と個人的感情の間の軋轢が大きすぎて本当に悩ましい。
ところで、シンガポール人は自らを「バナナ」と呼ぶ。外(皮膚)は黄色いが、中身(考え方)は白い(白人=西洋人のようにドライ)と。何人かの私のロシアの友人たちは、シンガポール人の反対である。外(皮膚)は白いが、中身は黄色い(ウエットで情緒的)というわけだ。(つづく)
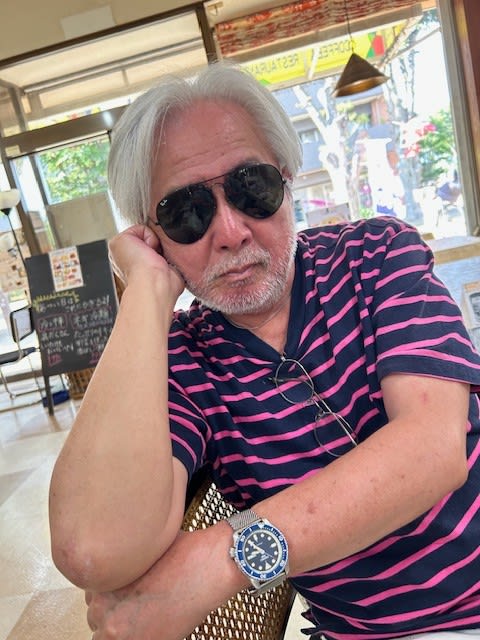
【藤原雄介(ふじわら ゆうすけ)さんのプロフィール】
昭和27(1952)年、大阪生まれ。大阪府立春日丘高校から京都外国語大学外国語学部イスパニア語学科に入学する。大学時代は探検部に所属するが、1年間休学してシベリア鉄道で渡欧。スペインのマドリード・コンプルテンセ大学で学びながら、休み中にバックパッカーとして欧州各国やモロッコ等をヒッチハイクする。大学卒業後の昭和51(1976)年、石川島播磨重工業株式会社(現IHI)に入社、一貫して海外営業・戦略畑を歩む。入社3年目に日墨政府交換留学制度でメキシコのプエブラ州立大学に1年間留学。その後、オランダ・アムステルダム、台北に駐在し、中国室長、IHI (HK) LTD.社長、海外営業戦略部長などを経て、IHIヨーロッパ(IHI Europe Ltd.) 社長としてロンドンに4年間駐在した。定年退職後、IHI環境エンジニアリング株式会社社長補佐としてバイオリアクターなどの東南アジア事業展開に従事。その後、新潟トランシス株式会社で香港国際空港の無人旅客搬送システム拡張工事のプロジェクトコーディネーターを務め、令和元(2019)年9月に同社を退職した。その間、公私合わせて58カ国を訪問。現在、白井市南山に在住し、環境保全団体グリーンレンジャー会長として活動する傍ら英語翻訳業を営む。























