
【連載】藤原雄介のちょっと寄り道㊵
誰も理解できないカタカナ語
日本

▲外来語 全部分かりますか?
このブログ記事「#37日本のテレビよ、さようなら②」で、「それ、日本語で良くない?」とカタカナ語の氾濫を憂える駄文をしたためた。
先日NHKのニュース番組で「インクルシーブ防災」という言葉を耳にした。「総てを含んだ包括的な防災???」である。えっ、一体何のこと? そう訝っていたら、「障害がある人もない人も、高齢者も、幼い子どもも、誰ひとり取り残さないことを目指した防災の理念」だと簡単な説明があった。
なるほど、素晴らしい理念である。しかし、「インクルシーブ防災」と聞いてその意味を瞬時に理解できる人が一体どれほどいるだろうか。
日本人が一番理解しやすいのは、大和言葉で、次は漢語熟語だろう。ならば「誰も取り残さない防災」「みんなが助かるための防災」「みんなの防災」など、いくらでも言い様はある筈だ。
英語の原文を調べてみると、’Disability Inclusive Disaster Risk Reduction (DIDRR) ‘ だった。「障害者を包括した防災」という意味である。Disability(障害)を省いてInclusive Disaster Risk Reduction (IDRR)ともいう。

▲障害者も見捨てないインクルーシブ

▲誰も置き去りにしないインクルーシブ

▲災害多発のバングラディシュには障害者が少なくない
東日本大震災では、身体的障害を持つ人の罹災率は健常者の2倍に達したらしい。身体障害者の罹災率は、発展途上国において更に高いことから、DIDDRに関する情報は、インドやパキスタンなどの南アジア、アフリカ、南太平洋などの地域に集中している。
次に、日本語の「インクルシーブ防災」を調べてみた。最初に目に入ったのは、「公益財団法人日本ケアフィット共育機構(そっと、さっと、あんしんを。)」という組織のホームページ(HP)である。誰もが暮らしやすい共生社会をめざして サービス介助士、防災介助士、認知症介助士の普及に取り組む組織らしい。ー悲しいかな、今度は「ケアフィット」の意味が分からない。
で、「ケアフィット(care fit)」で調べてみると、ケアフィットという単語そのものの定義は見当たらない。次に「一般社団法人ケアフィット推進機構」のHPに誘導された。曰く、「あらゆる場面で『ケア』を『フィット』する『人』『モノ』『コト』を社会に溢れる取り組みとその学びや気付きの機会を創出していきます」
ふーん。「ケアをフィットする? ナンジャそれゃ?」と目が点になってしまった。一体何を伝えたいのか。これでは、英語にも日本語にもなっていないではないか。まるでルー・大柴(コメディアン)のルー(英語)だ。
「インクルーシブ防災」について長々と書いているが、論点は、そこではない。安易なカタカナ語の使用は、日本人をバカにするという話だ。
外国とのビジネスでは、言葉の定義を明確にすることがとても重要だが、最近の日本では、氾濫するカタカナ語を皆がなんとなく分かったつもりで、日常生活が流れてゆく。だから、深い議論になると、曖昧な部分が露呈してしまうのだ。
毎週火曜日の夕方、近所の友人たち8人ほどが集まって、ダーツを口実にした飲み会を楽しんでいる。自衛隊、住宅公団、サラリーマン、フリーのジャーナリスト、水産業、自営業…と経歴は様々で、年齢は71歳から83歳と高め。共通しているのは、皆元気で、知的好奇心と(私はさておき)高い教養(?)を併せ持っていることだ。
毎回、酔いが進むに連れ、談論風発、硬軟取り混ぜた様々な話題で盛り上がり、時には机を叩いて激論になることも珍しくない。先日の出席者は7人だった。
そのメンバーに「インクルーシブ防災」という単語の意味を知っているかどうか問いかけてみた。「知っている。気になっていた」というのが一人。残りの6人は「知らない」。
「では、『インクルーシブ』と言う英単語の意味は分かりますか?」との問いには、全員「分からない」という答え。読者諸兄姉は如何だろうか。
文化庁が、120の「カタカナ語の認知率・理解率・使用率」について調査している。総ての項目で1位だったのは、「ストレス」で、「コンソーシアム」が120位だった。
因みに、理解率が50%以下だったのは、120のうち43も。興味のある方は、文化庁のURLで調べてもらいたい。
カタカナ語が増え続ける最大の理由は、正確な日本語訳がない、ということだろう。文化庁が調査したカタカナ語のほぼ総てが名詞であり、既に日本語の一部と化しているモノが大半だ。
これらに目くじらを立てるつもりはないし、外来語が増え続けることも避けられないとは思う。
しかし、「インクルーシブ防災」に話しを戻すと、「障害がある人も高齢者も取りこぼさないため」といいながら、何故この言葉の対象となる人々がすんなり理解できる、こなれた日本語を使わないのだろうか。不思議でならない。
日本語の揺れに関する研究では、外来語の増加に賛成する人の割合は全年代平均で6割を超えている。20代では85%に達し、年代が上がるにつれて減少する。70代では49%だ。
また、3割近い人は、和製英語を気にする必要は全くないと考えている。カタカナ語の増殖を憂い、和製英語を嫌悪する私は少数派に属するらしい。
カタカナ語のことを書いていたら、最近、気になる日本語の表記と使い方についてもひと言言いたくなった。私は、ずっと外国語を使う仕事に従事してきた。
であるが故に、日本語を大切にしたいと思っている。しかし、言葉というものは、揺れながら変わっていくものかもしれない。だから、あまり頑なになることもないだろうとは思う。だがしかし、イラッとすることも少なくない。
カタカナ語は年々増えてきているのに、漢字表記は減りつつある。例えば、能登大地震関連のニュースでは、「罹災証明書」ではなく「り災証明書」と表される。
「研鑽を積む」は「研さんを積む」である。ひらがなでは、本来の意味が伝わらないないばかりでなく、字面が美しくない。官僚答弁の「…ございます」の多用も気になって仕方がない。
「…と考えてございます」は、「考えています(おります)」だろう。「差し控えさせていただいてございます」。ウーッ、気持ち悪いが、「差し控えます」で良いのでは。
まだある。「そのとおり(ですね)」「仰るとおりですね」は、現在、若い人を中心に「確かに」と言う言葉に取って代わられていた。英語でよく使う相づち(‘certainly’‘surely’ )の直訳だろうが、耳障りである。
また、「半端じゃない」という言葉は、現在「半端ない」という人の方が多い。昔は、「半端ない」と聞くと、悍ましかったものだ。なのに最近では、あまり気にならなくなった。うー、慣れとは恐ろしい。
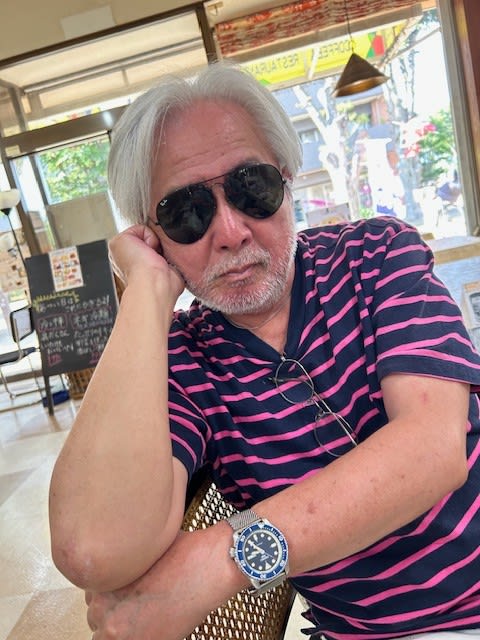
【藤原雄介(ふじわら ゆうすけ)さんのプロフィール】
昭和27(1952)年、大阪生まれ。大阪府立春日丘高校から京都外国語大学外国語学部イスパニア語学科に入学する。大学時代は探検部に所属するが、1年間休学してシベリア鉄道で渡欧。スペインのマドリード・コンプルテンセ大学で学びながら、休み中にバックパッカーとして欧州各国やモロッコ等をヒッチハイクする。大学卒業後の昭和51(1976)年、石川島播磨重工業株式会社(現IHI)に入社、一貫して海外営業・戦略畑を歩む。入社3年目に日墨政府交換留学制度でメキシコのプエブラ州立大学に1年間留学。その後、オランダ・アムステルダム、台北に駐在し、中国室長、IHI (HK) LTD.社長、海外営業戦略部長などを経て、IHIヨーロッパ(IHI Europe Ltd.) 社長としてロンドンに4年間駐在した。定年退職後、IHI環境エンジニアリング株式会社社長補佐としてバイオリアクターなどの東南アジア事業展開に従事。その後、新潟トランシス株式会社で香港国際空港の無人旅客搬送システム拡張工事のプロジェクトコーディネーターを務め、令和元(2019)年9月に同社を退職した。その間、公私合わせて58カ国を訪問。現在、白井市南山に在住し、環境保全団体グリーンレンジャー会長として活動する傍ら英語翻訳業を営む。

























