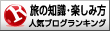池にたたずむ水鳥がとても高貴に見える
仙洞(せんとう)御所は京都御所のすぐそばにあり、天皇を退位した上皇の御所という意味が本来で、固有名詞ではない。かつて豊臣秀吉の正室・北政所が秀吉没後に居住していた屋敷の跡地に、1627(寛永4)年に譲位の意向を示した後水尾天皇の譲位後の御所として幕府が造営したものだ。後水尾天皇(上皇)は時の幕府から巨額の資金を引き出し、仙洞御所や修学院離宮など数々の美の殿堂を作り出した。現在京都に残る王朝文化はほぼ、江戸時代前期・寛永時代のものであり、その中心人物が後水尾上皇だ。
現在の庭園は後水尾上皇の時代からはかなり改変されており、幕末の1854(嘉永7)年には火災で建物を失っている。とはいえ江戸前期の寛永の王朝文化の名残を伝えるかけがえのない庭園であることは言うまでもない
仙洞御所は明治以降、隣接する大宮御所(皇太后の御所)と組み合わされ、天皇や皇族の京都滞在時の宿舎として利用されてきた。そのため人間社会とは長らく隔絶された自然が残されており、王朝文化の名残と相まって、同じ江戸時代でも大名庭園とは全く趣の異なる空間を醸し出している。
見学(参観)は、添乗員によるツアー(無料)に参加すれば可能だ。2016年7月までは、宮内庁に事前参観申し込みの上で抽選だったが、2016年7月から当日参観受付枠(先着順)が新たに設けられたことで、見学しやすくなった。英語・中国語・フランス語・韓国語・スペイン語による音声ガイドの無料貸出もあり、外国人の方も楽しみやすくなっている。とはいえ最も美しい桜や紅葉時期の休日は、申し込み抽選が宝くじ並みの倍率になることに変わりはないので、日程調整には注意されたい。
ツアーは大宮御所の御殿から始まる。現代でも宿泊できるようになっているとのことだが、実際には皇族の宿泊は隣接する京都迎賓館になることが多いとのこと。やはり設備が新しい方が使い勝手が良いのだろう。
最初に2つある大きな池のうち「北池」に案内される。北池は舟遊びできるように作られており比較的大きい。そのため周りを囲む紅葉の彩りは圧巻で、水面低くまで垂れた枝による彩りが美の空間をさらに増殖させる。借景には東山が少しだけ顔をのぞかせるが、江戸時代はもっとはっきり見えた。戦後になって建物が高くなり、それらを隠すために木々の背を高くしたからだ。東山をもっと見たいものだが、タイムマシンが発明されない限り無理である。

水面に映える紅葉が抜群に美しい
北池と南池の間は「紅葉山」と呼ばれる小高い丘になっており、その名の通り紅葉時期は一面が紅葉の絨毯となる。後世に造られた北池と南池をつなぐ掘割にかかる「紅葉橋」のまわりは、紅葉山の深山のうっそうした木々の中にぽっかり現れたオアシスのようだ。水辺を感じると実にすがすがしくなる。

紅葉の絨毯
南池の周辺は州浜が配されており、北池と全く異なり極楽浄土を感じさせる趣だ。州浜を形成するとても美しい丸石は小田原城主からの献上品で、石一個を米一升と交換して集めたという。数は11万1,000個あるそうで、原材料コストはしめて1,110石となる。

紅葉と州浜の「紅白」も見事
御所内には、蘇鉄を植えこんだ一角もある。京都で蘇鉄とは意外だが、二条城など他にも案外よくある。江戸時代初期、上流階級で薩摩にしかない蘇鉄が大ブームになり、島津家からプレゼントしてもらうことがステイタスだった。後水尾上皇もさりげなくトレンドを取り入れたのだろう。
ほかにも藤棚や銀杏の大木など、実に多様な自然美を楽しめる。天皇の住まいだった「京都御所」は、庭園が非常に小さい。仙洞御所はまさに、京都のど真ん中で自然美と王朝文化の両方を味わえる隔絶された空間だ。知名度から桂離宮や修学院離宮ほど混雑していないことも魅力の一つだ。

美しい銀杏の落葉にも出会える
日本にも世界にも、唯一無二の「美」はたくさんある。ぜひ会いに行こう。
今に残る京都の王朝文化のほとんどを伝えた稀有な天皇の生涯を日本文化史の第一人者が描いた名著
仙洞御所(宮内庁)
http://sankan.kunaicho.go.jp/guide/sento.html
原則休館日:月曜日
※見学は添乗員によるツアーに申し込む、自由見学は不可
※2016年7月から事前参観申し込み枠(抽選)に加え、当日参観受付枠(先着順)が設けられました