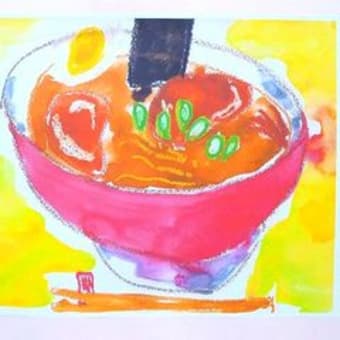「知的障害児者、発達障害児者 個性と可能性を伸ばす!」
造形リトミック教育研究所 玉野摩知佳
*楽しいからのパートナー
*新しく知るからのパートナー
*ちょっと簡単からのパートナー
 おはようございます。造形リトミック教育研究所の玉野 摩知佳です。
おはようございます。造形リトミック教育研究所の玉野 摩知佳です。指導者が一番陥りやすいのは、固定観念や知識偏重の落とし穴です。そこに嵌っていては、ブレイクスルー(壁を突破すること)はできません。
「病気を診て人を見ず」という言葉があります。知識に偏重すると、当たり前のことも見えなくなってきてしまいます。
かねてから療育の世界では、「自閉さん」「ダウンちゃん」という言葉がよく使われてきています。親しみを込めて言われているのかもしれません。しかし私には、とても抵抗があります。
もし自分の子どもだったら当たり前のことですが、「○○ちゃん」と名前で呼んでもらいたいと思います。「自閉症」や「ダウン症」である前に、一人ひとりには、「○○くん」「○○ちゃん」という名前があるのですから。
「自閉症の○○くん」ではなく、「○○くんは、自閉症」つまり「○○くんには、自閉症状がある」という認識の方が
療育における子どもとの関わりとして、本質的であると思います。前者には、子どもを「自閉症」というひと括りで捉えてしまう危険があります。すると、指導書の規則ばかりがひとり歩きしてしまいます。
・自閉症だから、いつも同じ対応をしなくてはいけない(親や指導者が言ったことは、覆してはだめ)。
・自閉症だから、ルールどおりにしなくてはいけない(ルールを変えたら混乱する)。
・自閉症だから、いつも同じ言い方で分りやすく話しかけなくてはいけない。「くつ、は・く!」「手、あ・ら・う!」
こういった指導に拘束されてしまっている状況を時おり目にします。そのたびに、私は思います。
「この子は何を望んでいるのだろう」
「どんなことに興味があるのだろう」
「どんなことにわくわくしたり、気持ちを惹かれるのだろう」
それが一人ひとりの「テーマ」です。「テーマ」は、人に生きる力を与えます。
生徒さんが言葉で伝えてくれなくても、生徒さんの反応や様子を見ていたり、親御さんから日常のようすを伺うことでわかります。一人ひとりが生き生きと生きるための「テーマ」は、生徒さん自身が示しています。
多くの生徒さんは本当に好奇心や学習意欲が旺盛ですから、人対人としてその意欲にしっかりと付き合って行きたい、それが私たちの療育です。こちらも図鑑や専門誌で調べたり、インターネットで最新情報を求めなくては対応しきれないことも多々あります。
「自閉症である」とか「ダウン症である」とかという前に、まずはこのような人として共に生きるものどうしとしての学習を大切にしていきたいと常々考えています。
info@zoukei-rythmique.jp 造形リトミック教育研究所