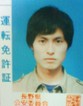12/1(水)、ユナイテッド・シネマ新潟で「ミュジコフィリア」を観てきました。
音楽の才能を持ちながら、若い頃から音楽の英才教育を受けていた兄と比較され、コンプレックスから音楽を諦めていた朔は、ひょんなことから大学の現代音楽研究部に入ってしまう。
そんな中、自由に音楽を表現する凪との出会いが、彼に音楽を好きな気持ちを思い出させ、彼を変えていく。
さらに、朔は大学で、若き天才作曲家として世界的にも注目されていた、兄・大成とも再会するが、彼もまた、才能故に苦悩していた。
しかし、朔と凪との出会いによって、大成さえも大切な気持ちを思い出す。
音楽との出会いが、人と人を出会わせ、窮屈なしがらみから人を解放していく。
音楽の楽しさと可能性を感じる、爽やかな感動に溢れた青春映画でした。
映画の冒頭、ずっとコンプレックスに苦しみ続け、自分を押し殺して周りに流されるように生きていた、朔役の井之脇海さんが、自分を解放して自由に楽しくピアノを弾く場面の開放感からして素晴らしい。
松本穂香さんの演じる好奇心旺盛で行動的な凪も本当に可愛かったし、何より現代音楽研究部の面白い演奏に合わせて自由に歌う場面が、本当に天才歌手なんじゃないかってくらい素晴らしかった。
天才作曲家・大成役の山崎育三郎さんも、大学の政治的な思惑とも対峙する知性も持ちつつ、孤高の天才故に苦しむという繊細な役柄もぴったりで、流石だなと思いました。
ただのお高く止まっただけの天才ではなく、実は現代音楽も含めた幅広い音楽に深く理解があるという役柄も、物語に深みを増していたと思います。
ずっとすれ違ったままだった朔と大成が、天才作曲家だった亡き父が残した音楽に込められた想いを知り、再び気持ちが通う、という場面も感動的だったのですが、原作漫画ではどう表現していたのか気になりました。
漫画を映画化する上で、音楽表現をどうするかは難しい部分だと思うのですが、この映画ではオーケストラから現代音楽まで、全体的に音楽表現の完成度が高く、かなりこだわって作られているのを感じ、映画化した意味があったなと思いました。
何より、松本穂香さんが歌う主題歌「小石のうた」は、日食なつこさんが手掛けているのですが本当に名曲でした。
彼女の爽やかな歌声と人々を解放していくという、この映画のテーマそのものを見事に表現していたと思います。
何より、この映画に登場する朔と凪をはじめ、現代音楽研究部の人達が、すごく楽しそうに楽器を演奏したり歌ったりするので、こんなに自由で楽しい音楽なら自分もやりたいなって思ってしまったほどでした。
すぐに映画に影響されてしまう人間なのですが、このくらい自由に音楽をやっていいなら、自分も始めたいと本気で思いましたね。