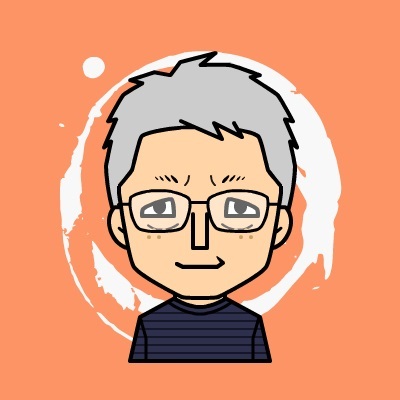「大阪・まち・再発見ぶらりウォ-ク」に参加しました。
大阪市交通局のイベントです。
地下鉄「井高野駅」近くの別府公園をスタートして、地下鉄「西中島南方駅」がゴールの、約10kmのコースを歩きました。
江口の君堂です。


遊女「江口の君」は、平資盛の娘で、平家没落の後、ここに来たと言うことです。
仁安2年(1167年)西行法師が天王寺詣の途中たまたま当地を通行中、にわか雨に会い、彼女に一夜の宿を乞うたところ断られたが、歌の贈答があって、その奥ゆかしさに、一夜を語り明かしたと伝えられているそうです。
この付近は、平安鎌倉初期にかけては、京都との水運の要衝に当たる関係上、大いに賑わい、多くの遊女がおり、当時の有名公卿等も訪れた記録が残っていると言います。
こんな説明書きもありました。

大隅神社です。

大隅神社のあたりは、1700年ほど前は、大隅島と呼ばれており、応神天皇がここに離宮を営まれたところだそうです。
応神天皇崩御の後、里人が天皇の御徳を慕い、宮址に神祠を建て、祭祀したのがこの神社の起源と言う事です。

せせらぎの遊歩道の辺りです。

この付近は、平安時代から乳牛を飼育していたところと言う事です。
ヨーグルト・チーズに類する乳製品を貢納するとともに、雌牛・子牛を乳牛院に送致しており、乳牛院では薬用に採乳し、古い牛は牧に返すなどしていたそうです。

遊歩道です。

逆巻地蔵です。

「逆巻地蔵」は、弘化3年(1846年)、豊里大橋付近の阪巻村に建立されたそうです。
この場所は水流が激しく、帆を逆に巻かなければ転覆することから「逆巻の難所」と名付け、恐れられていて、幾度も船が難破し、数多くの犠牲者が出たため、慰霊と船便の安全守護を祈願して、この地蔵が建てられたと言います。
遊歩道の続きです。

生き物も少し入れておきます。
道端で見たツマグロヒョウモンの幼虫です。

瑞光寺です。

この境内にある弘済池には、ひときわ目を引く橋が架かっています。
全国にもここだけと思われる、鯨の骨でできた「雪鯨橋」です。
4世住職潭住が、宝暦6年(1756年)に南紀を行脚しているとき、太地浦の漁師に不漁であったことから豊漁の祈念を請われ、潭住は「殺生は五戒の一つ」として断りましたが、ついに祈願に応じ、鯨がたくさん捕れたお礼として、30両と鯨骨18本が贈られましたが、潭住は鯨を供養し、すべての生き物を大切にするという祈りを込めて、この橋が作られたといわれています。


春日神社です。

天正6年(1578年)に奈良春日神社より御分霊を勧請遷祀し、榊神社から改称され、現在に至っていると言います。

崇禅寺です。

天平年間(729~748年)に法相宗の行基によって創建されたそうです。
境内には「細川ガラシヤの墓」「遠城(えんじょう)兄弟の墓」「義教の首塚」、宗派の別を問わずに永代納骨している「夢殿式永代納骨堂」、日本三景の松島を象っている「茶席庭園」がありました。
布袋尊もおられました。

ここで見られた生き物です。
ウラギンシジミです。

中島惣社です。

中島惣社は、孝徳天皇の白雉2年(651年)難波長柄豊碕に遷都されたころ、五穀豊饒を祈るために多くの神領を得て創建されたと言われています。
最初、稲荷神社と呼ばれていましたが、明治29年に中島惣社の現名に改めたそうです。
惣社というのは総社の意味で、中島郷48カ村の親宮(総社)ということから来ている様で、参道も長くて立派でした。

この日の参加者も多くて、1000名近くだった様です。