
北海道の名付け親でもある松浦武四郎は、1845年(弘化元年)に初めて蝦夷地探検を行い、1855年(安政2年)に蝦夷御用御雇に抜擢され、再び蝦夷地を踏査。道東を訪れたのはその6回目の踏査(1858年)の時であった。この時の様子は「久摺日誌」にまとめられ、その普及版として出された「戊午東西蝦夷山川地理取調日誌」に詳しく紹介されている。松浦武四郎は日誌に絵も付けている。それを見ると、彼が見た風景がよく分かる。あれから155年の時が流れた。時代は確かに変化した。もし松浦武四郎が今の風景を見た時、その変化をどのように思うのであろうか。
わが町周辺を訪れた日誌には、塘路湖の他、シラルトロ湖も描かれている。シラルトロ湖は現在の国道沿いから見たのではなく、釧網線が走る側から眺めていた。ここは現在湿原のど真ん中なので行くことはできなかった。だが塘路湖は国道391号線沿いに松浦武四郎が見た場所とほぼ同じである。先人と同じ場所に立って眺めることができる。場所はサルボ展望台の入り口周辺。実際はもう少し南に位置する場所から松浦武四郎は見たはずだが、そこには現在民家がたっており湖がよく見えない。サルボが当時の風景を見るには最も近い場所だ。

(日誌に描かれた塘路湖。半島のように突き出た場所には現在標茶歴史資料館がある)
絵と比べると、湖の対岸に見える山の稜線は当時とほぼ同じ。塘路湖が150年前の姿でそのまま残っていることがよく分かる。この周辺は釧路湿原の中。湿原という大きな壁が開発を拒んでいた。それが昔のままの自然を保ったと言って過言ではないだろう。
これが松浦武四郎が見た風景なのかと思うと、何か感慨深い。彼は次のように記述している。
『4月15日。シラリトルウゥ(シラルトロ沼の意味)に着いた。周りが7里ほどの沼という。それから5~6町(540~650m)ほどでトウロに着く。ここには村落があって16軒もの家があった。(中略、家々の名前まで記入されていた)沼の入り口に入ってみたが、4~5町(430~540m)の間は葦や萩の丘の上に家が立ち並び、それらの家々からはちょうど広々とした湖が眺められた。そこからの風景が素晴らしい。それから、この村はどの家でも、床にガマで織った幅4,5尺くらいの席(ゴザ)を敷いている。この席は誠に珍しく、良いもので、聞けばこの地の名産なのだそうだ。陽の高いうちに着いたので、村の者たちには十分な手当てを配した後、ゆっくりと眠ることにする』
塘路湖周辺に住んでいた人たち(アイヌの人)の生活の一端が偲ばれる。塘路湖の美しい風景とともに家々があり、豪華とは言えないまでもそれなりに豊かな生活ぶりが見えてくる。同時に、松浦武四郎の踏査は村人たちに食糧などを配りながらの旅であったことも分かる。これは他の地での記述にもあり、とくに老人や子供たちへの土産(食べ物)を配しながらの旅であった。松浦武四郎はアイヌの人たちとのコミュニケーションを非常に大切にしていた。また彼らの文化や生活を守ることにも苦心していたと伝えられている。すべてが正しいかどうかは分からないが、少なくても日誌を読むと、蝦夷地の征服とか土地を搾取するための踏査ではなかったことはうかがえる。

(日誌に描かれたシラルトロ湖。現在の釧網線が走る場所から見たものらしい)
この6回目の踏査は道東を中心としたもので、1858年3月24日に久摺会所(現在の釧路)を出発。大楽毛から阿寒、網走、美幌、女満別などの内陸をめぐり、西別側の源流部へ至っている。弟子屈やクッチャロに滞在したのは4月9日から13日まで。14日に弟子屈から標茶に向かっている。標茶で久摺からの食糧補充をしている。その間、食料が尽きて、ヒエなどの非常食を食べたり、猟をして飢えをしのいだらしい。標茶で食糧を補給して安心したのか、酒もないのに宴をして、ユーカラで踊り、歌まで詠んでいる。
塘路に着いたのはその翌日。そして16日には少し南から釧路川を下って久摺に戻って旅を終えている。この当時松浦武四郎は40歳。壮年の充実した体力を持っていた。とはいえ、道なき道を踏査した23日間。その過酷さは十分に理解できる。彼に同行したのは久摺に詰めていた同心一人と案内役を兼ねたアイヌの人11人であった。アイヌの人たちの助けでなしには達成できなかった踏査でもあった。彼らとの交流が、後の彼の人生を決めたとも言えるだろう。日誌では3月~4月にかけてとなっているが、当時の暦は旧暦。現在の4月~5月にかけてと考え、彼の見た時期にあわせて巻頭の写真にした。
松浦武四郎は北海道の名前をつけると同時に1869年(明治2年)に北海道開拓判官に任命されている。しかし、その翌年、開拓使を批判し職を辞している。開拓の名のもとに乱開発やアイヌの人たちへの圧力行政を批判したからだ。
1888年(明治21年)松浦武四郎は東京の自宅で逝去。波乱の人生を終わっている。彼の見た北海道の風景はいたるところで様変わりしている。そのことを彼が今どう思うのか、北海道人として考えると、少しばかり胸が痛む。

(釧路市の幣舞橋近くにある松浦武四郎の銅像。案内人のアイヌの人と並んでいる)
















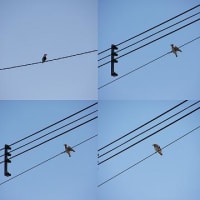


今年の天気は変ですね。
いや、これから毎年こうなのかも・・・
参りましたね。
いつ頃帰郷になりそうですか?道東の春は来週以降のようです。風邪に御注意を!