
摩周湖が2年連続で全面結氷した。冬だから湖が凍ることが当たり前のように思うかもしれないが、実は摩周湖の全面結氷というのは意外に珍しい。昨年の結氷が実は4年ぶり。なかなかお目にかかれない。地球温暖化とか言われている中で、昨年が特別だと思われていた。だが、今年もなのである。昨今の冷え込みの厳しさ(マイナス20度前後)がもたらしたもの。道東は冬を通じて雪も多かった。これも珍しい。3月初めの大雪のおかげで雪化粧の湖となったが、何とか写真に残すことができた。もし来年からしばらく全面結氷しないことになれば、貴重な記録となる。
摩周湖が全面結氷をあまりしないのは、温暖化だけが理由ではない。水深211メートルという深さにも要因がある。水の量が多いと凍りにくくなるからだ。水は熱伝導率が悪く、冷えたり温まったりするのに時間がかかる。そのために季節より少しずつ遅れる。零下26度以下の冷温が続くことによって湖全体がようやく冷え、それから氷へと進む。1月に結氷することはなく、2月中旬以降に凍るのはそのためだ。2月末にならなければ凍るかどうか分からないというのが摩周湖なのである。

摩周湖には神秘的な話がいくつもあるが、誤解のまま伝説となった話も多い。摩周湖の伏流水についても、そういう伝説の一つ。道東の各地に湧き、おいしい地下水があちこちに出ているような話ができあがっているが、ほとんどが摩周湖とは関係がない。そんな事実が最近の調査で分かってしまった。夢を壊すようで悪いが、神の子池の水も摩周湖と関係ないらしい。おいしい水には違いがないのだから、ヨシとしよう。

摩周湖の透明度の話にも幾つか誤解がある。1931年の調査で41.6メートルを記録し、バイカル湖をしのいで世界一の称号を得た。しかし、1950年以降、透明度はどんどん低下。今や日本一の地位も危なくなっている(19メートル、2004年調査)。その原因はヒメマスやニジマスの放流にあるとされていた。澄んだ水に魚は住めぬ、という格言が生きていた。どうやらこれも怪しいらしい。魚の放流と透明度の変化の因果関係はまだ解明されていない。地殻変動による水質の変化というのが事実らしい。
霧の摩周湖の歌で、すっかり摩周湖と霧がセットでイメージされるが、摩周湖の霧は意外に少なく、霧に出会える確立はかなり低い。それでも春から6月頃までにチャンスはある。この霧が海霧であることも意外に知られていない。釧路沖の太平洋で発生した海霧は、風に乗り釧路湿原を通る。この時、湿原の湿気で霧はさらに大きくなり、それが流れ流れて摩周湖にたどり着く。この海霧が摩周湖を包む風景は実に神秘的。残念ながら画像でしか見たことがないが、一度は遭遇したいと願っている。

摩周湖にまつわる誤解であろうと伝説神話であろうと、話題があるだけでもいい。そうした話が多いほど摩周湖に興味が持たれるからだ。弟子屈町の有志はいま、摩周湖を世界遺産に登録させたいと願っている。その実現の可能性は不明だが、実現すればメリットはやはり大きいだろう。
全面結氷した摩周湖が見られるのは3月まで。春の暖かさは、湖の氷を溶かし、道東の遅い春が本格化する。待ちかねた春の到来となる。
















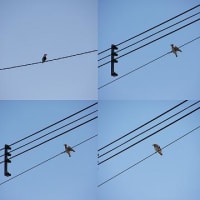


おっしゃる通り貴重な写真としてアーカイブの主要部分を
構成するかもしれませんね。
ところで、霧と透明度のデータは知ってましたが、全面結氷や結氷速度のこと、伏流水のことなど誤解だらけでした。
大変勉強になりました。でも、そこが摩周湖の神秘的なところだと考え直してみたりしてます。奥が深いですね。
今日のブログはいつにも増して説得力がありますね。
雪がなければ、摩周湖でもオミワタリが見られます。それこそ貴重な写真になります。私の程度はまだまだ役に立ちません。しかし、そのためには摩周湖に通い続けなければならず、やはり無理ですね。
運が頼りになります。今回も期待しないで行ったら、この状態でした。どうやら3月頭に全面結氷したようです。