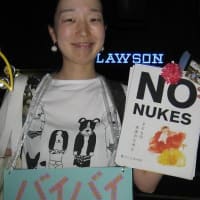本日の「京都新聞」に「東山ナラ枯れ ほぼ収束」の記事
”ほぼ収束”はその通りだが、「京都市 害中対策が奏功」は違うなぁ
京都市や京都府、予算がかけられる範囲で頑張って対策を打ったが、
残念ながら、対策が『奏功』したとは言えなかった。
私たちが行った吉田山の取り組みでも
爪楊枝を必死に打ち込み、それが虫が大量に拡散(攻撃)してくる規模とスピードに
(打ち込みが)かろうじて対応できていた時は、「枯死」を大幅に減らす効果があったが、
虫の侵入に、(打ち込みの)物理的な運動量が間に合わなくなった段階(年)では
コナラの大量枯死を引き起こしてしまった。
その年は、カシナガ侵入木(コナラ)の40%以上が枯死した。
カシナガの進出は、その”コナラ枯死ピーク”の年を過ぎても、
アラカシやシイへの侵入のピークをつくり、
その後、それも縮小させながら、今を迎えている。
記事でも少し触れられているが、侵入しやすく、枯れやすいコナラがなくなってしまって、カシナガが別の森に、多くは移って行ったのが『収束』の大きな要因だ。
ちなみに、コナラの侵入木(いちどカシナガが侵入したが、枯れずに残った個体)には、
翌年以降、カシナガは穴掘りを弱める傾向が明らかにあり、
総合的に見ると、吉田山では、ある年に大量のコナラが枯れ、一方、侵入を受けたが持ちこたえた”カシナガ接種”完了木がかなり生き続け、現在に至っている。
そして今、吉田山でのカシナガが入っていないコナラは一本もなくなった。
大文字山のコナラたちにも、同様なことが起こっているはず。
行政も頑張ったことは評価するが、以上のような内容なので、あまり『対策が奏功』などと言わないほうがいいと思います。
写真は、今年8月下旬の大文字山
森の表面は、きれいになっています。
”ほぼ収束”はその通りだが、「京都市 害中対策が奏功」は違うなぁ
京都市や京都府、予算がかけられる範囲で頑張って対策を打ったが、
残念ながら、対策が『奏功』したとは言えなかった。
私たちが行った吉田山の取り組みでも
爪楊枝を必死に打ち込み、それが虫が大量に拡散(攻撃)してくる規模とスピードに
(打ち込みが)かろうじて対応できていた時は、「枯死」を大幅に減らす効果があったが、
虫の侵入に、(打ち込みの)物理的な運動量が間に合わなくなった段階(年)では
コナラの大量枯死を引き起こしてしまった。
その年は、カシナガ侵入木(コナラ)の40%以上が枯死した。
カシナガの進出は、その”コナラ枯死ピーク”の年を過ぎても、
アラカシやシイへの侵入のピークをつくり、
その後、それも縮小させながら、今を迎えている。
記事でも少し触れられているが、侵入しやすく、枯れやすいコナラがなくなってしまって、カシナガが別の森に、多くは移って行ったのが『収束』の大きな要因だ。
ちなみに、コナラの侵入木(いちどカシナガが侵入したが、枯れずに残った個体)には、
翌年以降、カシナガは穴掘りを弱める傾向が明らかにあり、
総合的に見ると、吉田山では、ある年に大量のコナラが枯れ、一方、侵入を受けたが持ちこたえた”カシナガ接種”完了木がかなり生き続け、現在に至っている。
そして今、吉田山でのカシナガが入っていないコナラは一本もなくなった。
大文字山のコナラたちにも、同様なことが起こっているはず。
行政も頑張ったことは評価するが、以上のような内容なので、あまり『対策が奏功』などと言わないほうがいいと思います。
写真は、今年8月下旬の大文字山
森の表面は、きれいになっています。