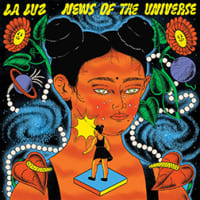中1の頃だったか、新世界交響曲を聞いていて3楽章に入ってしばらくすると猛烈に興奮してきてそのままシコシコ…。その後は音楽を聞いてそうなることはないが、3楽章に限らず新世界は魂の奥底をゆさぶる官能性に満ちた曲だと思う。
私の人生は高校3年間に凝縮されていて、今もいかに生きるべきかインスピレーションの源だ。おそらくそれは前段階、小中時代の経験によって培われた感受性=対人関係が苦手で心が貧しくなるので一人になって豊かな文化に触れて憂鬱を癒す=の最初の結実だったろう。

Serenade for Strings in E, Op. 22 - 5. Finale: Allegro vivace (1875)
この5楽章、テルデックの冷たい感じの廉価CDで少し聞いて、あとぜんぜん聞かなくなってたなと思い出す。買ったアルバムを全部聞かないという私の悪癖はレコード・カセット・CD・MDといった媒体が後景に退くことで大幅に改善され、落ち着いた取捨選択が可能に。

Violin Concerto in A minor, Op. 53 - 2. Adagio ma non troppo (1879)

Gipsy Songs, Op. 55 - 4. Songs My Mother Taught Me (1880)

Nocturne, Op. 40 (1883)

From the Bohemian Forest, Op. 68 - 5. Silent Woods (1884)

Slavonic Dance in E minor, Op. 72/2, "Starodávny" (1887)

Piano Quintet in A, Op. 81, B. 155 - 1. Allegro ma non tanto (1887)
チェコの国民楽派としてのドヴォルザーク(当地ではドヴォジャーク)らしさ=民族的な要素を吸収し、交響楽的な慣用表現と結びつけることによって国民的な慣用表現を確立する=を強く感じさせる独特の節回しを持つ、たとえばスラブ舞曲・謝肉祭序曲・新世界・弦楽四重奏曲アメリカ・チェロ協奏曲といった曲はスラブ舞曲を除いてアメリカ滞在期(1892~95年)周辺の短期間に集中しており、今回未聴の代表曲をあたってみると、大半の曲はシューベルトやメンデルスゾーンに連なる王道ロマン派志向であることが分る。これはそうした面を代表する華麗な室内楽曲で1楽章以外も良い。

Rondo in G minor, Op. 94 (1893)

Symphony #9 in E minor, Op. 95, "From the New World" - 1. Adagio - Allegro Molto (1893)
Symphony #9 in E minor, Op. 95, "From the New World" - 2. Largo (1893)
ドヴォルザークは1892年、ニューヨーク市の国立音楽院の院長として破格の待遇で招かれる。この学校は富裕で社会活動に熱心な女性ジャネット・サーバーによって設立され、当時としては稀なことに女性や黒人の学生も受け入れた。ドヴォルザークは滞米初期に米国の音楽について「アメリカ先住民とアフリカ系アメリカ人の音楽を基盤に含めることでアメリカ人は独自の国民音楽を成長させられるだろう」との所感をまとめる。
彼は作曲活動の初期、ワーグナーに心酔しており、絶大な影響を受けていたとされる。ところが、そうした初期ですら彼の音楽にワーグナーの聴衆を意識した派手さ、ハッタリ感は薄い。おそらくそのように導く、ドヴォルザークが敬虔なカトリック信徒で篤実な人柄の持ち主であることこそ、新興アメリカ国民音楽の指導者として望まれるものだったろう。そしてこの時期に傑作が集中しているのは、アメリカ側の意図が結実した結果であるともいえよう。

String Quartet #12 In F, Op. 96, B 179, "American" - 1. Allegro ma non troppo (1893)

Humoresque, Op. 101/7 (1894)

Cello Concerto in B minor, Op. 104 - 1. Allegro (1895)
若くして成功したが難病に襲われ演奏できなくなり42歳で亡くなったチェロ奏者ジャクリーヌ・デュ・プレ。伝記映画化はセンセーショナリズムとして批判されているらしいが、ユダヤ教に改宗しダニエル・バレンボイムとユダヤ式の結婚式を挙げるシーンなど印象的だった。最近ベートーヴェンの交響曲をはじめ次々とSpotify/ユーチューブ試聴して良い演奏に入れ替えているが、この激情ほとばしるデュ・プレの1楽章は不動。

Cello Concerto in B minor, Op. 104 - 2. Adagio ma non troppo (1895)

Rusalka, Op.114 - Act 1: Mesicku na nebi hlubokém (1900)