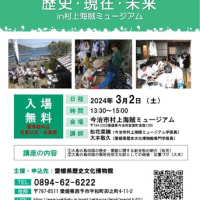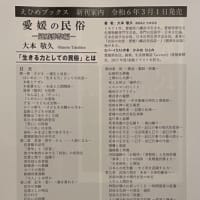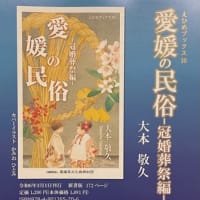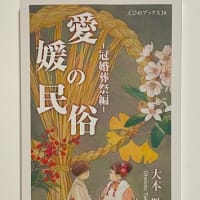8 愛媛県松山市沖の津波伝説
松山市内には地震による浸水の言い伝えが残っている。松山市沖の興居島ではいつの時代のどのような被害かというのは歴史学的には実証はできないが、鷲ヶ巣というところがあり、そこは、海が今のようには近くなくて田畑がもっと広かった。そして釣島まで歩いていけたという。興居島で最初に開かれたと伝えられる集落であるが、この鷲ヶ巣を大きな津波が襲い、大半の家が押し流されて田や畑も一緒に流されたという伝説が残る。そこに「かさね」という岩がぽっこりと顔を出し、海岸から100mほど離れた海の中となってしまったと伝えられている(松山市興居島中学校編『ふるさと興居島』(1985年発行)、「伝説から探る伊予灘の津波」(『松山百点』280号、2011年発行)でも紹介)。このように島の一部が沈んでしまったという話が興居島に残っている。これは現実的に考えると、南海トラフ地震、もしくは瀬戸内海付近を震源とする内陸型地震により沈降現象が起こり、海水が流入して長期に浸水しまう現象がもととなって、このような伝説が成立した可能性があるだろう。いつの時代の被害かは不明であるが、瀬戸内海の地震による地盤沈降、そして長期的な高潮等の被害を反映させた伝承ではないだろうか。
この興居島だけではない。中島本島の鐃地区にも類似伝承がある。「おたるがした」というころがあり、地震があって島中がぐらぐらと揺れだした。これは大事になる、津波じゃ。はよみんな山の中に逃げんと大事になる。家も畑も波に洗われて、何にもないと。とてつもない大きなたるがごろんと山の根っこにころがっている。村のもんは誰いうことなしに、あのたるのあったところを「おたるがした」というようになった。要するに大きなたるしか残らなくて、一面流されてしまったと伝承である(中島町教育委員会編『中島のむかし話―伝説―』(1982年発行)、「伝説から探る伊予灘の津波」(『松山百点』280号、2011年発行)にても紹介)。
もう一つ有名なのは、由利島の伝承である。現在は無人島であるが、由利島にあった寺院が、鎌倉時代の地震によって、松山市古三津に移ってきたという言い伝えがある。これは現在も古三津にある儀光寺のことであるが、寺伝では、もともと寺は由利島にあり、儀光上人の開祖と伝わっている。鎌倉時代の弘安年間に地震・津波の天災に遭い、本尊の導きによって、現在地の古三津に移転し、以来700年祀られていると境内の案内表示にも書かれている。この由利島が沈んだという言い伝えについては、鎌倉時代の弘安年間に津波が起きるような大きな地震があったという歴史上の記録が実は確認できない。これは実際には弘安年間でない可能性もあるし、南北朝、室町期かもしれない。もしかしたら、単なる創作の伝説かもしれない。ただし、島が沈んだ伝説というと、瀬戸内海周辺では愛媛県の対岸の別府湾に、瓜生島という島があり、それが沈んだという伝説がある。これは年代が確定できていて、慶長豊後地震の際の出来事とされている。この瓜生島伝説は実際には、別府湾沿岸が高潮被害、津波被害を受けて、それを地震後約100年経った後に、話が創作されて島が沈んだという形になっている(瓜生島伝説の形成過程については、加藤知弘「府内沖の浜港と『瓜生島』伝説」(『大分県立芸術文化短期大学研究紀要』35号、1997年)や岩瀬博「沈んだ島―大分県瓜生島伝説を中心に―」(『大谷女子大国文』33号、2003年)などに詳しい)。歴史学上はこの種の伝承はほぼ無視されることが多いが、由利島、中島、興居島という松山市沖の近接する島々に類似する伝承が残っている。これは過去の浸水被害の事実を反映させて伝承された伝説と考えられ、今後、瀬戸内海でも予想される地震による地盤沈降と浸水被害を考えたときに、あながち無視できない口承の文化遺産といえる。
松山市内には地震による浸水の言い伝えが残っている。松山市沖の興居島ではいつの時代のどのような被害かというのは歴史学的には実証はできないが、鷲ヶ巣というところがあり、そこは、海が今のようには近くなくて田畑がもっと広かった。そして釣島まで歩いていけたという。興居島で最初に開かれたと伝えられる集落であるが、この鷲ヶ巣を大きな津波が襲い、大半の家が押し流されて田や畑も一緒に流されたという伝説が残る。そこに「かさね」という岩がぽっこりと顔を出し、海岸から100mほど離れた海の中となってしまったと伝えられている(松山市興居島中学校編『ふるさと興居島』(1985年発行)、「伝説から探る伊予灘の津波」(『松山百点』280号、2011年発行)でも紹介)。このように島の一部が沈んでしまったという話が興居島に残っている。これは現実的に考えると、南海トラフ地震、もしくは瀬戸内海付近を震源とする内陸型地震により沈降現象が起こり、海水が流入して長期に浸水しまう現象がもととなって、このような伝説が成立した可能性があるだろう。いつの時代の被害かは不明であるが、瀬戸内海の地震による地盤沈降、そして長期的な高潮等の被害を反映させた伝承ではないだろうか。
この興居島だけではない。中島本島の鐃地区にも類似伝承がある。「おたるがした」というころがあり、地震があって島中がぐらぐらと揺れだした。これは大事になる、津波じゃ。はよみんな山の中に逃げんと大事になる。家も畑も波に洗われて、何にもないと。とてつもない大きなたるがごろんと山の根っこにころがっている。村のもんは誰いうことなしに、あのたるのあったところを「おたるがした」というようになった。要するに大きなたるしか残らなくて、一面流されてしまったと伝承である(中島町教育委員会編『中島のむかし話―伝説―』(1982年発行)、「伝説から探る伊予灘の津波」(『松山百点』280号、2011年発行)にても紹介)。
もう一つ有名なのは、由利島の伝承である。現在は無人島であるが、由利島にあった寺院が、鎌倉時代の地震によって、松山市古三津に移ってきたという言い伝えがある。これは現在も古三津にある儀光寺のことであるが、寺伝では、もともと寺は由利島にあり、儀光上人の開祖と伝わっている。鎌倉時代の弘安年間に地震・津波の天災に遭い、本尊の導きによって、現在地の古三津に移転し、以来700年祀られていると境内の案内表示にも書かれている。この由利島が沈んだという言い伝えについては、鎌倉時代の弘安年間に津波が起きるような大きな地震があったという歴史上の記録が実は確認できない。これは実際には弘安年間でない可能性もあるし、南北朝、室町期かもしれない。もしかしたら、単なる創作の伝説かもしれない。ただし、島が沈んだ伝説というと、瀬戸内海周辺では愛媛県の対岸の別府湾に、瓜生島という島があり、それが沈んだという伝説がある。これは年代が確定できていて、慶長豊後地震の際の出来事とされている。この瓜生島伝説は実際には、別府湾沿岸が高潮被害、津波被害を受けて、それを地震後約100年経った後に、話が創作されて島が沈んだという形になっている(瓜生島伝説の形成過程については、加藤知弘「府内沖の浜港と『瓜生島』伝説」(『大分県立芸術文化短期大学研究紀要』35号、1997年)や岩瀬博「沈んだ島―大分県瓜生島伝説を中心に―」(『大谷女子大国文』33号、2003年)などに詳しい)。歴史学上はこの種の伝承はほぼ無視されることが多いが、由利島、中島、興居島という松山市沖の近接する島々に類似する伝承が残っている。これは過去の浸水被害の事実を反映させて伝承された伝説と考えられ、今後、瀬戸内海でも予想される地震による地盤沈降と浸水被害を考えたときに、あながち無視できない口承の文化遺産といえる。