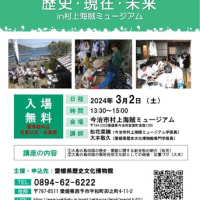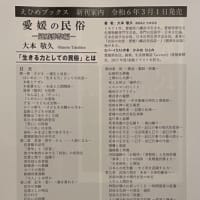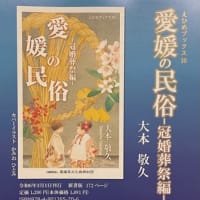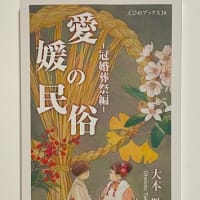今から四〇年程前までは正月は二度あった。そういった話を各地で聞くことができる。新暦と旧暦の正月の両方を祝っていたのである。二度、正月を祝うことは、明治五年(一八七二)に政府によって、それまでの太陰太陽暦を太陽暦へと改暦したことで、年中行事の日程に旧暦、新暦の混乱が生じたことにより始まっている。国家が新暦を採用しても、庶民はそれまでの旧暦によって季節を感じ、農業、漁業を営んできたわけで、直ちに旧暦を捨てることはできなかったのである。
さて、新と旧の正月の祝い方は同じだったわけではない。双岩地区で聞いたところでは、新暦の年末には、正月に食べる分だけの餅しかつかなかった。というのも新正月の時期は、芋の収穫や麦蒔きで忙しかったからである。正月休みも三ヶ日ではなく、一日だけだったという。ところが、旧正月の前になると、キビ、アワ、タカキビ、米の餅を大量につき、水餅にして、六月頃まで保存した。水餅にするには「寒の水」といって、大寒の時の水につけるのがよいとされたので、新暦の年末に水餅にするのは抵抗があった。旧正月は三日間が休日であり、親類など多くの来客があったという。昭和二〇年代までは旧正月のほうが盛んだったが、次第に廃れ、新暦へと移行している。
また、川之内地区で聞いたところでは、戦前は、新正月には氏神へ初詣に行くくらいで、現在の正月のような雰囲気はなく、雑煮も旧正月に食べていた。旧正月には三ヶ日が終わるとすぐに大洲祇園神社の大祭があり、大勢で参拝に行くなど、新正月よりも旧正月の方が楽しみだったという。
なお、正月の初詣は、江戸時代後半に流行した恵方参りという、良い方角にある寺社に参詣する習俗にはじまるもので、近代になり、年頭に氏神や有名寺社に行くようになったとされ、比較的新しい習俗で、初日の出も同様に近代に盛んになったものである。また、戦後になると大晦日に紅白歌合戦やゆく年くる年を見ることによって、年の変わり目を意識するなど、現在の新暦の正月の雰囲気は、ここ半世紀で形成されたものといえる。
八幡浜地方において正月が旧から新へ完全に移行したのは昭和三〇年代に入ってからのことであり、明治改暦後、九〇年の月日を要している。これは旧暦によって営まれていた農業、漁業などの生業中心の生活慣習が高度経済成長を遂げ、都市の慣習へ移行したことを物語っている。同時に、マスメデイア等の影響により家庭・地域内の規範に基づいていた正月から、全国的な国民行事としての正月へと移り変わったともいえるだろう。
1999年10月21日掲載
さて、新と旧の正月の祝い方は同じだったわけではない。双岩地区で聞いたところでは、新暦の年末には、正月に食べる分だけの餅しかつかなかった。というのも新正月の時期は、芋の収穫や麦蒔きで忙しかったからである。正月休みも三ヶ日ではなく、一日だけだったという。ところが、旧正月の前になると、キビ、アワ、タカキビ、米の餅を大量につき、水餅にして、六月頃まで保存した。水餅にするには「寒の水」といって、大寒の時の水につけるのがよいとされたので、新暦の年末に水餅にするのは抵抗があった。旧正月は三日間が休日であり、親類など多くの来客があったという。昭和二〇年代までは旧正月のほうが盛んだったが、次第に廃れ、新暦へと移行している。
また、川之内地区で聞いたところでは、戦前は、新正月には氏神へ初詣に行くくらいで、現在の正月のような雰囲気はなく、雑煮も旧正月に食べていた。旧正月には三ヶ日が終わるとすぐに大洲祇園神社の大祭があり、大勢で参拝に行くなど、新正月よりも旧正月の方が楽しみだったという。
なお、正月の初詣は、江戸時代後半に流行した恵方参りという、良い方角にある寺社に参詣する習俗にはじまるもので、近代になり、年頭に氏神や有名寺社に行くようになったとされ、比較的新しい習俗で、初日の出も同様に近代に盛んになったものである。また、戦後になると大晦日に紅白歌合戦やゆく年くる年を見ることによって、年の変わり目を意識するなど、現在の新暦の正月の雰囲気は、ここ半世紀で形成されたものといえる。
八幡浜地方において正月が旧から新へ完全に移行したのは昭和三〇年代に入ってからのことであり、明治改暦後、九〇年の月日を要している。これは旧暦によって営まれていた農業、漁業などの生業中心の生活慣習が高度経済成長を遂げ、都市の慣習へ移行したことを物語っている。同時に、マスメデイア等の影響により家庭・地域内の規範に基づいていた正月から、全国的な国民行事としての正月へと移り変わったともいえるだろう。
1999年10月21日掲載