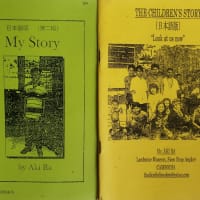かつてピタゴラスは「万物の根源は数である」と言った・・・なんてことを高校の時に習ったかもしれない。このような見解については、「いやいや芸術は?人間は?」といった突っ込みが思いつくわけで、いかにも荒唐無稽な主張と感じられたかもしれない。
しかし、こういう世界認識が例えば「音の数値化(可視化)」という発想に繋がり、それが「音階」というカテゴライズに繋がったという話であればどうだろうか?
こう表現すると、例えば高校数学で教わる三角関数や微積を用いた「フーリエ変換」などとも接続する。あるいは、「音」の性質という点では高校物理で学習するドップラー効果や交流などを思い浮べる人もいるだろう。
要するに、ただ「万物のアルケーは数だ」という言葉だけでは妄想にすら思えるかもしれないが、世界をそのように理解しようとする営み(まさに自然哲学)によって、一見すると数とは無関係に思えるようなもののアルゴリズム的体系化やそれを人間がどのように受容するのかという認知科学などにもつながる(こう考えると、例えばハーバード大の音楽学部をはじめ、リベラルアーツの一環としてアメリカの大学で音楽が広く学ばれていることは驚くに値しない)。
「音楽と世界理解・人間理解」と言うといかにも大上段な話に思われるかもしれないが、例えば宗教音楽、戦意高揚歌、ASMR、ノイズミュージック、プログレのパターンetc...と身近なものと密接に結びつく話である(このテーマについては、片山杜秀の『革命のクラシック音楽史』について前に記事を書いたことがある)。他にも、赤ん坊が泣いている時に犬が遠吠えをして赤ん坊を泣き止ませる動画というのを複数見たことがあるが、この「音」を体系化できれば、子育てにおいて悩ましいものの一つである赤ん坊の夜泣きなどに極めて効果的な音を出す器械を生み出す、といったことにもつながるかもしれない。これは人間理解と実利の話だが、こういった研究はまた動物の理解(例えばイルカの鳴き声の解析)などとも連動するだろう。
そしてもちろん、アルゴリズムの解析はパターン化へとつながり再生産やミックスといったサンプリングにもなっていく。
こういう形で「数値化不可能」と思われていたものがパターン化されていけば、その先に「人間(性)は数値化できるのか?」という問いが出てくるのは当然であろう(まあこういう発想は「確定記述の束」という表現ですでに提示されており、別段新しいものでもないのだけど)。こういう探究活動の中で、そのパターン化不可能に思えたような諸々の特徴もまた、「正常性バイアス」や「認知的不協和」といった傾斜によって解析されてきたわけである(ちなみにこの「正常性バイアス」は、以前「嘲笑の淵源」で述べた極限状況でも自分が日常と同じように振舞えると無根拠に思う人たちの様子を説明するのにそのまま使えたりする)。
このように書いてくると、あたかも「人間はおしなべて数値化(パターン化)できる」という主張に思えるかもしれないが、そうではない。この問いは、「数値化できる」とも「そうでない」とも言ってない。むしろ、わからないからこそ探究するのである・・・というところからマンハイムの毒書会について書いた「認識論と実証主義」の話が出てくるわけだが、むしろここでは、自分の好きな「BEASTARS」というアニメのOPを載せつつ、参考の材料としたい。