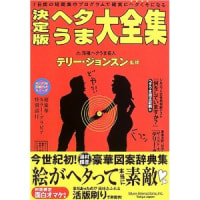このタイトルは、「空の神兵」の歌詞である。もちろん「空の神兵」は軍歌である。前回に述べたように、軍歌を超えた普遍性があると言ったが、それを語ってみたい。この一節は、じつは、曲そのものを聴き、前後の歌詞を知り、その中から生まれてくるイメージを直接耳にしていただけば、もっと話はわかりやすくなるはずである。
1942年に発表されたこの曲は、およそ日本の戦争中の軍歌とは想像も出来ないようなエキゾチックな雰囲気で始まる。なによりもおどろくのは、まさに敵国のどこか西欧の広い野の村にある教会の鐘の響きとともに曲ははじまるのである。もしくは、勇壮な軍歌らしい前奏のメロディで、歌詞が始まる寸前に、この鐘の音が響き渡る。それは空をイメージさせるのだ。その空に落下傘が開くのだ。戦闘よりも、落下傘が開く美しさに作詞家梅木三郎と作曲 高木東六は意を注いでいるのがわかる。この導入部の美しさに聴くものはまず打たれずにおれない。その一番の歌詞は、
藍より蒼き 大空に大空に たちまち開く 百千の
真白き薔薇の 花模様 見よ落下傘 空に降ふり
見よ落下傘 空を征く 見よ落下傘 空を征く
である。ここには、落下傘の美を歌う以外のなにもない。戦争中に軍部にむけて、このような大胆な歌詞を冒頭に置いたのは、稀有のことといえよう。
つぎに問題の2番の歌詞は、以下のようである。
世紀の華よ 落下傘 落下傘 その純白に 赤き血を
捧げて悔いぬ 奇襲隊 この青空も 敵の空
この山河も 敵の陣 この山河も 敵の陣
である。ここで、ようやく軍歌、つまり戦意高揚がうたわれているが、それでもなお、軍歌とはどこか違う。それは、パラシュートで空を降る若き兵士の赤き血を捧げて悔いぬ、純粋きわまりない心情を感じさせるからである。大空で孤独である。しかし、怖れない。この決意で空を降るかれらの美しさに感動させられる。戦闘ではなく、人を歌っているのだ。もし、この敵ということばを「困難」とか「不正」とかに置き換えてもいい。これは人生の在りかた、現実を象徴している。青臭いとよく言われるが若者の純粋性は、社会と戦っていかねばならぬ孤立を、抱え込む。それは人生の現実であろう。こう思い、その兵士に思いが重ねると、感動と、現代に生きる勇気をあたえられて、胸が熱くなる。これは戦争ではない。生きる勇気を鼓舞してくれるのである。このような解釈で、3番、4番も十分に受け止めることが出来る。
敵撃砕と 舞い降る舞い降る まなじり高き つわものの
いずくか見ゆる おさな顔 ああ純白の 花負いて
ああ青雲に 花負いて ああ青雲に 花負いて
最終歌詞:
讃えよ空の 神兵を神兵を 肉弾粉と 砕くとも
撃ちてしやまぬ 大和魂 わがますらおは 天降る
わが皇軍は 天降る わが皇軍は 天降る
ここで、私が言いたいのは、すぐれて芸術は、時代を超え、普遍性をもっているということだ。この芸術性が、人々に真実を自覚させ、生きる目標と行動を示唆するということだ。たとえ、戦時中の軍歌といえど、芸術の普遍性が滅びないということである。
この軍歌にはジーンときて、いつでも涙することができる。あさいちでは泣けない。このドラマには、本当の現実がないからである。
1942年に発表されたこの曲は、およそ日本の戦争中の軍歌とは想像も出来ないようなエキゾチックな雰囲気で始まる。なによりもおどろくのは、まさに敵国のどこか西欧の広い野の村にある教会の鐘の響きとともに曲ははじまるのである。もしくは、勇壮な軍歌らしい前奏のメロディで、歌詞が始まる寸前に、この鐘の音が響き渡る。それは空をイメージさせるのだ。その空に落下傘が開くのだ。戦闘よりも、落下傘が開く美しさに作詞家梅木三郎と作曲 高木東六は意を注いでいるのがわかる。この導入部の美しさに聴くものはまず打たれずにおれない。その一番の歌詞は、
藍より蒼き 大空に大空に たちまち開く 百千の
真白き薔薇の 花模様 見よ落下傘 空に降ふり
見よ落下傘 空を征く 見よ落下傘 空を征く
である。ここには、落下傘の美を歌う以外のなにもない。戦争中に軍部にむけて、このような大胆な歌詞を冒頭に置いたのは、稀有のことといえよう。
つぎに問題の2番の歌詞は、以下のようである。
世紀の華よ 落下傘 落下傘 その純白に 赤き血を
捧げて悔いぬ 奇襲隊 この青空も 敵の空
この山河も 敵の陣 この山河も 敵の陣
である。ここで、ようやく軍歌、つまり戦意高揚がうたわれているが、それでもなお、軍歌とはどこか違う。それは、パラシュートで空を降る若き兵士の赤き血を捧げて悔いぬ、純粋きわまりない心情を感じさせるからである。大空で孤独である。しかし、怖れない。この決意で空を降るかれらの美しさに感動させられる。戦闘ではなく、人を歌っているのだ。もし、この敵ということばを「困難」とか「不正」とかに置き換えてもいい。これは人生の在りかた、現実を象徴している。青臭いとよく言われるが若者の純粋性は、社会と戦っていかねばならぬ孤立を、抱え込む。それは人生の現実であろう。こう思い、その兵士に思いが重ねると、感動と、現代に生きる勇気をあたえられて、胸が熱くなる。これは戦争ではない。生きる勇気を鼓舞してくれるのである。このような解釈で、3番、4番も十分に受け止めることが出来る。
敵撃砕と 舞い降る舞い降る まなじり高き つわものの
いずくか見ゆる おさな顔 ああ純白の 花負いて
ああ青雲に 花負いて ああ青雲に 花負いて
最終歌詞:
讃えよ空の 神兵を神兵を 肉弾粉と 砕くとも
撃ちてしやまぬ 大和魂 わがますらおは 天降る
わが皇軍は 天降る わが皇軍は 天降る
ここで、私が言いたいのは、すぐれて芸術は、時代を超え、普遍性をもっているということだ。この芸術性が、人々に真実を自覚させ、生きる目標と行動を示唆するということだ。たとえ、戦時中の軍歌といえど、芸術の普遍性が滅びないということである。
この軍歌にはジーンときて、いつでも涙することができる。あさいちでは泣けない。このドラマには、本当の現実がないからである。